コミュニケーションが苦手でも人に好かれる方法
ネットでは、「コミュ障」という言葉があります。コミュニケーション障害を略したものですが、意見が通じない人に対してのネガティブなイメージで使われているようです。
精神医学におけるコミュニケーション障害という病名は、吃音など、言葉をうまく使いこなせない障害を指しています。コミュニケーションの障害を起こす精神疾患はそれ以外にもたくさんあります。
代表的なものとして、場の空気や相手の気持ちを理解するのが苦手なアスペルガー障害です。また、緊張がつよく人と話せなくなる社交不安症もそうでしょう。「コミュ障」と言われるのは、どちらかというと精神医学のコミュニケーション障害よりも、アスペルガー障害などの発達障害や社交不安症の人を指している印象があります。
コミュニケーションの障害の多くは、生まれつきの要素がつよいものなので、残念ながら自分の努力で劇的に改善させることはできません。これが理由で、自分に自信がもてず、職場の人間関係がうまくいかないことがあります。
しかし、根本は変えられなくても、ちょっとした努力で相手に良い印象を持たれる方法があります。ここでは、何らかのコミュニケーションの障害があって会話が苦手な人が、相手に良い印象をもたれるためのポイントを説明します。
精神医学におけるコミュニケーション障害という病名は、吃音など、言葉をうまく使いこなせない障害を指しています。コミュニケーションの障害を起こす精神疾患はそれ以外にもたくさんあります。
代表的なものとして、場の空気や相手の気持ちを理解するのが苦手なアスペルガー障害です。また、緊張がつよく人と話せなくなる社交不安症もそうでしょう。「コミュ障」と言われるのは、どちらかというと精神医学のコミュニケーション障害よりも、アスペルガー障害などの発達障害や社交不安症の人を指している印象があります。
コミュニケーションの障害の多くは、生まれつきの要素がつよいものなので、残念ながら自分の努力で劇的に改善させることはできません。これが理由で、自分に自信がもてず、職場の人間関係がうまくいかないことがあります。
しかし、根本は変えられなくても、ちょっとした努力で相手に良い印象を持たれる方法があります。ここでは、何らかのコミュニケーションの障害があって会話が苦手な人が、相手に良い印象をもたれるためのポイントを説明します。
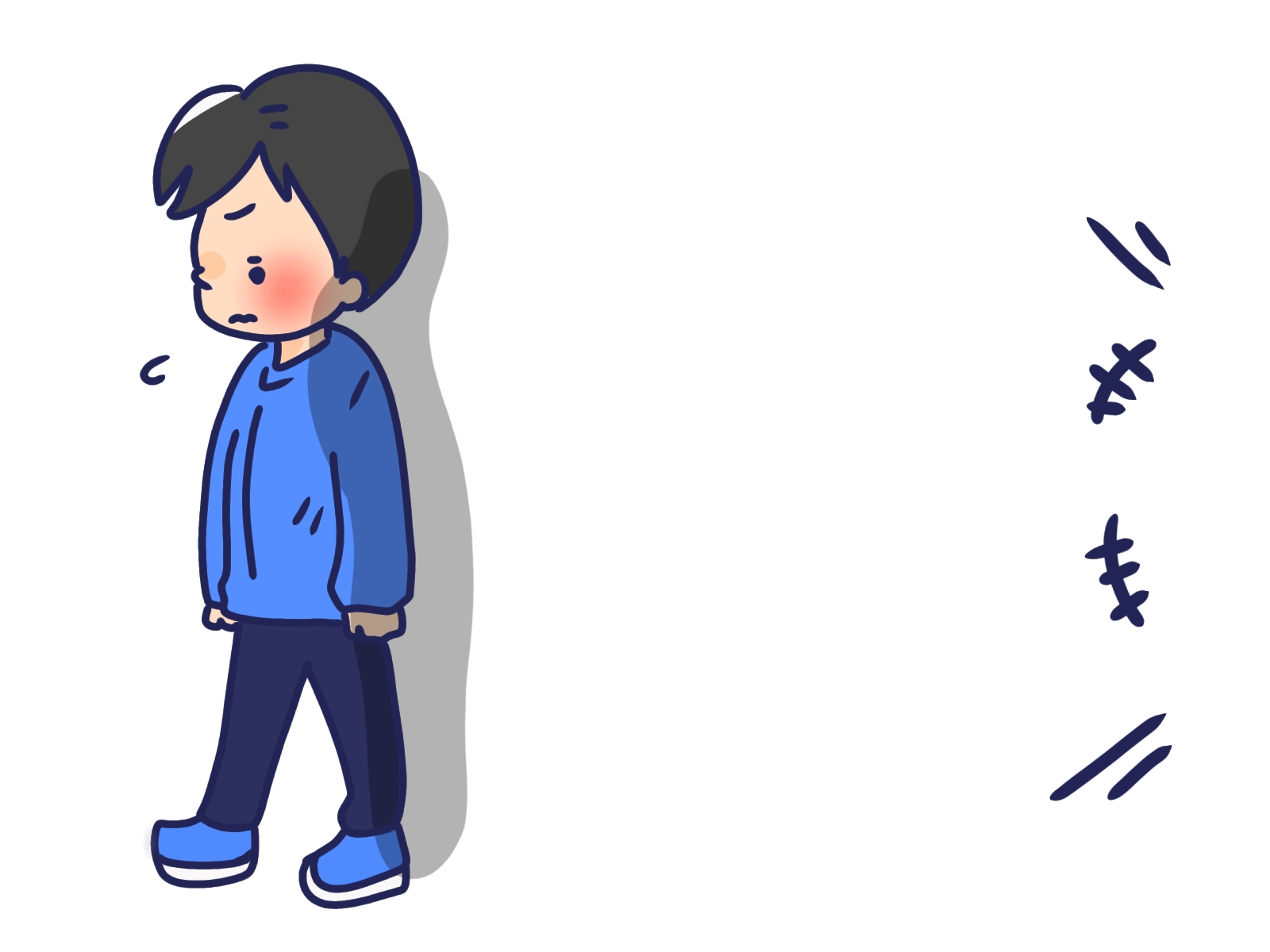
1 聞き役に徹する
自分から話題を提供したり、意見を言わずに、聞き役に徹しましょう。言葉のキャッチボールという言葉がありますが、キャッチャーに専念するのです。聞き役になるためには相槌(あいづち)が重要です。無理して言葉を添えなくても、相手の言葉に合わせてうなずきましょう。それだけでも相手は聞いてもらっていると感じることができ、良い印象を持たれます。
自分から話題を提供したり、意見を言わずに、聞き役に徹しましょう。言葉のキャッチボールという言葉がありますが、キャッチャーに専念するのです。聞き役になるためには相槌(あいづち)が重要です。無理して言葉を添えなくても、相手の言葉に合わせてうなずきましょう。それだけでも相手は聞いてもらっていると感じることができ、良い印象を持たれます。
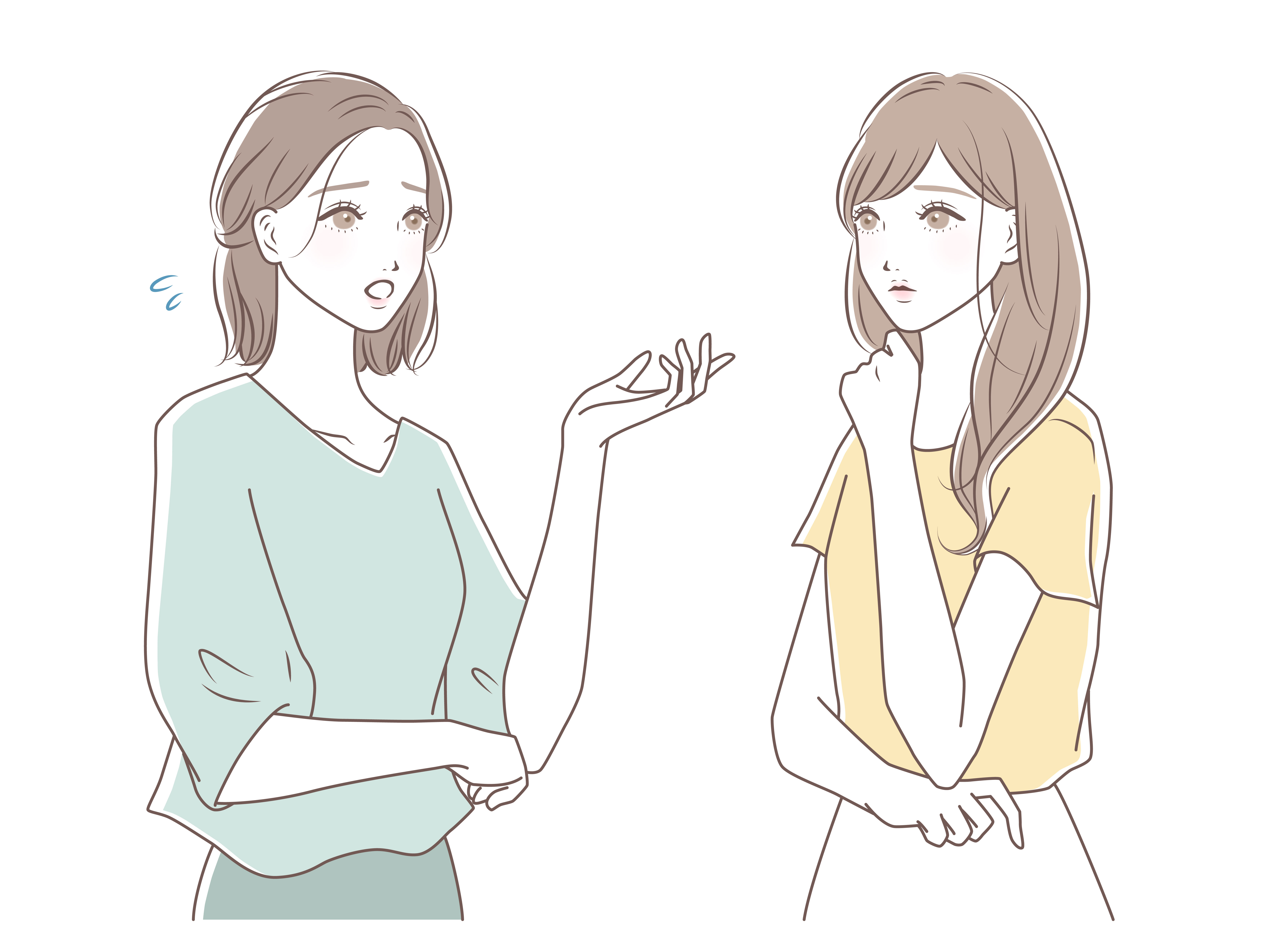
2.相手の言葉を否定しない
聞き役で大切なことは、相手の話を否定したり、遮ったりしないことです。少しでも自分の考えと違うと「それは違います」と言って否定していると、相手に嫌な印象を持たれます。考えが違っていても「そうなんですね」と聞き流すようにしましょう。
聞き役で大切なことは、相手の話を否定したり、遮ったりしないことです。少しでも自分の考えと違うと「それは違います」と言って否定していると、相手に嫌な印象を持たれます。考えが違っていても「そうなんですね」と聞き流すようにしましょう。

3.話し過ぎない
聞き役に回っていても、相手から意見を求められることがあります。このような場合は、話し過ぎに気を付けましょう。つい興味のある話題になると言いたいことが次々とこみ上げてくることがあります。自分に興味があるものを、他人も興味があるとは限りません。いつもだいたいの時間の目安をつくっておいて、話し過ぎないように気を付けましょう。「沈黙は金、雄弁は銀」という言葉もあります。
聞き役に回っていても、相手から意見を求められることがあります。このような場合は、話し過ぎに気を付けましょう。つい興味のある話題になると言いたいことが次々とこみ上げてくることがあります。自分に興味があるものを、他人も興味があるとは限りません。いつもだいたいの時間の目安をつくっておいて、話し過ぎないように気を付けましょう。「沈黙は金、雄弁は銀」という言葉もあります。
4.笑顔
コミュニケーションに自信がないと、顔を横に向けたまま話したり、目を合わせずに伏し目がちになります。それが相手にマイナスのイメージを持たせてしまいます。できるだけ相手の顔を見るようにしましょう。また、笑顔でいるのも、相手に良い印象を与えるための大切な秘訣です。家にいる時に、鏡を見ながら軽く口角を上げてみて、自然な笑顔の練習をしてみましょう。
コミュニケーションに自信がないと、顔を横に向けたまま話したり、目を合わせずに伏し目がちになります。それが相手にマイナスのイメージを持たせてしまいます。できるだけ相手の顔を見るようにしましょう。また、笑顔でいるのも、相手に良い印象を与えるための大切な秘訣です。家にいる時に、鏡を見ながら軽く口角を上げてみて、自然な笑顔の練習をしてみましょう。

5.悪口を言わない
人の悪口を言うと、悪口を言った人の印象が悪くなってしまいます。悪口は聞いていて気持ちの良いものではないからです。また、聞いた人の意地が悪いと、「あの人が悪口を言ってたよ」と言いふらすこともあります。人前で他人の悪口は言わないようにしましょう。
人の悪口を言うと、悪口を言った人の印象が悪くなってしまいます。悪口は聞いていて気持ちの良いものではないからです。また、聞いた人の意地が悪いと、「あの人が悪口を言ってたよ」と言いふらすこともあります。人前で他人の悪口は言わないようにしましょう。
6.怒らない
少しでも否定されると怒ってしまう人がいます。怒られて気持ちの良い人はいません。すぐ怒る人は嫌われます。イラっとしてもその場で怒ることは避けましょう。怒りがこみ上げてきても数秒間グッとこらえると、怒りのピークは過ぎ去ります。
ただし、自分の力で怒りをコントロールできていない場合は、「易怒性(いどせい)」という精神症状かも知れません。治療方法があるので、カウンセリングや精神科を訪ねてみましょう。
少しでも否定されると怒ってしまう人がいます。怒られて気持ちの良い人はいません。すぐ怒る人は嫌われます。イラっとしてもその場で怒ることは避けましょう。怒りがこみ上げてきても数秒間グッとこらえると、怒りのピークは過ぎ去ります。
ただし、自分の力で怒りをコントロールできていない場合は、「易怒性(いどせい)」という精神症状かも知れません。治療方法があるので、カウンセリングや精神科を訪ねてみましょう。
7.無理をしない
嫌われないように相手に合わせて気を遣いすぎると疲れてしまいます。職場で毎日会うような人ならば、次に会うのが辛くなります。心をすり減らしてまで、好かれる必要はないでしょう。無理をして好かれるよりは、嫌われても自分の心を守ることが大切です。意見をふられても、分からなければ、「分かりません」で良いし、無理に話題に入らなくても良いでしょう。
そもそも相手に気を遣わせてしまう人の方に問題があります。こちらと気持ちよく付き合う気のない人とは距離を置きましょう。それがもし職場で毎日会う人ならば、できるだけコミュニケーションを避けて、最低限のやり取りだけで終わらせるのが賢い方法です。
嫌われないように相手に合わせて気を遣いすぎると疲れてしまいます。職場で毎日会うような人ならば、次に会うのが辛くなります。心をすり減らしてまで、好かれる必要はないでしょう。無理をして好かれるよりは、嫌われても自分の心を守ることが大切です。意見をふられても、分からなければ、「分かりません」で良いし、無理に話題に入らなくても良いでしょう。
そもそも相手に気を遣わせてしまう人の方に問題があります。こちらと気持ちよく付き合う気のない人とは距離を置きましょう。それがもし職場で毎日会う人ならば、できるだけコミュニケーションを避けて、最低限のやり取りだけで終わらせるのが賢い方法です。
