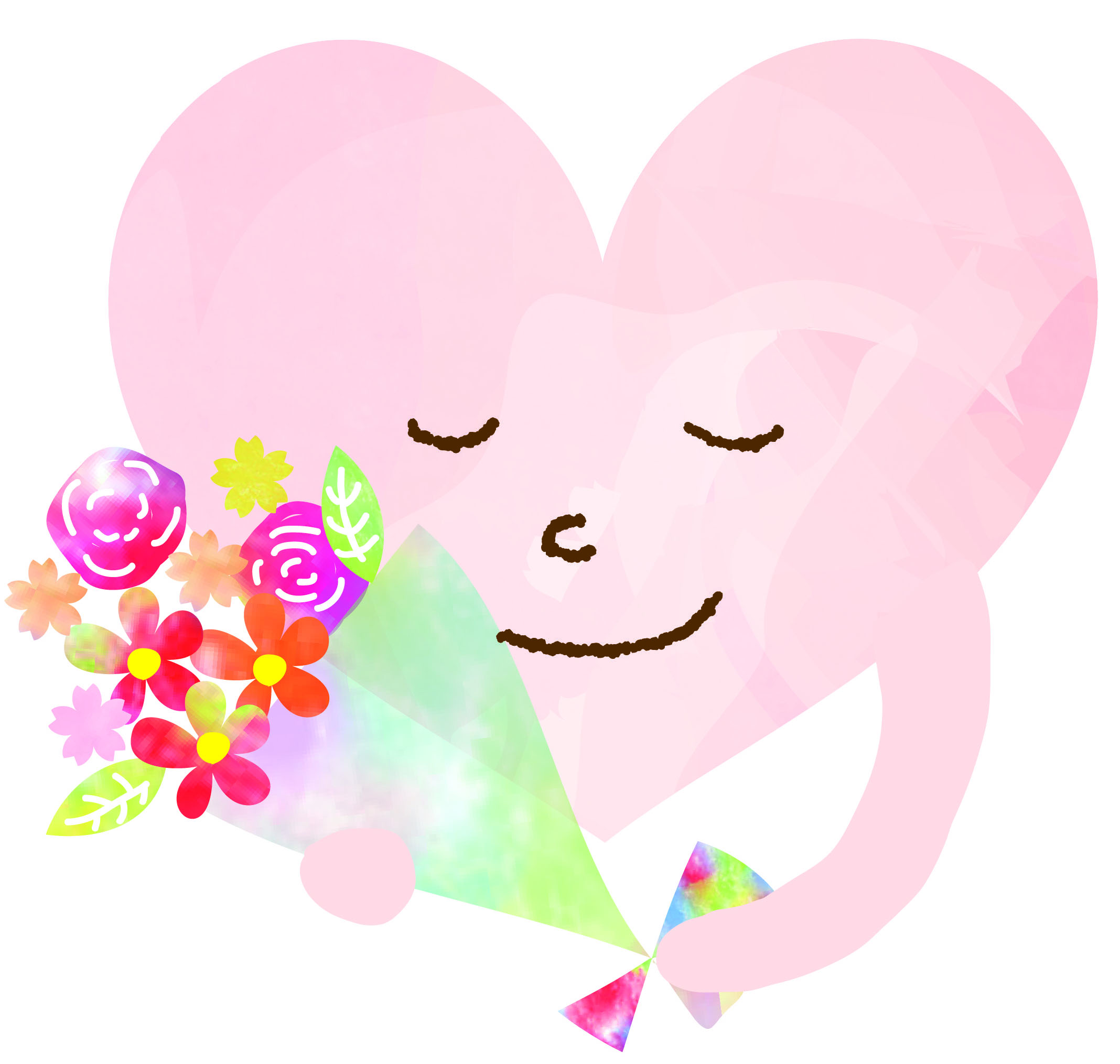良い子症候群の4つのサイン
親は、子供に向かって「良い子になりなさい」という言葉をよく使います。一般的に良い子とは、「大人しくて、育てやすい子」「親のいうことを聞く優しい子」といった意味で使われます。
「良い」というのは、あくまでも親の視点からですので、親の目をいつも意識して、親の期待を裏切らない子が良い子なのです。ところが、良い子が大人になると、そのまま親や周りの人にとっての良い人を続けることがあります。いつも周りの目を意識して、その期待を裏切らないように努力してしまうのです。
このような人の心の中は、自分を主張することに不安を感じており、顔色を見て人に合わせることで安心を感じていることがあります。いつのまにか他人にとって都合の良い人となり、自分の幸せがなくなっているのです。このような生きづらさを感じる場合を「良い子症候群」と呼びます。
今回は、良い子症候群のサインを4つ紹介しましょう。

1. いつも人にどう思われているかを気にする
人と接する時は、何よりも自分の評価を気にしてしまいます。嫌われずに、良く思われることに大きなエネルギーを使ってしまうのです。このような心の癖は、素直な性格が土台にあるのですが、親子関係が大きな影響を与えています。
親によっては、子供の存在そのものを愛するのでなく、勉強ができるから愛する、容姿が良いから愛する、など、子供に注ぐ愛情が条件付きの場合があります。また、親の情緒が不安定で、機嫌を損ねると怒りを爆発させるような場合でも、子供はいつも親の顔色をうかがって生活するようになります。
このように親から注がれる愛情が偏っていると、「親の願う良い子でいると愛される、良い子でいないと愛されない」という心の癖が身についてしまいます。この癖が抜けないままに大人になったのが、良い子症候群なのです。親子の情的関係を愛着と呼びますが、良い子症候群には愛着の問題が関わっているのです。
2. 自分の考えをはっきりと持たない
人間関係はいつも受け身で、職場では指示待ちです。周りにどう思われるのかが心配で、自分で判断することができないのです。しかし、言われたことに対しては全力でこなし、最高の結果を出そうとします。
実はこのような生き方は、封建時代、高度経済成長期には必要な生き方でした。権威ある人に従うことは、出世に必要ですし、終身雇用があったので一生を守ってもらえました。良い人でいることは、生きていく上で最も大切なことであり、一つの処世術でもあったのです。
ところが時代が変わり、人に主体性が求められる社会になりました。人に合わせる生き方では利用されるだけで、むしろ損をすることが多くなりました。良い人には、生きづらい世の中になったのです。
3. 争いを避けて自分の思いを押し殺す
争いを避ける平和主義者です。人と争うくらいのなら、「このままでいい」と思い、主張せずにあきらめます。自分の思いを押し殺してしまうのです。良い人は、我慢づよい人でもあり、自己否定ができる人です。
しかし、我慢は無限にできるものではありません。我慢の度がすぎると心がおかしくなってしまいます。聖職者、教師、医師などの厳しい倫理を求められる職業の人が、性的な犯罪や暴力の問題を起こすことがあります。これは我慢しすぎて心が爆発した結果です。

4 人にしたがって心を病む
自分を押し殺して働き続け、仕事を休みません。休むことは罪深いことだと感じます。人の期待に応えることが生きがいですから、そうできない状況では自分を責めてしまいます。
こうした生活が続くと徐々にストレスが溜まるようになりますが、そのために心身に異常が出ても気づきません。ついに、うつ病を発症したり、最悪の場合は、過労死、過労自殺という問題も起きてしまいます。
良い子症候群で生きづらさを感じているならば、良くない心の癖をもっていることを自覚しましょう。そして、自分の素直な気持ちを押し殺さずに大切にするようにしましょう。ストレスや疲れを感じ時には、無理をしないことも大切です。万が一、うつ病などの心の病気を発症してしまったら、今後の仕事の取り組み方について見つめ直すことも必要です。
親の願いの本質は、子供が幸せに生きることです。しかし、親が不幸な生い立ちから、偏った考えをもっていることがあります。親なりに子供を幸せにしようと思いながら、実は自分のいいなりにしようと間違った愛情を注いでしまうことが多いのです。
そのような親の間違った願いや価値観にそって生きていると、むしろ幸せになれません。人生の目的は、自分の持っている能力を生かして幸せになることです。自分が何に向いているのか、本当は何をしたいのか、素直な気持ちを大切にしましょう。