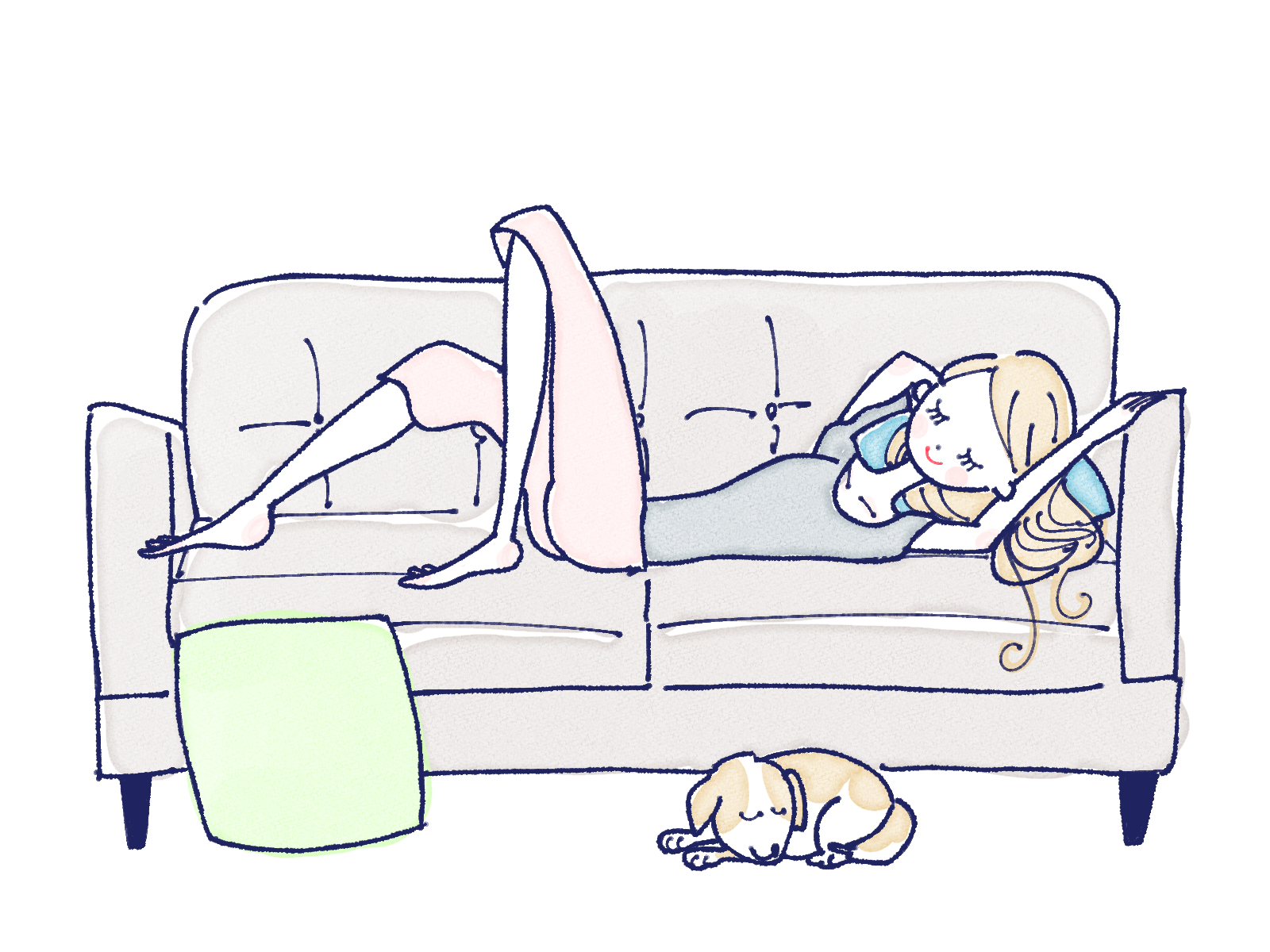難治性のうつ病とは
うつ病で、十分な薬の治療を2年以上行っても良くならない場合を、難治性(なんじせい)うつ病とか慢性うつ病と呼びます。
薬の治療はうつ病の人の7割に効果があります。薬で良くならない場合には、通電治療や磁気治療などの特殊な治療を行うと、さらに1割くらいの人に効果があります。しかし、残りの2割くらいの人は治療にも関わらず、症状が改善されずに難治性になります。現在でもかなり多くの人が難治性うつ病に苦しめられているのです。
今回は、難治性うつ病について説明しましょう。

1 薬を飲んで発病前と同じ生活が送れていれば難治性ではない
薬を飲んでいれば、仕事ができて日常生活が送れているならば難治性ではありません。
難治性とは、薬を飲んでも、発病前の生活に戻れない人を指します。「薬を飲むのをやめるまでは治ったことにならない」と考える人もいますが、抗うつ薬などの精神科の薬は長い期間でも服用できるので、焦らずゆっくり薬を減らしていけば良いのです。同じ薬で状態が安定しているなら薬への依存は心配ありません。

ただし、薬を減らすためには生活の見直しが必要です。現代社会において、ほとんどの病気の原因は自分の心身のキャパを越えた生活にあります。さらに、お酒やたばこなどの嗜好品の取り過ぎ、運動不足、不規則な生活も良くありません。背伸びをしなくては生きていけない時代ですが、病気をきっかけに無理のし過ぎを少しずつ改善させていきましょう。
10年、20年と薬を飲んでいても、現役を引退して薬をやめた人、ローンを返済できて薬をやめた人、よいパートナーと出会って薬をやめた人、など、生活が改善されて薬が必要なくなった人はたくさんいます。長く飲んでいても、薬はやめることができるのです。
10年、20年と薬を飲んでいても、現役を引退して薬をやめた人、ローンを返済できて薬をやめた人、よいパートナーと出会って薬をやめた人、など、生活が改善されて薬が必要なくなった人はたくさんいます。長く飲んでいても、薬はやめることができるのです。

2 治りにくいうつ病がある
現在のうつ病の診断の方法は、発病の原因は考慮せず、いくつかの症状がある場合をうつ病と呼ぶことになっています。例えば、ストレスが原因でうつ症状が出た人も、生まれつきの発達障害が原因でうつ症状が出た人も、出産後のホルモンバランスの影響でうつ症状が出た人も、同じうつ病と診断されます。
ですから、うつ病は一つの病気というよりも、いくつかの病気をまとめた症候群のようなものです。発達障害が基礎にあったり、産後うつ病などは長期化しやすいと言われています。同じうつ病でも、治りやすい場合と治りにくい場合があるのです。
現在のうつ病の診断の方法は、発病の原因は考慮せず、いくつかの症状がある場合をうつ病と呼ぶことになっています。例えば、ストレスが原因でうつ症状が出た人も、生まれつきの発達障害が原因でうつ症状が出た人も、出産後のホルモンバランスの影響でうつ症状が出た人も、同じうつ病と診断されます。
ですから、うつ病は一つの病気というよりも、いくつかの病気をまとめた症候群のようなものです。発達障害が基礎にあったり、産後うつ病などは長期化しやすいと言われています。同じうつ病でも、治りやすい場合と治りにくい場合があるのです。

また、難治性の大きな原因の一つに、生きることへの絶望があります。大切な人や物を失う、信頼していた人から裏切られる、大きな事故や事件に合う、など避けがたい不幸が重なり、生きていくエネルギーがなくなってしまうのです。絶望感からうつ病になり、うつ病がまた絶望感をつくり、そのサイクルから抜け出せなくなってしまいます。
こうした場合、「希望を持ちましょう」と言われても、そんなに簡単に楽観的になれません。時間が問題を解決してくれるのを待つしかない場合もあります。
こうした場合、「希望を持ちましょう」と言われても、そんなに簡単に楽観的になれません。時間が問題を解決してくれるのを待つしかない場合もあります。
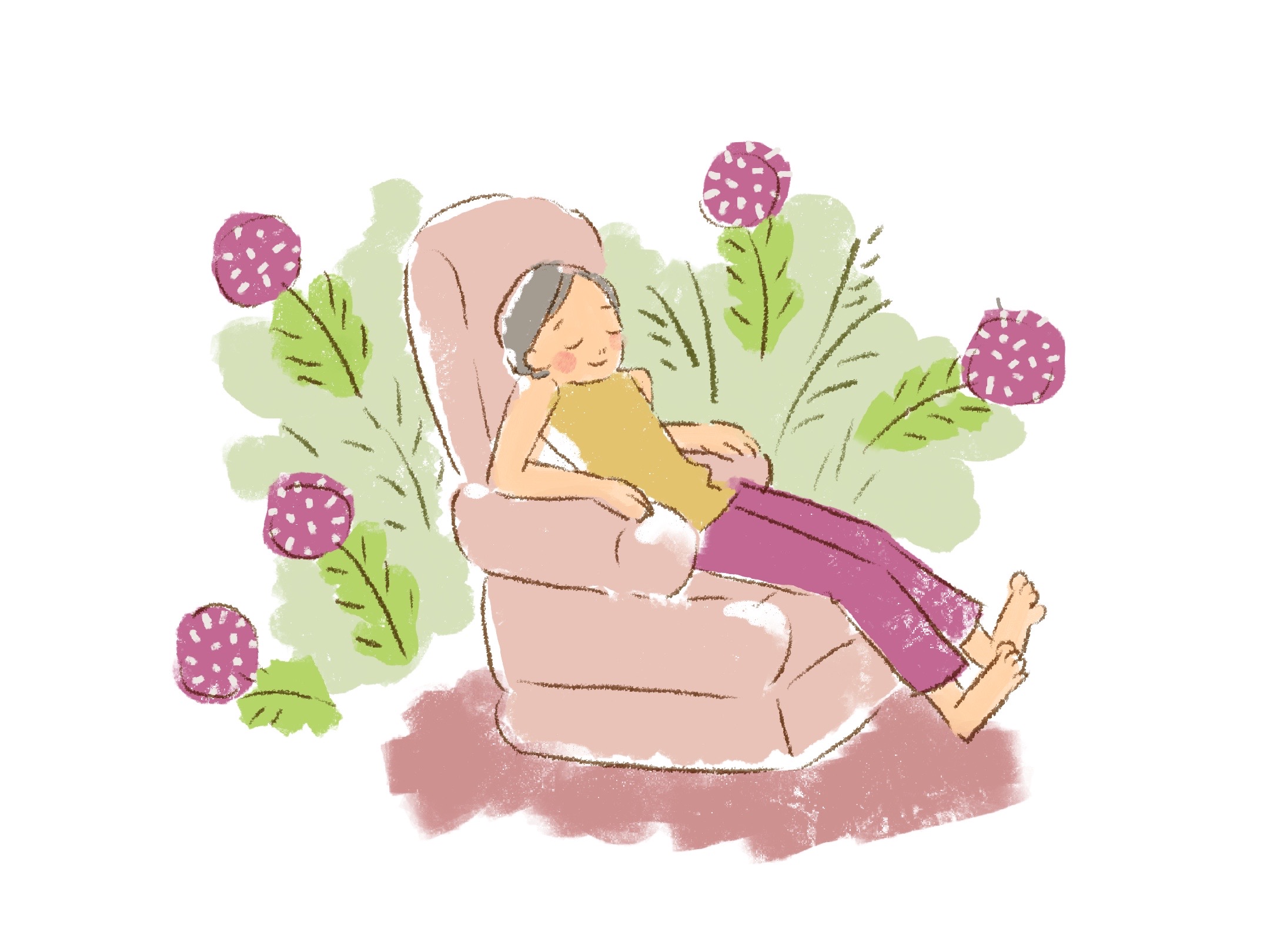

3 難治性の人はどうなるか?
ずっと寝たきりで一生を過ごすようなことはありません。障害年金や生活保護などの経済的な援助を受けて、少しずつ改善していく人が多いようです。見た目は元気がないだけで普通なために、福祉の援助を受けていることを負債に感じる人もいますが、うつ病は脳の機能が弱ってしまう病気です。決して怠けているのではありません。公的な援助を受けながらゆっくり回復を持ちましょう。

うつ病はまだ十分に解明されていない病気ですから、予期していなかった何かのきっかけで良くなることがたくさんあります。10年近くほとんど寝たきりに近い状態でも、家族関係に変化が起きて良くなること、病院を変えて新しい主治医との相性で良くなること、簡単な仕事を少しずつ手伝って良くなること、など色々なケースがあります。

4 難治性うつ病の治療は進歩している
20年くらいから前から難治性うつ病が注目されるようになり、その治療も少しずつ進んでいます。以前は医療側に問題があったのも事実です。治らないからと言って、同じような薬を重ねて処方する多剤投与がありました。
また、双極性障害Ⅱ型を難治性うつ病と診断してしまい、治療がこじれることもありました。こうした医原性の問題は、現在では解決されつつあります。また、難治性うつ病に有効な薬の使い方も工夫されており、治療は日々進歩しています。
20年くらいから前から難治性うつ病が注目されるようになり、その治療も少しずつ進んでいます。以前は医療側に問題があったのも事実です。治らないからと言って、同じような薬を重ねて処方する多剤投与がありました。
また、双極性障害Ⅱ型を難治性うつ病と診断してしまい、治療がこじれることもありました。こうした医原性の問題は、現在では解決されつつあります。また、難治性うつ病に有効な薬の使い方も工夫されており、治療は日々進歩しています。

5 とりあえず好きなこと・楽しいことからやってみましょう
病気のことばかりを考えることは良くありません。病気を早く治そうと焦らずに、むしろ病気から意識を離すようにしましょう。そのためには、気軽にできる楽しいこと、好きなことから始めましょう。音楽、ゲーム、ペットを飼う、物作り、スポーツなど、少しでも「生きていて良かったな」と感じられることに出会えたら良いでしょう。
病気のことばかりを考えることは良くありません。病気を早く治そうと焦らずに、むしろ病気から意識を離すようにしましょう。そのためには、気軽にできる楽しいこと、好きなことから始めましょう。音楽、ゲーム、ペットを飼う、物作り、スポーツなど、少しでも「生きていて良かったな」と感じられることに出会えたら良いでしょう。