うつ病で療養中の人に言ってはいけないこと
心の病気を治すために必要なものは何でしょうか?病院、薬、支えてくれる人など、いろいろなことが思いつきますが、実は最も大切なものは安心感です。
仕事の心配、お金の心配、将来の心配のために、生活に安心感がなければ治るものも治りません。名医とは、何よりも安心感を与えてくれる人とも言えるでしょう。体を維持するためには空気を吸わなくてはならないように、心にとっての空気が安心感です。これがなければ心の自然治癒の力も働きません。
ですから、療養中の人に接する場合、家族、職場の人たちは、何よりも安心感を与えてあげるべきです。ところが、昔から心の病気は、「怠け」と見られてしまう傾向があります。病気で何もできずに苦しんでいるのに、家族や職場の人から、「頑張れ」、「努力しろ」と言われてしまうと、針のむしろの状態になってしまいます。
風邪で熱が出て苦しんでいるのに、「運動したら治るよ」なんて言う人はいません。しかし、心の病気に関しては、言ってはいけないこと、やってはいけないことが普通に行われてしまうのが現実です。良かれと思って、病気の人を苦しめていることが多いのです。
それでは、家族や職場の人はどんなことを言ったり、やったりしてはいけないのでしょうか?今回は、特にうつ病で療養中の人に言ってはいけないこと、やってはいけないことを6つ紹介しましょう。
仕事の心配、お金の心配、将来の心配のために、生活に安心感がなければ治るものも治りません。名医とは、何よりも安心感を与えてくれる人とも言えるでしょう。体を維持するためには空気を吸わなくてはならないように、心にとっての空気が安心感です。これがなければ心の自然治癒の力も働きません。
ですから、療養中の人に接する場合、家族、職場の人たちは、何よりも安心感を与えてあげるべきです。ところが、昔から心の病気は、「怠け」と見られてしまう傾向があります。病気で何もできずに苦しんでいるのに、家族や職場の人から、「頑張れ」、「努力しろ」と言われてしまうと、針のむしろの状態になってしまいます。
風邪で熱が出て苦しんでいるのに、「運動したら治るよ」なんて言う人はいません。しかし、心の病気に関しては、言ってはいけないこと、やってはいけないことが普通に行われてしまうのが現実です。良かれと思って、病気の人を苦しめていることが多いのです。
それでは、家族や職場の人はどんなことを言ったり、やったりしてはいけないのでしょうか?今回は、特にうつ病で療養中の人に言ってはいけないこと、やってはいけないことを6つ紹介しましょう。
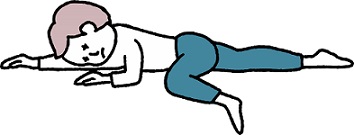
1 説教する
うつ病ほど誤解されやすい病気はありません。元気がないのは、「気の持ちようだ」と思っている人もたくさんいます。確かに、認知療法という、うつ病の人の考え方に働きかける治療があります。
勘違いする人もいますが、認知療法はプラス思考にさせる治療法ではありません。ものの捉え方を心理学では認知と呼び、一部のうつ病の患者さんに、ネガティブな情報ばかりを集めやすい認知の偏りがあることが知られています。これを、客観的な認知を学ぶことで改善させていくものが認知療法です。強制的に考え方を変えるような治療ではありません。
そもそも、うつ病とは、生きるエネルギーが枯れ果ててしまい、プラス思考になれない病気です。「気の持ち方を変えなさい」と説教されてもできる訳がありません。足の骨が折れているのに、「歩きなさい」と言っているようなものです。
2 強要する
うつ病は、現代病の代表になったので、その情報がネットにたくさん溢れています。しかし、根拠のない情報もたくさんあります。病院では、調査で証明されている確実な治療だけを提供しています。
健康保険が使えないものは、一部に効く人がいても、確実性がありません。安易にサプリメントを紹介するなど、「これで治るらしいよ」と不確かなことを強要するのは避けましょう。
3 追い詰める
うつ病は、病気でなく「甘え」だと思っている人がいます。人は追い詰められたら、本気を出すとばかりに、追い詰められたら病気も良くなると勘違いしている人が多いのです。うつ病は生きるエネルギーがなくなっている状態なので、追い詰められても、そのまま何もできないか、逃げ出すことしかできません。
実際によくある話ですが、死にたいと訴える人に向かって、「死ねるものなら死んでみろ」「死ねる勇気があるなら頑張ってみろ」と言う人もいます。それで本当に自殺してしまう人もいます。うつ病は「甘え」でなく、病気です。うつ病の人を追い詰めることは、決してしてはいけません。

4 焦らせる
何カ月も療養していると、家族からこんな言葉が出ることがあります。「いつ治るの?」「学校どうするの?」「そろそろ仕事をしたら」。家族も心配しての言葉ですが、一番焦っているのは病気をしている本人です。
うつ病からの回復には数カ月、人によっては年単位に必要な人もいます。十分に回復しない状態で、焦って仕事や学校に戻れば、すぐに悪くなってしまいます。むしろ、「焦らなくてもいいよ」とブレーキをかけてあげることが大切です。
5 無関心
療養中は、自宅でゆっくりしているのが一番良いのですが、孤独はよくありません。みんなから忘れられてしまうのも辛いことです。
特に、「医者が何とかしてくれるだろう」と、家族が無関心でいるのはよくありません。少しでも言葉をかけてあげたり、短い時間でも話を聞いてあげることが回復への力になります。
6 薬をやめさせる
うつ病は、脳の神経伝達物質であるセロトニンの分泌が少なくなる病気です。抗うつ薬で調整することで回復に向かいます。また、十分な睡眠が必要なため、睡眠薬を使うこともあります。
これらの薬は大きな副作用はなく、もちろん麻薬ではないので、依存症になることもありません。こうした薬は世に出て60年以上が経ちますが、大きな問題なく今に至っています。
ところが、「いつまでも薬に頼っていてはダメになる」、「薬は体に悪い」とそれをやめさせようとする人もいます。薬の処方は、専門家の主治医に任せましょう。
うつ病は気持ちの問題ではありません。生きるエネルギーがなくなり、脳の活動も弱っている状態です。薬で脳の神経伝達物質を調整し、ゆっくり休むことで少しずつ回復していきます。「ダラダラしているから治らない」「好きなことばかりしているから治らない」ということはありません。家族や職場の人は、暖かく見守りながら、自然な回復を待ってあげましょう。そして、安心できるような言葉をかけてあげましょう。

