こころが疲れているときに現れる10個のサイン
心配事が絶えず、やらなくてはならない事が多いと、休んでいるつもりなのに、頭の中を色々な思いがグルグル回っています。眠ろうとしても、なかなか寝つけません。朝早くから目が覚めてしまうこともあります。これは、「心の疲れ」とか、「精神疲労」と呼ばれるものです。
脳の使い過ぎにより、脳が常に目覚めた状態になっているのが原因です。脳は本来、活動と休息を切り替えることが大切なのですが、頭を使うことが多すぎると、常に活動している状態になってしまいます。これを「覚醒状態」と呼びます。
覚醒と言っても、集中力が上がって効率よくできる状態ではなく、目覚めているのに疲れているというアンバランスな状態です。例えれば、充電が切れかけたスマホを、無理やり使っているような感じです。
心の疲れは少しずつ蓄積していきます。やらなくてはならないことがあり、まだまだ頑張れると思っていても、すでに限界になっていることもあります。そんな時、心はいろいろな形でSOSのサインを出しています。仕事への義務感から心の悲鳴を聞き逃すことがないようにしましょう。放っておくと、うつ病などの病気になる危険性があります。
今回は、心のSOSのサインを見逃さないように、あなたの心が疲れている10個のサインをご紹介します。
脳の使い過ぎにより、脳が常に目覚めた状態になっているのが原因です。脳は本来、活動と休息を切り替えることが大切なのですが、頭を使うことが多すぎると、常に活動している状態になってしまいます。これを「覚醒状態」と呼びます。
覚醒と言っても、集中力が上がって効率よくできる状態ではなく、目覚めているのに疲れているというアンバランスな状態です。例えれば、充電が切れかけたスマホを、無理やり使っているような感じです。
心の疲れは少しずつ蓄積していきます。やらなくてはならないことがあり、まだまだ頑張れると思っていても、すでに限界になっていることもあります。そんな時、心はいろいろな形でSOSのサインを出しています。仕事への義務感から心の悲鳴を聞き逃すことがないようにしましょう。放っておくと、うつ病などの病気になる危険性があります。
今回は、心のSOSのサインを見逃さないように、あなたの心が疲れている10個のサインをご紹介します。

1 悪夢
心の疲れをとるためには、何よりも十分な睡眠が必要です。ところが、脳が覚醒状態のために睡眠の質が悪くなります。眠っていても、夢ばかりで疲れがとれません。特に悪夢が多くなります。夢の内容は、現実の嫌な場面がそのまま出てきたり、過去の辛かった思い出です。疲れが、象徴的な内容で現れることもあります。例えば、「戦争や犯罪者に追われる」、「家や車が壊れる」、「高いところから落ちる」、「洪水にのまれる」、「たくさんの虫に襲われる」、などの夢は、心が不安定である証拠です。変わったところでは、「歯が抜ける」という夢も、国や人種に関係なく、心が疲れた時に見る夢です。
2 ネガティブ
覚醒状態とは、脳が常に危険に注意を払っている状態です。いつ獣(けだもの)に襲われるかドキドキしながら、1日中ジャングルの中をさまよっているようなものです。ちょっとしたことでも心配になり、不安感に襲われます。良いことがあっても、「どうせダメになるに違いない」と、悪い側面しか目に入りません。
3 イライラ・怒りっぽい
情緒が不安定になるため、些細なことでイライラします。すぐに人を叱ったり、怒ってしまい、職場や家庭の雰囲気を悪くしてしまいます。
突然涙がこみあげてくることもあります。ちょっとした言葉がスイッチになり、悲しい感情が襲ってきて、涙が出てくるのです。
4 大事なことを先延ばしにする
脳は覚醒していても、脳の活動自体は弱っているので、気力が出ません。大事な仕事をやらなくてはならないのに、気持ちが乗らずに先延ばしにします。「すぐにやって欲しい」と頼まれても、何度もトイレに立ったり、スマホをいじってみたりで、なかなか取り掛かることができません。
家庭でも同じで、部屋の片付けも後回しになります。流しに汚れた皿が山積みになっていたり、脱いだ服がそのままであったり、いつかやろうと思っていても、気がつくと部屋に足の踏み場がなくなっています。
5 集中できない・うっかりミス
集中力が落ちるため、入力の間違い、誤字や脱字、計算の間違い、など、ちょっとしたミスが増えます。
書類や本などの文字に集中しようとしても、頭に入ってきません。周りの音に敏感になり、ドアの開け閉めの音、人の足音、子供の声など、それまで気にしなかった音でも不快に感じ、集中が妨げられるようになります。
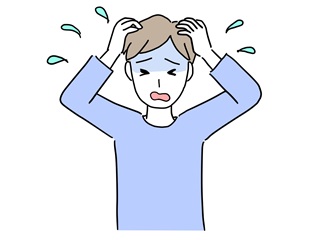
6 物忘れ
脳の働きが弱るため、物忘れが増えます。歯医者や美容院の予約を間違えたり、仕事の約束を勘違いして、大失敗してしまうかも知れません。スマホや財布を電車の中に置き忘れたり、人の名前や暗証番号を思い出せなくなることもあります。認知症になったのかと慌てる人も多いのですが、その前に心が疲れていることを疑いましょう。
7 体調不良
心の疲れは体にも現れます。代表的なものが自律神経の失調です。動悸や息苦しさを感じるようになり、心臓の病気かと不安になる人もいるでしょう。
免疫力も落ちるので、風邪をひきやすかったり、長引いたりもします。また、アレルギーによる喘息や皮膚のトラブルも増えるでしょう。
8 コリや痛み
心の疲れから、肩こり・腰痛・頭痛などの痛みが出ることがあります。神経の緊張から血の巡りが悪くなり、それがコリや痛みになるのです。検査をしても異常がないため、痛み止めで我慢するしかありません。マッサージを受けて良くなっても、一晩寝ると痛みが戻ってきます。
9 食べられない・食べ過ぎる
自律神経の失調から、食欲がなくなり、人によっては吐き気を感じます。病院で検査をしても大きな異常がない場合は、心の疲れが原因かも知れません。
これとは逆に、過食になることもあります。特に、味の濃いスナックやスイーツをたくさん食べたくなるのは、アルコールやタバコと同じような効果があるためです。
10 嗜好品が増える
アルコールやタバコには、心の疲れを一時的におさめてくれる効果があります。しかし、切れてくると、よけいに疲れを感じるので、量がどんどん増えて行くでしょう。これは、無意識のうちに、心の疲れを嗜好品で誤魔化しているサインです。

心が疲れている10のサインを紹介しました。これらは、あなたの脳が覚醒状態である証拠です。こうした症状は、サプリを飲むとか、2~3日休んだら改善するというものではありません。1つでも思い当たるものがあれば、2週間以上の休みをとった方がよいでしょう。
長い休みがとれない場合は、できるだけ仕事を減らします。通常の6割くらいが目安です。これを「6割主義」と呼びます。
また、睡眠を大切に考え、寝床につく1時間前からは、スマホをいじらず、のんびりと過ごすようにしましょう。暴飲暴食やお酒の飲み過ぎに注意します。このような生活を続けることで、少しずつ脳の覚醒状態が改善されるはずです。
2週間以上も改善されず、仕事や日常生活に支障が出ている場合は、うつ病の可能性がありますので、精神科に相談してみましょう。

