ADHDの人の考え方
注意欠如多動症・ADHDの人の思考回路はとても独特です。ADHDには、不注意、多動性、衝動性の3つの症状がありますが、これらが考え方に影響しています。そこで、今回はADHDの人がどのような考え方をするのか解説していきましょう。
ADHDの人は、感情的で落ち着きのない人というイメージをもたれてしまい、誤解される傾向があります。しかし、その思考のパターンを理解すれば、周りの人とのすれ違いの原因を知ることができます。また、周りの人もADHDの人の言動を納得するきっかけになるでしょう。
ADHDの人は、感情的で落ち着きのない人というイメージをもたれてしまい、誤解される傾向があります。しかし、その思考のパターンを理解すれば、周りの人とのすれ違いの原因を知ることができます。また、周りの人もADHDの人の言動を納得するきっかけになるでしょう。

1. 連想ゲームのような思考
ADHDの人と会話をしていると、話題が次々と飛んでしまうことがあります。これは、会話の内容と関係なく、頭の中で新しい話題が連想ゲームのように次々と湧いてくるのが原因です。例をあげて説明しましょう。
「この間久しぶりに飲みに行って楽しかったんだ」と、共通の友人の話題をしていたかと思うと、突然「最近小麦粉が高くなってるよね」と話題が変わります。相手にとっては、友人の話題から全くつながりのない「小麦粉が高くなっている」話題に突然変わったのでビックリしますが、本人の頭の中では、友達と飲みにいって、行った帰りにラーメン屋に寄りそこで食べたラーメンが値上がりしていたので、小麦粉が高くなっている話題が出てきただけなのです。本人としてはつながりがある話題ですが、相手には理解できません。
いつもこんな感じであると、話についていく相手が疲れてしまいます。一つの話題で話している最中にも、頭の中で連想ゲームが始まってしまうのです。
ただし、この症状がつよい場合、例えば、次々と話題をかえて、マシンガンのように話す場合は双極症の可能性もありますので注意しましょう。
2. 遅刻したくないのに遅刻をする
遅刻癖はADHDの人によく見られます。何度失敗しても治りません。ADHDで遅刻の多い子供を観察していると、外出の時間がせまっているのに準備をしないでのんびり他のことをしています。出かけることよりも、今やっているゲームや遊びに意識が集中してしまい、外出のことがどこかへ飛んでしまうのです。
大人のADHDの人も同じような理由で遅刻をします。何を着て行こうか、忘れ物はないかと迷っているうちに、そこに意識が集中してしまい、肝心の出かける時間を逃してしまうといった感じです。このようにADHDの人は悪気があって遅刻しているのではありません。
3. 目先のことが優先で長期的なことが考えられない
ADHDの人は家計簿をつけられず、お金の収支を把握することが苦手です。例えば、欲しいと思ったら借金をしてでも買ってしまう衝動買いがあります。今月の生活費があと1000円しか残っていないのに、欲しかったバッグを見つけたらカードで借金して買ってしまいます。
普通の人ならば、今月1000円でどうやって生活するかが最優先ですが、ADHDの人の場合、欲しいものを見つけたらそれが最優先されるのです。「欲しい」という思いが頭の中を占領してしまい、残金1000円のことはどこかへ飛んでしまいます。さらに負債を増やしてしまうので後悔をしますが、その後も衝動に負けてしまい、同じ失敗を繰り返すことがあります。
ところが、ADHDの人の中には、この衝動性が行動力につながり、事業を成功させることがあります。スティーブ・ジョブスのように有名な経営者の中には、ADHDの人が多いのもこれが理由です。
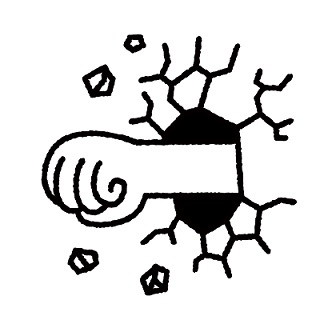
4. 興味のないことは手につかない
学校では、好き嫌い関係なくすべての教科を平均的に学ばなくてはいけません。ADHDの人は、興味の湧かないことに対しては、高いハードルを感じてしまい、「できない」と感じます。それでも頑張ってやろうと努力しても、全く頭に入って来ません。ですから、学校の成績にもムラができてしまいます。
大人になってからの仕事も同じです。興味の湧かないことには、やはり「できない」と感じて尻込みをしてしまいます。そして、無理やりやろうとしても集中ができません。イライラを感じる人や投げやりになる人もいます。大事なことが先延ばしになるということも起きます。
5. 余計なことを言ってしまう
つよい感情が湧いてきて理性で抑えられません。言うべきでないことを言ったり、手が出てしまうこともあります。後悔しますが後の祭りです。例えば、職場で上司の指示に「はい」と言っておけばよいことを、一言「それは違います」と余計なことを言ってしまい、職場の評価が下がってしまいます。
夫のちょっとした小言に「私は悪くない」と反発してしまい、大喧嘩に発展します。それを言ってしまうと、関係が壊れて大変な結果になると頭で分かっていても、言葉が先に出てしまうのです。
6. 集中し過ぎると他のことが入ってこない
何かに集中している時は、声をかけられても反応しないことがあります。これを過集中と呼びます。頭の中では、いまやっていることだけを考え続けているのです。疲れているのに、それを感じることなくやり続け、終わった後にどっと疲れを感じて数日寝込んでしまうこともあります。
2002年に韓国では、オンラインゲームに集中するあまり、80時間飲まず食わずでゲームに没頭し、エコノミー症候群で突然死をした24才の青年がいました。
逆に興味のないことには全く集中できません。感覚過敏は、ADHDの人にも見られることがあり、光や音の刺激や、頭の中に浮かぶイメージが、注意や思考の流れを乱します。大事な作業中でも、ちょっとした物音で集中が途切れたり、「そういえばドラマの新作いつ配信されるんだっけ?」「夕食何食べよう?」といった考えが浮かんで、手が止まったりもします。

以上、ADHDの人の考え方について紹介しました。今回の内容がすべてのADHDの人に当てはまるわけではありませんが、「そういえばこんな感じかな」と似ている項目があるかも知れません。どれも不注意や衝動が抑えられないという脳の構造から来ていることですが、人間関係で損をしている人がたくさんいます。
我慢すれば良いものを、余計なことを言ってしまったことから出世を逃した、離婚になった、という話もよく聞きます。しかし、自分の特性を理解することで、若干の改善も期待できます。また、思いっきりの良さから大成功を収める人もいますので、「災い転じて福となす」と考えましょう。

