うつ病の思考
人は不思議なもので、同じ出来事を経験しても人によって違った捉え方をします。例えば、マンションの上の階から大きな足音が突然聞こえた時に、全く気にしない人もいれば、「うるさい迷惑だ」と腹を立てる人、「何か事件があったのかな?」と不安になる人、「私がうるさいから怒っているのかな?」と自分を責めて考える人など様々です。
これは人がそれぞれ異なる考え方のパターンを持っているからです。心理学では、考え方のパターンを「考え方の鋳型」とか、「スキーマ」と呼びます。クッキーの生地を丸い鋳型に入れて焼けば、丸いクッキーになり、星型の鋳型に入れて焼けば、星型のクッキーになるのと同じです。目や耳から入る情報は、脳の中の考え方の鋳型に入れられ、その人の情報として加工されて結論が導きだされます。人はそれぞれに違う考え方のパターンをもっているので、同じ情報を手に入れても違った結論を導きだすのです。
先ほどの足音の話に戻ると、ネガティブな考え方のパターンを持っている人は怒りを感じたり、不安になったりしますが、ポジティブな考え方のパターンを持っている人は気にしないといった感じです。人によって、ネガティブやポジティブだけでなく、物事を素直に考えるパターン、深く原因を追究しようとするパターンなど、その人の特徴的な考え方のパターンがあるので、同じ経験でも人によって別の結論が出てしまうのです。
アメリカの精神科医アーロン・ベックは、うつ病の人には3つの特徴的な考え方のパターンがあることを発見しました。特にうつ病を若い時に発症した人、慢性化している人の場合は、うつ病を発症する前からこのパターンがあることが分かっています。
今回は、うつ病の人の特徴的な3つの思考パターンを紹介しましょう。これに気づくことで、うつ病の生きづらさを減らすヒントになるかも知れません。
これは人がそれぞれ異なる考え方のパターンを持っているからです。心理学では、考え方のパターンを「考え方の鋳型」とか、「スキーマ」と呼びます。クッキーの生地を丸い鋳型に入れて焼けば、丸いクッキーになり、星型の鋳型に入れて焼けば、星型のクッキーになるのと同じです。目や耳から入る情報は、脳の中の考え方の鋳型に入れられ、その人の情報として加工されて結論が導きだされます。人はそれぞれに違う考え方のパターンをもっているので、同じ情報を手に入れても違った結論を導きだすのです。
先ほどの足音の話に戻ると、ネガティブな考え方のパターンを持っている人は怒りを感じたり、不安になったりしますが、ポジティブな考え方のパターンを持っている人は気にしないといった感じです。人によって、ネガティブやポジティブだけでなく、物事を素直に考えるパターン、深く原因を追究しようとするパターンなど、その人の特徴的な考え方のパターンがあるので、同じ経験でも人によって別の結論が出てしまうのです。
アメリカの精神科医アーロン・ベックは、うつ病の人には3つの特徴的な考え方のパターンがあることを発見しました。特にうつ病を若い時に発症した人、慢性化している人の場合は、うつ病を発症する前からこのパターンがあることが分かっています。
今回は、うつ病の人の特徴的な3つの思考パターンを紹介しましょう。これに気づくことで、うつ病の生きづらさを減らすヒントになるかも知れません。

1 「自分は必要のない存在」
人の考え方のパターンは、子供の頃に経験してきたことの影響が大きいと考えられています。人生がずっとうまく行ってきた人は、何をやっても失敗しなかったので、物事を深く心配しません。常に気楽でポジティブな考え方のパターンが身に付きます。ところが、挫折が多かった人、失敗ばかりしてきた人は、用心深くなり、新しいことにチャレンジしようとしても、最初にうまく行かなくなることを考えます。常に慎重でネガティブな考え方のパターンを持つようになるのです。
子供の頃に人から大切にされた経験が少ない人は、「自分は必要のない人間だ」というネガティブな考え方のパターンが身についてしまいます。何か困ったことが起こった時に、「何とかしよう」という気持ちが起こらずに、必ず「私のせいでうまく行かない」、「私は迷惑な存在」と考えてしまい、気持ちが萎えてしまいます。これが重なることでうつ病を発病することになるでしょう。
このように、若い頃にうつ病を発症したり、慢性化したりする人には、「自分は必要のない存在」という考え方のパターンが染みついている場合が多いのです。
2 「世の中に味方はいない」
いじめを経験したり、信頼していた人から裏切られたりした経験があると、「世の中に味方はいない」、「人を信じてはいけない」という考え方のパターンが身についてしまいます。詐欺にあった後に、一時的に人を信じられなくなることがありますが、それが長く考え方のパターンとして残ってしまうのです。
周りを敵視することは、危険から身を守るために必要でもあるのですが、人間関係は広がりません。人と親しくなりそうでも、「いつか裏切るに違いない」と猜疑心をもって付き合うことになるので、自分から距離を縮めることができません。孤独になることも多く、そこからうつ病に発展することがあるでしょう。

3 「何をやってもうまく行かない」
子供の頃から失敗や挫折ばかりを経験していると、うまく行かないことが当たり前と考えるようになります。「何をやってもうまく行かない」という考え方のパターンが出来上がってしまうのです。例え良い出来事があっても、「どうせダメになるにちがいない」と心から喜ぶことができません。
未来のことはすべてネガティブに予測するので、新しいことに向かっていく気力が湧きません。その上、環境が変わる度に「悪いことが起こるに違いない」と心を消耗してしまい、うつ病になってしまうのです。
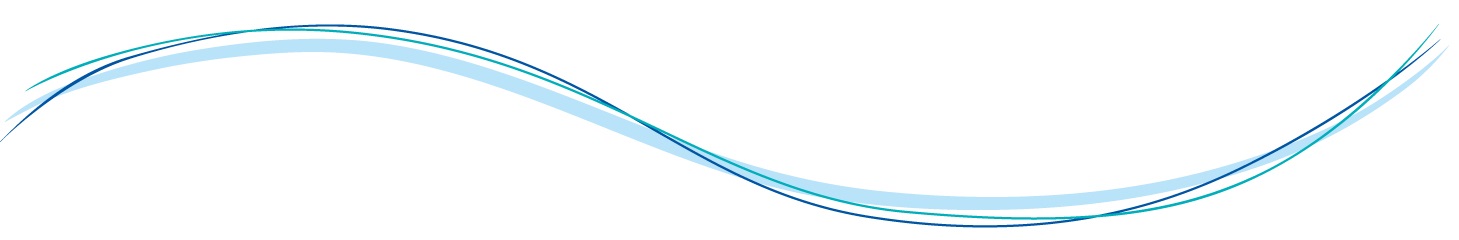
スマホやパソコンのやり過ぎで首の骨が変形してしまうことを「スマホっ首」と呼んでいます。ずっと前かがみの姿勢でいることから首の骨が逆の方向に曲がってしまい、首の痛みや肩こりを起こします。スマホっ首を治すには、マッサージを受けるのも大切ですが、自分でも姿勢を意識して生活することが大切です。
うつ病も同じで、若い頃からの辛い経験が考え方を歪ませてしまい、「自分は必要のない存在」、「世の中に味方はいない」、「何をやってもうまくいかない」という3つの考え方が癖になってしまい、これが原因でうつ病になってしまう人も多いのです。スマホっ首を治すためには、染みついた前かがみの姿勢を治さなくてはならないように、うつ病の人は、この3つの考え方が浮かんだ時には、「悪い考え方の癖が出た」と気づくようにしましょう。
世の中のあらゆる存在は自然の法則で繋がりあっているので、どんな人でも必要があって生まれてきています。決して「自分は必要のない存在」ではありません。広い世界にはあなたを必要としている人が必ずいるはずです。
また、世の中には自己中心な悪い人はたくさんいますが、思いやりのある優しい人もいます。これまでに良い出会いがなかっただけで、「世の中に味方はいない」ということはありません。これから良い人と巡り合えたならば、その出会いを大切にしましょう。
そして、人生でうまく行ったことが全くないという人であっても、深く思い出せば人から褒められたり、喜んでもらったりした経験はゼロではないはずです。こうした体験を思い返し、人に喜んでもらえる努力を少しずつ重ねていけば、必ず何らかの結果を残すことでしょう。
時間はかかりますが、こうした積み重ねをすることを通して、悪い考え方のパターンは修正されていくはずです。

