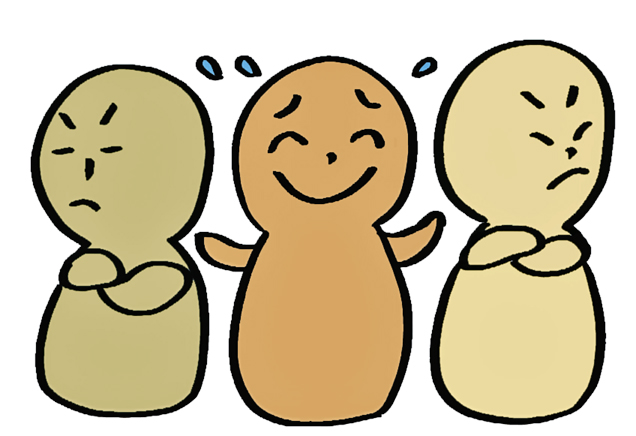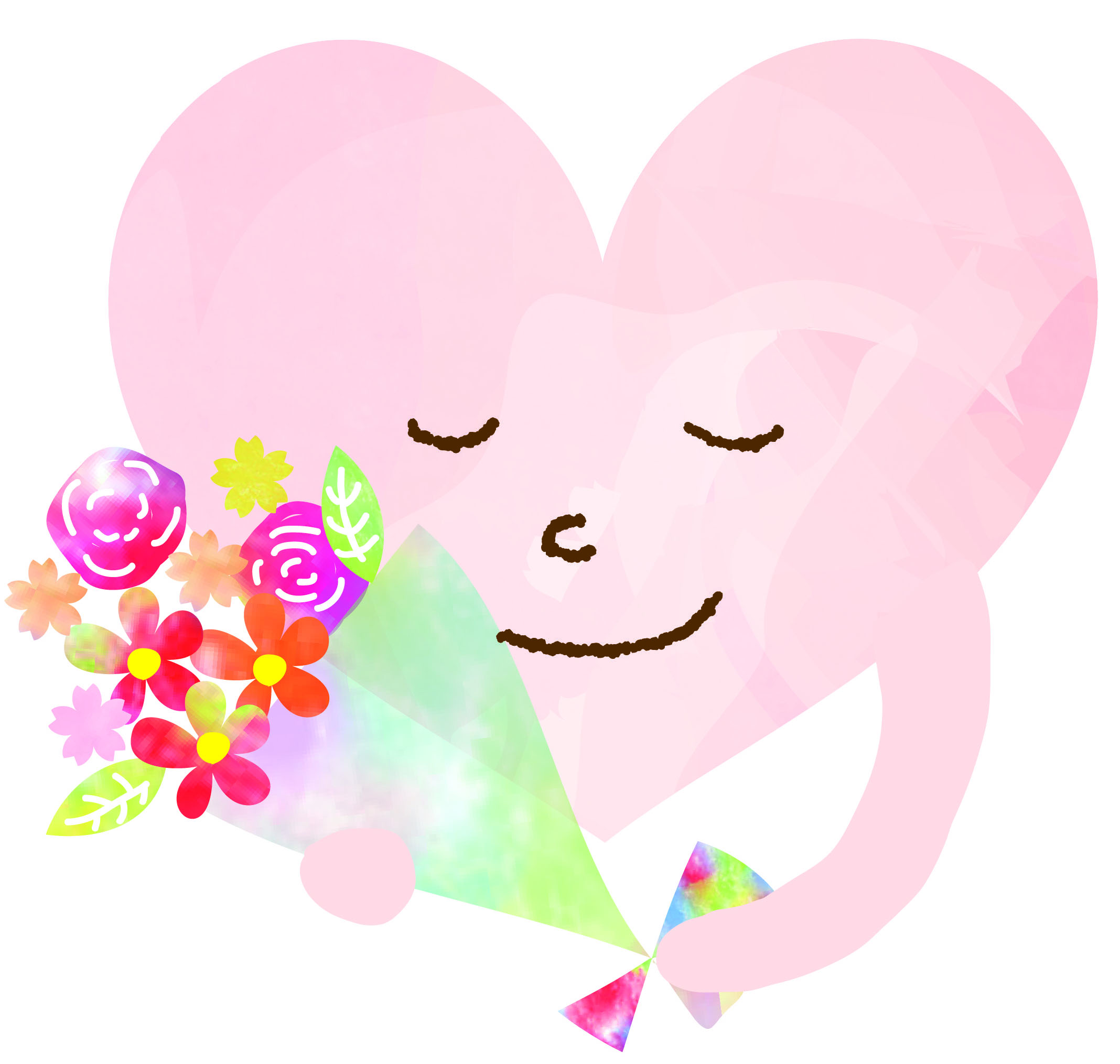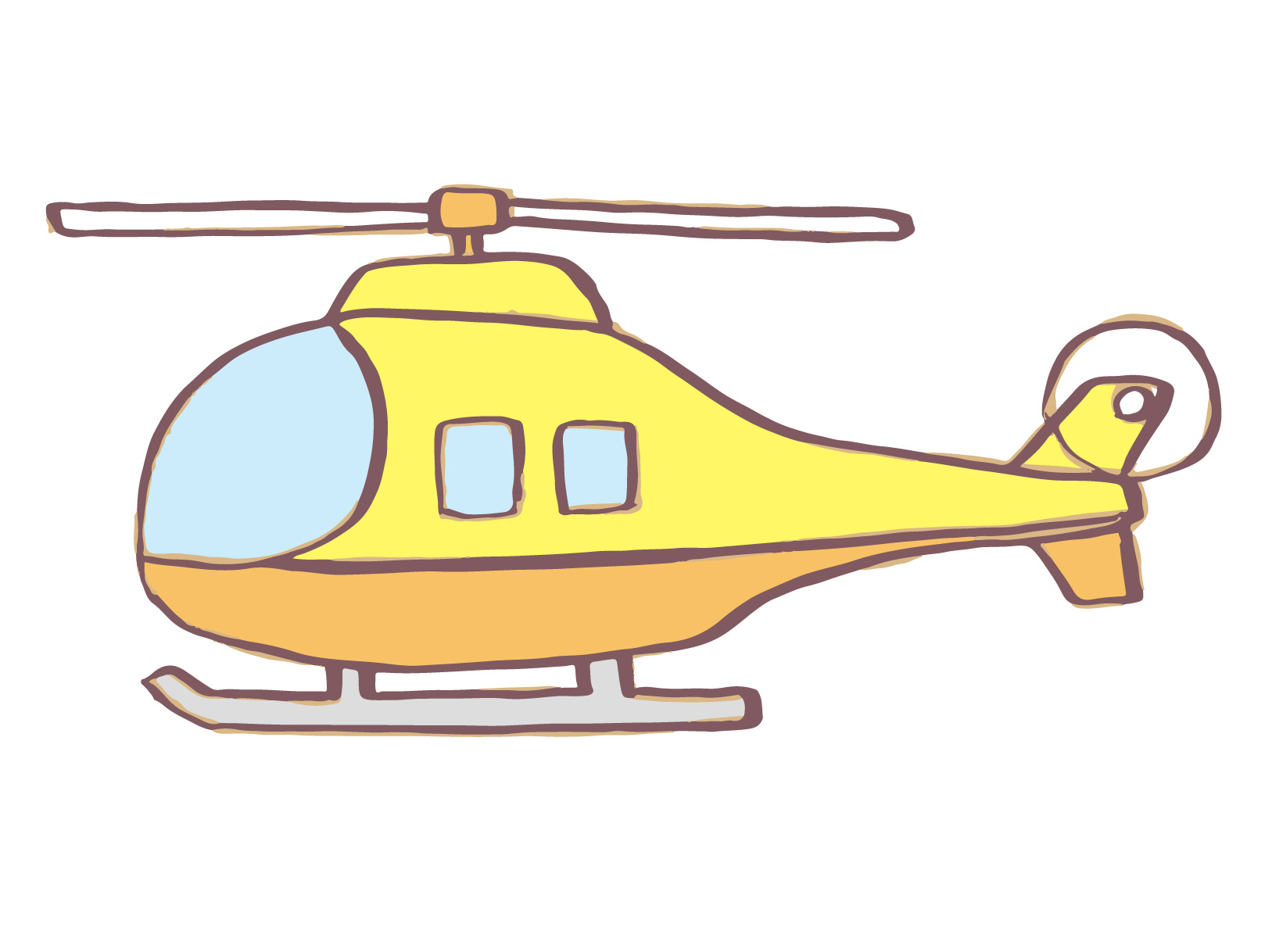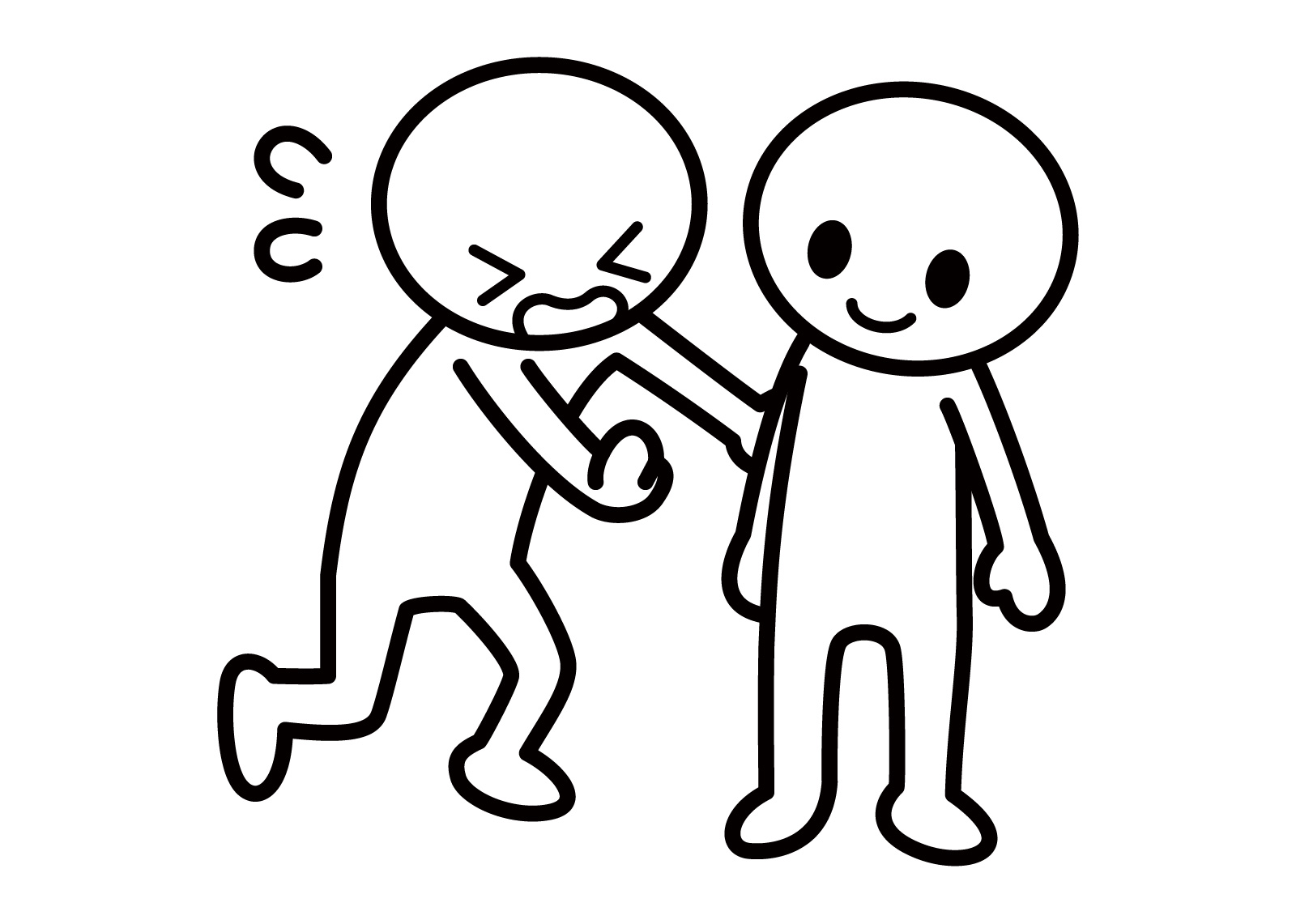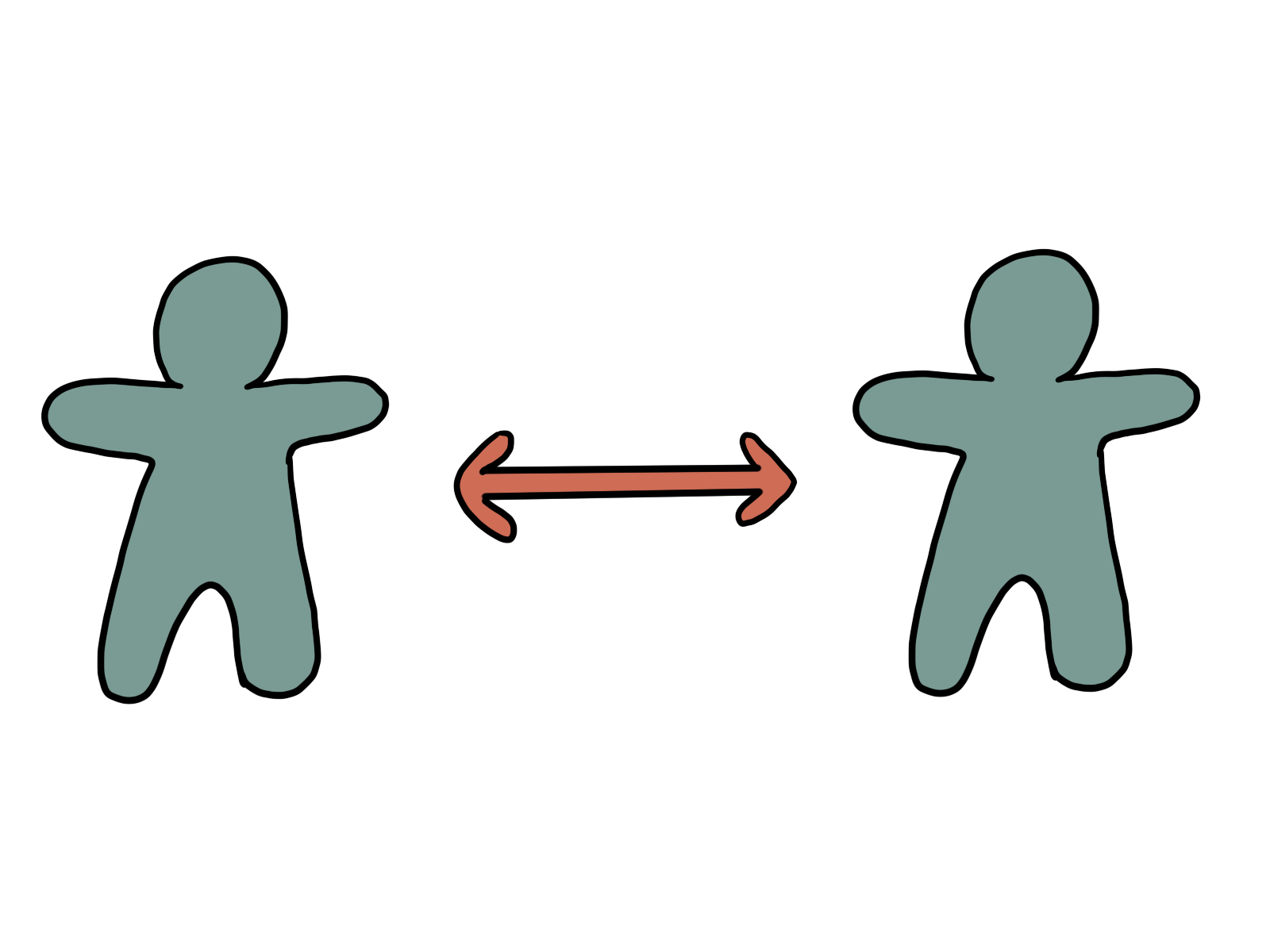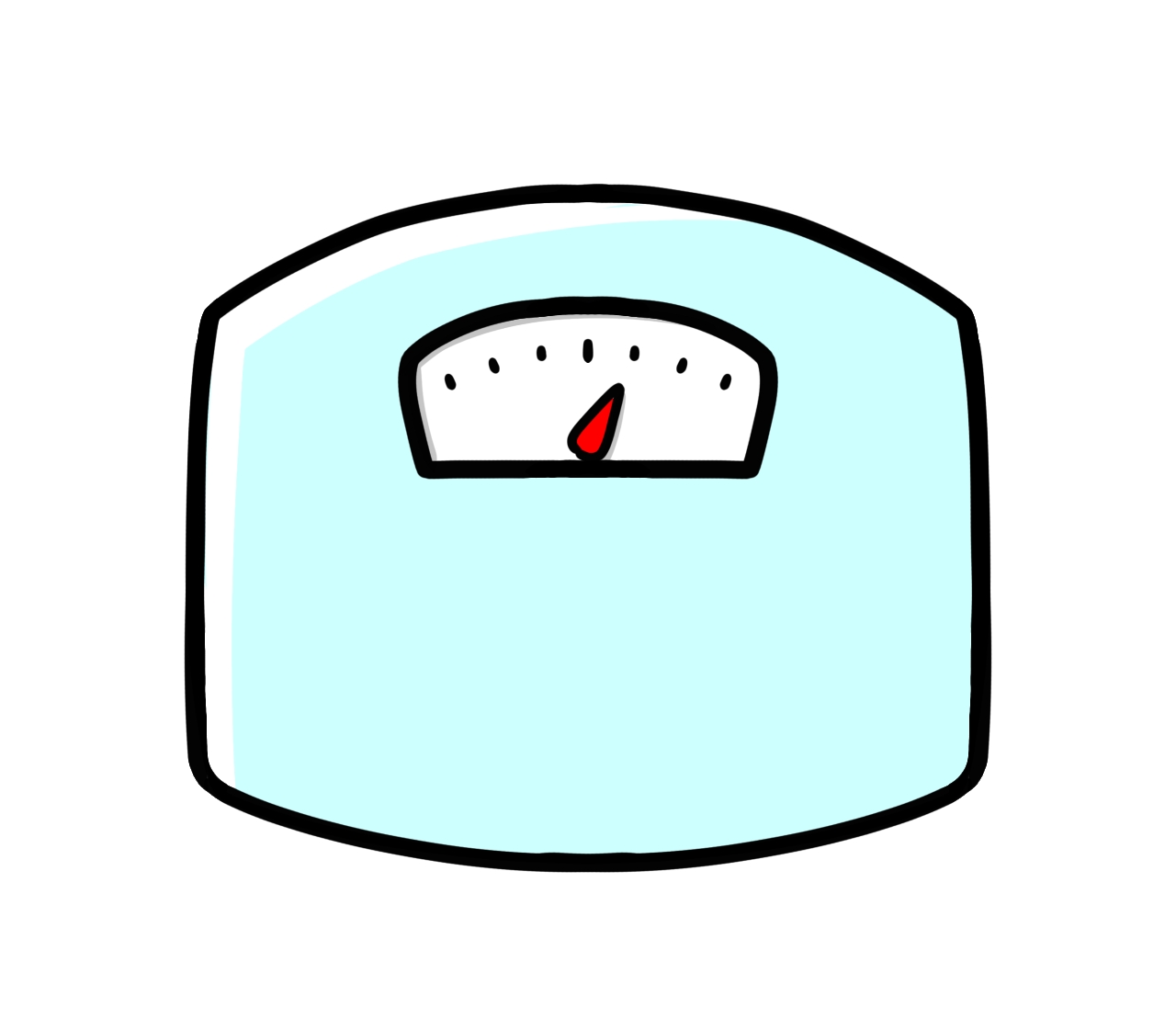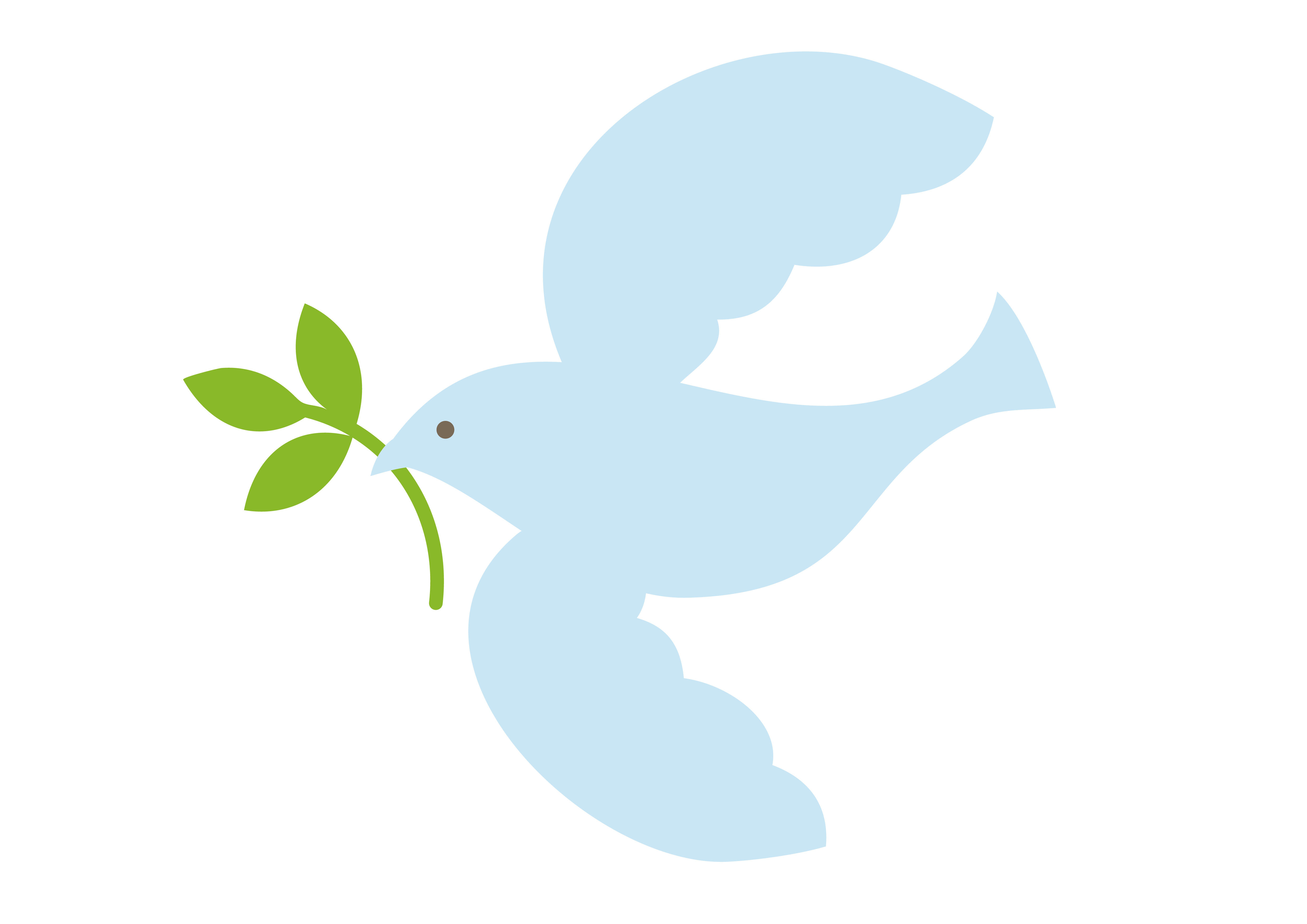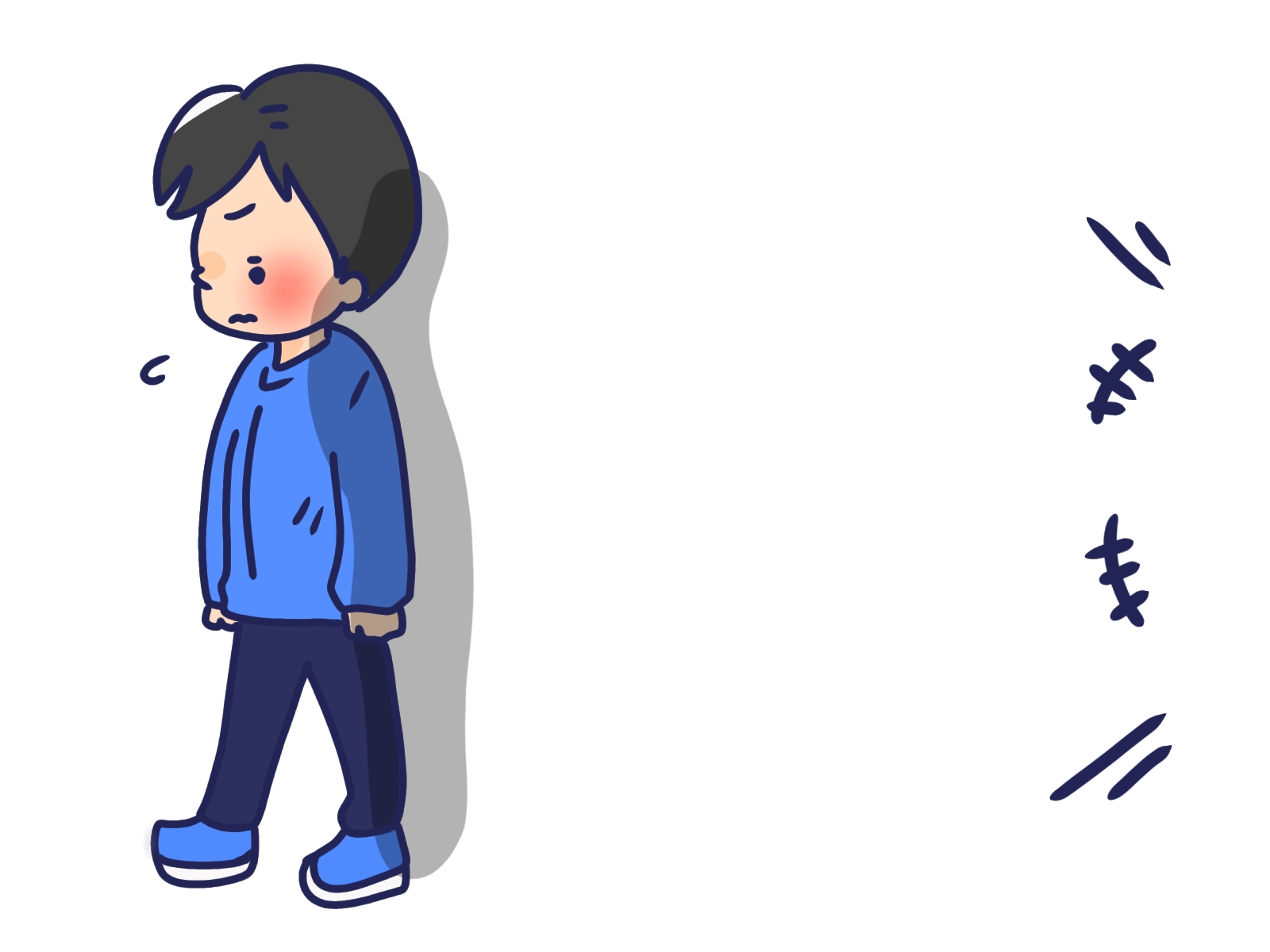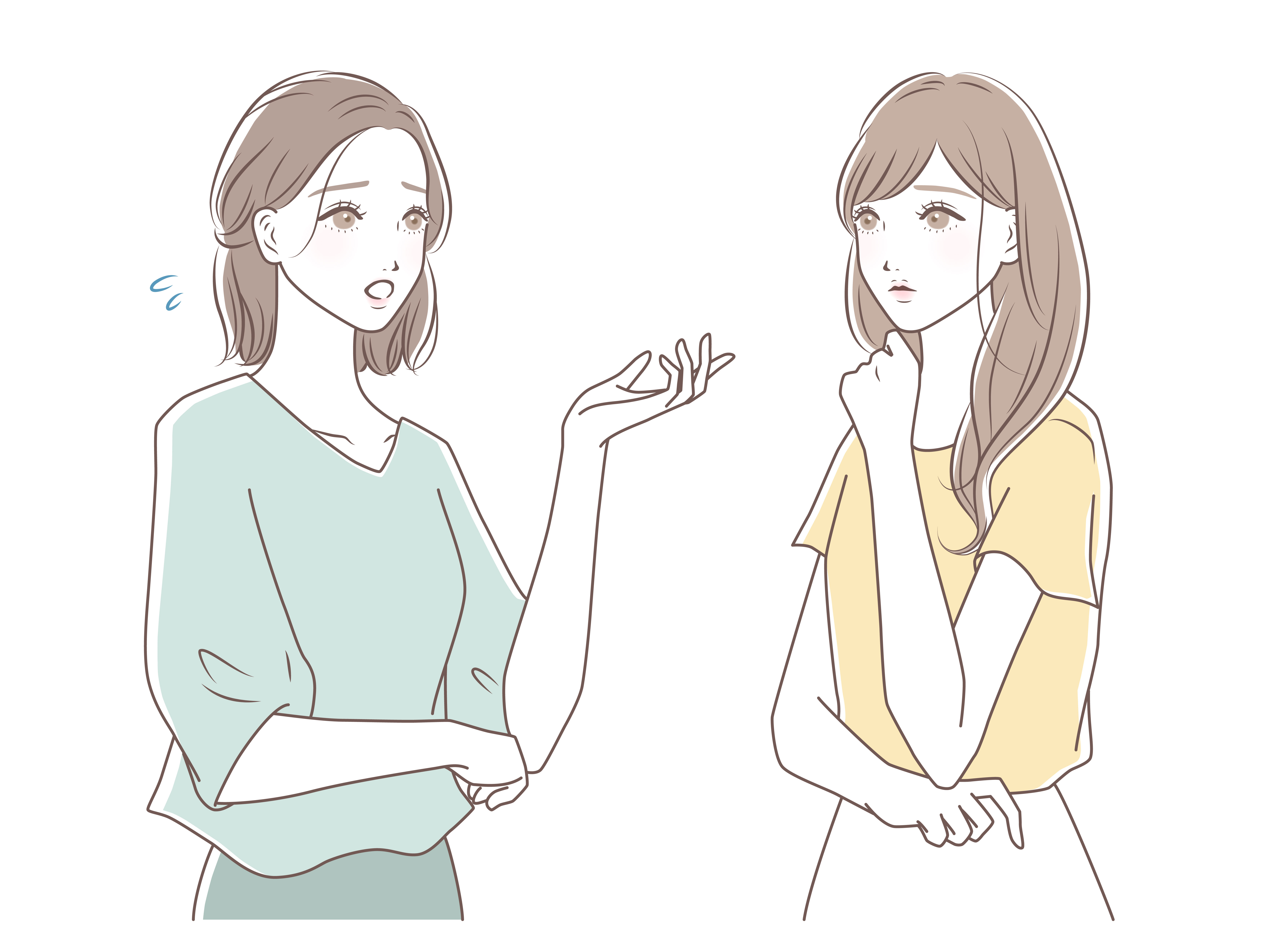家族のなかにある三角関係
三角関係といえば、男女3人が恋愛関係に陥った状態のことで、こじれた人間関係の代表的なものです。例えば1人の女性を2人の男性が取り合う場合、男性は自己アピールすると同時に、もう一人の男性の悪口を言って、女性との関係を裂こうとします。自分だけが女性と関係を持てるように画策するのです。
そもそも3人の人間関係は難しいものです。親友3人が集まっても、どこかの関係がうまくいかなくなると、もめごとに加わっていない人がどちらの側につくかで奪い合いになり、やはり三角関係になってしまいます。最終的に2対1の敵対関係となってしまうと3人の関係は分裂、崩壊してしまいます。
しかし、争いに加わっていない人が機転を利かして、他のもめている2人の両方の肩を持ちながら、仲裁するとします。すると、3人の関係は壊れることなく、争っていた2人は何かのきっかけで仲直りすることができるでしょう。3人が三角関係に陥ってしまったら、争いに加わっていない人の振る舞い方で、3人の関係が維持できるか、崩壊するかが決まるのです。
家庭の中にも父親、母親、子供の3人の関係があります。結婚直後は夫婦2人きりなのでうまく行っても、子供が生まれて3人となることで家庭生活に難しさが出てきます。万が一、家族のどこかの関係に争いが生じると、家庭の中に三角関係が生まれてしまうこともあるでしょう。そうなると対応の仕方によっては2対1の敵対関係ができてしまい、家庭が分裂し、崩壊する危険性もあるのです。
それでは、家庭にどのような三角関係ができてしまうのか、代表的なケースを紹介しましょう。これに気づくことで様々な家庭問題を解決するヒントが見えてくるでしょう。

1. 子供を挟んで夫婦がもめている
父親と母親がけんかをして夫婦仲が悪くなると、子供を挟んで三角関係ができます。一般的な家庭では、子供は父親よりも母親と交流する時間が長いため、母親は子供を味方につけようとします。父親の悪口を言ったり、自分は父親のせいで苦労をしていることを子供に訴え、子供と父親の仲を無意識のうちに引き裂こうとするのです。
純粋な子供は母親に同情し、父親に敵意をもつようになります。こうなると家庭は「母子チームvs父」の敵対関係になってしまいます。寂しさを感じた父親が、職場や趣味での人間関係に癒しを求めるようになり、ついに不倫にでも発展したら、家庭は完全に崩壊です。
夫婦がいつも仲良くできるのは不可能です。意見が食い違うことがあって当然でしょう。しかし、お互いの悪口を子供に吹き込んで味方につけるなど、争いに子供を巻き込んでしまうことは良くありません。問題は拡大し、子供の心にも傷跡をつくってしまい、二次被害、三次被害が生まれてしまいます。
最悪の場合には家庭は崩壊してしまいます。夫婦は子供を巻き込むことなく、頼るのであったら信頼できる第三者を仲裁にして夫婦同士で問題を解決しましょう。
2. 母親を挟んで父親と子供がもめている
子供の将来の進路などで父親と子供がもめると、母親を挟んで三角関係ができます。子供は身近な母親を味方につけようと、父親の不満をぶつけます。ここで母親が子供側についてしまい、やはり「母子チームvs父」の状態に陥ってしまうと良くありません。
解決するためには母親の立場が鍵を握っています。母親は子供と父親の両方の味方をしながら、もめている2人の仲裁役に専念するべきです。この立場で辛抱づよく耐えていると、関係修復のチャンスが巡ってくるでしょう。

3. 父親を挟んで母親と子供がもめている
母親が情緒不安定であったり、精神障害がある場合に、思春期になった子供が母親に反発することがあります。このような場合、父親を挟んでの三角関係ができます。ここで父親が子供に同情してばかりいると、「父子チームvs母」という敵対関係に陥ってしまいます。
そこで重要なのは、父親の立場です。母親と子供の両方の味方をしながら、2人の仲裁役をしましょう。
4. 親を挟んで兄弟がもめている
兄より弟の方が勉強ができる、姉より妹の方が可愛い、など、兄弟の位置関係とは逆の優劣があると、兄弟間のもめごとに発展することがあります。母親を挟んで兄弟の三角関係、もしくは父親を挟んで兄弟の三角関係となります。
親が兄弟と平等に接することなく、どちらかだけと仲良くなってしまうと、2対1の敵対関係が生まれてしまいます。家庭に味方のいなくなった子供は、家庭の外に癒しを求めて非行に走ったり、心を病んでしまうでしょう。親はあくまでも子供たちと平等に接することが問題解決のポイントです。
家庭内のもめごとに三角関係を考えると、問題を整理しやすく、家族それぞれの立ち回り方が分かってきます。これは、実際に心理カウンセリングでも応用されています。家庭の三角関係が2対1の敵対関係にならないように、挟まれた人の役割が問題解決の鍵を握っています。
うつ病がよくなっているサイン
うつ病は、疲れや怠けと状態が似ている上に、血液検査や画像検査で異常が出ません。そのために、病気の自覚において難しいところがあります。
風邪ならば、熱が下がり、咳やのどの痛みがなくなれば、治ったことを自分で理解することができます。しかし、うつ病に関しては、そうは行きません。良くなっているのか自分でなかなか判断がつかず、十分治っていないのに、「がんばれば何とかなる」と勘違いすることもあります。昔の自分はどうだったか、元気な頃の感覚を忘れてしまう人もいます。
ここでは、うつ病が回復している目安となる、日常生活でのサインを8つ紹介しましょう。
1. 部屋の片付けをする
ほとんどの人が、回復してまずやることは部屋の片づけです。久しぶりに掃除機をかける、机の上の古い書類や手紙の整理をする、服の断捨離をする、家具の配置換えをする、などです。「やりたいな」とずっと頭の片隅にあったことが、少し力が出てきたので行動に移せるようになったサインです。
2. 睡眠・食事が安定する
夜は睡眠がとれるようになり、食事をおいしく感じるようになります。睡眠、食事はうつ病を治すための要(かなめ)です。これができるようになると、回復は早いのです。
うつ病の原因は、脳内物質のセロトニンの分泌が減っているためと考えられています。十分な睡眠と食事は、脳のセロトニン分泌を改善するために最も大切なことです。
3. 現実感が出てくる
頭のモヤがとれて、何かをしている実感が出てきます。うつ病の時は、脳がきちんと働いていないので、頭にモヤがかかったように感じます。何をしても現実感がありません。食事をしてもおいしくない、人と話しても頭に入ってこない、何をしても楽しくない、といった感じです。これらがなくなり、頭がスッキリして、生きている実感が湧いてくるのは回復のサインです。
4. 心配が減る
心配や不安が減って、「なぜあんな小さなことを心配してたのだろう?」と、むしろ以前の自分を不思議に思うようになります。うつ病の時は、脳内物質のセロトニンが減ることで、脳が警戒モードになっています。ちょっとした出来事でも「危険だ!何とかしろ!」と反応するようになっているのです。普段ならば気にもとめない出来事が頭の中でグルグル回り続け、「このままではいけない!」と追い立てられてしまうのです。
しかし、セロトニンが増えて、うつ病が良くなってくると、脳の警戒モードが解除されます。すると、何か出来事があっても、「なんとかなるさ」という気持ちがつよくなり、あまり心配をしなくなるのです。
5. イライラしなくなる
情緒が落ち着いてくるので、イライラしなくなります。治療を受ける前は、家族や職場の人に対してイライラして、ちょっとしたことで怒ったり、もめ事になることが多かったと思います。身近な人から「怒っているの?」と聞かれたこともあったでしょう。失敗や注意を受けることで、「もうダメだ」と投げやりになっていたのも症状です。うつ病が回復してくると、辛かった人間関係もスッキリしてきます。
6. 薬を飲み忘れる
調子の悪い時は、きちんと薬を飲みますが、良くなってくると薬のことを忘れるようになります。「1回飛ばしてしまった」ということが起こるようになります。もちろん、そこで勝手にやめてしまっては良くないのですが、これは辛い気持ちが消えたため、病気のことを忘れられるようになったサインでもあるのです。
7. エンタメを楽しめる
集中力が回復してくるので、動画や音楽などのエンタメを楽しめるようになります。具合が悪い時は、集中力がないので、動画を少し見ただけで疲れてしまったり、音楽が雑音にしか聞こえなかったりします。好きな歌を口ずさむようになったら相当回復しているサインです。
8. ひまを感じる
休職中に「ひまだな」と感じるのは、回復のサインで、仕事に戻るチャンスかも知れません。逆に、「何かしなくては」「早く仕事に戻らなくては」と追い立てられているのは、焦燥感といううつ病の症状です。症状ですから、焦っている時は、むしろ働かない方が良いのです。ひまを感じてきたのは、このような焦燥感や緊張感が取れてきたサインなのです。
うつ病の回復のサインは、薬を飲み始めてから2週目くらいから、薬の治療なしで休職するならば1か月くらいで現れてきます。そこから本来の自分の体調を取り戻すまでは、最短で1カ月くらいですが、さらに半年から1年くらいかかる人もいます。回復時間には個人差があるのです。
仕事に戻るのは、ほぼ自分の体調を取り戻せたタイミングです。ただし、復職しても再発の予防のためにプラス1年くらい、無理は禁物です。薬を飲んでいる場合は、働きながら予防服薬を続けましょう。治ってからの1年間が最も再発しやすいからです。
1年間の再発予防で問題がなかったら、次は薬を減らしていくステップです。月に1錠ずつ減らせたら良いペースです。スムーズに減らせたらよいのですが、現実には、再発とまで言えなくても、薬を減らすと具合が悪くなることがあります。そのために、何年も服薬する人もたくさんいます。
これは薬の依存ではなく、ストレスの原因が改善されていないために、脳内でセロトニンを十分分泌できていないからなのです。薬は長期に飲めるものですので、「いつまでやめる」と期限は決めないで、主治医と相談しながら時間をかけてゆっくり減らしていきましょう。同時に、生活の中のストレスを減らすような努力をしましょう。
また、万が一再発してしまう場合、最初のサインは睡眠と食欲に出てきます。治ったはずなのに、寝つけなくなった、眠りが浅くなった、朝早く起きてしまう、食欲が減った、となると危険なサインです。この場合は早めに医師に相談しましょう。
愛に関する心理学
愛とは、日常よく使う言葉ですが、あらためて「愛とは何?」と聞かれても、すぐに答えられる人は少ないと思います。愛というと、男女の性的なものを思い浮かべることが多いかも知れません。
しかし、愛は、親子、友人、職場の仲間の間にあり、そしてペットや大切な物との間にもあります。さらには故郷や母国など、とても大きなものとの間にもあります。想像以上に幅広い感情です。
愛を辞書で引くと、「思いやり」「相手をいとおしく思う気持ち」などという説明が出てきます。愛は心理の一つですから、心理学の研究対象でもあります。それでは、心理学では愛をどうとらえているのでしょうか?
1. つながりたい感情
人は生まれながらに、誰かとつながりたい欲求があります。愛とは、相手とつながった瞬間に湧き出るポジティブな感情と言えます。実際には数秒から数分しか続きませんが、喜びの最高の瞬間であり、引き続いて幸せや安心を感じることができます。何度でも感じたいと思い、さらにつながりを深めようとします。
愛はつながった人同士で感じることができるため、片方だけに所属する感情ではありません。同時に相手も感じ、共有することになります。これをシンクロすると言います。シンクロすることによって、もっとつながりを深め、さらに新しくつながる相手を求めて広がろうとします。
お母さんが、子供を思い浮かべた時に愛おしいと思い、この愛が出発点となって美味しい料理をつくってあげます。子供は料理を食べて、お母さんの愛を感じます。お母さんの心が子供とシンクロし、親子の心が愛でつながるのです。
喜ぶ子供の笑顔にお母さんはもっと美味しい料理を作ってあげようと力をもらい、子供もお母さんの愛にこたえられるように勉強をがんばろうと思います。さらに、人とつながることの喜びを感じた子供は、友達に優しくできます。友達との間に新しいつながりができるのです。
このように人と人を結び付け、それを発展させるのが愛の力です。愛は、家族や社会の根っ子となっているのです。
2. 心の栄養
愛を体験すればするほどに、安心や幸せを感じるようになります。安心や幸せは、生きていく上で最も大切な要素です。これを土台にして心は成長していきます。したがって、愛は心の栄養と言うことができるでしょう。
体の健康と成長のためには食べ物が必要なように、心の健康と成長に愛は不可欠なのです。ですから、子供の頃に十分な愛を受けられなった人は、大人になっても自己肯定感が低く、さまざまな心の問題を抱えることが多くなります。
3. 仕事を成功させる力
経営の神様、松下幸之助は、「商売は金もうけにあらず、接した人に感動を与えてこそ発展する。」と言っています。ビジネスにおいて、「お客さんの期待に応えたい」という気持ちも愛の一つです。喜んでもらいたい気持ちが伝わり、お客さんとのつながりで愛のシンクロが起きる時、ヒットが生まれます。
経済活動の根っ子にも愛の原則が働いているので、「お金を儲けてやろう」と言う気持ちだけではビジネスは成功しないのです。
4. 癒しの力
脳が相手を認識すると、下垂体というところからオキシトシンという物質が分泌されます。オキシトシンは脳に働きかけ、つながりを求める感情をつよめます。
オキシトシンの効果はそれだけではありません。脳には扁桃体という不安を感じる部分がありますが、そこに働きかけて、不安感を抑える効果があります。さらにオキシトシンが血液中に放出されると、ストレスホルモンのコルチゾールを減らす作用もあります。このように、オキシトシンには不安やストレスを和らげる作用もあるのです。愛はオキシトシンという物質によって支えられており、実際に不安やストレスを緩和する癒しの効果があるのです。
オキシトシンが増えているかどうかは、唾液に分泌されたものを測ることで分かります。それによると、最も多く分泌されるのが、男女のスキンシップや、女性の出産や授乳の時です。
その他にも、親子で遊ぶ、楽しい会話をする、新しい友達ができる、動物とふれあう、仕事でよいパートナーと合意する、マッサージを受ける、など人と人がつながるたくさんの場面でオキシトシンは分泌されます。好きな人同士でのアイコンタクトでも増えることが確認されています。
5. 病気を治す力
孤独やストレスは、ストレスホルモンであるコルチゾールを増やします。コルチゾールは、体の免疫システムを弱め、血管や臓器の炎症反応を悪化させてしまいます。
これによって心臓病、脳卒中、認知症、癌などのさまざまな病気を引き起こします。これに対して、オキシトシンは、コルチゾールの働きを抑えることができます。オキシトシンがたくさん分泌されるほどに血管や臓器の炎症を抑え、病気の発症を防ぐことができるのです。ですから、愛には病気を治す力があると言えるでしょう。
愛は心の栄養です。人と人を結び付けて家庭や社会をつくり、繁栄させるエネルギーでもあります。さらにストレスや病気から守ってくれる力でもあります。インターネットの進歩とコロナ禍もあり、人と人との直接のふれあいが少なくなってきました。このような時代だからこそ、愛することや触れ合うことの大切さを意識しましょう。
良い子症候群の4つのサイン
親は、子供に向かって「良い子になりなさい」という言葉をよく使います。一般的に良い子とは、「大人しくて、育てやすい子」「親のいうことを聞く優しい子」といった意味で使われます。
「良い」というのは、あくまでも親の視点からですので、親の目をいつも意識して、親の期待を裏切らない子が良い子なのです。ところが、良い子が大人になると、そのまま親や周りの人にとっての良い人を続けることがあります。いつも周りの目を意識して、その期待を裏切らないように努力してしまうのです。
このような人の心の中は、自分を主張することに不安を感じており、顔色を見て人に合わせることで安心を感じていることがあります。いつのまにか他人にとって都合の良い人となり、自分の幸せがなくなっているのです。このような生きづらさを感じる場合を「良い子症候群」と呼びます。
今回は、良い子症候群のサインを4つ紹介しましょう。
1. いつも人にどう思われているかを気にする
人と接する時は、何よりも自分の評価を気にしてしまいます。嫌われずに、良く思われることに大きなエネルギーを使ってしまうのです。このような心の癖は、素直な性格が土台にあるのですが、親子関係が大きな影響を与えています。
親によっては、子供の存在そのものを愛するのでなく、勉強ができるから愛する、容姿が良いから愛する、など、子供に注ぐ愛情が条件付きの場合があります。また、親の情緒が不安定で、機嫌を損ねると怒りを爆発させるような場合でも、子供はいつも親の顔色をうかがって生活するようになります。
このように親から注がれる愛情が偏っていると、「親の願う良い子でいると愛される、良い子でいないと愛されない」という心の癖が身についてしまいます。この癖が抜けないままに大人になったのが、良い子症候群なのです。親子の情的関係を愛着と呼びますが、良い子症候群には愛着の問題が関わっているのです。
2. 自分の考えをはっきりと持たない
人間関係はいつも受け身で、職場では指示待ちです。周りにどう思われるのかが心配で、自分で判断することができないのです。しかし、言われたことに対しては全力でこなし、最高の結果を出そうとします。
実はこのような生き方は、封建時代、高度経済成長期には必要な生き方でした。権威ある人に従うことは、出世に必要ですし、終身雇用があったので一生を守ってもらえました。良い人でいることは、生きていく上で最も大切なことであり、一つの処世術でもあったのです。
ところが時代が変わり、人に主体性が求められる社会になりました。人に合わせる生き方では利用されるだけで、むしろ損をすることが多くなりました。良い人には、生きづらい世の中になったのです。
3. 争いを避けて自分の思いを押し殺す
争いを避ける平和主義者です。人と争うくらいのなら、「このままでいい」と思い、主張せずにあきらめます。自分の思いを押し殺してしまうのです。良い人は、我慢づよい人でもあり、自己否定ができる人です。
しかし、我慢は無限にできるものではありません。我慢の度がすぎると心がおかしくなってしまいます。聖職者、教師、医師などの厳しい倫理を求められる職業の人が、性的な犯罪や暴力の問題を起こすことがあります。これは我慢しすぎて心が爆発した結果です。
4 人にしたがって心を病む
自分を押し殺して働き続け、仕事を休みません。休むことは罪深いことだと感じます。人の期待に応えることが生きがいですから、そうできない状況では自分を責めてしまいます。
こうした生活が続くと徐々にストレスが溜まるようになりますが、そのために心身に異常が出ても気づきません。ついに、うつ病を発症したり、最悪の場合は、過労死、過労自殺という問題も起きてしまいます。
良い子症候群で生きづらさを感じているならば、良くない心の癖をもっていることを自覚しましょう。そして、自分の素直な気持ちを押し殺さずに大切にするようにしましょう。ストレスや疲れを感じ時には、無理をしないことも大切です。万が一、うつ病などの心の病気を発症してしまったら、今後の仕事の取り組み方について見つめ直すことも必要です。
親の願いの本質は、子供が幸せに生きることです。しかし、親が不幸な生い立ちから、偏った考えをもっていることがあります。親なりに子供を幸せにしようと思いながら、実は自分のいいなりにしようと間違った愛情を注いでしまうことが多いのです。
そのような親の間違った願いや価値観にそって生きていると、むしろ幸せになれません。人生の目的は、自分の持っている能力を生かして幸せになることです。自分が何に向いているのか、本当は何をしたいのか、素直な気持ちを大切にしましょう。
過保護・過干渉で育った人の5つの特徴
虐待やネグレクトは、子どもの心を傷つけてしまい、大人になってもそれを引きずってしまいます。それでは、過保護や過干渉も子どもの心の成長を妨げてしまうことはご存知でしょうか。
少子化の影響を受け、アメリカや中国に代表されるように、子どもを過保護・過干渉する親が世界的に増えています。まるで子どもの上をいつも飛び回って監視しているヘリコプターのような存在なので「ヘリコプターペアレント」とも呼ばれています。
本来親は、子どもが成人すれば一人の人間として尊重して接するようになり、子育ての役割を卒業します。ヘリコプターペアレントは、子どもが成人しても子離れができず、いつまでも自分の所有物のように接します。「私がいなければ、この子はダメになる」という言い訳があるのですが、いつまでも親の夢や理想を押しつけ、子どもがするべき決断や課題を先にやってしまうため、子どもが精神的に自立できなくなってしまいます。
ヘリコプターペアレントに育てられた人は将来どのようになってしまうのでしょうか。今回は、過保護・過干渉で育った人の特徴を5つ紹介しましょう。
1. 自信がない
過保護というと親に大切にされているイメージがありますが、子どもが自分で乗り越えるべき課題を親が先回りしてやってしまうために、子どもの心は成長しません。また、子どもがやりたいことが親の理想と一致しないと、頭ごなしに否定されてしまいます。
このために自信がなく、自分を好きになれず、自己評価が低くなってしまいます。成功も失敗も体験できずに育つために、自己肯定感が低くなってしまうのです。
反抗期は、子どもが反発することで、親が接し方を修正するきっかけになります。ところが、子どもが素直で反抗期がないと、親はいつまでも自分のやり方が正しいと思ってしまいます。反抗期はとても大切なものなのです。
2. 自主性がない
親の引いたレールの上での要求はなんでも聞いてもらえますが、それを外れるような主張は聞いてもらえません。
そのために親の顔色をうかがうようになり、本心を主張できなくなります。家庭の外でも自分を主張できず、決断することもできなくなり、いつも人に考えを合わせるようになってしまいます。これでは人としての責任感も育ちません。
3. 人に頼りがち
自主性がなく、自信もないので依存心が強くなります。これは親に対してだけでなく、人間関係全般にそうなります。
相手にやってもらって当たり前、支えてもらって当たり前、という態度になるため、人に信頼してもらえずに人間関係のトラブルも増えるでしょう。特にパートナーとの関係では、相手に依存しすぎて嫌がられてしまい、関係が壊れるきっかけになります。
4. 失敗や挫折に弱い
子どもの頃の失敗や挫折は、大人になって社会の困難を乗り越えるための練習になります。自分で問題を解決する体験をしていないと、対処方法や立ち直り方が分かりません。
失敗を自分で乗り越えていると、「ピンチはチャンス」というプラス思考もできるようになりますが、それを学べていません。問題に直面しても自分で何とかしようとせずに、人に丸投げすることが多く、逃げ出すこともあります。助けを得られない場合には、うつ病になりやすいとも言われています。
5. 偏ったプライド
親に社会的な地位があると、子どもに対して「お前は特別だ」と育てることが多く、子どもは偏ったプライドを持つようになります。特に親子の情的関係があまりなく、親がお金で問題を解決していると、「俺は何でもできる」といった偏った万能感ももつようになり、他人を見下すようになります。善悪の区別を学んできていないこともあり、何かトラブルがあっても自分の間違いを認めようとせず、相手を責めてしまいます。
韓流ドラマには、必ずわがままな韓国財閥の息子娘が出てきて事件を起こしますが、親子の情的なつながりがないまま、お金に守られ育てられた典型的な例ではないでしょうか。ドラマのほとんどは架空の話でなく、実際の財閥二世たちが起こした事件を元にしているのです。
自分の親がヘリコプターペアレントであると気づいたら、早めに親との距離をとるようにしましょう。具体的には、やることに口を出さないようにしてもらう、簡単に行き来できないように離れて住む、連絡を取らないようにする、などがあります。
いくつになっても遅いことはありません。むしろ、親子の距離を取った方が、時間はかかっても最終的には親子関係もよくなるでしょう。
心がダイエットに支配されてしまっている5つのサイン
女性は痩せていること、男性は筋肉がついていることが美しいと思われています。コロナ禍の在宅生活でダイエットブームはさらに高まり、ダイエット食品、筋トレグッズなどのダイエットビジネスも盛んです。
一度ダイエットに成功して、鏡に映った自分に喜びを感じると、その喜びが心から離れなくなる人がいます。
体系を維持するために、ダイエットのことしか考えなくなり、ついに生活に支障が起きることもあります。本来、体重をコントロールするのがダイエットですが、逆に体重に心がコントロールされてしまうようになると、ダイエットでなく摂食障害です。
ダイエットから摂食障害が始まる人はたいへん多く、すでに日本では20万人いじょうが患っているとも言われています。10代から30代の女性が多いのですが、細マッチョに憧れて摂食障害になってしまう男性も増えています。
ダイエット習慣と摂食障害では、なかなか線が引けないところがあります。今回は、ダイエットのつもりが、すでに心がダイエットに支配されてしまっているサインを5つ紹介します。これに当てはまる場合は摂食障害の可能性があるので、早めに精神科を受診することをお勧めします。治療を早く始めるほど、早く回復できます。
1. 体重が増えることへの恐怖
体重が増えることを何よりも恐れていませんか?体重を測ると、前日と同じか、それ以下でないと不安になりませんか?
0.1キロでも増えていると、なんらかの手段ですぐに減らさないと気がすみません。今日は飲み物だけにしようか、ジムで限界まで運動をして減らそうか、下剤を使ってみようか、など、ボクサーの減量のようにすぐに体重を減らすことを考えて実行します。また、予定より多く食べてしまったときは、トイレで吐いてしまうこともあります。
こうした体重を減らすための過激な行いが、週に1回以上あるようならば摂食障害を疑いましょう。
人と比べて自信を無くす必要はありません。自分なりの幸せがあるので、それを探しましょう。
2. 週に1回は過食してしまう
期間を決めずに、常にダイエットを意識しているので、すぐに我慢の限界がきます。疲れや嫌なことがあると、食欲が抑えられなくなり、「どうにでもなれ」と過食していませんか?
たまに思いっきり食べると気晴らしになるのが普通なのですが、過食の後には、必ず後悔の気持ちが待っています。そして、自分はダメな人間だと自己嫌悪感に襲われてしまうのです。
このような過食が週に1回以上あるようならば、摂食障害の可能性があります。
3. 終わりのない自己流ダイエット
ダイエットは効果が出たら一旦やめて、また体重が増えるようなら再チャレンジするのが普通です。そうでないと気持ちも身体も続きません。ところが元に戻るのが不安で、永遠に終わりのないダイエットを続けようとするのは摂食障害です。
自分で決めたダイエットのルールが、いつのまにか儀式のようになり、それをしないと後悔したり、苦しくなります。
このように、ダイエットに生活が支配されて身動きがとれなくなってしまうのは普通のダイエットではありません。
4. 体重で自分の評価が変わる
太っている自分は醜いと感じ、必要のない存在と感じる時はありませんか?こんな時は、人に姿を見られるのが嫌で、外へ出たくありません。体系や体重で自分の評価が決まってしまうのです。重症になると、人と会わないように引きこもりになる場合もあります。
逆にダイエットに成功して痩せていると、自分に満足です。気分もよくなり、外へ出るのが楽しくなり、社交的にもなります。
5. 食べ物、体型のことが頭から離れない
いつも体型や体重のことを考えていませんか?鏡やガラスなどの自分の姿が映るものがあると、体型を必ず確認していませんか?
体重が気になる日は、人と会いたくないので、大事なアポイントもキャンセルしてしまいます。大事な会食の場でも、体重が多い日は食べ物を口に入れようとしません。このように日常生活が体型や体重に左右されるようならば摂食障害です。
常に無理なダイエットをしているので、テレビやネットのグルメ番組を見ただけでも、食欲のスイッチが入ってしまいます。例えば、ラーメンの特集を見ると、ラーメンを食べるまでずっとラーメンのことが頭から離れなくなります。
こんな感じで、体重と食べ物の事に心を支配されてしまうのが摂食障害です。
幸せになることを邪魔する6つのこと
誰でも幸せになりたいと願っています。生きる目的は、幸せをつかむことともいえるでしょう。それぞれに幸せの形は違いますが、幸せを簡単に言うと、私たちの欲望が満たされることです。
欲望というと食欲などの生理的なものを考えがちです。しかし、人を愛したい、幸せな家庭を築きたい、社会に貢献したい、などの次元の高い欲望もあります。
高い次元の欲望とは、より内面的で心の成長を伴うものです。次元の低い欲望は、満たされてもその場限りの幸せしか得られません。しかし、次元の高い欲望が満たされると、永続的な幸せを得ることができます。
低次元の欲望ばかりを満たしていると、自分の内面をみつめることができなくなり、本当の幸せを掴むことができません。ところが、物質や情報にあふれた現代社会では、低次元の欲望を満たすものがいくらでも簡単に手に入ります。それが悪いという意味ではありません。
頑張った時や疲れた時に、おいしいものを食べて満足、欲しかったバッグを買って満足、旅行に行ってリフレッシュ、というのは生活に必要なことです。しかし、そればかりでは、心は成長せずになかなか願っているような幸せにはたどり着くことができません。
そこで今回は、私たちがやりがちですが、実は幸せになることを妨げてしまっている6つのことを紹介します。
1. 人と比べてしまう
SNSには高い買い物をした、ヨーロッパ旅行をした、たくさん友人がいる、など、自分の幸せを自慢する情報にあふれています。
年齢の近い人が成功している姿を見ると、うらやましい気持ちになり、心が惑わされます。「自分はダメな人間だ」と感じてしまい、自身を失っていないでしょうか。
しかし、人それぞれに持っている才能や立場は違います。社会で生きていく使命がそれぞれに違うのです。人は人、自分は自分です。いまは成功している人でも将来は失敗するかもしれません。若い頃に一世を風靡した有名人が、老人ホームで孤独に亡くなることも多い話です。
人と比べて自信を無くす必要はありません。自分なりの幸せがあるので、それを探しましょう。
2. 勝ち負けにこだわる
「勝ち組」、「負け組」という言葉がありますが、何事も勝ち負けにこだわり、相手のマウントを取ろうとする人は幸せになれません。
こういう人は物事を測る物差しが、自分の心の中になく、他人の目になっているのです。これでは、何をやっても、いつになっても本当の満足を感じることが出来ません。
3. 人脈を広げすぎる
友人が多いことがリア充であると思っていませんか。誕生日会にたくさんの人を呼んで自慢する人もいますが、知り合いが多ければ多いほど、一つ一つの関係は情的に薄くなります。
情的に薄い人間関係ばかりの人は、虚しさを感じやすいと言われています。人間関係は少なくても、一つ一つの関係を大切にする方が心を成長させます。幸せをつかむためには人脈を広げすぎない方が良いのです。
4. 収入を上げることを人生の目標とする
幸せを研究するポジティブ心理学という分野があります。ポジティブ心理学では、「財産を築く」「高い教育を受け学歴がある」「ハワイなどの気候に恵まれた土地に移住する」といった、一般的に幸せと思われている出来事を経験したアメリカ人が、実際に幸せになっているかを調査しました。
その結果、これらの出来事と幸せとはほとんど関係がないという結果が出ました。誰でもお金があれば幸せになれると勘違いしますが、実際はいくら収入があがっても幸せとは関係がないのです。
世の中には、人の価値を年収で判断する傾向があります。収入が上がれば周囲からの評価は上がるかもしれませんが、本人が幸せになるわけではありません。むしろ、年収を上げるために自分や家族と向き合う時間を犠牲にするため、幸せから遠ざかってしまうことが多いのです。
5. 働き過ぎる
現代人が最も心を病む原因は、働き過ぎです。常に健康に気を配り、心のためには静かに自分を見つめる時間が必要です。
欧米では、マインドフルネスといって、瞑想の時間を大切にする習慣が増えてきました。仏教や日本の禅に起源をもつものが、むしろキリスト教社会である欧米で評価されているのです。
瞑想というと寺で座禅を組むことをイメージする人もいますが、集中できるならば場所も時間も自由です。目をつぶり、よけいなことを考えず、自分の心を客観的に見つめるのです。
これを毎日、できれば決まった時間に習慣として行うとよいでしょう。マインドフルネスを通じて、自分に本当に必要なことは何か、いまやるべきことは何か、答えが出るかもしれません。
6. 過去にとらわれる
大切な人との別れ、失敗や挫折など、過去にとらわれて前に進めなくなることがあります。心の傷を癒すためには立ち止まる時間が必要です。
しかし、「昔は良かった」とため息をついてばかりでは幸せにはなりません。前に進めば、失ったものより大きな幸せに出会えるかもしれません。
ポジティブ心理学では、過去にとらわれず、今と未来に集中することが幸せになるコツであると言っています。
夫が発達障害である5つのサイン
妻の気持ちが理解できない夫
仕事熱心で学歴も職歴も立派な男性、ところが結婚したところ何か普通の人と違います。マイペースで、自分のことしか話さずに会話は一方通行、冷たい人ではないのですが、いたわりを感じられません。
妻が育児で大変でも、スマホやゲームをやって手伝わず、ねぎらいの言葉もないのです。文句を言っても喧嘩になるだけなので、もう夫の支えを期待できなくなりました。
このような妻の気持ちを理解できない夫は、アスペルガー障害の可能性があります。
アスペルガー障害とは、相手の立場で物事を考えられないという脳の発達の障害です。そのために相手に共感ができません。
発達障害のひとつですが、ごく軽症であると子ども時代には気づかれずに、家庭をもってから初めて気づかれることがあります。なお最近では、アスペルガー障害を自閉スペクトラム障害・ASDと呼ぶことが多くなっています。
今回は夫がアスペルガー障害であるサインを5つ紹介しましょう。
1. 妻の気持ちを分かろうとしない
場の空気を読んだり、人の気持ちを察することができません。家の大変な状況やSOSを読み取れないのです。例えば、病気で寝ていても慰めの言葉がなく、いつも通りに仕事に行ってしまいます。「具合が悪いから弁当を買ってきて」と頼んでも自分の分しか買ってきません。
これは夫が冷酷なのではなく、場の空気が読めず、「何に困っているか分からない」、「手伝ってほしいと言われないので、何もしなくて良いのだろう」という理屈なのです。雰囲気から人の気持ちを読み取ることが苦手なので、明確に言葉で説明しないと察することができないのです。
2. 自分の興味のあることだけ一方的に話す
興味のあることは一方的に話しますが、相手の話を聞くことは苦手です。相手の意見を否定して、感情的に自分の意見を通そうとします。
妻は聞き役に専念するしかありません。ただし、一方的に延々と話すようなら、優しい言葉でストップをかけた方が良いでしょう。
逆に、妻から伝えたいことがあれば、明確で簡潔な内容にすることが必要です。むしろ文字にすると伝わりやすいので、ラインやメモなどを利用するとよいでしょう。
3.マイルール
毎朝同じものしか食べない、同じ種類の服しか着ない、同じ店でしか買わない、といった、自分なりの生活のルールがあり、それにこだわります。また、仕事の雰囲気をそのまま家庭に持ち込み、家族の団らんには加わりません。スマホやゲームなど、一人で何かに没頭している時間が長くあります。
アスペルガー障害の人は変化に弱く、マイルールは安心を感じるために必要なものです。ルールが守られないとパニックになり、突然怒り出すことがあります。ただし、家族を不愉快にするルールであったら、よく説明してやめてもらうようにしましょう。
4.音、光、臭いに敏感
ドアの開け閉めの音、上の階の足音、遠くの工事の音など、普通の人ではほとんど気にならない小さな音をうるさいと感じます。臭いや明るさにも敏感です。これを感覚過敏と呼んでいます。中には皮膚感覚も敏感なために、スキンシップを嫌がる夫もいます。妻が手を握ろうとしたところ、サッと手を引っ込めて、妻が傷つくことがあります。
5.子どもが苦手
自分の思い通りに行かないので、子どもは最も苦手な分野です。子どもに怒りを爆発させたり、子どもが嫌で仕事を理由に家に帰らなくなることがあります。子どもの扱い方が分からず、子育てができないのです。結局子育ては妻一人でやることになり、妻が体調を崩す大きなきっかけになります。
アスペルガー障害の夫との生活からストレスを感じ、妻がうつ病などの精神疾患を患うことがあります。これをカサンドラ症候群と呼び、妻が精神科を受診して、医師の指摘から初めて夫の障害に気づくことがあります。
夫に障害を自覚してもらうことで、妻の負担はずいぶん減ります。では夫を医療機関に連れて行けばいいのかと言うと、実は難しい問題があります。大人のアスペルガー障害は、比較的新しい概念のために、確実な検査や診断のガイドラインがありません。そのために、医師によっても判断が分かれてしまいます。本人がコミュニケーションに難しさを感じ、仕事などに支障が出ている場合には診断がつけられますが、妻におかしいと言われても「俺は病気じゃない」と否定するならば診断はできません。
しかし、妻が障害を理解すると、「なるほどこれが症状だな」と夫の行動にそれほど腹が立たなくなります。実は、夫もなぜそんなに嫌われるのか分からなかったのです。その過程で、夫婦で少しずつ理解し合い、家庭での役割分担を決めていきましょう。
アスペルガー障害の人は、心の共感はできなくても、人の気持ちを推理して知的に理解することは可能です。また、妻にウソをついてお金を使ったり、浮気をしたりという裏表はありません。人を裏切ることはしない人です。
コミュニケーションが苦手でも人に好かれる方法
ネットでは、「コミュ障」という言葉があります。コミュニケーション障害を略したものですが、意見が通じない人に対してのネガティブなイメージで使われているようです。
精神医学におけるコミュニケーション障害という病名は、吃音など、言葉をうまく使いこなせない障害を指しています。コミュニケーションの障害を起こす精神疾患はそれ以外にもたくさんあります。
代表的なものとして、場の空気や相手の気持ちを理解するのが苦手なアスペルガー障害です。また、緊張がつよく人と話せなくなる社交不安症もそうでしょう。「コミュ障」と言われるのは、どちらかというと精神医学のコミュニケーション障害よりも、アスペルガー障害などの発達障害や社交不安症の人を指している印象があります。
コミュニケーションの障害の多くは、生まれつきの要素がつよいものなので、残念ながら自分の努力で劇的に改善させることはできません。これが理由で、自分に自信がもてず、職場の人間関係がうまくいかないことがあります。
しかし、根本は変えられなくても、ちょっとした努力で相手に良い印象を持たれる方法があります。ここでは、何らかのコミュニケーションの障害があって会話が苦手な人が、相手に良い印象をもたれるためのポイントを説明します。
1 聞き役に徹する
自分から話題を提供したり、意見を言わずに、聞き役に徹しましょう。言葉のキャッチボールという言葉がありますが、キャッチャーに専念するのです。聞き役になるためには相槌(あいづち)が重要です。無理して言葉を添えなくても、相手の言葉に合わせてうなずきましょう。それだけでも相手は聞いてもらっていると感じることができ、良い印象を持たれます。
2.相手の言葉を否定しない
聞き役で大切なことは、相手の話を否定したり、遮ったりしないことです。少しでも自分の考えと違うと「それは違います」と言って否定していると、相手に嫌な印象を持たれます。考えが違っていても「そうなんですね」と聞き流すようにしましょう。
3.話し過ぎない
聞き役に回っていても、相手から意見を求められることがあります。このような場合は、話し過ぎに気を付けましょう。つい興味のある話題になると言いたいことが次々とこみ上げてくることがあります。自分に興味があるものを、他人も興味があるとは限りません。いつもだいたいの時間の目安をつくっておいて、話し過ぎないように気を付けましょう。「沈黙は金、雄弁は銀」という言葉もあります。
4.笑顔
コミュニケーションに自信がないと、顔を横に向けたまま話したり、目を合わせずに伏し目がちになります。それが相手にマイナスのイメージを持たせてしまいます。できるだけ相手の顔を見るようにしましょう。また、笑顔でいるのも、相手に良い印象を与えるための大切な秘訣です。家にいる時に、鏡を見ながら軽く口角を上げてみて、自然な笑顔の練習をしてみましょう。
5.悪口を言わない
人の悪口を言うと、悪口を言った人の印象が悪くなってしまいます。悪口は聞いていて気持ちの良いものではないからです。また、聞いた人の意地が悪いと、「あの人が悪口を言ってたよ」と言いふらすこともあります。人前で他人の悪口は言わないようにしましょう。
6.怒らない
少しでも否定されると怒ってしまう人がいます。怒られて気持ちの良い人はいません。すぐ怒る人は嫌われます。イラっとしてもその場で怒ることは避けましょう。怒りがこみ上げてきても数秒間グッとこらえると、怒りのピークは過ぎ去ります。
ただし、自分の力で怒りをコントロールできていない場合は、「易怒性(いどせい)」という精神症状かも知れません。治療方法があるので、カウンセリングや精神科を訪ねてみましょう。
7.無理をしない
嫌われないように相手に合わせて気を遣いすぎると疲れてしまいます。職場で毎日会うような人ならば、次に会うのが辛くなります。心をすり減らしてまで、好かれる必要はないでしょう。無理をして好かれるよりは、嫌われても自分の心を守ることが大切です。意見をふられても、分からなければ、「分かりません」で良いし、無理に話題に入らなくても良いでしょう。
そもそも相手に気を遣わせてしまう人の方に問題があります。こちらと気持ちよく付き合う気のない人とは距離を置きましょう。それがもし職場で毎日会う人ならば、できるだけコミュニケーションを避けて、最低限のやり取りだけで終わらせるのが賢い方法です。
うつ病の家族を支える方法
家族が病気になったら、誰でも看病します。それではうつ病の場合はどうでしょう。熱があるわけでなく、自分で食事が取れないわけでもなく、元気はありませんが最低限の生活はできています。
。部屋にこもって、声をかけても明確な返事がありません。どうしてあげたら病気が良くなるのか、家族は混乱してしまいます。一体どのように看病してあげたら良いのでしょうか。
ここではうつ病になった時の家族がやるべきことを簡単にまとめました。6つのポイントに分けて紹介します。
1 うつ病を理解する
家族に一番理解して欲しいのは、うつ病は「怠け病」ではないことです。何かのきっかけで脳の神経伝達物資の分泌が少なくなり、脳の一部の機能が低下する病気です。すぐには治らず、治療機関は数か月から年単位にかかることもあります。
最も効果があるのは服薬と休養です。運動が良いとか、日にあたるのが良いとか言われていますが、あくまでも補助的なものです。一日ゴロゴロして何もしていないと、これでいいのかと思ってしまいますが、初期の頃は何もしないことが必要です。何もできないで一番焦っているのは本人ですので、むしろ安心して休めるようにしてあげるのが家族の役割です。主婦のうつ病の場合は、元気な家族が積極的に家事を代わってあげましょう。
良くなってくると好きなことからできるようになります。これは回復のサインです。しかし、肝心なことから逃げて、楽しいことだけやっているように家族の目に映ることがあります。良くなっていることを確信して、暖かく見守ってあげましょう。
2.いっしょに通院する
1回でも良いので、いっしょに通院して主治医と会いましょう。病院と主治医がどんな雰囲気なのかを知ることは大切です。家では相当悪い状態なのに、主治医の前で緊張して何も言えなかったり、薬を増やされたくないために良くなっているフリをしていることもあります。医師はあくまでも患者さんの言葉で状態を判断していますので、本人が本当のことを言っていないと治療が進みません。そんな時に家族からの情報は治療に役立ちます。
3.薬を飲めているかチェックする
うつ病で最も効果があるのは抗うつ薬の治療です。ただし即効性はなく、効果が出てくるのは2週間から1ヶ月してからです。辛い時はきちんと飲めるのですが良くなってくると薬を飲み忘れがちです
飲み忘れをしないように家族が見てあげましょう。良くなっていたのに急に悪くなることがありますが、その一番の原因は、薬を勝手にやめてしまうことです。
信じられないかも知れませんが、家族が薬を調べて、「その薬は依存性があるから飲まない方が良い」と言ってやめさせてしまうことがあります。
。実はこれは大変多い話です。ネットには根拠のない記事がたくさんありますので注意をしましょう。主治医が精神科専門医であるならば、きちんと勉強をしていますので、害になる薬は処方しません。
4.関心をもってあげる
うつ病で辛いことは、家族から無関心でいられることです。特に更年期の女性のうつ病は孤独になりがちです。それが病気を悪くさせる原因にもなっています。家族が1日1回15分で良いので話を聞いてあげましょう。必ず聞くことに専念して、自分の考えばかり話すことは絶対にやめましょう。説教は禁物です。
5.焦らせない
子供や配偶者がうつ病の場合、「いつ治るの?」「学校どうするの?」「いつ会社に戻るの?」と言ってしまいがちです。一見普通に見えるのに、肝心なことをやらないので、このような言葉が出てしまうのだと思います。
しかし、一番焦っているのは本人自身です。家族は追い詰めるのでなく、むしろ学校や会社をより長くゆっくり休める方法といっしょに考えてあげましょう。うつ病の人にとっての家庭は、安心できる一番の療養の場であるべきです。
6.強要しない
ネットでは、「うつ病は朝の散歩で治る」という記事をよく見かけます。確かにある程度回復した状態ならば効果があるのは事実です。
しかし、そもそもうつ病は何もできなくなる病気ですから、初期の頃は朝起きることも、散歩をすることもできません。治療で一番大切なのは、薬の治療と休養です。できないこを無理強い(むりじい)するのは、追い詰めてしまうだけです。
ネットは情報であふれています。うつ病に効くサプリなど、うまい話がたくさんあります。しかし、確実に効果があるものならば主治医が勧めているはずです。うつ病の回復には時間がかかります。うまい話には振り回されないようにしましょう。
以上、家族の役割について6つ説明しました。うつ病の回復に家族の力はとても大きいものです。また、家族は、安心して過ごせる療養の場であるべきです。主治医と家族でチームを組んで治療に取り組めたら一番良いでしょう。