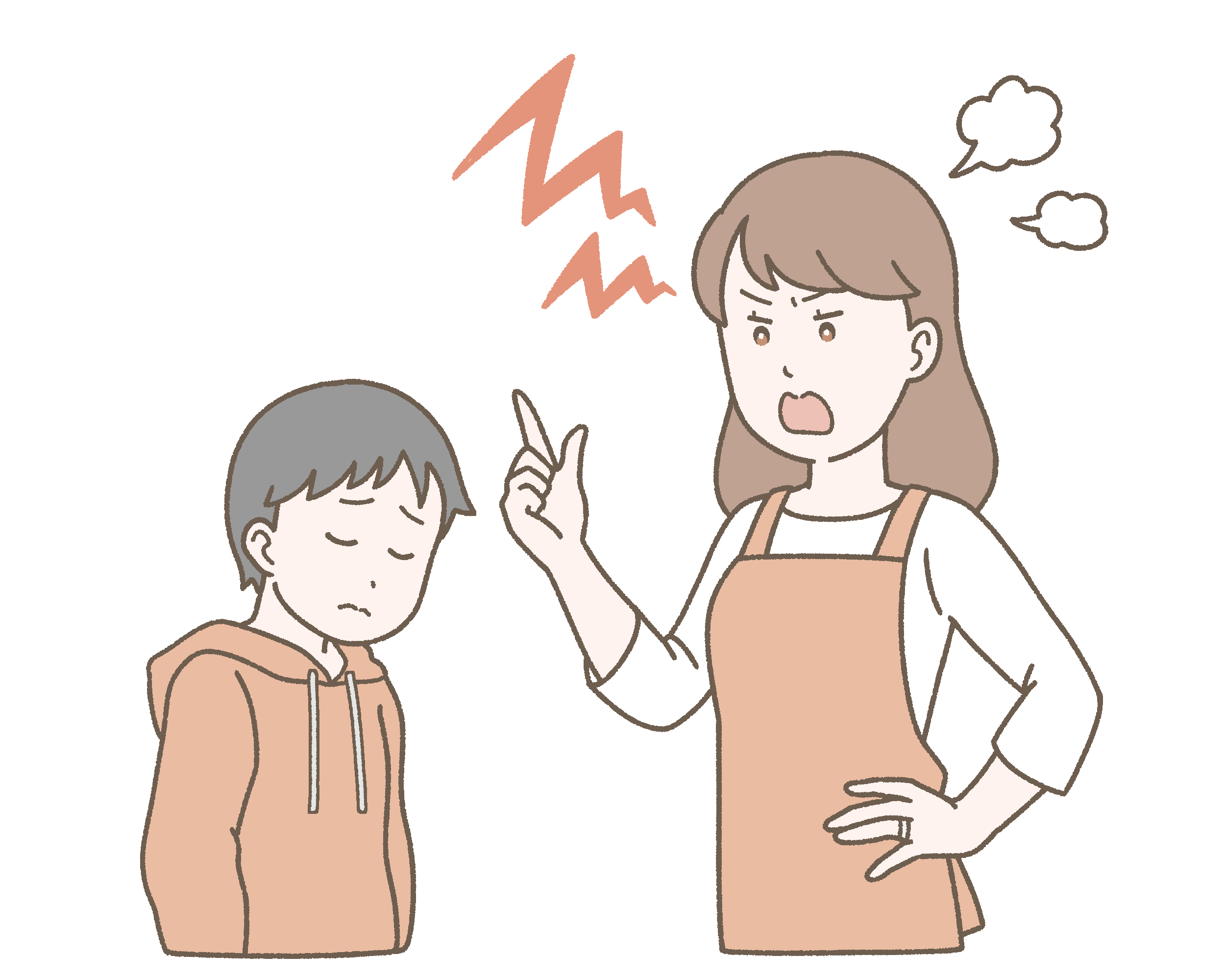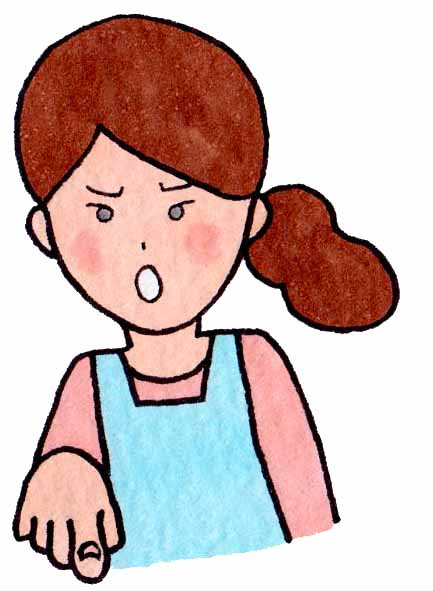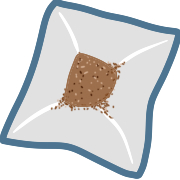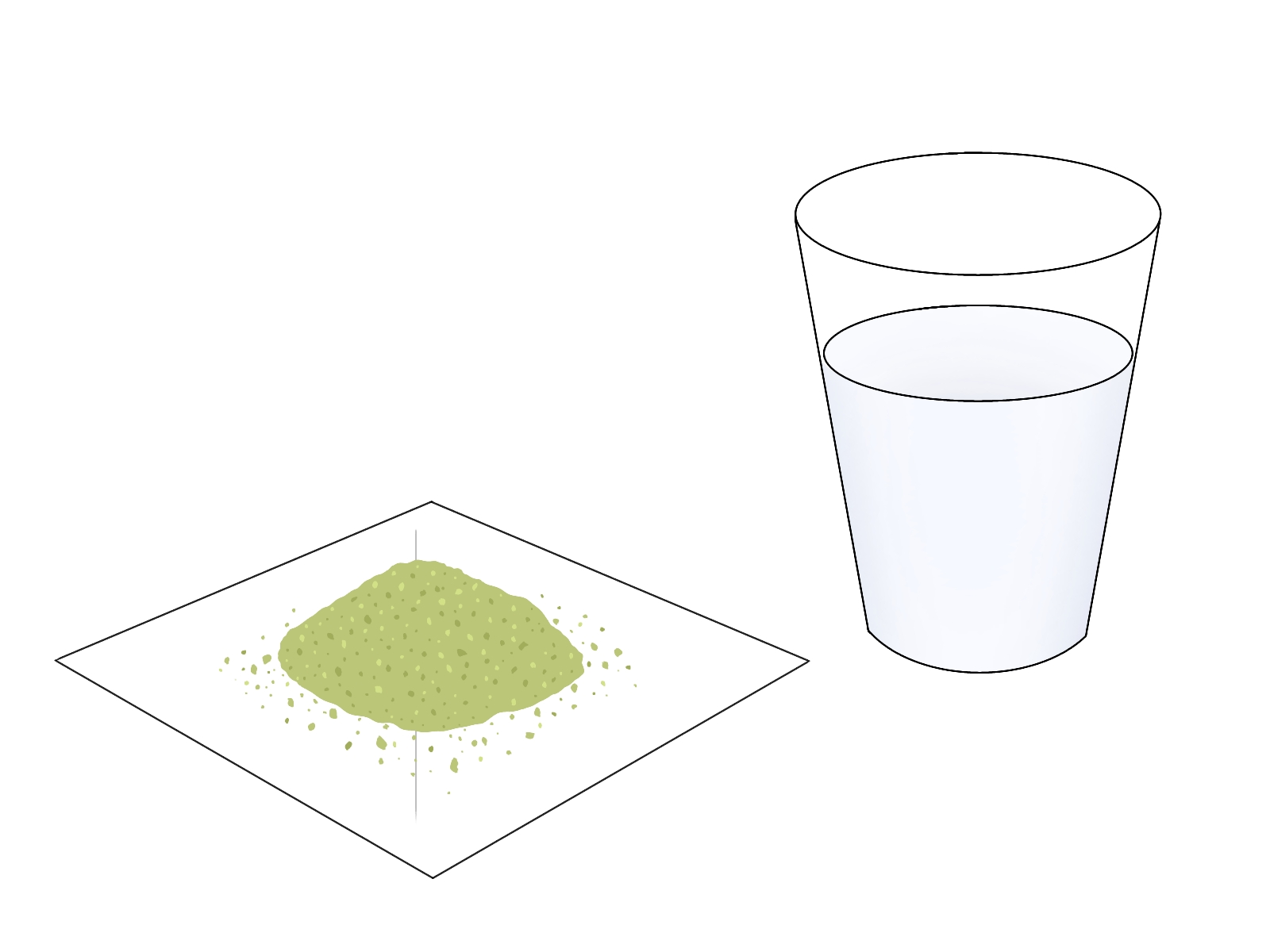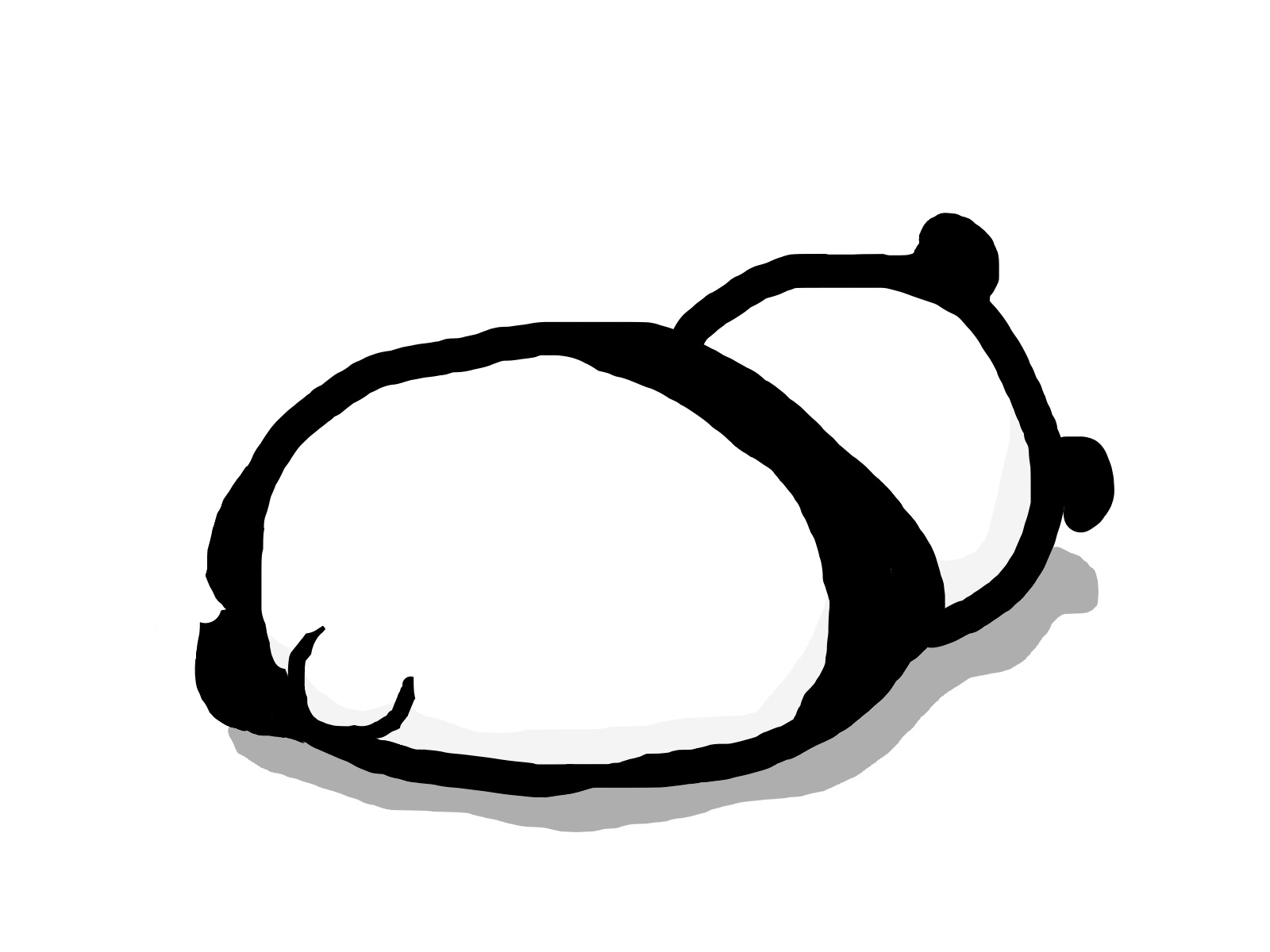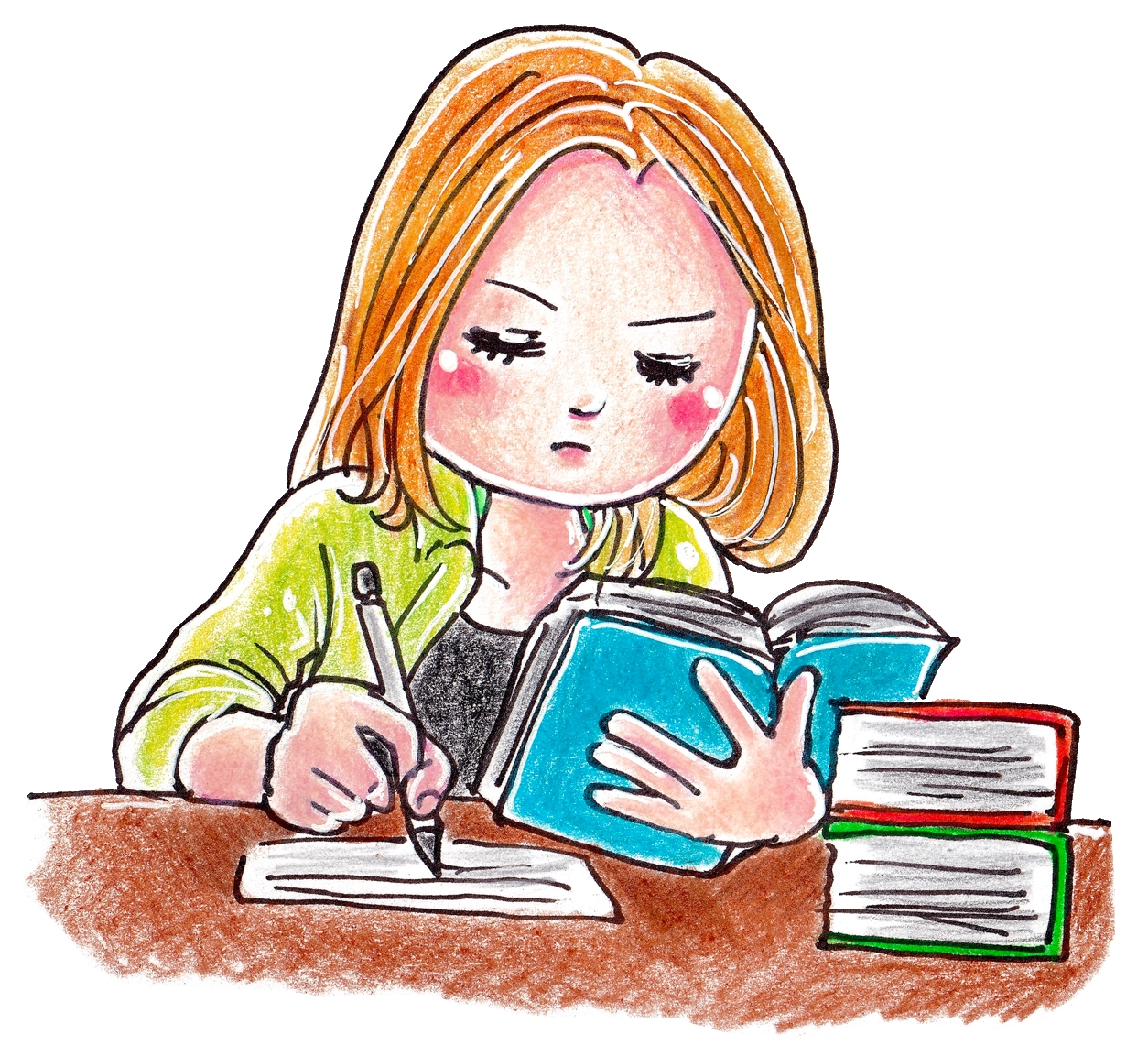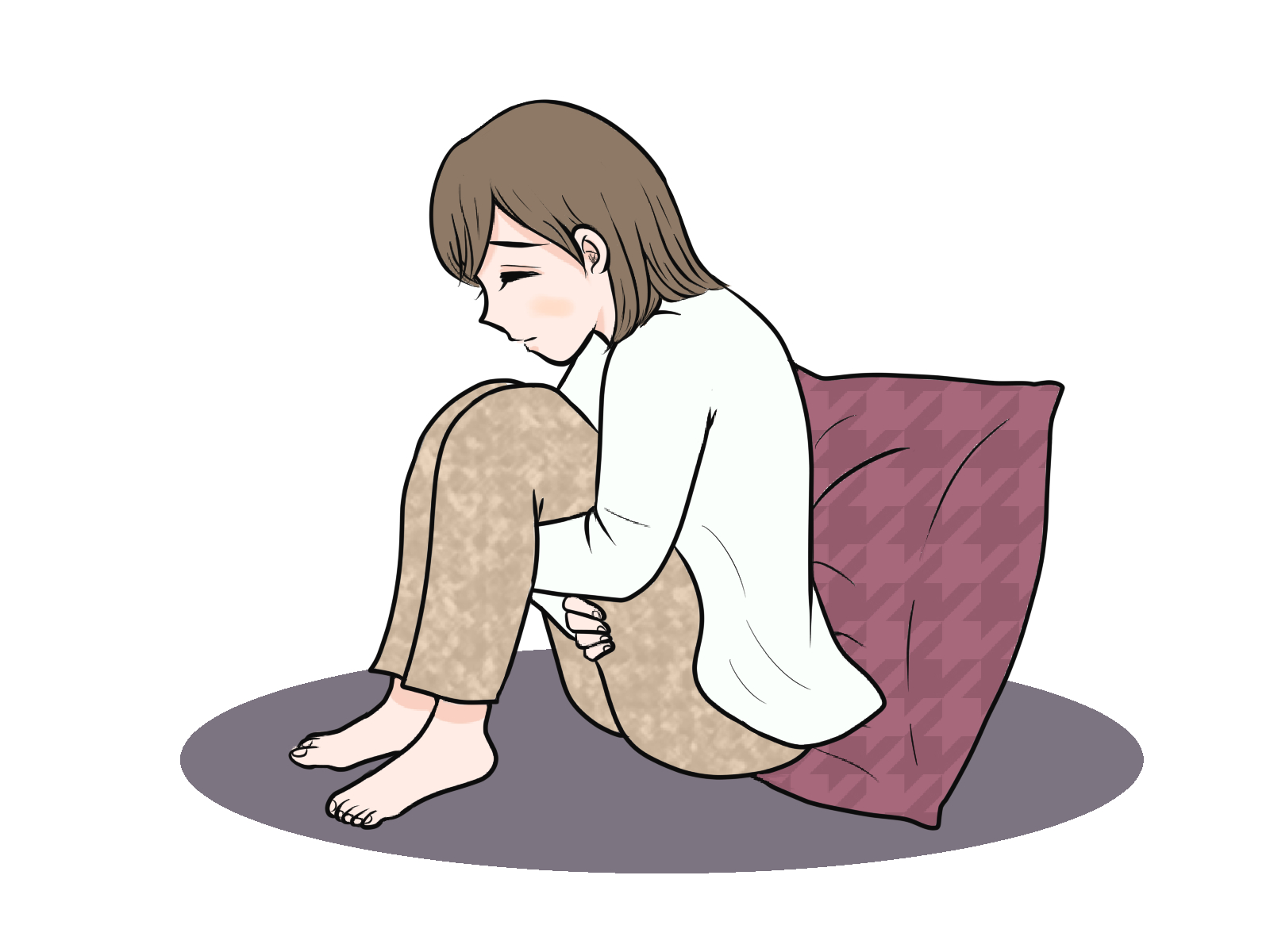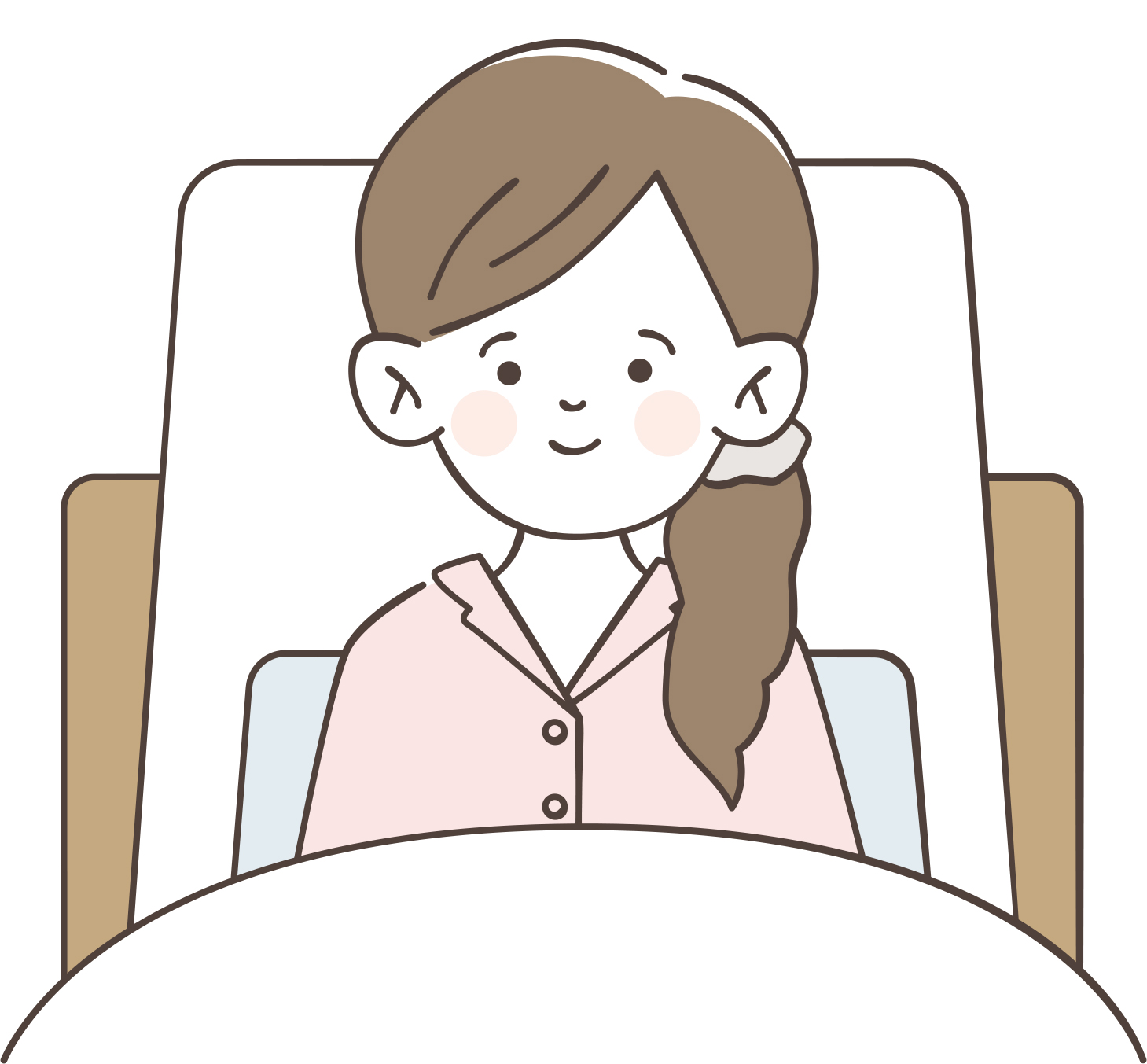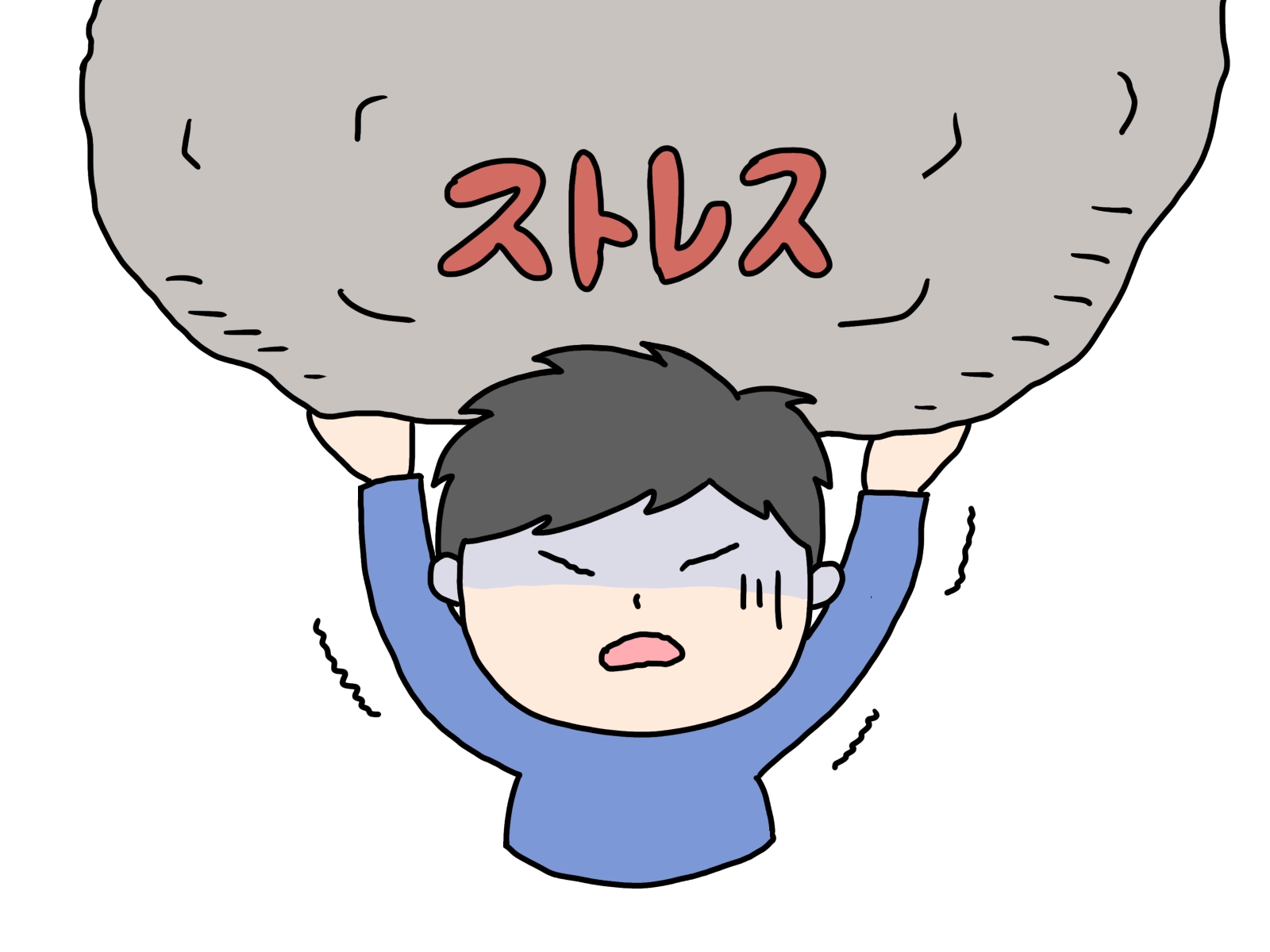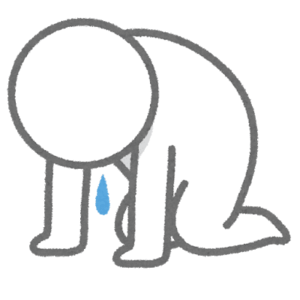産後うつ病
「マタニティーブルー」という言葉をご存知の方も多いと思います。妊娠中や出産後の女性の情緒が不安定になってしまうことです。妊産婦の2割くらいが経験すると言われており、妊娠の初期や出産後に現れます。原因は、女性ホルモンのバランスの変化によるもので、出産後にホルモンの状態が安定すれば、マタニティーブルーも自然におさまります。
ところが、出産後3週間以上たっても不安や気分の落ち込みが治らない場合があります。これを産後うつ病と呼びます。うつ病の一つですが、女性ホルモンの影響が大きいと考えらています。症状は、気分の落ち込みだけではなく、痛みなどの体の症状から精神病的なものまで、人によってうちして様々なものがあります。軽い場合には、気のせいだと放置してしまい、次の子供を産んでから重症になって気づかれるケースもあります。中には、治療の過程で躁状態が現れるようになり、あとから双極性障害と診断され、長い治療期間が必要になるケースもあります。
軽い場合には、気のせいだと放置してしまい、次の子供を産んでから重症になって気づかれるケースもあります。中には、治療の過程で躁状態が現れるようになり、あとから双極性障害と診断され、長い治療期間が必要になるケースもあります。
産後うつ病は、家族関係の影響も受けます。夫や夫の実家との関係が悪いことや、先に産まれた子供に手がかかることも発病の原因になります。出産は、家族がうまくまとまっている状況でないと、妊産婦に大きな心理的負担がかかってしまうのです。
産後うつ病の難しさは、母親が子育てや家事を十分にできなくなることです。調査によると、虐待やネグレクトを起こした母親の多くが、産後うつ病と診断されています。家族の協力なしで、病気の母親だけで子育てはできないのです。
夫や親が子育てや家事の代わりができても、同時に普段の仕事もあります。そのために、家族が病気の母親のことに十分に関わることができないこともあります。母親は孤独を感じ、自分は邪魔者であると思い、よけい病状が悪くなります。最悪の場合、自分がいない方がみんなは幸せだと思い込んで自殺してしまうケースもあります。
実は、出産後1年までの母親の死亡原因の1位は、病気や事故でなく自殺なのです。こうした悲しい出来事を防ぐためにも、産後うつ病は早めに気づく必要性があります。
ここでは産後うつ病のサインを6つ紹介しましょう。
1.子供を可愛いと思えない
子供を産んでも嬉しくありません。むしろ産まなければ良かったと後悔します。家族は喜んでいるので、そんなことは誰にも言えません。子供を愛せない自分を責めてしまい、母親失格だと思ってしまいます。そして、罪深い人間であり、生きている価値がないと思ってしまいます。
2.落ち着かない
子供を育てられるか心配でたまりません。心配は子供のことだけでなく、お金のこと、将来のこと、心配事が次から次へと浮かんできます。何か起きた時に1人で対処できない不安があるので、子供と2人きりで留守番ができません。不安が高じるとパニックを起こすこともあります。
3.情緒が不安定
理由もなく涙が出ます。イライラして怒りっぽく、夫の言動が気になって文句を言ってしまいます。つまらないことで夫婦喧嘩が絶えません。これが原因で離婚話に発展することもあります。さみしくて、用がないのにたくさん電話をします。さみしさを解消するために高価な買い物や過食をすることもあります。
4.家のことができない
いつも疲れて体調が悪く、すぐ横になります。腰痛など痛みが出ることがあります。そのために家事が十分にできません。食事作りができない、掃除ができない、と家のことができない自分を責めてしまいます。できなくて苦しんでいるのに、「しっかりして欲しい」と夫に文句を言われて傷つきます。
5.眠れない
子供の夜泣きがなくなっても、よく眠れません。目をつぶっても嫌なことばかり頭に浮かんできます。夢ばかり見て眠りが浅く、2時間くらいで目がさめてしまいます。お酒や睡眠薬に頼りたくても母乳に影響があることを考えるとそれもできません。
6.死にたい
子育てができない自分を責めて死にたくなります。自分は家族に迷惑をかけているだけの邪魔な存在なので、いない方が幸せだと思います。何かの失敗や家族の言葉が引き金になって衝動的に自殺を試みることもあります。
産後うつ病の治療は、抗うつ薬、睡眠薬による薬の治療が基本です。飲んだ薬は血液を介して母乳にも混じるため、母乳を与えるのは原則禁止になります。ただし、母乳を飲んだ方が赤ちゃんの健康にメリットがある場合もあるので主治医と相談してみましょう。
薬の治療で大きな症状は1か月以内に収まりますが、子育てが家事や十分にできるまでは長くかかります。治療の一つとして家族の育児負担を減らすことが大切です。役所に相談してヘルパーや保育園を利用しましょう。どうしても家で育てられない場合は、子供を乳児院に預けるなどの方法もあります。
このような公的な支援もたくさんありますが、やはり一番大切なのは家族のサポートです。産後うつ病は一人で乗り越えられるものではありません。家族、友人、みんなで支え合って乗り越えていきましょう。
親が発達障害
本来、発達障害は知的障害とほぼ同じ意味で使われていました。知性や言葉に大きな問題はなく、コミュニケーションの能力だけに問題がある発達障害が知られるようになり、1994年に「アスペルガー障害」と正式に呼ばれるようになりました。
現在、アスペルガー障害は「自閉症スペクトラム障害」、略して「ASD」の一つとして扱われています。
アスペルガー障害の一番の特徴は、相手の立場で物事を考えられないことです。子供の時に人が嫌がることをすると、「あなたが同じことをやられたらどうなるか考えてみなさい。」と叱られることがあります。
これができないのがアスペルガー障害です。他人に共感ができないのです。中には、脳の別の回路をつかって相手の気持ちを推理できるようになる人もいますが、普通の人の共感とは違うものです。
通常は小学校高学年までに障害に気付かれますが、軽い場合は、結婚や子育てをして初めて判明するケースがあります。家庭生活で人間関係が密になり、初めて障害が見えてくるのです。
そこで起きる一番の問題は、子育てがうまくできないことです。早めに気付いてあげて、配偶者や祖父母が子育てをサポートすることが必要になるでしょう。保育園などの公的な保育支援が必要になることもあります。
それでは、親がアスペルガー障害である場合、どのような特徴があるのでしょうか?子育ての色々な場面でみられる5つの特徴を紹介しましょう。
1.子供より自分の楽しみが優先
シングルマザーの場合、子供を置いて彼氏との生活を優先してしまうこともあります。暑い日に子供を車に放置したままパチンコをして、子供を死なせてしまう事件もありました。
このようにアスペルガー障害の親は、子供を置いて自分の友人や趣味を優先しがちです。これは子供を愛していないからではありません。1度に1つのことしか考えられないので、自分の楽しみで頭が一杯になると他のことは意識からなくなってしまうのです。
2.自分の考えを押し付ける
しつけ、生活週間、教育のいろいろな場面でこだわりがあり、それを子供に押し付けようとします。はたから見ていると、おせっかいで過干渉です。
普通の親ならば、子供の機嫌をとりながら穏やかに教えようとしますが、それができずに力ずくになります。「野菜をたべないとダメ」、「ゲームは絶対やってはダメ」、「東大へ行かないとダメ」と子供が嫌がっているのに強要します。言うことを聞かないと突然怒り出すので、子供も従わざるをえません。
3.子供と会話ができない
子供の気持ちや関心あることが分からないため、どう接したら良いか分かりません。子供を愛しているのに、思いやりのない言葉や言動で子供の気持ちを傷つけてしまうこともあります。
それに気付かず謝ることもなく平気にしているので、子供はさらに傷ついてしまいます。子供から見れば冷たい親で、同居人としか思えなくなります。
4.突然怒り出す
アスペルガー障害の親は、いつもと違う突然の状況に頭が混乱してパニックになります。子供は自分の思い通りにならないことが多いため、子育てのさまざまな場面でパニックを起こします。
パニックを起こすと、子供に向かって暴言を吐いたり、叩いたりします。子供が憎いから怒っているのでなく、どうしたら良いか分からず混乱して怒るのです。子供は一方的に怒られるので、親の前ではいつも緊張して委縮するようになります。
子供も発達障害の場合は、いっしょにパニックを起こして手がつけられなくなり、力づくで子供を従えようとするために虐待になります。力加減が分からず、子供に大怪我を負わせてしまうケースもあります。
5.学校に文句をいう
いわゆるモンスターペアレントです。特にADHDの傾向がある場合に見られます。怒るのは子供がいじめられた時など、子供を守ろうとする正義感から始まるのですが、文句の言い方が尋常ではありません。先生や他の父兄に向かって、女子が部下を叱り飛ばすように文句を言います。学校側に非があったとしても、ヤクザのように怒るので、どちらが悪いのか分からなくなります。
残念ながら、アスペルガー障害は生まれつきのもので治すことはできません。障害に気づいたら、周りがサポートしてあげましょう。ただし、子育てに悩んでうつ状態になった場合には精神科で治療できます。
自分の親のことを振り返ってみて、「友人の親と違って変わった親だ」、「子供の気持ちを理解しないひどい親だ」と感じている人は親がアスペルガー障害なのかも知れません。中には、毒親のために縁を切っている人もいるでしょう。しかし、親に障害があるのかと思うと、子供の頃の辛かった仕打ちの理由が分かってくると思います。「親も障害で辛かったのかな」と思えば、少し許してあげられるかもしれません。
漢方薬で心の病気は治せるの?
「精神科に行ってみたいけれども薬を飲まされるのが怖い。漢方薬で治せないか?」と思われる方がいらっしゃいます。確かにネットには、精神科の薬は長く飲まなくてはならない、副作用がある、などの記事がたくさん出ています。
こういった記事を読まれた方が、「何とか精神科の薬を飲まないで済まないだろうか」という思いで漢方薬を希望されるのでしょう。果たして漢方薬で心の病気は治せるのでしょうか?
ここでは心の病気は漢方薬で治せるか、というテーマで説明します。
そもそも漢方薬とはどのようなものでしょうか。漢方薬の原料は生薬(しょうやく)というもので、主に薬草を加工したものです。生薬とは、例えば、朝鮮ニンジンは疲労回復に効果がある、柴胡(さいこ)はうつ気分を改善させる、など古くから効能が知られて来ました。これらの生薬を複数組み合わせることで効果を調整したものが漢方薬です。継続して長く飲むことで自然治癒力を高め、体質改善の効果があります。
ただし漢方薬は症状を抑えるのが目的ではないために、症状を和らげるという観点からは効果が出るまでは遅く、効き目もマイルドです。
うつ病、パニック症、躁うつ病、統合失調症などの精神疾患は、しっかり症状を抑え込むことが必要です。症状を取ることで自然治癒の力が働き、病気が治っていきます。ですから、漢方薬は精神疾患の治療に向いていません。
しかし、漢方薬は精神科で使われないということではありません。検査しても異常はないけれども何か調子が悪い、ということを不定愁訴と呼びますが、漢方薬は不定愁訴によく効きます。特に自律神経失調症、心身症、軽いうつ病の体の症状などには効果があります。例えば、頭痛、めまい、肩こり、消化不良、体温調整不良、倦怠感、不眠などの症状を改善させることができます。
また、防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)のように、精神科の薬による体重増加、むくみ、便秘などの副作用を改善させるために使われるものもあります。
精神科でよく使われる漢方薬を紹介しましょう。
1.抑肝散(よくかんさん)・抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんちんぴはんげ)
神経が高ぶっており、怒りやすく、イライラ、不眠のある人に効果があります。気分安定薬のような作用があり、自閉症の子供や認知症のお年寄りのイライラにもよく使われています。
2.当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)・加味逍遙散(かみしょうようさん)
虚弱体質の女性で、生理不順や更年期障害による自律神経失調のある人、特にうつ気分や体のコリや痛みがある人に効果があります。更年期の女性の自律神経失調症によく処方されています。
3.酸棗仁湯(さんそうにんとう)
心身の疲れによる不安、不眠がある人に効果があります。睡眠約を飲むのが怖いという不眠症の方によく処方されています。しかし、睡眠薬ほどの効果は期待できません。
4.補中益気湯(ほちゅうえっきとう)・六君子湯(りっくんしとう)
疲労かたくする食欲不振があり、体力や気力がない人に効果があります。
5.加味帰脾湯(かみきひとう)
食欲不振で元気がなく、貧血、不安、不眠などがある人に効果があります。
6.柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこ・か・りゅうこつぼれいとう)
血圧が高く、比較的体力がある人で、ストレスが原因のイライラや不眠がある人に効果があります。
7.防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)
やせ薬としてテレビのコマーシャルでもよく紹介されています。精神科の薬による体重増加、むくみ、便秘の改善に効果があります。
精神科の薬は脳の神経に働きかけて、症状を抑えることで神経の活動を整え、それによって自然治癒の力が働きます。精神疾患は症状をダラダラと放置しているとむしろ慢性化してしまいます。精神科の薬の副作用を気にされている方がいますが、「角を直して牛を殺す」ということわざがあるように、薬の副作用を恐れるあまりに、薬を飲まないで病気を慢性化させてしまうことは一番よくないことです。
漢方薬だけで精神疾患を治すことは難しいことです。しかし、漢方薬は自律神経失調症などの不定愁訴によく効くので、精神科の薬といっしょに使うことで力を発揮することがあります。漢方薬に詳しい精神科医もいますので気になる方は相談してみてください。
うつ病休養中にやってはいけない7つのこと
うつ病の回復は日々少しずつです。十分に回復していない時期は、時間を持て余すことがあります。暇を感じるので、これをやってみよう、あれをやってみようと、いろいろ頭に浮かんできます。やりたいことが出てきたのは回復してきたサインですが、実際に行動に移すまでは自信がありません。
また、心配した家族や友人から気晴らしの誘いもあるでしょう。乗り気ではないけれど、「せっかくの誘いなので断ったら悪いな」、「もしかしたら付き合うことで何か変わるかな」と悩んでしまいます。こんな時、どうやって過ごしたら良いのでしょうか。やってはいけないことはあるのでしょうか。
ここでは、うつ病の療養中にやりがちだけれどもやってはいけないことを7つ紹介します。
1.旅行へ行く
「旅行先できれいな景色を見て温泉につかったら、リフレッシュしてうつ病が治るかも知れない」と誰でも思いがちです。心配した家族や友人に誘われることもあるでしょう。しかし、うつ病は単に元気がない状態ではありません。
気分転換したから良くなるような単純な疲労とは違います。無理して旅行へ行っても、気を遣って楽しめないどころか、心身を消耗してしまいます。寝床が変わって眠られなかったり、何かのトラブルに巻き込まれることもあります。多くの場合、疲れ切って帰ってきて、よけいに具合が悪くなります。うつ病の時の旅行はやめた方が良いでしょう。
2資格の勉強をする
しばらく家で療養するので、この時間を有意義に過ごそうと思いがちです。よく思いつくのが資格をとることです。しかし、集中の持久力がないので、最初は良くてもだんだん勉強が負担になっていきます。
結局あきらめてしまい、受講料を無駄にしたり、できなかった自分を責めて、自己嫌悪に陥ることがあります。休養中は資格を取る、習い事をするのはお勧めではありません。
3.大きな買い物をする
うつ病が回復していくと、いろいろ欲しい物がでてきます。買い物の欲が出てくることは良いサインです。自分へのご褒美のちょっとした買い物は良いことです。
「元気になって、がんばって働けばいいや」と言い訳をして、女性ならブランドバッグや着物、男性なら車や電化製品などを買ってしまいます。しかし、病気はいつ治るか予定が立てられないものです。ローンの負担が回復を妨げることもあります。「なんでこんなものを買ったのだろう」と後悔しないように、先を見越して大きなお金を使うのは控えましょう。
4.夜更かしをする
休みの間に「やりたかったゲームを思いっきりやろう」「見たかったビデオを見よう」というのは悪くはないですが、夜更かししてまでやるのは良くありません。生活のリズムは崩さないように夜は12時までに床につくようにしましょう。
5.会社をやめる決断をする
ハラスメントや過重労働でうつ病になったので、「もうこんな会社とはすぐに縁を切ってやる」という人もいます。しかし、転職するのもエネルギーがいることです。
衝動的に会社をやめないで、とりあえずゆっくり休職しましょう。休職中は傷病手当金を1年半まで受け取ることができます。補償は給料の6割ですが、節約すれば何とか生活はできるでしょう。ゆっくり休み回復してから次のことを考えましょう。もしかすると良くなった頃には、職場から嫌な上司はいなくなっているかも知れません。
6.引っ越す
二宮和也主演の「フリーター家を買う」というドラマは、うつ病の母親のためにフリーターの息子が家を買う話でした。母親は近所の意地悪な主婦にいじめられてうつ病になったのです。
家に病気の原因がある場合は引っ越しは一つの解決策でしょう。しかし、引っ超しには大変なエネルギーを使います。新しい町での生活にも慣れなくてはいけません。「引っ越しうつ病」というものもあるくらい、ストレスが高いものです。どうしてもという事情がない限りは、引っ越しは良くなってからにしましょう。
7.薬をやめてしまう
休んでいる時はネットで病気のことを調べがちです。中には根拠のない記事もあります。特に、薬は体に悪いという記事をよく見かけますが、かなり偏ったものが多いようです
こうしたものを信じて薬をやめてしまう人もいますが、やめた直後に変化はなくても、1か月くらいすると元の症状が出始めることがあります。抗うつ薬はゆっくり効果が出て、やめてもしばらく効果が続くという特徴があるのです。一度悪くなってそこでまた薬を飲み始めてもすぐには良くなりません。薬は途中でやめないで、十分な期間を飲みましょう。薬に関しては処方している医師と良く相談してみてください。
うつ病を治すコツは、遠回りなようでも、新しいことはせずに平凡な規則正しい生活が良いのです。栄養バランスのとれた食事、十分な睡眠、そして短時間のウォーキングなどの軽い運動が大切です。
むしろ、何か新しいことをして早く治そうとか、時間を有効に使おうと焦ること自体がうつ病を長引かせる原因です。もしかすると症状としての焦りなのかも知れません。「今日も何もしなかった」というような、あきらめの日々の積み重ねが意外と回復につながっているのです。
うつ病の入院
うつ病が長引いている人は、入院したら早く良くなるのでしょうか?何か入院するメリットはあるのでしょうか?しかし、精神病院と聞くと、鍵のかかる部屋に閉じ込められて薬をたくさん飲まされる、など怖いイメージをもたれる方も多いようです。
近所に精神病院があっても近寄りがたい雰囲気もあります。実際にうつ病の入院はどのような感じなのでしょうか?
基本的に、うつ病は通院で薬の治療が中心です。入院しても薬を中心とした治療は同じで、入院でなければ使えない薬も特にありません。例外として通電治療、磁気治療などを行う場合は入院が必要ですが、最近ではこれらの治療を通いで行う施設もあります。
薬の治療と併行して、うつ病は静養することがとても大切です。住み慣れた自宅でゆっくりするのが一番良いことです。しかし、自宅では仕事の連絡が来て休めない、小さなお子さんがいるのでゆっくり寝てられない、と言う人もいて、静養を期待して入院する人もいます。
ところが精神病院には他の患者さんがいるので余計落ち着けない場合が多いようです。大部屋では隣の人のいびきで眠られず、余分にお金を払って個室に入院できても、食事はホールでたくさんの患者さんといっしょですし、入浴も順番を守らなければいけません。せっかく入院したのに制約の多さによけいイライラしてすぐに退院するという人もいます。
うつ病の患者さんが一番多く入院するケースは、同居している家族と一時的に距離を置きたいという理由です。長い闘病生活から看病する家族にもストレスがたまり、些細なことから言い合いになり、患者さんは自分が家族の邪魔な存在ではないかと自分を責めてしまい病状が悪化してしまうことがあります。短期間でも家族から離れることで、お互いに気持ちを整理してリセットできます。
そのために気軽に入院を利用したいのですが、さきほどの理由でよけいに落ち着けないことが多いのです。どうしても入院する場合は、その前に病棟の見学ができるので、よく雰囲気を知ってから入院しましょう。精神病院よりも、総合病院の精神科の方が比較的軽症の患者さんが多いので落ち着いた雰囲気があります。どうしても相性のよい病院に巡り合えない場合は、ビジネスホテルに何泊するのも手です。
社会的にうつ病の患者さんが増えるようになり、2000年頃からうつ病専門の静養病室というものができてきました。広い個室でテレビ、パソコン、シャワーが完備はもちろん、中には高級ホテル並みのサービスで、フロア内にフィットネス、ジャグジー、図書館、映画室が備わっているところもあります。
ただし、治療費とは別に1日10000円以上の差額ベット代がかかります。通常のうつ病の治療費は1か月10万円くらいなので、合計で月に40万円以上がかかります。これでは庶民には縁遠い費用です。政治家や芸能人がスキャンダルを起こして、社会の目から逃げるための入院ではよく利用されているようです。
うつ病の治療は基本的に自宅でゆっくりしながら通院するのが良いのです。しかし、どうしても入院が必要な場合があります。だいたい次のような場合です。
まず、急性期の治療が必要な場合です。例えば、死にたい気持ちがつよくて誰かが管理していないと本当に自殺してしまう、食事ができないために体調が弱っていてこのままでは命の危険がある、不安や興奮で人に危害を加えてしまうようなケースです。
これらは命の危険があるために、時に本因の承諾なしに入院することもあります。本人の承諾のない入院には、家族の承諾で入院する医療保護入院、警察に保護されてから精神保険指定医によって入院が決められる措置入院の2種類があります。安全のために保健室という自由に出られない部屋に入ったり、意にそぐわない扱いをされた記憶だけが残っていて、入院が恨みになる人も多いようです。
医療保護や措置入院は好ましい入院の形ではありませんが、命を守るためにはやむをえない対応です。退院後にはよく家族で話し合い、入院中の嫌な思い出をよく聞いてあげて、辛かったことを慰めてあげましょう。
他にも昼夜逆転を治したい、孤独を改善したい、一人暮らしで介護してくれる人がいない、などの理由で入院する場合もあります。
精神病院には、急性期が得意なところ、療養が中心のところ、など、それぞれ特色があります、入院してから「こんなはずではなかった」とならないように見学をしてから入院をすることをお勧めします。短期間の静養だけならば、病院ではなくビジネスホテルなどを利用するのも良いでしょう。
頑張り過ぎないコツ
頑張るとは、困難に負けずに我慢してやり抜くことです。それは、誰もが認めるすばらしいことです。学校ではその大切さを学び、漫画やアニメのくじけないヒーローに憧れて育ちます。
ところが現代社会では、頑張り過ぎて体調を壊してしまう人がたくさんいます。原因は自分のキャパを超えた仕事量や人間関係にあります。しかしそれを乗り越えなくては今の仕事を失う、出世はない、という理由で無視をしてしまうのです。
うつ病に代表されるように過労による病気は、自分のキャパを超えた頑張り過ぎによるものです。実は、頑張るには、「我を張る」というネガティブな意味もあるのです。悪い意味の頑張るにならないように、頑張り過ぎないように注意しましょう。
ここでは、頑張り過ぎないためのことわざや格言を7つ紹介します。
1.「無理をしないことも大切。むちゃをして体を壊せば何もかも台無し。ハリウッドスターに対して、皆さんは華やかできらびやかなイメージをお持ちでしょう。でも彼らは努力を惜しまないし、自己管理をしっかりしています。」戸田奈津子
頑張ることは、無理をすることではありません。頑張り過ぎとは、自分のキャパを超えて無理をしてしまうことです。無理をして健康を害しては元も子もありません。健康を管理するのも仕事のうちです。特に大切なことは、体調が悪い時は無理をせずに、積極的に休むことです。
「諦める」という言葉の響きは、負けを認めるようなネガティブな印象があります。しかしその起源は仏教にあり、本来は、真理や道理を明らかにして、物事を見極めるというポジティブな意味でした。何も考えずに進むのではなく、このまま進んで良いのかを一度立ち止まってよく考えることなのです。やみくもに最後までやり遂げるのが良いわけではありません。中途半端も良しとしましょう。
100%の力を出し尽くして働いて、やっとの思いで家に帰り寝ることしかできない、こういう生活は健康に良くありません。このような生活は、うつ病は過労死が起きやすいのです。家でゆっくり自分の時間を楽しむために、余力を残して帰りましょう。夜の時間は翌日の力を蓄える大切な時間です。仕事は100%でなく、80%の力でやるのがお勧めです。残りの20%は他のことのために取っておきましょう。
4.「疲れた時は休みたくなるんだ。そういう時は潔く休めばいい。怠けたい気持ちが湧き上がったら、無理してもいい仕事はできないよ。」
黒澤明
「疲れたな」、「体が痛い」、「嫌になってきた」など、仕事に集中できなくなったら、休んで欲しいという心と体のSOSです。仕事のキリが良いところまでやってしまおうと思わずに、疲れを感じたらまず休みましょう。無理をしてやることは効率が悪いことです。
5.「助けを求めることは恥ずかしいことではない」 桜井翔
問題が自分に解決できるかどうかを見極めることは大切なことです。できないと思ったら、いつまでも抱え込まないで助けを求めましょう。仕事でも同じです。できない仕事を自分一人で抱え込まないで、人に任せることも考えましょう。山のような大量の仕事を減らすには、協力することが最も効率が良いことです。
6.「偽りの自分を好かれるより、ありのままの自分で嫌われる方が良い。」 アンドレ・ジッド
言われたことを引き受けるのは、「はい」と言うだけで、その場は簡単です。しかし、気軽に引き受けて、後から後悔したことはないでしょうか。また評価を気にして、無理をして引き受けることもあるでしょう。結局良い結果を出せなくて迷惑をかけてしまう、このような結末にならないように、頼まれたその場で断ることも必要です。「できません」と言える勇気を持ちましょう。
勝ち目のない勝負はしないことです。まずは逃げて次に備えましょう。例えば、職場がどうも自分に合っていない、仕事内容が期待していたものと違うし、上司ともうまくいかない。そんな時は潔く辞めてしまうのも手かもしれません。
頑張ることの格言やことわざは山ほどありますが、頑張り過ぎないというものは意外とありません。なぜならネガティブな印象があるためです。しかし、今の時代に最も必要なのは心のゆとりです。頑張り過ぎないことは悪いことではありません。頑張り過ぎに注意して、無理のない生活を心がけましょう。
孤独の解消の仕方
人間は一人で生きられるものではありません。どんなに優秀な人でも、社会の歯車の中に組み込まれているからこそ、その才能を発揮できるのであって、一人で生きているわけではありません。
社会、家庭、友人、などの人間関係が少なくなってくると、人は孤独を感じるようにできています。「一人ではいけない」という心のサインが孤独という感情なのです。
孤独な時に私たちがよく行うのは、好きなものを食べたり、友人とお酒を飲みに行ったり、欲しかったものを買ったりと、食欲や物欲を満たしたり、SNSでつながりを求めたりすることです。私たちの周りには、手っ取り早い孤独解消法がたくさんあります。
こうしたことは一時的に孤独を癒してくれますが、すぐに元の孤独に戻ってしまうことはないでしょうか。またよけい孤独になってしまうことはないでしょうか。
お腹がすいた時に、手っ取り早く手に入り、味の濃いジャンクフードばかり食べていると体を壊してしまいます。食べることは空腹の満足だけでなく、体の成長の力になり、健康を維持する目的があります。同じように、孤独だからと言って、その場限りの対応をしていると、心が病んだり、心の成長も期待できないでしょう。
お坊さんは、寺にこもる修行があります。仏教に限らず、どんな宗教にもあえて自分を孤独な状況に置くという修行があります。これは心身を痛みつけるのが目的ではありません。外からの刺激を絶ち、孤独の中から何か大きなものを感じ取り、心を成長させるために行うものです。悟る内容は宗教は人それぞれに違いますが、いくつかの共通点があります。
それは、世の中に見えない大きな生命の力、愛の力が働いていること、人はその中で自分が生かされている小さな存在であること、こうしたことを悟るために行うのです。
こうした体験をすると、心が成長し、些細なことでも不安やイライラしなくなり、人に優しくできるようになります。ですから孤独はそれほど悪いものではありません。うまく利用すれば、自分を見つめなおし人を成長させる機会となります。
ただし、私たちのような普通の人がこのような修行をすることは大変難しいことです。できるだけその場限りでない孤独の解消法を通して、少しでも自分を成長させることができたら良いかも知れません。
ここでは、このような意味のある孤独の解消法を5つ紹介します。
1.理解してくれる人に相談する
人の心の中心には承認欲求と言うものがあります。理解されて、認めてもらって、生きている価値を感じるのです。世の中に誰か一人でも自分の苦労や苦しみを知ってくれている人がいれば孤独を感じません。
家族の中に理解者、相談者がいれば一番良いのですが、最も近くで生活している家族が心の距離の遠い存在であることも多いようです。信頼できる先輩や友人などに思い切って相談するのも良いかもしれません。周りにそういう人がいない場合は、カウンセリングを利用するのも手です。
2.人の喜ぶことをしてあげる
人間関係は待っていては始まりません。魅力のある人は、周りから人が寄ってくるのでしょうが、普通は自分から交流を始めることが必要です。まず、人を喜ばせることから始めましょう。
喜ばせることが、感謝となって返ってきて良いコミュニケーションが生まれます。家族や友人に誕生日のプレゼントをする、さみしい思いをしている人に連絡をしてみる、など簡単なことから始めてみましょう。
プライドがある人は、なかなか自分から行動を起こせません。プライドの高い人ほど孤独をつくりやすいとも言われています。
3.自然にふれてみる
インスタ映えの目的で話題のパワースポット巡りをしたところ、「実際に見えないパワーを感じた」という人も多いようです。自然の中には生命の力が宿っています。公園などの自然の中で、ゆっくり深呼吸をしながら、時間が過ぎるのを忘れてしばらくたたずんでみるのも良いでしょう。余裕があれば、家で生き物を飼ったり、植物を育てるのも良いかもしれません。
4.職場以外の所属をつくる
職場は、利益を目的とする集まりです。会社が儲かることが活動の中止なため、人を才能や実績だけで評価し、仲間同士での競争があります。こうしたところに長く所属することおは心をすり減らしてしまいます。
しかし、趣味を中心とした集まりは、利害のない人間関係であり、生きがいを感じる居心地のよい場所となる可能性があります。職場の集まりだけでなく、趣味を中心とした集まりにも参加できたら良いでしょう。
5.運動をする
日頃デスクワークばかりで運動不足となり、そのストレスから孤独感がきているかも知れません。心と体には相関関係があります。体を動かすことは、心も開放的にします。かといってスポーツジムに行って激しい運動をする必要はありません。心をスッキリさせることには、週に4日程度、1回に20分程度の早歩きで十分です。このようなウォーキングはうつ病や認知症を予防する効果があることが証明されています。
最後ですが、いつも孤独で苦しい場合は、もしかしてうつ病の症状かも知れません。人の中にいても疎外感を感じて、孤独であるというのもうつ病の症状です。
孤独で不眠や食欲が落ちるなど、日常生活にも支障が出てしまう場合もあります。このような場合はうつ病の可能性があるので精神科を受診することをお勧めします。
アダルトチルドレンとヤングケアラー、親と縁を切りたい人
アダルトチルドレンとは、「アダルトチルドレン・オブ・アルコホーリクス」を略したもので、日本語に訳すと「アルコール依存症の家庭に産まれた人」という意味です。
アメリカには日本と比べものにならない数のアルコール依存症の問題があり、1970年代のアメリカでは、アルコール依存症の家族の研究が盛んに行われました。
アルコール依存症の家庭の子供は、いつ親が酒を飲んで暴れ出すか分からない不安の中にあり、つねに緊張が抜けず、感情を抑え込まれた生活を送りました。そのために、大人になっても自分の感情が出せなくなり、自分を責め、自尊心が低く、生きづらさを感じていることがわかりました。
その後、この現象は薬物依存、ギャンブル、ワーカホリック、暴力で虐待された家庭に育った人に共通にみられることが知られるようになりました。このような親の都合で子供が抑圧されている過程を機能不全家族と呼ぶようになりました。
アダルトチルドレンの考え方は、日本には1989年に入り、当時の20代から40代の人たちに受け入れられました。書かれた本はベストセラーになり、テレビでは何度も特集が組まれました。アダルトチルドレンを治療するという施設には行列ができたくらいです。
なぜここまで受け入れられたかと言うと、この世代の多くの人が厳しく仕事中毒の父、子供に学歴をつけることを目的にした良妻賢母の母、という昭和の高度成長期の家庭に育っていたからです。日本ではこのような家庭も機能不全家族ととらえました。
アダルトチルドレンの考え方は、自分の生きづらさは自分のせいでなく、家庭が機能不全家族だったから仕方ない、自分をせめずに人生を先に進もうという、新しい自分をつかむための心の啓発として大きな役割を果たしました。
しかし、残念ながら親を責め続けて許せないまま、恨みに囚われて人生を先に進めなくなってしまう人も多く現れました。また、アダルトチルドレンの意味が拡大解釈されて内容が曖昧となり、心理学や精神医学などの学術の分野からは扱われなくなりました。現在は当時と家庭のあり方が変化したこともあり、一時のブームが去ったという印象です。
最近アダルトチルドレンと似ているヤングケアラーという言葉がメディアでよく取り上げられます。ヤングケアラーは親の病気のために家事や介護を強要される子供を言います。彼らの中には、親の心配ばかりして全く甘えられず、本音を言ったら親に嫌われる不安から、親の顔色だけを見て育った人もいます。
こうした人は心を病み、大人になっても自分の気持ちを抑えたり、悪いことがあると自分をせめる癖がついてしまいます。つねに緊張感や絶望感があり人生を楽しめません。このような心を病んだヤングケアラーもアダルトチルドレンと呼べるでしょう。
アダルトチルドレンやヤングケアラーで苦しんでいる人たちは、子供の頃に親から無償の愛情を受けられず、親の事情に振り回され、親の要求を満たさない限り親に認めてもらえなかった苦しみを味わった人たちです。
成人して経済的に自立することで、一時的に親の束縛から逃げ出すことができます。形としては親と縁を切ることはできますが、何か辛いことがある度に親の顔が浮かんで許せない気持ちになります。いつまでたっても親への恨みがとれず、それが心の成長を妨げて人生を先に進めないでいます。
低い自尊心と恨みの感情は悪い循環をつくり、心の傷が癒されるどころかさらに心が病んでしまいます。一言でも「悪い親ですまなかった」と謝ってもらえれば救われるのに、思い切って連絡しても、以前と変わらない親の様子によけい辛い思いになります。
この悪い循環を抜けるためには特効薬はありません。やはり親には期待せずに距離を取り続けた方がよく、むしろ信頼できる人との出会いを積み重ねていく方がよいでしょう。友人、恋人、なかなか良い出会いがなければ心理カウンセラーに相談するのも良いかもしれません。こうした利害関係のない良い人間関係が唯一傷ついた心を癒してくれる方法ではないでしょうか。
精神科医の夏苅郁子さんは、統合失調症の母、暴力をふるう父の家庭に育ちました。幼少期、自分勝手な父は留守がちで、病気の母と2人だけの孤立した生活を送りました。妄想で狂って暴れる母とそれを殴る父の姿が忘れられないと言います。病気の母親は離婚し追い出され、父と生活をすることになります。
。学校の成績が良く医学部に進学しましたが、リストカット、摂食障害、薬物依存になり、精神科を通院するようになります。低い自尊心と絶望感に囚われ、2度の自殺未遂をしたそうです。心の中には常に両親の姿が恐怖や怒りとして残っていたそうです。
しかし、よき理解者である夫や、統合失調症の母を持つ同じ境遇の漫画家中村ユキさんとの出会いを通じ、両親を理解し許すために自分の過去と向き合うようになります。そうせざるを得なかった両親を理解する中で自分自身の心も解放され成長していくことを語っています。現在は児童精神科の診療とともにヤングケアラーの啓蒙活動をして活躍されています。
夏苅さんのように、親に愛してもらえなかった恨みは、親と縁を切って終わらせてはいけないのかも知れません。信頼できる人との出会いを通じ、心に少しでも余裕が出たら、親の不完全さを受け入れて、いつか親を許すことが必要なのかも知れません。
人格障害って何? 境界性について
精神病とまでは言えませんが、考え方や言動が変わっていて、社会に溶け込めずに困っているという状態を人格障害、もしくはパーソナリティ障害と呼びます。変わっているといっても個性的の域をこえており、異常性格とか病的性格とも言われるものです。以前は精神病質、サイコパスと呼ばれていました。
考え方や言動が偏っているといっても、どこまでが正常でどこからが障害なのかは明確なラインはありません。社会と歯車が合わず、本人も周囲も困っている場合に診断がつけられます。明らかに人格障害と思われるハリウッドセレブなどの有名人もいるように、障害があってもうまく社会に適応していることもあります。
人格障害は大きく3つのタイプに分類されます。
(A)猜疑心がつよく人との関わりをもとうとしないタイプ。妄想性人格障害などがあります。
(B)自己中心的で感情のコントロールがつかないタイプ。言動や暴力で相手を傷つけたり、社会で問題を起こすことが多くあります。犯罪行為に至ることもあります。
(C)こだわりがつよく、依存的で心配性のタイプ。引きこもりになるケースが多いです。回避性人格障害、依存性人格障害などがあります。
人格障害の中でも私たちの身近で問題となるのが、境界性人格障害というものです。これは、ボーダーラインパーソナリティ障害とも呼ばれており、(B)に分類されます。いつも虚しさがあり、見捨てられてしまうのではないか不安感をもっています。見捨てられそうになると、なりふり構わず暴力や自殺未遂などで狂ったように相手の気を引きます。怒りのコントロールがつけられません。精神病的な妄想の症状がある人もいます。
家族や恋人が境界性人格障害であると、生活が振り回されることが多く、その対応に大変苦労することがあります。そのために人格障害の中では最も関心を持たれるものです。
ここでは境界性人格障害について説明します。
1970年代にはアメリカで境界性人格障害の患者数が増え、精神分析的な研究が盛んに行われました。発病と幼児期の虐待やトラウマとの関連性が指摘され、このような神経症的な要素と、精神病的な症状もあることから、神経症と精神病の境界線上にある疾患と考えられました。そこで「境界性」と命名されました。そして治療には専門家による精神分析治療が必要であると考えられました。
しかし、1990年代から精神疾患を脳科学の観点から研究する傾向が主流となりました。特に大人の発達障害の研究が進む中、境界性人格障害と診断されている人たちは注意欠如多動性障害(ADHD)などの発達障害ではないかという意見も出るようになりました。幼児期の体験などの心理的な問題以上に、脳の一部が生まれつき十分に機能していないために人格障害がおこるのではないか、という考え方です。
これは、画期的な発想の転換でした。なぜなら過去の心の傷が人格障害の原因ならば、それを治すためには専門的な精神分析的治療が必要となります。その上、結局は親のせいで病気になった、という発想になりがちで、親が責め立てられて状況がよけい悪化することもしばしばありました。
しかし、生まれつきの脳の問題であるとなると、治すという観点よりも、障害をもちながらどう社会に適応するかを考えればよいことになります。例えば、気分の変動が激しく、すぐに怒ってしまう場合は、それを抑える薬を服用してみる、生活が不規則になったら、入院して生活を整える、など症状に応じた対症療法が有効になります。
次に家族や恋人の対応の仕方です。
変わった言動が単なるまがままでなく、障害であるとこを前提として対応してあげることがポイントです。そうすれば自然に大切にしてあげようと思えますし、いい加減な対応をしなくなります。どうせわがままだからと思って、いい加減な対応をすることで、怒りのスイッチを押してしまうことが多いのです。
万が一怒らせてしまった場合は、相手の怒りに巻き込まれず、こちらも怒らずに冷静に対応することです。こちらに非がある場合は冷静に謝罪することも必要です。
ただし、暴力、お金の使いすぎ、自傷などの自己破壊的な行動については、話し合って制限を儲けることが必要です。暴力の場合は、警察や役所のDV相談センターなどの公的機関に関わってもらうことも必要です。
境界性人格障害は、虐待などの過去のトラウマが関わっているケースもありますが、それ以上に脳機能の障害の影響がつよいと考えられるになりました。そのために最近では境界性人格障害という診断名をつけられることは少なくなり、ADHDとか双極性障害と診断がつけられることが多いようです。
診断名はどちらにしても、わがままな人として見下すのではなく、障害と考えて対応することが必要でしょう。
他の人格障害についても同様に、アスペルガー障害などの発達障害があることが知られるようになっています。どの人格障害も残念ながら治すことは難しいのが現状です。しかし怒り、不安、こだわりなどの症状を抑える薬もあり、こうしたものを利用しながら社会への適応を考えてあげることが必要でしょう。
リストカット 家族や友人の方に知ってほしいこと
自分の周りにリストカットをされている人はいますか?
リストカットをしている人を救うには周りの人の支えが大変重要です。
支えとなるためにも、是非今回の文章を読んでいただけると幸いでございます。
リストカットのように自分を傷つける行為を自傷行為と呼びます。自傷行為には、髪の毛を抜いてしまう抜毛症(ばつもうしょう)、皮膚をひっかく、皮膚を焼く、頭やこぶしを壁に打ち付ける、などがあります。また間接的に自分を傷つける行為も自傷行為として考える場合もあります。
過食嘔吐、全身のタトゥーやピアスの穴開け、薬物乱用、相手を選ばない性的交渉などがあげられます。リストカットと平行して、これらの間接的に自分を傷つける行為をしていることがあります。
自傷行為を自殺ととらえる方も多いと思いますが、とても死にたい気持ちを伴うものの全く異なるものです。自殺は命を絶つ目的で行いますが、自傷行為は体を傷つけたい衝動にかられて行ってしまうのです。
むしろ、辛い人生を生きていくための気持ちの逃げ場のようなものです。癖のように無意識にやってしまうこともあります。
ただし、自殺と違うと言っても、リストカットで手首の深いところにある動脈を切ってしまう場合は死に至ることもあります。死ぬわけでないからと安心するのは禁物です。
動物にも自傷行為がみられます。閉じ込められたペットや養殖の動物が自分の手足や尻尾を咬んだり、毛をむしったりすることがあります。これは動物たちが命を絶つためにやっていることでなく、不快な空間に閉じ込められ、怒りや絶望などの負の感情のやり場がなく起きてしまう行動なのです。
これには脳の中のセロトニンという物質が関係しているという研究もあります。人間も同じです。自分で処理することのできない負の感情が蓄積していくと、衝動的に自分を傷つけてしまうことがあるのです。
リストカットの心理的な背景には次のようなことがあります。
1.家族や恋人から虐待を受けている。孤立している。
2.学校や職場でストレスが多い。過度の競争の中にいる。いじめやハラスメントを受けている。
3.失恋、家族の死などの喪失体験。
4.受験や就職の失敗などの挫折体験。
5.自傷行為を肯定するような映画やドラマを見ている。アンジェリーナ・ジョリーやレディー・ガガなどのハリウッドセレブが過去の自傷体験を語っており、こうしたメディアの影響を受けている。
リストカットをする人に、なぜそうするのかを質問すると、様々な答えが返ってきます。
「血をみると生きている実感がする」「傷の痛みで辛いことが忘れられる」などがあります。また、よく憶えていないとか、血が流れるのをテレビの画面を見るようにボーっと見ている、という人もいます。リストカットをする半分以上の人が痛みを感じていないという報告もあります。なぜリストカットをしてしまうか、本人にとっては説明がつかないことが多いのです。
リストカットをする人は、気持ちを言葉にすることが苦手です。何が辛くて、自分を傷つけてしまうのか、それを質問しても明確な回答が得られないことが多いのです。また思い込みがつよかったり、感情のコントロールが苦手な人もいて、辛い気持ちをうまく解消することが不得意であったりします。
中高校生のリストカットの場合は、成長することで、苦しい気持ちを客観的に捉えられるようになり、それを言葉で表現したり、他の安全な方法で解消できるようになることでリストカットは減っていきます。
それでは、家族や友人にリストカットをしている人がいる場合にどうしたらよいでしょうか?
まず、リストカットを無意識のSOSと考えるべきでしょう。ここで誤解してもらいたくないことは、リストカットは周囲にアピールするためにわざとやっているわけではないことです。気持ちの逃げ場として仕方なくやってしまうことですから、叱ったり、無理にやめさせようとすることは逆効果です。
また、「何が辛いの!」と感情的になって追及しても明確な答えが出てくるとは限りません。自分を客観的に見る力や自分に気持ちを言葉にする力が不足している場合が多いのです。暖かく見守りながら、苦しい原因を周りが推測して取り除いてあげることが必要です。
リストカットの治療には心理療法が向いているので、カウンセリングを受けるのがよいでしょう。カウンセリングでは家族関係を見直したり、苦しい気持ちを言葉で表現することを手伝ってくれたり、リストカット以外の気持ちの解消法を探すような治療を行ってくれるでしょう。
しかし、本人に治療に消極的なことが多く、家族だけがカウンセリングを受けるケースが多いようです。
死にたい気持ちが非常につよく他の自殺方法も試みるような重症の場合や、背後にうつ病、躁うつ病、統合失調症などの精神疾患があると思われる場合は精神科での薬物治療が必要となります。
また、形成外科ではリストカット痕を消してくれるレーザー治療や植皮手術を受けられます。
リストカットは自殺行為と違います。命を終わらせようとしているのでなく、むしろ生きていくために無意識にやってしまう行為です。何が辛いのか、そこを理解してあげることが大切です。