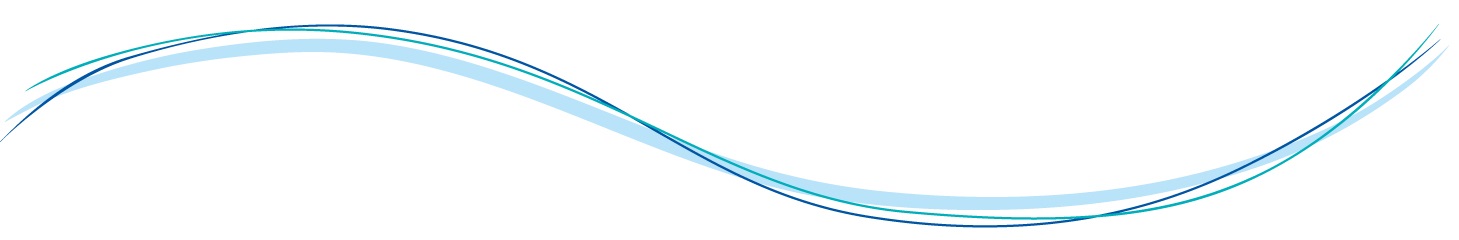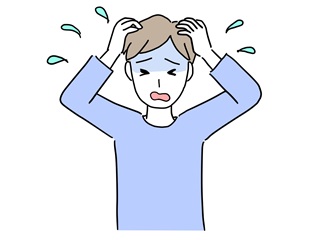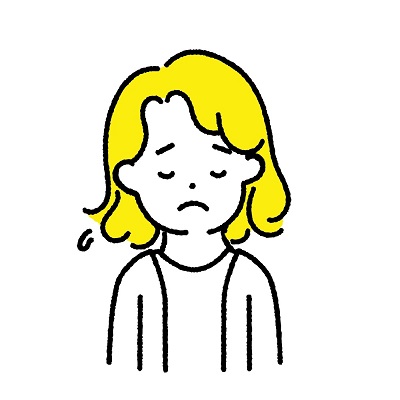うつ病が良くなっていっているサイン
うつ病とは、「出口の見えないトンネルの中を歩いている」と例える人がいます。出口の明かりが見えないと、暗闇の中をどこまで進んで来たのかが分かりません。何か標識でもあれば安心できるのですが、それすらもないと先へ進むことも不安になります。
うつ病も同じように、いつになったら元気な頃の自分に戻れるのか、どれくらい改善されているのか、いつも不安で一杯です。身近な人から「元気になってきたよ」と言われたら慰めになりますが、自分ではなかなか変化に気づけません。
うつ病の回復は期待よりもゆっくりであるため、変化が分かりづらいのです。残念ながら、体の病気のように検査で測ることもできません。また、「昨日は元気だったけれど、今日は具合が悪い」というように波があるのも、回復を感じにくい理由です。
そこで今回は、うつ病が回復していっているサインについて解説していきましょう。うつ病をトンネルに例えれば、「あと何キロで出口」という標識のような出来事です。これらのサインに気づいたならば、うつ病が確実に回復している証拠です。

1 「まあいいか」
普段気にも止めないことが心配になり、グルグル思考の沼にハマってしまうのがうつ病です。例えば、「今の体調不良が癌だったらどうしよう」、「明日災害が起きたらどうしよう」など、普通ならば「何とかなるかな」という考えを、いつまでも引きずってしまいます。
うつ病が良くなってくると、グルグル思考の沼にハマりそうになっても、すぐに「まあいいか」と引き返せるようになります。これは、物事を深く考えなくなったのでなく、むしろ、良くなっているサインなのです。
2 何か言われても聞き流せる
うつ病の時は情緒が不安定になるので、ちょっとした一言で心が大きく傷つきます。例えば、家族から「ゴロゴロし過ぎじゃない?」、「うつ病は気のせいだよ」と言われると、受け流すことができず、腹が立ったり、涙が出たり、気持ちのアップダウンを激しく感じます。
ところが、回復に従い心に余裕ができてくるので、これまでだったら気になって仕方のないことを、スルーできるようになります。「以前はこんなことでも怒っていたな」と冷静に感じとることができるようになるのです。
3 楽しめるようになる
うつ病は物事への興味や関心がなくなる病気です。回復して来ると、まずは自分の好きなことから興味や関心が湧いて来るようになります。同時に集中力も回復してくるので、動画や音楽などのエンタメを楽しめるようになるでしょう。
具合が悪い時は、動画を少し見ただけでも疲れ、音楽は雑音にしか聞こえません。それが、動画を楽しめる、音楽を聴きながら歌を口ずさむようになったら相当回復している証拠です。こうした状況を「好きなことばかりやって肝心なことをやらない」と勘違いして自分を責めてしまう人もいますが、そうではありません。
4 できなかったことができるようになってくる
失っていた意欲が蘇ってくるので、これまでできなかったことを少しずつできるようになります。ゴロゴロする時間が少なくなり、短時間でも何かしようという意欲が生まれてきます。
ほとんどの人がまず始めることは、部屋の片づけです。「久しぶりに掃除機をかける」、「机の上の古い書類や手紙の整理をする」、「服の断捨離をする」、「家具の配置換えをする」といったことが多いようです。「やりたいな」とずっと頭の片隅にあったことが、少し力が出てきたので行動に移せるようになった証拠なのです。

5 頭のモヤが取れる
うつ病は、脳がきちんと働くなる病気です。頭にモヤがかかったようになり、何をしても現実感がありません。回復するにつれて、頭も徐々にスッキリしていきます。視界が開けたようになり、現実感も出て来るでしょう。人と会話をしていて、はっきりと理解できるようになったと言う人もいます。
6 退屈を感じる時間が出て来る
「休んでばかりいないで、早く仕事をしなくては」と焦る気持ちは、うつ病の症状です。焦りから無理に働き始めても、すぐに具合が悪くなってしまうでしょう。むしろ、仕事に戻るタイミングは、「ひまだな」、「何かしたいな」と感じるようになった後です。時間を持て余すように感じるのは、焦りや緊張感が取れてきたのが理由であり、うつ病が良くなっているサインです。
7 人と会おうとする
うつ病になると、自分から人を避けて孤独を好むようになります。回復してくると、普段の自分に戻り、むしろ自分から人に会おうとします。メールやラインに返信するようになったり、電話をしたりするようになります。
大勢と会うのは疲れるので避けてしまいますが、「友人と外で会ってランチをした」、「家族と外食した」といったことがあるならば、それはうつ病が良くなっているサインです。
ただし、うつ病の時には孤独を感じるので、寂しさを感じるけれど、人と会う力がないという状態です。実際に人と会う力が出てきたかどうかで判断すると良いでしょう。
8 食事がおいしい
うつ病は体の症状が多い病気で、食欲不振がよく見られます。回復に従って体調も良くなるため、お腹が空くようになり食事が美味しくなります。「焼肉を食べたいな」という感じで、好きだった食べ物を恋しくなるのはうつ病が回復しているサインです。

以上、うつ病が良くなっていっているサインについて解説しました。
うつ病が良くなってふだんの日常を取り戻してくると、病気であることを忘れ、現実的なことに意識が向かうようになります。病院のアポイントをすっぽかしたり、薬を飲み忘れることも増えてくるでしょう。これも良くなっているサインなのですが、そのまま治ったと勘違いして、病院に行かなくなるのは良くありません。
1度うつ病になると、症状は消えても、脳のダメージが数年間は残ります。そのために何かのきっかけで再発をする可能性があります。元の自分に戻ったと思っても、脳のダメージが改善されるまでの最低1年間は薬の継続が必要です。何度も再発がある人、薬を減らすと調子を崩す人はもっと長い期間服用しましょう。
薬は長期に服用しても問題はありません。それよりも、再発して一からやり直しということの方が面倒なことです。薬を減らすタイミングは担当の医師に任せて、毎日元気に過ごすことを考えましょう。「薬を飲んで元気ならば、それで治っている」と考えることが大切です。
失感情症の特徴的な行動
「家に帰って考え込んでいると、職場で嫌なことを言われたことに気づいて、気分が悪くなった」という経験はありませんか?
その場では「この人は何を言っているのだろう?」とよく理解できなくて、時間が経ってから意味が分かって怒りが湧いて来たのです。このように出来事と感情がずれてしまうのは、失感情症かも知れません。
失感情症は、アレキシサイミアとも呼ばれ、自分の感情を認識したり、言葉で表現したりすることが苦手な心の傾向のことです。
「失感情」と呼びますが、決して感情を失っている訳ではありません。その場の状況と感情がうまくリンクしない現象のことです。日本人の10~20%くらいにみられるとも言われるくらい、特別なことではありません。
今回は、失感情症の特徴的な行動と、最後には対応の仕方について解説していきます。

1 人に誤解される
失感情症の人は、自分の感情を言葉で表現することが苦手です。例えば、友人とテーマパークに遊びに行って、それなりに快適に過ごしているのに、その場で楽しさを表現できません。
友人には、「楽しくないのかな?」と勘違いされてしまい、楽しさを共有できない友人は、「せっかく誘ってあげたのに…」と良い気持がしません。こうしたことが重なると人間関係がギクシャクすることもあるでしょう。
2 表情が少ない
表情の変化が少ないのも特徴です。みんなが笑っている場面でも一人だけ真顔でいます。悲しいことでみんな泣いているのに自分だけ涙が出ません。クールな人、不愛想な人と思われがちです。
例えば、隣の席の同僚が、帰省した時のおみやげをくれました。とっさのことなので一言「ありがとう」と言うだけで、無表情のままです。後から感謝の気持ちは出てくるのですが、受け取った時には反応がないので、同僚も不愉快な気持ちになります。同僚を軽んじている気持ちは一切ないのに、「失礼な人」と誤解されてしまいます。
3 場にそぐわない言葉を言う
言葉に感情が伴わないので、相手に共感することも苦手なことの一つです。例えば、先輩が一生懸命に激励の言葉をかけてくれているのに、先輩の応援の気持ちを感じることができません。
それどころか、先輩の言葉の多さに、「私は怒られているのかな?」と勘違いしてしまいます。状況を把握できないまま、「申し訳ありません」と謝ってしまい、「変わった人だな」と思われてしまいます。
こんな感じですから、深い人間関係を築くのが苦手です。相手が心を開いてくれても、どう対応したら良いのか分からないため、自分から人との深いつながりを避けてしまうこともあります。

4 心を病むまで休まない
失感情症の人は疲れを感じにくいのも特徴です。ふつうの人が疲れてくると感じる「めんどくさいな」という感じが言葉にならないので、休むタイミングが分かりません。そのために倒れてしまう限界まで仕事をやってしまいます。
その上、困ったことがあっても誰にも相談できず、ストレスを溜め込みやすい傾向もあります。心のモヤモヤをどう対処して良いか分からず、過食をしたり、アルコールやたばこなどの嗜好品で誤魔化したりすることがあります。体を自分で傷つける自〇行為や、うつ病に発展することもあるでしょう。
5 突然の体調不良
失感情症の人は、ストレスを言葉で表現できない分、体で感じやすい傾向もあります。例えば、嫌な上司のことを「あの上司は酷い人だよ」と、同僚や家族と言葉で共有するだけでストレスは発散されますが、それができないので、ストレスが自律神経系を通じて、頭痛、腹痛、倦怠感などのさまざまな体の症状をつくってしまいます。ですから、上司と話をする前になると必ず体調不良が起こるのです。こうした症状は病院で検査をしても異常が見つかりません。
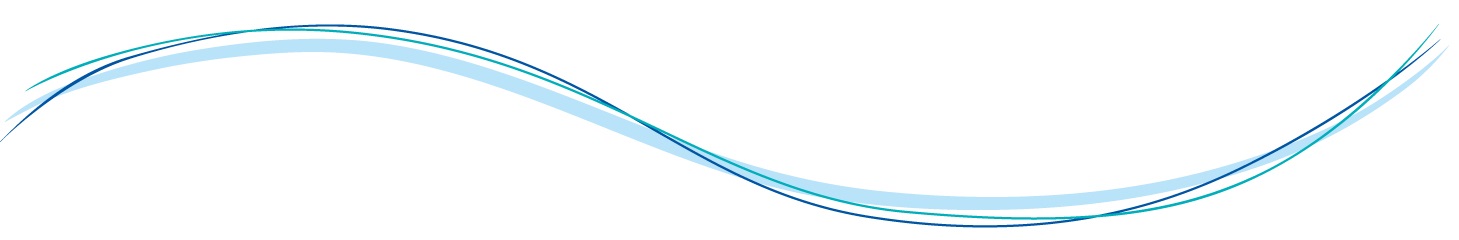
以上、失感情症の人の特徴的な行動について解説しました。
失感情症は、ストレスから一時的に起こることもありますが、基本的に生まれつきの性格傾向なので、決定的な治療方法はありません。むしろ、自分の特徴と理解して、無理に直そうとせずに、うまく付き合っていくことが大切でしょう。自分には「失感情症がある」と意識するだけで、他人に気を遣い過ぎることが減り、生活しやすくなる人もいます。
ただし、自分の努力で少しずつ改善させることも不可能ではありません。それは、出来事と感情をつなげる練習を重ねていくのです。最後に失感情症を改善させるための具体的な方法を2つ紹介しましょう。
1つめは、マンガや本の物語を読むことです。ただ読めば良いということでなく、自分が気に入った登場人物になったつもりで、自分だったらどう考え、どう感じるかをイメージしながら読んでみましょう。
場人物の感じ方と自分の感じ方を比べながら、「こんな場面で怒るんだ」、「こんな感じに笑うんだ」とよく観察してみましょう。もちろん映画やドラマでも良いのですが、画面がすぐに次に移ってしまうので、自分のペースで話を追えるマンガや本の方がお薦めです。
2つめは、「感じたこと日記」を書くことです。失感情症の人は昔から感想文が苦手だったと思います。例えば、卒業の思い出を書いても「修学旅行に行った」、「運動会で優勝した」といった感じで、出来事の羅列だけで終わってしまい、感情を書いてこなかったはずです。
今度は、自分が感じたことだけを毎日日記に書いてみましょう。「今日は雨だった」、「公園を歩いた」と事実を書くだけで終わらせるのでなく、「雨で服が濡れて、不愉快だった」、「公園を歩いたら、日差しが暖かくて気持ちが良かった」という感じです。別に人に見せるものではないので、文章にこだわる必要はありません。自分がどう感じたかを文字にする練習をするのです。
このような出来事と感情をつなげる練習はすぐに結果が出ませんが、やって損をすることではないと思います。気長にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
女性のうつ
うつ病は女性の方が2倍かかりやすいことをご存じでしょうか?日本人男性の10人に1人がうつ病になりますが、なんと女性は5人に1人がなるという数字が出ています。
今回は男性に理解できない女性のうつ病について説明したいと思います。

1 女性にうつ病が多い理由
女性にうつ病が多いのは、まず、女性は男性に比べて繊細でストレスを感じやすいことがあげられます。同じストレスでも男性ならば流せるものが、女性は気持ちに引っ掛かってしまい前に進めないことも起こります。
その上、世の中では男女平等が叫ばれていても、まだまだ男性からの力の圧力に苦しむ女性はたくさんいます。こうした理由から、職場でうつ病を発症する女性はたくさんいるのです。
2 生理期間中のうつ
女性の生理は、エストロゲンという女性ホルモンの分泌の周期によって起こります。エストロゲンはうつ病の発症とも関連があり、生理前にエストロゲン分泌が急激に少なくなる女性は、それに伴いうつが起こりやすくなります。
生理の1週間前くらいから、生理痛や体調不良を起こす女性は多く、「月経前症候群・PMS」と呼ばれています。それだけでなく、うつ気分、情緒不安定、イライラ、頭痛が起こり、日常生活にも大きな支障をきたす場合は、「月経前不快気分障害・PMDD」と呼ばれるうつ病の一つです。毎月10日間程度、周期的にうつ病になるという女性特有の病気です。
ふだんは優しい人なのに、生理期間中になると機嫌が悪くなり、ちょっとしたことで怒ってけんかになってしまう女性は、月経前不快気分障害の可能性があります。抗うつ薬に効果があり、薬で治すことのできる病気です。
3 産後うつ病
出産直後の女性が理由もなく気分が落ち込み、涙が出るということがあります。これも女性ホルモンの変化が大きな原因です。マタニティーブルーとかベビーブルーと呼ばれており、一時的な現象であることが多いのですが、10%くらいの女性は2週間以上もうつ気分に苦しむことがあります。これは産後うつ病という女性特有のうつ病です。
産後うつ病は女性のうつ病で最も多く、「子供を可愛いと思えない」、「産まなければ良かった」といったことから自分を責めたり、家族からも責められたりすることもあるでしょう。女性の自殺で最も多い原因としても知られているくらい深刻な状態です。
「子供のことでいつもイライラしている」、「ちょっとしたことで子供を叱り飛ばしてしまう」、「子育てに限界を感じている」といった場合は、産後うつ病の可能性があります。
やはり抗うつ薬による治療に効果がありますが、長い治療期間が必要な病気です。

4 更年期うつ病
女性ホルモンは50才を境に徐々に減るようになり、女性は生理が止まり更年期を迎えます。女性ホルモンが急激に減る女性もいて、自律神経失調症や関節痛などの症状が現れます。いわゆる「更年期障害」です。特に気分の落ち込みがつよいケースは「更年期うつ病」と呼びます。
この時期は子供が独立して家を出る時期とも重なり、子供を失う喪失感からよけいにうつを感じやすくなります。命がけで育て上げた小鳥たちが巣立ってしまい、空っぽになった巣に取り残された状態に似ているので、「空の巣症候群」とも呼ばれます。
5 老年期うつ病
女性が老年期を迎えると女性ホルモンの分泌がほとんどなくなります。それに伴い美容の衰えが気になるようになり、これがうつの原因となることがあります。
年をとれば肌がたるみ、シワが増えるのは当たり前というのは男性の理屈です。女性はいくつになっても美を保ちたいのです。60才、70才になっても美容整形を受ける女性もいます。
また、老年期は体の病気の問題、配偶者との死別、孤独なども起こるために、これがうつの原因になることもあるでしょう。
肉体的にも、環境的にも、女性がうつ病になりやすいことを理解していただけたと思います。心の繊細さ、生理の問題、子育ての問題などは、男性にとって理解しがたい問題でもあります。職場でも家庭でも、女性が心の問題を抱えやすいことを理解するべきでしょう。
こうしてみると、「女性の方が損をしている」と感じる方もいるかも知れません。しかし、女性の方が男性よりもコミュニケーションの能力は高く、辛い時に周囲に相談できるという強みもあります。むしろ、男性は弱みを見せずに我慢してしまい、うつ病をこじらせてしまう傾向があるのです。
実際にうつ病による自殺率は男性の方が女性よりも2倍高いという数字が出ています。男性は心の問題を自分だけで抱え込んでしまい、突然自ら命を絶ってしまう傾向があるのです。
心の問題は、周りの人に助けを求めることがどれだけ大切なことか理解できると思います。
ADHDの人の生活
ADHDの症状は大きく分けて、【衝動性】【不注意】【多動性】3つがあります。人によって、どの症状が強いか分かれます。今回は、ADHDの人の生活について解説していきます。

1. 時間の感覚が独特
ADHDの人は、「時間の見積もりが苦手」「今この瞬間しか見えていない」ような感覚を持つことがあります。
たとえば、朝出かける準備をしているとき、「あと10分あるから大丈夫」と思ってスマホを開いたら、気づけばバスが出発した後だった…ということがよくあります。
また、「締切は来週」と思って安心していたら、急に焦り出して夜中に一気にやろうとしてしまうことも。これらはADHDの人にとって日常茶飯事です。
2.スケジュール通りに動くのが苦手
タイムマネジメントが苦手であったり、計画的に動くのが苦手であったりするため、スケジュールを詰めこみすぎるとパニックを起こします。何分にこの電車に乗って、乗り換えは何分でと細かいスケジュールで決めるのがとても怖く、遅刻しないために30分前に着くようにしたりと工夫する人が多くいます。
3. 忘れ物が多い
ADHDの人は、短期的な記憶や段取りの記憶を扱う「ワーキングメモリ」が弱い傾向があります。そのため、
• 財布や鍵を家に忘れてしまう
• 薬を飲むのを忘れて、二回分飲んでしまう
• 「あの人に返信しなきゃ」と思っていたのに、気づけば数日経っている
などの「うっかり」が日常に溶け込んでいます。自転車を駅にとめていたのに、うっかり歩いて帰ってきてしまったという話もあります。
4. やっていることがコロコロ変わる
ADHDの不注意傾向が強い人は、やっていることがコロコロ変わります。事務作業をやっている時に途中で営業の外回りに飛び出しにいったり、片づけをしていたのに、漫画を読み始めたりと、集中がすぐに切れてしまうのです。
5. 感情のコントロールが難しい:「小さなことにすぐ反応しちゃう」
ADHDの人は感情の起伏が激しくなることがあります。ちょっとしたことでイライラしたり、逆に嬉しすぎて落ち着かなくなったり。
• 誰かのちょっとした言葉に強く反応してしまう
• 思い通りにいかないとパニックになってしまう
• 気持ちが切り替えられず、ずっと落ち込んでしまう
ということが、周囲の人には「情緒不安定」に見えるかもしれません。ですが、本人にとっては刺激に対する反応が強く出やすいだけであり、意図的にやっているわけではないのです。
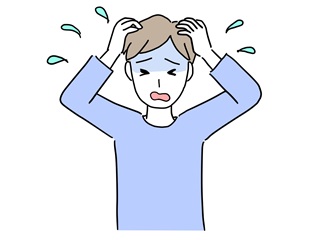
6 .整理整頓が苦手
部屋やカバン、デスク周りなどがすぐに散らかってしまうのもADHDの人に多い特徴です。大体の人は取り出したものを元の場所に戻したり、飲み終わったペットボトルを捨てたりしますが、ADHDの人は、取り出しもの用事が済んだら次のことに考えが移ってしますので、片付けることができず、ごちゃごちゃになってしまうのです。
こうした混乱は、単に「だらしない」のではなく、情報の整理や優先順位づけが苦手な脳の働きによるものです。
7. 思ったことをすぐに口にしてしまう
ADHDの人は、会話の中で「思ったことをすぐ口にしてしまう」「相手の話にかぶってしまう」ことが多くあります。また、他人の表情や空気を読むのが苦手な人もいます。
• 「また話脱線しちゃった」とあとで落ち込む
• 冗談のつもりが相手を傷つけてしまった
• 相手との距離感がうまくつかめない
といった経験をして、自信をなくしてしまう人も少なくありません。
それでも、ADHDの人の中にはとてもユニークで優しい発想を持つ人も多く、「自分らしさ」を大切にできる関係性を見つけることで安心して過ごせるようになります。
8. 頭の中に色々なアイディアが浮かんでくる
ADHDの人は色々なアイディアがポンポンと出て来ることがあると言います。夜にアイディアがさえわたって色々なことが浮かんできて、眠れないということも多くあります。
あの瞬間に戻ったとしても、やはり同じように悩み、同じように決断したでしょう。それは、結果論でしかないのです。だから、あのときの自分を責める必要なんて、どこにもありません。
9.目先のことが優先で長期的なことが考えられない
ADHDの人は、「今」の感情が圧倒的に強い傾向があります。たとえば、「ダイエットしなきゃ」と思ってても、目の前のケーキが美味しそうだったら「今幸せになること」が優先されてしまう。
長期的結果よりも短期的結果を求めてしまいがちです。将来のリスクよりも、目先の快楽や回避が勝ってしまいやすいのです。
ADHDの人は「時間を直線的に捉える力」が弱いとも言われていて、未来のことが自分ごととして感じづらいということも考えられるでしょう。

以上、ADHDの人の生活について解説しました。
ADHDの特徴は「障害」というよりも、「社会との相性のズレ」として考えた方が理解しやすいかもしれません。周囲の理解と、本人の工夫があれば、日常は少しずつラクになっていきます。
人生がうまく行かない理由
あなたの人生がうまく行かない理由は何でしょうか?
例えば、「病気がなかなか治らない」、「仕事がうまくいかない」、「お金に困っている」、「よいパートナーに出会えない」など、思い通りにならないことを通して、誰しも人生がうまく行かないと感じます。私たちは幸せを求めて生きていますが、うまく行かないことが多すぎて、「苦しみを乗り越えるだけの人生」と感じている人もいるはずです。
うまく行かない大きな理由の一つは、願いと結果が一致しないことです。私たちは、結果を何とかしようと苦しむのですが、実は願いを考え直すことを通して、結果に対する感じ方を変えることができます。
例えば、一流大学に入りたいと願って、なかなか成績が伸びないで苦しんでいるとします。それならば、どこの大学でも学ぶ内容は同じだと考え方を変えて、目標の大学のレベルを下げれば苦しみから解放されるはずです。このように、あなたの願い自体を考え直すことが、苦しみから解放される大きな手段の一つなのです。
そうは言っても、「絶対に東大に入る」と言って譲らない人もいるでしょう。学歴への執着が取れないのです。実際には一度抱いた願いを変えることは大変なことで、他の選択肢があることに自分ではなかなか気づけません。こうしたことから人生がうまく行かないことがあります。
今回は、あなたの心を修正できないことから、人生がうまく行かない理由について説明しましょう。心をほんの少し修正することから、人生がうまく回っていくかも知れません。

1 執着していることはありませんか?
人は親から言われ続けたことや、子供の頃に憧れたことを通して、「自分は○○であるべきだ」という自分の虚像をつくります。「人から好かれるべきだ」、「出世するべきだ」、「お金をたくさん儲けるべきだ」、「結婚してたくさん子供をつくるべきだ」、「親子は仲良くするべきだ」など、考えてみるとたくさんの「○○するべきだ」に支配されている私たちなのです。
そして、そうなれない自分に苦悩しています。幻の自分を追い求めて疲れ果てているのです。別に人から好かれなくても生きて行けるし、お金は生活できる分だけ稼げれば良いのです。
結婚せず、子供がいなくても幸せな人はたくさんいます。世の中には仲の悪い親子もたくさんいます。「○○べきだ」をなくしてしまうと、心はずいぶん楽になるのです。それは分かっていても、「○○するべきだ」を諦められないことを執着と呼びます。
執着を捨てられないことが、人生がうまく行かない大きな理由の一つなのです。
2 比べていませんか?
執着はなかなか自分で気づけません。それが当たり前と考えていることの中に執着があるのです。「友達が一流大学に行っているから、自分も一流大学へ行かなくてはならない」、「いとこが子供をたくさん産んでいるから、私も子供をつくらなくてはいけない」という感じで、執着が自分にとっての常識になっている場合があります。
執着の根っ子をたどっていくと、私たちのプライドや負けず嫌い、そこからくる嫉妬の気持ちが隠れています。プライドや負けず嫌いは、自分を不幸にすることもあるのです。
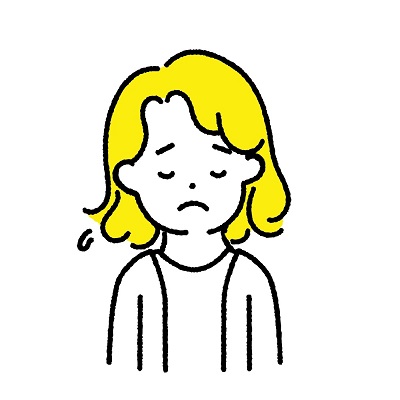
3 現実から目をそむけていませんか
何かの執着を抱えていると、自分に都合が良い情報しか視野に入らないため、客観的に物事を考えられません。現実に起きていることを冷静に見られなくなるのです。
例えば、先ほどの一流大学に入りたい人の場合、「自分の成績でも合格している人もいるようだ」という都合の良い情報に振り回され、自分の実力では受からないという現実から目を背けがちです。
うまく行っていない時ほど物事を冷静に見なくてはいけません。執着がフィルターとなって、物事を正しく見られなくなっているからです。
4 変えられないことを変えようとしていませんか?
起きてしまった結果や過去は変えることはできません。しかし、執着がつよいと、変えられない結果や過去までもどうにかならないかと悩んでしまいます。私たちが変えられるのは、現在と未来だけです。結果や過去をクヨクヨしてエネルギーを使うことは、人生がうまく行かない原因にもなります。
「夢があるから」、「みんながそうだから」、「誰でもやっているから」という理由で、それに合わせようと背伸びをして生きていることがあります。これが生きづらさの原因であることは大変多いことです。
とりあえず最低限、住む場所があって食べられているのだから良いと考えましょう。周りの目を気にせず、できないこと、やれないことがある時は、「もう無理」、「できない」で良いのです。
夢に向かって頑張ることよりも、執着を捨てて、自分にあった生き方をしてみることが人生をうまく回すコツかも知れません。
2016年に亡くなられたノートルダム清心女子大学名誉教授の渡辺和子シスターは、うつ病を経験したことのある人です。シスターは「置かれた場所で咲きなさい」と言いました。
欲張らず、無理をせず、自分に合った生き方をしたら良いという意味です。ちょっとした心の変化があなたの生きづらさを解消してくれるでしょう。
うつ病はいつ治りますか
いつになったら気分が晴れる日が来るのでしょうか?
本来うつ病はゆっくり休むことで半年から1年半で自然に良くなる病気です。ところがそれで終わりではなく、何かのきっかけで再発を繰り返します。
データによると、1度うつ病を経験した人は、その後の20年間に平均して5~6回の再発を繰り返すとも言われています。これは、最初のうつ病の経験で脳がダメージを受けており、症状が良くなっても潜在的な脳のもろさが残っているためです。
再発を繰り返していくと、そのうちうつ病が慢性化してしまい、気分の落ち込みが性格だか病気だか分からなくなってしまいます。これを「慢性うつ病」とか、最近では「持続性抑うつ症」と呼びます。
これを防いでくれるのが抗うつ薬です。薬を飲むと1カ月から3カ月程度で症状は良くなり、さらに続けて服薬をすることで再発の予防もしてくれます。
それではいつになったら薬をやめてうつ病から解放されるのでしょうか?今回は、うつ病に必要な治療期間について詳しく説明しましょう。

1 回復後も最低1年間の予防服薬が必要
原則として、症状がなくなった後も予防のために1年くらい服薬を続けて、問題がなければ薬をやめることはできます。これでうつ病とさよならをできれば良いのですが、再発は絶対にないとは言い切れません。生きている限り、ストレスを避けて生活することは不可能だからです。
お金の心配をせずに、自然の中で趣味だけやって悠々自適に生活できたら再発はないのでしょうが、そんなことができる人はいません。ですから、最初の治療がうまく行ったとしても、再発する人はいるのです。
そして、万が一再発した場合は、2度目の再発を防ぐために、さらに5年以上は薬を飲むことを考えましょう。
2 慢性うつ病の人は長い予防服薬が必要
「思い返したら、10年くらい前からうつ病だったかも知れない」と訴えて、精神科を受診する人もいます。仕事が続けられたので、気分が晴れないのは性格の問題と思い込んでしまい、まさかうつ病であると気づけなかったのです。ずっと休みをとることができずに、限界が来たのでようやく受診するという話はとても多いことです。
しかし、こういった場合は、すでに慢性化していることが多く、抗うつ薬の治療で良くなっても、やめてしまうとすぐに再発します。発病から何年も経って治療を受けたなら、患っていた期間と同じくらい薬を続けた方が良いでしょう。例えば、治療を始めるまでに10年かかったら、10年は薬を飲むといった感じです。
慢性うつ病の場合は、薬を飲んで日常生活を普通に送れたら、それで治ったと考えても良いと思います。主治医の指示に従えば、抗うつ薬などの精神科の薬を長く飲むことは危険なことではありません。血圧や糖尿病の薬をずっと飲み続けることと同じです。一生涯飲み続けていても問題はないので、慌てて薬を減らす必要はありません。

3 いくら薬を飲んでも十分に良くならない人
一言でうつ病と言っても、実際にはいくつかの種類があります。中には最初から治りにくいうつ病もあるのです。
例えば、「出産後に起こる女性のうつ病」、「幻覚や妄想などの精神病症状があるうつ病」、「パニック症を合併しているうつ病」などは、薬の治療でも十分良くならないことが知られています。このように治療の効果が十分でなく、働けないなどの障害が残ってしまう場合を「難治性うつ病」と呼びます。
さらに、「ADHDやASDなどの発達障害がある人」、「子供の頃に虐待やいじめを受けた経験がある人」も難治性うつ病になりやすい傾向があります。
難治性の場合は、薬の治療だけでなく、通電治療や磁気治療などが行われることもあります。しかし、生まれつきの要素が関わっていることも多いので、こうした治療にも反応しにくいのが難治性うつ病です。
色々手を尽くしてもなかなか良くならない場合は、焦って元の生活に戻そうと努力するよりも、病気があることを前提とした生活をするのが良いでしょう。障害手帳や障害年金などを利用することで経済的な負担を減らすことができます。お金の心配が少なくなるだけでも、うつ症状が軽くなることもあります。
短時間でも働けそうならば、「障害雇用」や「就労移行施設」を利用するのも良いかも知れません。最近は、在宅バイト、スキマバイトなどの短時間で負担の少ない仕事も選べますので、こうしたことを利用するのも賢い選択です。
4 もしかしたら双極Ⅱ型障害かも
どんな治療をしても十分な効果がないまま何年間もうつが続いて、ある日から突然元気になったという場合は、双極Ⅱ型障害が考えられます。残念ながら再びうつに戻ってしまう可能性があるので、気分安定薬による治療を続けることが必要です。
双極性Ⅱ型障害のうつは治りにくいのが特徴で、躁状態がほとんど目立たない場合もあります。難治性うつ病として10年以上治療をして、後から双極性障害と判明することもあります。
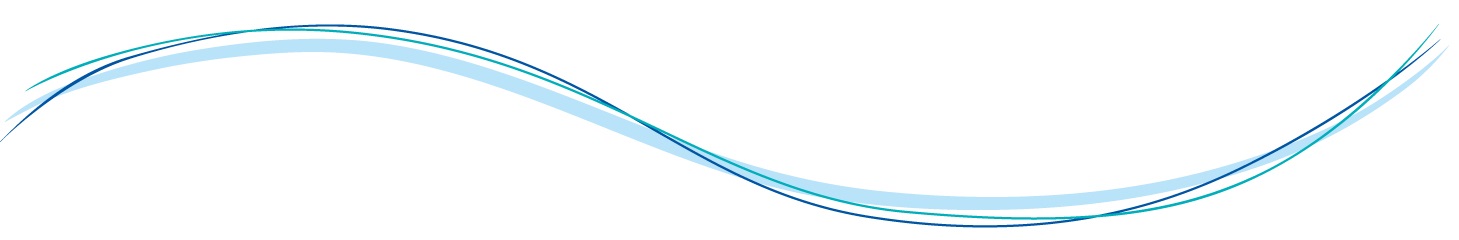
うつ病を卒業できる時期は、人それぞれです。病気そのものの問題だけでなく、家族関係、職場の事情、経済的な事情などの環境の問題も絡むので、必ずいつまでに治るとは言えません。支えてくれる人との出会いなど、巡り合わせの問題も絡むこともあります。スケジュール通りに回復しないのがうつ病なのです。
うつ病の治療は、高血圧や糖尿病と同じと考えましょう。薬を飲みながら背伸びをしない生活を続けることが必要です。うつ病だからといっても何もできない訳ではありません。障害雇用や就労移行施設を利用するなど、今できることから始めてみましょう。焦らないことが回復への一番の近道です。
見捨てられ不安がある人の特徴
LINEの返信がいつまでも来ないと、「何か悪いこと言ったかな」と気になってしまうことはありませんか?いつも相手の顔色ばかりをうかがって、ちょっとしたことで「嫌われたかも」と感じてしまうことを「見捨てられ不安」と呼びます。これが酷くなったのが「境界性パーソナリティー症」です。
「私は人から嫌われている」、「みんなから見放される」といった見捨てられ不安があって、生きづらさを感じている人がいます。見捨てられ不安は、お母さんが突然いなくなった時に子供が感じる不安と同じ種類です。子供の頃に、親や信頼していた人から見捨てられたり、裏切られたりしたことがトラウマとなって心に根深く残っているのが原因です。
いくつになっても見捨てられ不安につきまとわれ、あえて孤独な人生を選んだり、親しい人にしがみついたりして生きている人もいます。また、いつもつよい見捨てられ不安を抱えていて、親しくなった人にストーカーのようにつきまとわる場合は、「境界性パーソナリティー症」と呼ばれることがあります。
今回は見捨てられ不安がある人の特徴について解説していきましょう。

1. 相手の小さな変化に過敏
例えば、相手の口調がちょっとだけ冷たかったり、LINEの絵文字がいつもよりも少なかったりすると、「怒ってるの?」、「私が何か悪いことをした?」とすぐに不安になります。
恋愛中に好きな人の返事が遅かったり、いつもと違った返事だと不安になったりするのは普通のことかも知れませんが、我慢できないほど辛いならば、それは見捨てられ不安と考えたら良いかも知れません。
深夜でも連絡をとろうとしたり、職場まで訪ねて行ったり、脅迫に近い行動をとることもあります。
これは、心の中で常に「拒絶されるかもしれない」、「嫌われるかも知れない」という前提があるために、相手の些細な変化にも敏感に反応してしまうのです。
2. 自分の気持ちを後回しにしてしまう
見捨てられ不安がある人は、嫌われないように本音を言いません。「本当はこうしたい」と思っても、「こう言ったら嫌われるかな」という思いが先に来てしまうのです。それで何事も相手のペースに合わせようとします。しかし、優しさが動機で相手に合わせようとしているのでなく、自分が嫌われて見捨てられないようにしているだけなのです。
3. 一人の時間に耐えられない
一人で過ごす時間が苦手なため、いつも誰かといっしょに過ごそうとします。一人でいると、不安や孤独感が強くなるためです。見捨てられ不安のある人にとって、一人の時間は自由に好きなことができる時間と感じられず、人から見放された状態に感じてしまうのです。
そのために、常に人に会うスケジュールを入れたり、単に寂しさを埋めるための異性関係をもったりする場合があります。

4. 相手を試すような行動
例えば、「どうせ私のことなんて好きじゃないでしょ」と言ってみたり、ラインを既読無視してみたり、あえて冷たく接して反応を見たりと、相手を試す行動を起こします。これは本当に自分のことを好きでいてくれるかを確かめるために行う行動です。
そして、相手が期待通りに接してくれたら安心できますが、相手を不快にさせてしまうことで関係が悪化することの方が多いようです。結局嫌われて、大切な関係を自分から壊してしまい、あとから後悔する人も少なくありません。
5. 人に過度な期待や依存をしてしまう
見捨てられ不安のある人は、一人の相手に「全部満たしてもらおう」としてしまいます。「あなたがいないと生きていけない」といった思考になり、過度な依存をします。子供の頃に満たされなかった親の愛情を求めてしまうのです。
しかし、どれだけ大切な人であっても、親代わりになってすべての不安を埋めてくれることはできません。結果的に、相手も一緒にいることに疲れてしまい、関係が壊れてしまう結果になるでしょう。
6. 感情の起伏が激しい
見捨てられ不安が強い人の中には、感情の起伏が激しいこともあります。子供が親に見捨てられた時に泣きじゃくるように、「なんで分かってくれないの?」「私のことはどうでもいいの?」という想いが爆発します。爆発が激しく、相手を脅迫したり、暴力に至ったり、自分を傷つけたりするような場合は、精神科で「境界性パーソナリティー症」と診断されることがあります。
この感情の爆発は自分でコントロールできません。あとから後悔して自分を責め、うつになることがあります。さらに、感情のアップダウンに本人自身が疲れてしまい、自己肯定感まで失ってしまうという悪循環に陥ります。
以上、見捨てられ不安がつよい人の特徴について解説しました。

見捨てられ不安は、子供の頃に親が突然いなくなってしまったり、大切な人から裏切られたりしたことが原因です。「大切な人はいなくなってしまう」という思いが心に染みついてしまい、それが解消されていないのです。
解決するためには、安心できる人との交流を通して、不安が少しずつ解消されることが必要です。「大切な人はいなくならない」という人への信頼感が、自然に育まれることによって改善されるのです。
また、見捨てられ不安によるうつ気分や感情の爆発には、精神科の薬が効きます。長期に服薬する場合もありますが、生きづらさを改善させてくれるでしょう。
最も良くないことは、自分を不安にさせてしまう人と付き合うことです。ところが、見捨てられ不安を抱えている同士でパートナーになるケースはとても多く、互いに傷つけ合いながら関係を続け、暴力や事件に至ることもあります。心理学では「トラウマ・ボンド」と呼んでいますが、お互いの不安を悪化させる原因となるので避けるようにしましょう。
アメリカの調査によると、境界性パーソナリティー症と診断された人であっても、10年後に90%近い人が改善されていると報告されています。医療関係者との安定した交流が見捨てられ不安を解消させたのです。良い人間関係に巡り合えることが、見捨てられ不安が解消される一番の治療です。
ASDの思考
見たものを一瞬で覚えてしまう「カメラアイ」という能力をご存じですか?例えば、一瞬見ただけの本のページの内容を隅から隅まで全部覚えて、いつでも思い出すことができます。まるで目がカメラのようになって、そのままの情景が脳の中にいつまでも記憶されるのです。
「試験の時に便利でいいな」と考える人もいるかと思いますが、実際には、辛かったことや見たくなかったものまでそのまま記憶されて、いつまでもフラッシュバックして思い出されるのですから、決して喜べる能力ではありません。カメラアイを持つ人の頭の中はどのようになっているかはまだ完全に解明されていません。
カメラアイはASDの人に多く見られます。ASDとは、自閉スペクトラム症の略で、生まれながらにコミュニケーションの問題と、特定の物事や行為に強いこだわりがみられる障害です。別々の障害と考えられていたアスペルガー症候群と自閉症が、程度の差だけで同じ障害であることが分かったため、2013年からまとめてASDと呼ぶようになりました。
ASDというと、無表情で付き合いにくい人のイメージをもってしまいますが、カメラアイを始め、天才的な知能を持つ人など、まだまだ解明されていないことがたくさんあります。では、ASDの本人は、実際にどのように感じたり、考えたりしているのでしょうか?
今回はASDの人の言葉を元に、その不思議な感じ方や思考方法について説明します。ASDの人の生きづらさを少しでも理解できるきっかけになることを願っています。

1 目からの情報で考える
ASDの人は、すべてがカメラアイを持っている訳ではありませんが、目からの情報をつかって物事を考える傾向があります。
人は論理的に考える時には言葉が必要です。ところが、ASDの人の思考には言葉が必要ありません。むしろ、思考と言葉がうまくつながっていないために、思考を言葉に変換するのに手間がかかってしまうくらいです。言葉を介さずに、目にした出来事を直接に理解するのです。途中に余計な言葉への変換が必要ないので、これがカメラアイにつながっているのかも知れません。
ASDの人は目からの情報に頼っており、耳から入った言葉は瞬時に理解することができません。耳からの情報を集めることができないので、会話においては、「聞いていない」、「言っても覚えてくれない」ということが起こります。中には、会話よりも筆談にした方がうまくコミュニケーションがとれる人もいます。
2 感情の後出し
例えば、嫌なことをされてもその場はモヤモヤするだけで何も反応できません。ところが、後から悲しくなったり、悔しさが湧いてきたりします。いじめにあっても、その場では意味が分からずに抵抗しないために、さらにいじめられてしまいます。しかし、後からフラッシュバックのように辛さを感じるのです。
同じように、人から親切にしてもらっても、その場は何事もなかったように過ごしてしまいます。後から感謝の気持ちが湧いてくるのですが、その場では何も言えなかったために、「失礼な人だ」と勘違いされます。

3 タイムスリップ現象
ASDの人は時間の感じ方が独特で、時間と感情・思考がうまくつながっていません。昔のことを思い出すのに、まるで今起きているように感じることがあり、心だけが過去にタイムスリップしたようになります。これを「タイムスリップ現象」と呼びます。
楽しかった過去の出来事を、今も再体験して楽しめるのは良いかも知れませんが、忘れたい過去やトラウマまでもフラッシュバックしてしまうので、これは大変苦しいことです。
過去だけでなく、「今が現実かどうか分からない」というフワフワした感覚を訴えることもあります。私たちは、時間を連続した一本の直線としてとらえますが、ASDの人にとっての時間とは、ハッキリとした一つ一つの点のようにして存在しているのです。
4 ロボットの操縦席体験
ASDの人は、心と体がうまくつながっていない感じを訴えることがあります。特に体調が悪い時には、体が心に連動してくれません。体の中に小さなコックピットがあって、そこに小さな自分がいて、一生懸命操縦しようと焦っていると表現する人もいます。まるでロボットの操縦をしているような感覚と言います。
自閉スペクトラムの「自閉」とは、自分の心の中に閉じこもっているという意味ですが、ASDの人の日常とは、体の中のコックピットに心があって、そこのモニター越しに現実とつながっているような感じなのです。特に気持ちが不安定であったり、体調が悪かったりする時に感じやすいと言います。
以上、ASDの人の感じ方と思考方法について説明しました。
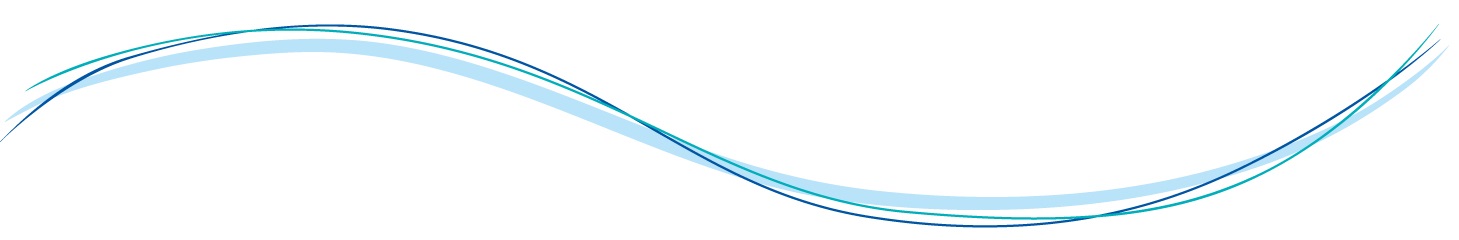
ASDの人がもっているのは、「目で理解する」、「感情の後出し」、「タイムスリップ現象」、「ロボットの操縦席体験」の不思議な感覚です。これらは、心と現実がうまくつながっていない状態と考えたら良いでしょう。ガンダムのように、体の中のコックピットに心があって、コックピットの中からモニター越しに現実と向き合っていると考えると、イメージが湧きやすいかも知れません。
ASDの人は、コミュニケーションを取ることが苦手な人が多いことから、社会で生きづらさを感じている人もいます。しかし、世界一のお金持ちであるイーロンマスクや、フェイスブック創業者マーク・ザッカーバーグなど大成功している人にはASDの人が多いのです。
IT、AI分野においてはASDの人のつよみが生かされていきます。今後も社会の進歩に従って、ASDの人がより活躍していく時代が続いていくでしょう。
統合失調症の知られていない6つのこと
統合失調症は、幻覚や妄想、思考の混乱が特徴の病気です。いまだに病気の正体は十分に解明されておらず、症状や経過は人それぞれであるので、一つの病気でなく、いくつかの病気の集合体ではないかと考えられています。そのため、「統合失調スペクトラム症」という呼び方をされることがあります。「スペクトラム」とは、「連続体」という意味です。
統合失調症は、思春期から20才代の若い人が発病する病気です。発病のために社会へ出るタイミングを失ってしまう人が多いため、早期発見・早期治療をすることが願われています。
初期の段階で病気に気づき、早めに治療を受ければ、それだけ早く回復することができますが、実際の調査によれば、統合失調症の人の半数は専門的な治療を受けていません。自分が病気であることに気づけず、自宅にひきこもっている人が大変多いのが現状です。
今回は、統合失調症とはどのような病気かを知っていただくために、統合失調症の知られていない6つのことについて解説していきます。特に、薬の治療とSSTというリハビリがとても大切であることを紹介したいと思います。

1 人間関係が苦手な人がなりやすい
統合失調症になりやすい人には特徴があります。子供の頃から物静かで優しい人なのですが、主張することが苦手で、何事も受け身的です。人と付き合うのが好きでなく、親しい友達がいません。野球やサッカーなどの団体スポーツを自分で楽しむことができず、アニメ・音楽・ゲームが大好きです。
こうした性格の傾向から、社会で追い詰められたり、孤独になったりすることが多く、そこから自分の心の世界に閉じこもってしまうことがあります。いつしか現実と心の世界に境界線がなくなってしまい、発病すると考えられています。
2 見えない声と会話する
統合失調症では幻聴が起こります。これは、何となく聞こえる空耳(そらみみ)のようなものでなく、現実の声と全く区別がつきません。内容はさまざまで、悪口が聞こえてきたり、噂話であったり、中には死んだはずのお母さんが優しく語りかけて来るという人もいます。
病気が進行すると、現実と心の中の世界に区別がつかなくなり、幻聴と会話をするようにもなります。幻聴と会話をする姿は、近くで見ていると独り言を言っているようです。統合失調症の人が一人でブツブツ話していたり、空に向かって怒っていたり、理由もなく笑ったりするのは、幻聴と会話をしている姿なのです。
また、幻聴がアドバイスをくれることや、命令をしてくることもあり、それに逆らえずに従ってしまうこともあります。重症になると、声に命令されて電車に飛び込んでしまったり、人を傷つけてしまったりと危険なことが起こることもあるのです。
3 薬がよく効く
覚醒剤を使用した人は、幻聴や妄想を起こして統合失調症と似た状態になることがあります。これは脳の中でドパミンという物質が過剰に分泌されることで起こる現象です。これに対して、抗精神病薬にはドパミンの分泌を抑える作用があるため、幻聴や妄想が治まります。この理屈から、統合失調症には抗精神病薬の治療が行われます。
抗精神病薬は統合失調症にとても効果があり、早めに治療を始めれば、服用を始めて1か月くらいしてくると、幻聴が聞こえなくなります。抗精神病薬は、統合失調症の人を心の中の世界から現実世界に引き戻してくれるものと言えるでしょう。ただし、治療の開始が遅ければ、それだけ回復にも時間がかかってしまいます。

4 人間関係を改善させるSSTが効果的
抗精神病薬が現実世界に引き戻してくれたとしても、再び追い詰められたり、孤独になったりと、現実に生きている世界が居心地の悪い場所であったら、また心の世界に戻りたくなるのは当然です。幻聴と会話をしていた頃の方が楽だったと感じます。だんだん薬を飲むことに意味を感じなくなり、ついには飲むのをやめて再発が起こってしまいます。
こうならないように、薬の治療と並行して行いたいのが、世の中をスムーズに生きていくテクニックを学ぶことです。統合失調症の人は、仲間をつくることが苦手で孤立したり、つよく言われると断れずに嫌な思いをしたり、辛い時に人に相談ができないといった生きづらさをもっています。そうならないような対人関係の取り方を学ぶため考えられたのが、社会技能訓練・SSTというリハビリです。
5 カウンセリングは向いていない
心理カウンセリングを受けると、統合失調症の人の具合が悪くなってしまうことがあります。カウンセリングを通して現実と向き合ったり、心の中を自分で分析したりすることで、症状を悪化させてしまうことがあるのです。カウンセリングを希望しても、「主治医から許可をもらってください」とカウンセラーから言われるのは、これが理由です。
もし、薬の治療だけでは十分でないならば、カウンセリングよりもSSTのようなリハビリを受けるのが良いでしょう。SSTは、病院や保健所のデイケアや地域の生活支援センターで行っているので、主治医に相談してみましょう。
6 怖い病気ではない
緊急入院が必要な重症の統合失調症は、数十年前から少なくなってきました。統合失調症全般に症状が軽くなっているのです。これは世界的な現象で、理由は良く分かっていません。もしかすると、インターネットやサブカルチャーの広がりで、現実世界にも心の逃げ場所が簡単に見つかるようになったのが理由かも知れません。
ところが、世の中には、統合失調症は幻聴に操られて重大な犯罪を犯す怖い病気という偏見が残っています。実際の統計調査によると、統合失調症の人による〇人事件はむしろ健常者に比べて少ないことが分かっています。統合失調症は薬やSSTで良くなる病気で、社会で活躍している人も沢山います。

以上、統合失調症の知られていない6つのことについて解説しました。
統合失調症は適切な治療を続ければ、社会で活躍できるようになる病気です。ただし、現実と向き合うことが苦手な人が多いために、再発率が高いのが現実です。再発を防ぐためにも自己判断で薬をやめないこと、リハビリでSSTを利用してみましょう。
今年はSST30周年記念大会が7月5日(土)、7月6日(日)に
帝京平成大学池袋キャンパスで開催されます。
もし、ご興味のある方は、
概要欄よりお申込みをお待ちしております。
心にポッカリ穴が空いているサイン
「心にポッカリ穴が空いている」と感じる人は、自分でも説明しにくい「虚しさ」や「満たされない感覚」を抱えていることがあります。「何をしていても楽しくない」「自分が何を求めているか分からない」など、今を楽しめないことだけでなく、将来にも希望を持つことができません。この感覚は一時的なものなら良いのですが、長期間にわたって続くことがあり、普段の生活で大変な生きづらさを感じます
そこで今回は、心にポッカリ穴が空いている人の特徴について解説していきます。
1. 何か後悔していることがある
あなたは何かに後悔していることはありませんか?もしかしたらその後悔している事柄があなたに満たされない感覚の原因かも知れません。好きだった人との関係が中途半端で終わってしまった、もっとあの時仕事を頑張っていれば良かった、青春をもっと大切にしていれば良かったなど、人によって様々です。後悔はあなたを自己否定の感情を引き起こします。その出来事が解決していないことから心にポッカリと穴が空いている感じがしてしまうのです。
2. うつ病
うつ病によっても満たされない感覚は起こります。何をしても楽しくない、何をしても満たされない、将来に希望を持てないという感情はうつ病による症状かも知れません。うつ病の症状が回復していくことによってこの満たされない感覚は回復していきます。
3. 人と比較してしまっている
SNSの普及により、人の成功が身近に見れるようになりました。どうして目の前の画面にいる人はキラキラして人生を楽しそうに謳歌しているのに自分は毎日を必死に生きるだけで精一杯の人生なんだと、成功者と比較することで、虚しさを感じる人は増えました。スマホを手放せない人は多くいます。そのため、もしかしたらスマホの中の人達があなたの現実になってしまっているのかも知れません。
自分の現状に満足していない

4. 孤独 人を信用していない
孤独は心の空白を生み出します。孤独になることで自分がこの世にいる意味が分からなくなってしまうという人は多いのです。また、過去のトラウマから人を信用しきれず、周りに人がいたとしても孤独感を感じる人もいるでしょう。孤独から感情が鈍化していき、感動することが少なくなってしまったり、人と話しても満たされない気持ちになってしまうのです。
5. 大きな喪失体験がある
大切な人を失った。大切なペットを失ったなど、大きな喪失体験があると、心にポッカリと穴が空いた状態が続きます。喪失体験は人やペットだけではありません。夢や自分のアイデンティを失うことも入ります。その苦しみは時に深く、出口の見えないトンネルにいるような感覚に陥ることがあるでしょう。
6. 幼少期の親の愛が足りていない
子供の頃に親から充分な愛情を愛情をもらえていないと、大人になってからも満たされない感覚に陥ります。常に誰かからの愛情を求めて、依存的になったり、周りに迷惑をかけてしまう行動を起こすでしょう。これを大人の愛着障害とかアダルトチルドレンと呼びます。
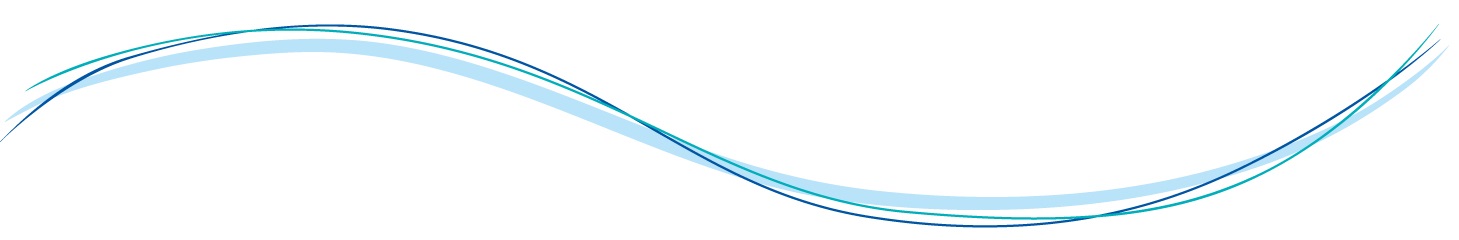
以上、心にぽっかり穴が空いているサインについて解説しました。
では、この満たされない感覚を取るにはどうしたら良いのでしょうか。まず、自分の満たされない感覚はどこから来ているのか考えることが大切です。そしてその満たさない感覚に対して、少しだけ向き合ってみてください。何かに後悔している人は、その後悔している出来事を上書きできるようなことをしてみてください。
例えば、恋愛で悩んでいるのであれば新しい出会いを探してみる。仕事で悩んでいるのであれば、スキルアップすることをしてみるなどです。ただ、無理は良くないので、少しずつ心の傷が開かない範囲で行ってみましょう。人と比較してしまう場合は、自分に悪い影響を及ぼす成功者などのSNSは見ないようにすると良いです。
孤独から満たされない感覚が来ている場合は、習いごとやイベントなど人と関わるようにしてみてください。
幼少期の親の愛が不足していることから起こる場合は、信頼できる人と接することで心の傷が癒されます。そのような人を探すのが難しい場合は、自分自身が癒されることをしてみてください。また、喪失体験はすぐに癒えるものではありません。ある程度の時間が必要です。無理に忘れようとするのではなく、その喪失体験を受け入れられるまで、無理をせずゆっくりと過ごすことが大切です。時間とともに他の小さな幸せを見つけることで、心が受け入れる体制になっていくかも知れません。