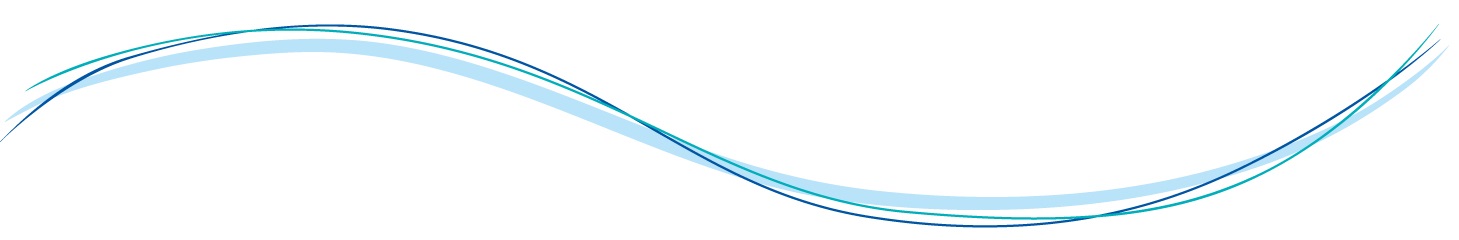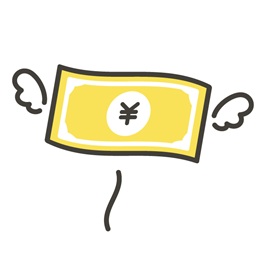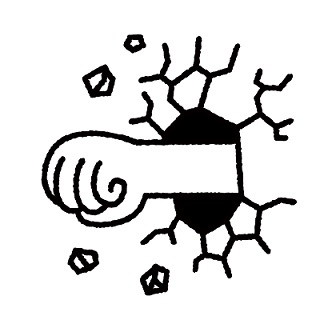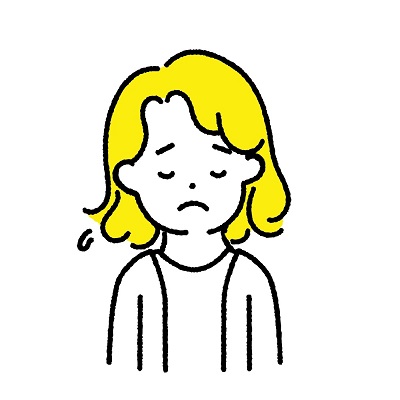親を許せない人の特徴
何かの拍子に「親を許せない」という気持ちが湧いて来て、イライラする人がいます。思春期の子供ならよくあることかも知れませんが、実は中高年になってから感じている人も多いのです。当時の親と同じ年齢になって、子供の気持ちを理解しなかった親の姿がフラッシュバックのように蘇ってくると言います。
親子の情的な絆を心理学では「愛着」と呼びます。子供の頃の愛着関係がきちんとつくられることが、大人になってからの自己肯定感や対人関係につながります。それができないままに大人になってしまったら、親から愛されなかったことや理解してもらえなかったことは恨みになってしまい、いつまでも心に残ってしまいます。それが親を許せない気持ちとして蘇ってくるのです。
今回は、親を許せない気持ちが湧いて来る人の特徴を6つ紹介しましょう。
1 孤独
自分のことを本当に理解してもらったという体験がないために、辛い時の心のよりどころがありません。大人になっても心の真ん中にぽっかり穴があいていて、いつも寂しさや虚しさを感じています。何をやっても心から満たされた感覚をもてません。
パートナーや友達がいても表面的に仲良くしているだけで、親密な関係をつくることができず、いつまでも孤独感がとれない人もいます。孤独感がスイッチとなって、親を許せない気持ちがムラムラと湧いて来るのです。
2 自己肯定感が低い
親に褒めてもらったり、認めてもらったりした経験がないために、自分に自信がありません。どんなに立派な学歴や資格をとったとしても自信につながらないのです。
こうした人は、子供の頃に頑張って良い結果を出しても、親は決して褒めてくれず、「できて当たり前だ」、「親のお蔭だ」と言われてきました。その時の言葉は大人になっても頭から離れません。何かの拍子に思い出してしまい、親を許せない気持ちのスイッチが入ってしまうのです。
3 劣等感
自分に自信がないので、いつも他人からの評価を気にしています。自分で自分の価値を決められず、人と比べることで自分を評価してしまうのです。そのために劣等感を抱きやすい傾向があります。
人より劣っていたり、うまく行かないことがあったりすると、「親のせいでうまく行かない」という怒りが湧いてきます。

4 心の傷が癒えていない
「親を許せない」という気持ちが続いているということは、心の中でまだ解決されていない痛みや傷が残っていることを意味しているかもしれません。
これは例えば、親からの言葉や行動が、今も自分の中で「納得できないもの」として残っていたり、親に期待していたことが叶わず、喪失感や裏切られた気持ちがある。子どもの頃に抱えていた感情(怒り・悲しみ・孤独感など)が、いまも癒されずに影響しているといった、心の奥に残った感情が整理されていない状態です。
5. 親を許せない自分を許せない
父の日や母の日があるように、世の中では、親子が仲良く、子供が親に恩返しをするのが常識になっています。このような世の中の常識に照らし合わせて、いつまでも親を許せないでいることを情けなく感じることがあります。年をとっても恨みを抱えている自分自身を許せないのです。
しかし、恨みは自然に湧いて来るもので、自分ではどうしようもできません。「親を憎んではいけない」と、親への恨みを抑え込もうとすればするほどに、意識はそこに集中してしまいます。これを心理学では「精神交互作用」と呼んでいます。
6. 年をとっても変わらない親
大人になってから親を怒鳴りつけて、怒りをぶつける人もいますが、親は言い訳をしたり、黙り込んでしまったりと、期待した反応はありません。これがよけいに怒りを蓄積させてしまいます。
年をとって子供に間違いを指摘されたら、反省や謝罪をするのが人間としてあるべき姿です。ところが、親自身に発達障害、脳血管障害、認知症などの障害があると、子供から何を言われても心の問題は理解できません。子供の気持ちを永遠に理解できない親もいるのです。
こうした親を持っている人は、親と接する度に、許せない気持ちが倍増してしまうでしょう。
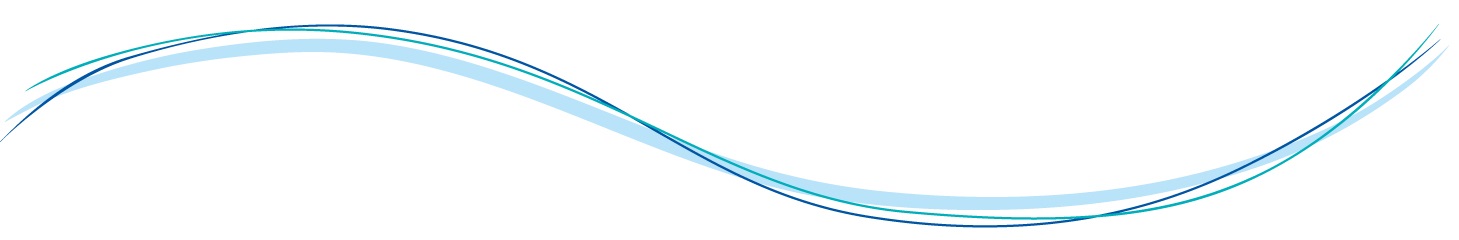
親を許せない気持ちは、抑え込んでもダメ、親にぶつけてもダメ、一体どう処理したら良いのでしょうか?
「親孝行」という言葉もありますが、これは親から受けた愛情への恩返しです。愛情を受けていないならば、返す恩もありません。親を許せない気持ちが湧いて来ても、バチはあたらないでしょう。
とりあえず親に自分のことを分かってもらえることは諦めて、親を許せない気持ちは放置しておきましょう。親が死んでから許せる人も多いので、いまは無理に解消させなくても良いのです。
そもそも「生みの親より、育ての親」と言われているように、親子には愛着という情的な繋がりが大切です。血の繋がりだけが親子ではありません。愛着関係をつくるのは実の親でなくても良いのです。親を許せない気持ちが強い人は、親の存在は無視して、親とは別の存在に心の拠り所を探しましょう。一番良いのは、あなたを大切にしてくれる人と良い関係を継続することです。良い出会いがないのならば、友達を大切にしたり、ペットを可愛がったり、推し活をしてみるのも良いでしょう。満足や安心を感じられる関係を続けてみることが大切なのです。
うつ病の思考
人は不思議なもので、同じ出来事を経験しても人によって違った捉え方をします。例えば、マンションの上の階から大きな足音が突然聞こえた時に、全く気にしない人もいれば、「うるさい迷惑だ」と腹を立てる人、「何か事件があったのかな?」と不安になる人、「私がうるさいから怒っているのかな?」と自分を責めて考える人など様々です。
これは人がそれぞれ異なる考え方のパターンを持っているからです。心理学では、考え方のパターンを「考え方の鋳型」とか、「スキーマ」と呼びます。クッキーの生地を丸い鋳型に入れて焼けば、丸いクッキーになり、星型の鋳型に入れて焼けば、星型のクッキーになるのと同じです。目や耳から入る情報は、脳の中の考え方の鋳型に入れられ、その人の情報として加工されて結論が導きだされます。人はそれぞれに違う考え方のパターンをもっているので、同じ情報を手に入れても違った結論を導きだすのです。
先ほどの足音の話に戻ると、ネガティブな考え方のパターンを持っている人は怒りを感じたり、不安になったりしますが、ポジティブな考え方のパターンを持っている人は気にしないといった感じです。人によって、ネガティブやポジティブだけでなく、物事を素直に考えるパターン、深く原因を追究しようとするパターンなど、その人の特徴的な考え方のパターンがあるので、同じ経験でも人によって別の結論が出てしまうのです。
アメリカの精神科医アーロン・ベックは、うつ病の人には3つの特徴的な考え方のパターンがあることを発見しました。特にうつ病を若い時に発症した人、慢性化している人の場合は、うつ病を発症する前からこのパターンがあることが分かっています。
今回は、うつ病の人の特徴的な3つの思考パターンを紹介しましょう。これに気づくことで、うつ病の生きづらさを減らすヒントになるかも知れません。

1 「自分は必要のない存在」
人の考え方のパターンは、子供の頃に経験してきたことの影響が大きいと考えられています。人生がずっとうまく行ってきた人は、何をやっても失敗しなかったので、物事を深く心配しません。常に気楽でポジティブな考え方のパターンが身に付きます。ところが、挫折が多かった人、失敗ばかりしてきた人は、用心深くなり、新しいことにチャレンジしようとしても、最初にうまく行かなくなることを考えます。常に慎重でネガティブな考え方のパターンを持つようになるのです。
子供の頃に人から大切にされた経験が少ない人は、「自分は必要のない人間だ」というネガティブな考え方のパターンが身についてしまいます。何か困ったことが起こった時に、「何とかしよう」という気持ちが起こらずに、必ず「私のせいでうまく行かない」、「私は迷惑な存在」と考えてしまい、気持ちが萎えてしまいます。これが重なることでうつ病を発病することになるでしょう。
このように、若い頃にうつ病を発症したり、慢性化したりする人には、「自分は必要のない存在」という考え方のパターンが染みついている場合が多いのです。
2 「世の中に味方はいない」
いじめを経験したり、信頼していた人から裏切られたりした経験があると、「世の中に味方はいない」、「人を信じてはいけない」という考え方のパターンが身についてしまいます。詐欺にあった後に、一時的に人を信じられなくなることがありますが、それが長く考え方のパターンとして残ってしまうのです。
周りを敵視することは、危険から身を守るために必要でもあるのですが、人間関係は広がりません。人と親しくなりそうでも、「いつか裏切るに違いない」と猜疑心をもって付き合うことになるので、自分から距離を縮めることができません。孤独になることも多く、そこからうつ病に発展することがあるでしょう。

3 「何をやってもうまく行かない」
子供の頃から失敗や挫折ばかりを経験していると、うまく行かないことが当たり前と考えるようになります。「何をやってもうまく行かない」という考え方のパターンが出来上がってしまうのです。例え良い出来事があっても、「どうせダメになるにちがいない」と心から喜ぶことができません。
未来のことはすべてネガティブに予測するので、新しいことに向かっていく気力が湧きません。その上、環境が変わる度に「悪いことが起こるに違いない」と心を消耗してしまい、うつ病になってしまうのです。
スマホやパソコンのやり過ぎで首の骨が変形してしまうことを「スマホっ首」と呼んでいます。ずっと前かがみの姿勢でいることから首の骨が逆の方向に曲がってしまい、首の痛みや肩こりを起こします。スマホっ首を治すには、マッサージを受けるのも大切ですが、自分でも姿勢を意識して生活することが大切です。
うつ病も同じで、若い頃からの辛い経験が考え方を歪ませてしまい、「自分は必要のない存在」、「世の中に味方はいない」、「何をやってもうまくいかない」という3つの考え方が癖になってしまい、これが原因でうつ病になってしまう人も多いのです。スマホっ首を治すためには、染みついた前かがみの姿勢を治さなくてはならないように、うつ病の人は、この3つの考え方が浮かんだ時には、「悪い考え方の癖が出た」と気づくようにしましょう。
世の中のあらゆる存在は自然の法則で繋がりあっているので、どんな人でも必要があって生まれてきています。決して「自分は必要のない存在」ではありません。広い世界にはあなたを必要としている人が必ずいるはずです。
また、世の中には自己中心な悪い人はたくさんいますが、思いやりのある優しい人もいます。これまでに良い出会いがなかっただけで、「世の中に味方はいない」ということはありません。これから良い人と巡り合えたならば、その出会いを大切にしましょう。
そして、人生でうまく行ったことが全くないという人であっても、深く思い出せば人から褒められたり、喜んでもらったりした経験はゼロではないはずです。こうした体験を思い返し、人に喜んでもらえる努力を少しずつ重ねていけば、必ず何らかの結果を残すことでしょう。
時間はかかりますが、こうした積み重ねをすることを通して、悪い考え方のパターンは修正されていくはずです。
心の傷-トラウマとは
みなさんは、ずっと昔に経験した辛かった出来事の夢を見ることはありませんか?何年も、何十年も前の出来事なのに、夢の中ではまるで今起きているようです。
目覚めてしばらくは現実との区別がつかなくて混乱し、意識がハッキリしてくるとようやく夢であったことを認識できます。ところが、不快な気持ちは1日中消えません。まるで寝ている間に過去にタイムスリップしてきたような感覚です。
これはあなたの心に残っているトラウマです。過去の辛かった出来事が心の傷となって、それが完全に癒されていない証拠と言えるでしょう。大ケガをして、見た目で傷はふさがっていても、何かの度にズキズキ痛むのと同じで、過去の出来事が何度も蘇ってくるのです。心理学ではこれを「再体験」と呼びます。
トラウマになる出来事は、災害、事故、事件、性的被害が代表的です。それだけでなく、いじめ、親からの虐待や厳しい教育、大切な人との別れ、信頼していた人から裏切られる、厳しい試験勉強などもトラウマになる可能性があります。
トラウマの原因は人それぞれで、他人にとっては「そんなことで苦しんでいるの?」と思われる出来事でも、その人にはトラウマになります。同じ災害の被害者でも、トラウマになる人とならない人がいるのと同じことです。
今回は、心の傷・トラウマについて解説しましょう。

1 フラッシュバック
トラウマは夢の中で再体験を繰り返すと言いましたが、再体験は夢の中だけではありません。例えば、いじめを受けたトラウマを持っている人は、テレビでいじめのシーンを見ただけで当時の辛い記憶が蘇ります。過去の出来事に関連する内容に触れるとスイッチが入り、心は過去にワープしてしまうのです。
再体験は、何かのきっかけでいつでも起こりうることです。これをフラッシュバックと呼びます。
2 時間がたってからトラウマに気づくこともある
例えば、交通事故の被害にあって、その場では取り乱すことなく過ごすことができても、数カ月してからトラウマとして再体験することもあります。
周りの人から、「あの時普通にしていたじゃない?」と言われても、事故の直後は警察に連絡したり、体のケガの確認で必死だったり、やるべきことに意識が行ってしまい、心の中で起きていることを冷静に感じることができなかったのです。また、動揺して感情が動かなくなっていたのかも知れません。ところが、心には大きなトラウマが残っていて、後から症状が現れることがあるのです。
このようにトラウマは後から気づかれることがありますが、数カ月どころか数年たってから蘇ることもあります。例えば、小学生の頃に受けたいじめの経験が、何かのきっかけで大人になってからフラッシュバックを繰り返すようになることもあります。
3 その場所や話題を避ける
酷い仕打ちをした人とは二度と関わりたくないのは当たり前ですが、それがトラウマになると、その人に関係する場所や話題すべてにアレルギーのようになってしまい、全く触れることができません。
無意識のうちにトラウマの出来事に関係することを避けて生きて行くようになります。これは、心が自分を守るために、過去を連想させるような出来事を避けるようになっているのです。

4 また起きるのではないかという緊張感がとれない
トラウマが深刻であると、また起こるのではないかという不安がとれず、1日中緊張感が取れません。食欲はなくなり、夜も熟睡することもできなくなります。常に気分がすぐれず、うつ状態となり、日常生活もふつうに送れません。
このような深刻な状態は、災害、犯罪、性的被害のように命の危険にさらされるような出来事によって起こりやすく、これをPTSDと呼びます。
5 トラウマが消えるのは人によって違う
トラウマがいつ良くなるかは、人によって違います。軽症の場合は2カ月くらいで改善されていきます。ただし、PTSDのような深刻なトラウマの場合、70%の人が何らかの形で一生残ってしまうとも言われています。症状は必ず徐々に減っていきますが、軽いフラッシュバックや夢で見ることがいつまでも続くことがあるのです。
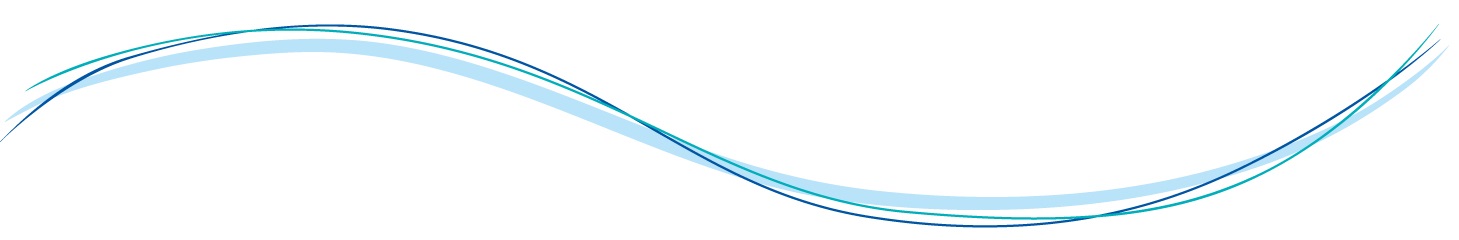
以上、トラウマについて解説しました。
体の傷を治すためには、傷の部分を保護して守り、自然にふさがるのを待つことです。トラウマも同じで、安心できる生活を送りながら、癒されるような体験を重ねることで自然に消えて行きます。
関西の方では、「日にち薬(ひにちぐすり)」という言葉があります。「どんな悲しみや苦しみでも、月日を経ることによって、それを乗り越える力を時間が与えてくれる」という意味です。トラウマを治すためには、むしろ過去の出来事を意識しないようにして、楽しいと思える体験、癒されるような体験を重ねていくことが大切なのです。
また、信頼のできる人といっしょに、トラウマになった出来事を話し合うことも、トラウマを解消する方法です。安心のできる人の前で、辛かった思いを言葉にすることで、トラウマの毒が消えて行くのです。ただし、無理をして話すのでなく、自分から話したいという自然な気持ちを大切にしましょう。無理をして話すことは逆効果にもなるので注意してください。
眠れない、食欲がない、不安、うつ気分で日常生活に支障があり、前に進めない場合は精神科で薬の治療を受けることもできます。あくまでも対症療法ですが、体調や気分が楽になる分、トラウマも解消されやすくなります。
トラウマが良くなるには、「日にち薬」が大切です。「過去を自然に話せるようになった」、「夢で見なくなった」、「近寄れなかった駅に行くことができた」、こうしたことが起きているならば、あなたのトラウマは消えかかっているサインです。
双極症の8つの特徴
双極症は、うつ状態と躁状態を繰り返す病気ですが、ほとんどがうつ病から始まります。どういうことかと言うと、ほとんどの双極症の人は、うつ状態が数カ月から数年続いた後に突然躁状態になり、改めて双極症と診断されます。
逆に躁状態から始まる双極症はわずか30%です。ですから、うつ病と診断されて、5年、10年たって初めて躁状態になり、実は双極症だったという人も珍しくありません。
このように説明すると、双極症とは、うつ病に躁状態がくっついただけの病気と勘違いされやすいのですが、実は双極症とうつ病は最初から別の病気です。そもそも、うつ病の「うつ状態」と双極症の「うつ状態」には違いがあります。
このようなことを踏まえながら、今回は双極症の8つの特徴を紹介しましょう。

1 過眠・過食
普通、うつ病というと「眠れない」、「食べられない」ことが特徴ですが、双極症のうつ状態は、過眠と過食をするのが特徴です。「1日10時間以上寝ても寝たりない」、「いくら食べてもお腹がすいて仕方ない」といった感じのことが起こります。
また、双極症は季節の影響を受けやすく、秋から冬にかけてうつ状態が起こりやすいという傾向もあります。ですから、寒くなると熊が食いだめをして冬眠するのと同じように、双極症の人も寒くなると、やたらと食欲が亢進し、睡魔に襲われるようになります。
2 体が鉛のように重くなる
双極症の人は、うつ状態になると寝込んでしまうことが多く、「体が鉛のように重い」と表現します。これを鉛様麻痺(なまりようまひ)と呼び、双極症のうつ状態に大変よく見られる症状です。まるで手足に鉛を入れられたような感覚になり、体を動かすことが億劫になります。
ずっと立っていることも辛くなり、すぐに横になりたくなるのです。その上、過眠・過食が加わりますから、「1日中ゴロゴロして、起きている時は何か食べているだけ」という怠惰な生活です。
注意していただきたいのは、過眠・過食・鉛様麻痺は双極症だけでなく、「非定型うつ病」というタイプのうつ病にも見られます。このために双極症とうつ病は鑑別が難しいのです。
3 突然元気になる
「三年寝太郎」という日本昔話をご存じの人は多いと思います。寝太郎は3年間ただずっとゴロゴロ寝て過ごし、ある日むっくり起き上がります。そして、外に出ると大きな岩を一人で動かし、川の水が流れるようにして村の飢饉を救ったという話です。双極症の人も似たような感じで、何カ月も何年もずっと寝て過ごし、ある日突然活動を始めます。
うつ病ならば、数カ月かけて徐々に回復していくのが普通ですが、双極症の場合は回復が急激です。ある日を境に、掃除、おしゃれ、買い物、SNS発信など、それまで何もできなかったことを取り戻すような感じで動き回ります。
そのまま普通に生活ができれば良いのですが、段々言動がエスカレートして元気すぎるようになることもあり、これが躁状態です。
4 大きな買い物をする
躁状態になると気持が大きくなり、「いくらでもお金が湧いて来る」という感覚になります。ブランド物、高級時計、高級車、マンションなど次から次へと欲しいものが止まらなくなり、無茶なローンを組んでしまいます。100円ショップに立ち寄ったところ、支払いが1万円だったという話もあります。
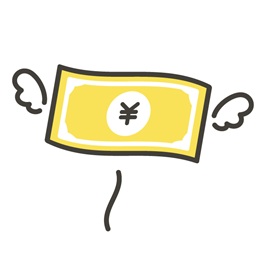
5 すぐに結果を出そうとする
躁状態では大きなことを考えるようになり、同時に、寝込んでいた期間を取り戻そうと焦ります。元々コツコツ積み上げて何かをすることが苦手なので、すぐに結果が出るような仕事に手をつけます。深く考えずにうまい儲け話にのってしまい、騙されてしまうこともあるでしょう。宝くじやギャンブルで一攫千金を狙う人もいます。
6 何ごとも待てない
待つことができないので、すぐに実行です。失敗した時のことは考えられません。すでに買い物のことを紹介しましたが、就職、退職、起業、投資、結婚、離婚など、人生の大事なことも深く考えずに決めてしまうことがあります。
もちろん身近なところでも「待てない」が出て来ます。レストランで注文したものが遅いと怒る、レジの行列もイライラして文句を言う、といったことでトラブルになることがあります。
7 ドタキャン
寝ないで動き回っていたら、人のエネルギーはいつまでも続きません。数週間から数カ月過ぎると、ある日突然、電池が切れたように動けなくなります。体が重くなり、睡眠時間が長くなり、うつ状態に逆戻りです。人と会う約束、面接の予定、大事な会議など、すべてドタキャンすることになります。
双極症のうつ状態は突然やってきます。仕事などがうまく回り始めた時に突然うつになってしまうことが多いので要注意です。
8 手を広げ過ぎて後悔
躁状態の時に色々なことに手を広げ過ぎてしまうので、うつ状態になると収拾がつかなくなります。「新しい会社に勤めたのに通えない」、「会社を起業したのに寝てばかり」、「買ったマンションのローンが払えない」、「高級ゴルフセットを買い揃えたけれども、ゴルフをしたくない」といったように、後悔や借金が残ってしまい、周りの人に助けてもらいながら、辛い期間を過ごすことになるのです。
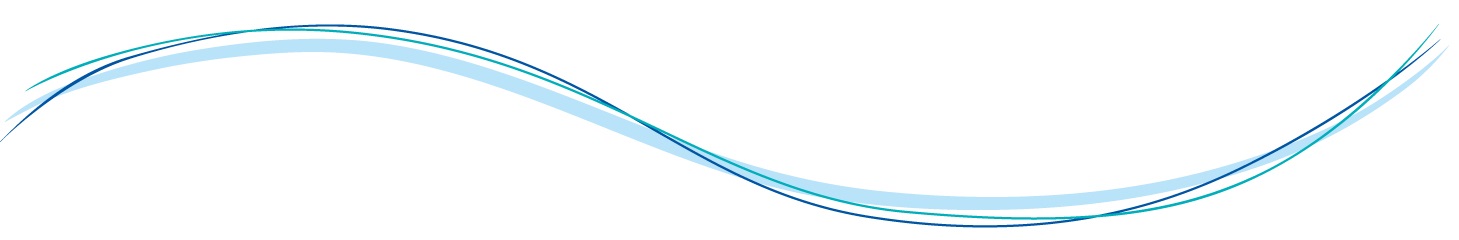
双極症の治療を受けないでいると、「躁状態で手を広げて、うつ状態になって後悔」という失敗のパターンを何度も繰り返します。周りの人からは、「何で一度の失敗で学ばず、同じ失敗を何度も繰り返すのだろう」と不思議に思われますが、これは脳の活動が病的な変化をするために起こる現象です。
特に躁状態では気分が良くなるので、「治療は必要ない」と思ったり、「もう2度とうつにはならない」という根拠のない自信を持ったりするために、治療を受けない人もいます。
双極症は治療に長くかかる病気ですが、薬の治療で気分の変動を最小限に抑えることができます。治療には炭酸リチウム、バルプロ酸、ラモトリギンなどの気分安定薬が中心に使われています。薬で気分をうまくコントロールしながら、社会で活躍し、成功している人もたくさんいます。
また、双極症と発達障害のADHDは似ているので間違えられやすい病気です。今回紹介した症状がある場合は双極症ですので、精神科に相談してみましょう。
迷惑をかけたくないのに迷惑をかけてしまう人
世の中には、悪意でわざと迷惑をかける人がいますが、「人に迷惑をかけないで生きて行きたい」と思うのが普通の人です。
ところが、何か事件が起きてみんなが大変な時に、自分だけ感情のコントロールがつかなくなり、人と違う行動をとってしまったり、パニックを起こしたりする人がいます。周りの人は自分のやるべきことで精一杯なのに、それを邪魔する存在になってしまうのです。
こうした人は、好きでそうなっているのではないのに、「迷惑をかけるな!」と誤解されてしまうことがあるでしょう。世の中には、こうした誤解のために自信を失っている人がたくさんいるのです。
このような人は、なぜ周りに迷惑をかけてしまうように見られるのでしょうか?今回は、「迷惑をかけたくないのに迷惑をかけてしまう人」について詳しく説明しましょう。

1 繊細な人
心が繊細な人は、人一倍物事の大変なことを理解できてしまうために、感情のコントロールがつかなくなることがあります。自分の大変さを言葉で伝えることが苦手であると、人と違う行動をしたり、パニックになったりすることがあります。それで周りに迷惑をかけてしまうのですが、これは、その状況の大変さを一番つよく感じていることが理由です。
実際にあった話を紹介しましょう。Aさんは知的な障害があり、とても繊細な人です。Aさんの家庭ではおばあさんが認知症になってしまい、介護が大変になりましたが、Aさんは障害のためにほとんど手伝えません。ある日、Aさんは捨て猫を拾ってきました。おばあさんが猫好きだったので、喜ぶのではないかと考えたからです。
「家族が介護で大変なことが分からないのか!迷惑だよ!」と、お父さんはAさんのことを叱りました。Aさんは泣いてしまいましたが、猫を見たおばあさんはニコニコ笑顔です。何年も笑ったことのなかったおばあさんの姿を見て両親は驚いて、それ以上Aさんを叱れません。結局その猫を飼うことになり、おばあさんは猫と遊ぶようになりました。
そして、認知症にも改善が見られるようになったのです。実は、おばあさんの孤独な気持ちを一番理解していたのが、両親でなくAさんだったのです。
2 能力が足りない人
チームでの競技や仕事をしていると、能力が足りないがためにチームの足並みを乱してしまう人がいます。特に結果のみを最優先するような職場では、能力の劣る人に批判が向きやすくなります。一生懸命やっているのに、周りの冷ややかな視線を感じた人は、「自分はみんなの足を引っ張る迷惑な存在なのかな」と悩むようになります。
しかし、チームとは本来、互いに援助しあい、知識を共有しながら、成果を上げていくところに意味があります。能力の優れた人が、能力の足りない人を「迷惑な存在だ」と言っている限りは、よい結果は生まれません。
それどころか、いじめやパワハラにつながります。むしろ、「迷惑だ」と言っている人の方が、チームにとって迷惑な存在なのです。

3 依存的な人
頼り過ぎてしまうことから、人に迷惑をかけてしまうことがあります。「頼ってもいいよ」と言われても、相手の事情を考えずに、24時間いつでも連絡を取り続けていたら、さすがに迷惑に思われることがあるでしょう。これは一人の人にだけ頼り過ぎてしまうことから起こる現象です。相手を束縛するくらい頼ってしまえば、「依存」と呼ばれても仕方がありません。
こうした人は、「依存してばかりいないで、自立しなさい」と怒られてしまうことがあります。では、そう怒る人は、誰にも頼らないで生きて来たのでしょうか?そんなことはなく、親や先輩など、たくさんの人を頼って生きて来たはずです。人を全く頼らないで生きている人など世の中にいません。
自立とは、たくさん頼るところを持っていて、一つのところばかりを頼らないことなのです。たくさんの人に広く浅く頼っているから一人で立っているように見えるだけです。不器用なために、一人の人にしか頼れないから依存的に見られてしまいます。
私たちは、子供の頃から「人に迷惑をかけない人になりなさい」と言われて来ました。実は、この「迷惑」という言葉は、仏教から来ています。
仏教では、すべての人は必ず誰かに迷惑をかけて生きて来たのだから、迷惑をかけてくる人のことを許すことが大切であると説いています。決して、人に迷惑をかけてはいけないとは説いていません。ましてや、「お前は迷惑な存在だ」と人を批判するために使う言葉ではありません。
ですから、自分のことを「迷惑をかけている存在だ」と悩む必要はないのです。むしろ、他人のことを「迷惑だ」と言ってくる人こそ、何事も自分だけでやっていると勘違いしている本当に迷惑な人なのです。
ADHDの人の考え方
注意欠如多動症・ADHDの人の思考回路はとても独特です。ADHDには、不注意、多動性、衝動性の3つの症状がありますが、これらが考え方に影響しています。そこで、今回はADHDの人がどのような考え方をするのか解説していきましょう。
ADHDの人は、感情的で落ち着きのない人というイメージをもたれてしまい、誤解される傾向があります。しかし、その思考のパターンを理解すれば、周りの人とのすれ違いの原因を知ることができます。また、周りの人もADHDの人の言動を納得するきっかけになるでしょう。

1. 連想ゲームのような思考
ADHDの人と会話をしていると、話題が次々と飛んでしまうことがあります。これは、会話の内容と関係なく、頭の中で新しい話題が連想ゲームのように次々と湧いてくるのが原因です。例をあげて説明しましょう。
「この間久しぶりに飲みに行って楽しかったんだ」と、共通の友人の話題をしていたかと思うと、突然「最近小麦粉が高くなってるよね」と話題が変わります。相手にとっては、友人の話題から全くつながりのない「小麦粉が高くなっている」話題に突然変わったのでビックリしますが、本人の頭の中では、友達と飲みにいって、行った帰りにラーメン屋に寄りそこで食べたラーメンが値上がりしていたので、小麦粉が高くなっている話題が出てきただけなのです。本人としてはつながりがある話題ですが、相手には理解できません。
いつもこんな感じであると、話についていく相手が疲れてしまいます。一つの話題で話している最中にも、頭の中で連想ゲームが始まってしまうのです。
ただし、この症状がつよい場合、例えば、次々と話題をかえて、マシンガンのように話す場合は双極症の可能性もありますので注意しましょう。
2. 遅刻したくないのに遅刻をする
遅刻癖はADHDの人によく見られます。何度失敗しても治りません。ADHDで遅刻の多い子供を観察していると、外出の時間がせまっているのに準備をしないでのんびり他のことをしています。出かけることよりも、今やっているゲームや遊びに意識が集中してしまい、外出のことがどこかへ飛んでしまうのです。
大人のADHDの人も同じような理由で遅刻をします。何を着て行こうか、忘れ物はないかと迷っているうちに、そこに意識が集中してしまい、肝心の出かける時間を逃してしまうといった感じです。このようにADHDの人は悪気があって遅刻しているのではありません。
3. 目先のことが優先で長期的なことが考えられない
ADHDの人は家計簿をつけられず、お金の収支を把握することが苦手です。例えば、欲しいと思ったら借金をしてでも買ってしまう衝動買いがあります。今月の生活費があと1000円しか残っていないのに、欲しかったバッグを見つけたらカードで借金して買ってしまいます。
普通の人ならば、今月1000円でどうやって生活するかが最優先ですが、ADHDの人の場合、欲しいものを見つけたらそれが最優先されるのです。「欲しい」という思いが頭の中を占領してしまい、残金1000円のことはどこかへ飛んでしまいます。さらに負債を増やしてしまうので後悔をしますが、その後も衝動に負けてしまい、同じ失敗を繰り返すことがあります。
ところが、ADHDの人の中には、この衝動性が行動力につながり、事業を成功させることがあります。スティーブ・ジョブスのように有名な経営者の中には、ADHDの人が多いのもこれが理由です。
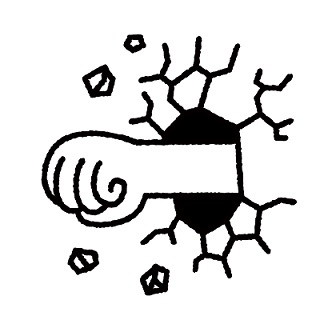
4. 興味のないことは手につかない
学校では、好き嫌い関係なくすべての教科を平均的に学ばなくてはいけません。ADHDの人は、興味の湧かないことに対しては、高いハードルを感じてしまい、「できない」と感じます。それでも頑張ってやろうと努力しても、全く頭に入って来ません。ですから、学校の成績にもムラができてしまいます。
大人になってからの仕事も同じです。興味の湧かないことには、やはり「できない」と感じて尻込みをしてしまいます。そして、無理やりやろうとしても集中ができません。イライラを感じる人や投げやりになる人もいます。大事なことが先延ばしになるということも起きます。
5. 余計なことを言ってしまう
つよい感情が湧いてきて理性で抑えられません。言うべきでないことを言ったり、手が出てしまうこともあります。後悔しますが後の祭りです。例えば、職場で上司の指示に「はい」と言っておけばよいことを、一言「それは違います」と余計なことを言ってしまい、職場の評価が下がってしまいます。
夫のちょっとした小言に「私は悪くない」と反発してしまい、大喧嘩に発展します。それを言ってしまうと、関係が壊れて大変な結果になると頭で分かっていても、言葉が先に出てしまうのです。
6. 集中し過ぎると他のことが入ってこない
何かに集中している時は、声をかけられても反応しないことがあります。これを過集中と呼びます。頭の中では、いまやっていることだけを考え続けているのです。疲れているのに、それを感じることなくやり続け、終わった後にどっと疲れを感じて数日寝込んでしまうこともあります。
2002年に韓国では、オンラインゲームに集中するあまり、80時間飲まず食わずでゲームに没頭し、エコノミー症候群で突然死をした24才の青年がいました。
逆に興味のないことには全く集中できません。感覚過敏は、ADHDの人にも見られることがあり、光や音の刺激や、頭の中に浮かぶイメージが、注意や思考の流れを乱します。大事な作業中でも、ちょっとした物音で集中が途切れたり、「そういえばドラマの新作いつ配信されるんだっけ?」「夕食何食べよう?」といった考えが浮かんで、手が止まったりもします。

以上、ADHDの人の考え方について紹介しました。今回の内容がすべてのADHDの人に当てはまるわけではありませんが、「そういえばこんな感じかな」と似ている項目があるかも知れません。どれも不注意や衝動が抑えられないという脳の構造から来ていることですが、人間関係で損をしている人がたくさんいます。
我慢すれば良いものを、余計なことを言ってしまったことから出世を逃した、離婚になった、という話もよく聞きます。しかし、自分の特性を理解することで、若干の改善も期待できます。また、思いっきりの良さから大成功を収める人もいますので、「災い転じて福となす」と考えましょう。
自分を大切にできていない人の7つのサイン
誰でも好きな人に対しては、愛情をもって接します。強制された訳でなく、愛情は自然にあふれてくる感情で、相手に注ぐことを通して自分自身も幸せを感じることができます。
愛情とは、相手を大切に思う気持ちです。家族、恋人、友達、会社の仲間、憧れの人、ペットなど、様々な愛情の対象があります。
ところで、肝心の自分自身には愛情を注ぐことはできていますか?自分自身を大切に感じていないと、自分に愛情を注げません。そもそも人は成長の過程で、自分を愛することを学び、次に人を愛することを学びます。自分を愛することができなくて、人を愛することはできないはずなのです。人は大切にできるのに、自分を大切にできないことはとても矛盾した生き方です。なぜこのような生き方をしてしまうのでしょうか?必ず理由があるはずです。
今回は自分を大切にできていない人の7つのサインを紹介しましょう。この中から自分自身を大切にできない理由を知ることができるかも知れません。

1. 自分を否定する考えが多い
人生で人から褒められたことがない、ずっと失敗や挫折ばかりだった。このような生き方をしていると、自己評価が低くなり、自分のことが好きになれません。どうせ何をやってもダメだと考えるようになります。
自分自身に対して「ダメだ」、「できない」と否定的な言葉をかけることが多く、常に最悪のケースを考える傾向もあります。そうすると新しいことに挑戦する気持ちも失っていくでしょう。仮にうまくいったとしても、「たまたまだ」と考え、自分の評価につながりません。
これが習慣になってしまうと、自分自身を大切にする気持ちがなくなってしまいます。
2. 他人の評価に敏感
自己肯定感が低くなると、それに反比例して、人からの評価が気になるようになります。自分で判断することに自信がなくなり、すぐに人の意見に左右されてしまうでしょう。
SNSをやっている場合は、他人のコメントや反応が気になりすぎて、つねにチェックをしています。否定的な内容を読むと具合が悪くなるのですが、自分の評判が気になるので、発信することもチェックをすることもやめられません。
3. 自分の気持ちを抑え込む
自分を大切にできない人は、自分の感情を抑え込んで本音を言いません。仕事や人間関係で辛いことがあっても、我慢して嫌な気持ちを心の中にため込んでしまいます。
「本当はこんなことをやりたい」、「あんなことをやりたい」という願望も抑え込みます。まるで、心に蓋をしてしまっている生活を送っています。

4. 自己犠牲的な行動を取る
他人の期待に応えようとするあまり、自分の本音を我慢することがあります。表面的に自己犠牲に見えるのですが、気持ちよく自分を犠牲にしているのではなく、認めてもらう見返りであったり、不満を我慢していたりと、決して志(こころざし)の高いものではありません。心の根っ子に「誰かの役に立っていないと価値がない」という考え方があるのです。
5. 自分を優先することに罪悪感を感じる
周りの人よりも良い思いをすることに罪悪感を抱きます。例えば、ファッションや美容にお金をかけたり、習い事をしたり、旅行を楽しむなど、自分に投資することに罪悪感を感じます。
それとは反対に、他人に付き合ったり、おごったりすることにはためらいがなく、むしろ積極的です。自分に投資することよりも、人に認めてもらいたい気持ちが優先してしまうのです。
6. 無理をしがち
疲れていても、休むより仕事を優先します。自分の限界を超えて無理をすることが多く、「もう少し頑張らなければならない」と義務感が働いてしまうのです。この背景には、忙しさでさみしい気持を誤魔化したり、忙しくすることで自分に価値を見出そうとする気持ちがあります。
7. 自分の健康を疎かにする
無理をするので、健康を疎かにしがちです。仕事や人の世話を優先するので、不摂生な食生活、睡眠があっても放置してしまいます。背後に「もうどうでもいいや」という投げやりな気持ちがあります。健康診断で引っ掛かっても気にしない人もいて、タバコやお酒をやめられないこともあるでしょう。

自分を大切にできてから、他人を大切にできるようになります。自分を大切にしないで、他人を優先するのは、本来の生き方ではありません。これを続けていると、徐々に心が病んでいきます。
自分の本当の気持ちに正直になって、「嫌なことは嫌」、「できないことはできない」と少しずつ主張するようにしましょう。「やりたくないことは断る」という態度も必要です。
また、自分が心からやりたいことにお金を使って、自分に投資してみましょう。「どうせお金の無駄になる」と考えないで、自分にご褒美をあげるのです。これを続けていくと気持ちが変わって行くでしょう。お金は貯めるためにあるのでなく、使うためにあるのです。
いつもSNSで人と比べる生活もやめるべきです。自分の価値は他人の目が決めるのではなく、自分で決めるものです。「人はどう思おうとも、私はこう思う」という気持ちを大切にしましょう。
うつ病の人が感じる6つの孤独
誰もが生きていると、「寂しいな」、「孤独だな」と感じる時があります。ところが、うつ病の人が感じる孤独感は、健康な人が感じるものと比べて、つよさでも質でも異なります。今回は、うつ病の人の孤独感について説明しましょう。
うつ病は気分が落ち込む病気ですが、それを孤独感として感じる人がいます。うつ気分と孤独感は似ている感情だからです。また、うつ病が原因で世の中と疎遠になり、そこからさらに孤独をつよく感じます。
うつ病で孤独を感じ、そこから2次的に現実でも孤独になって、さらに孤独感がつよくなるという悪循環に陥るのです。まさに、「孤独地獄」と言えるような苦しいものです。
うつ病の孤独感は、不安や恐怖とも重なります。胸の痛み、息苦しさ、このまま一人でいると死んでしまうのではないかというようなパニック発作が伴うこともあります。病気になる前は、一人でいることが好きだった人であっても、一人が怖くなります。
うつ病の人にとって孤独は何よりもつらい症状です。それでは、うつ病の人が感じる孤独を6つ紹介しましょう。

1 社会とのつながりがなくなる孤独
療養している人は、社会との接点がなくなり、人と話す機会が減ります。「今日は誰とも話さなかった」という日もあるかも知れません。人と接する機会をつくるために、イベントにでかけようとしますが、そもそも何かをするエネルギーがないため、通い続けることができません。また、心配した友達からの誘いがあっても、「情けない自分の姿を見せたくない」と思い、断ってしまうことも多いでしょう。
このように、孤独を解消したいのに、何もできない自分の無力さに直面して余計に苦しくなるのが、うつ病の孤独です。
2 世の中の流れから取り残される孤独
一度うつ病にかかると、数年間療養しなくてはならない場合もあります。この間、世の中の活動には参加できないため、周りから取り残されている感覚です。特にSNSで同年代の人が活躍している姿を見ると、自分が情けなくなります。自分以外の人はどんどん先に行ってしまい、残された自分がみじめで仕方ありません。
3 理解してもらえない孤独
家族と同居していると、「いつから働けるの?」、「いつまで薬を飲むの?」と言われることがあります。もちろん家族も心配で言っているのですが、一番気にしているのは自分ですから、「怠けている」、「努力していない」と、嫌味を言われているような感じです。病気で何もできないと説明しているのに、いつまでたっても理解してもらえません。近くにいる人から理解されないことほどつらいことはありません。
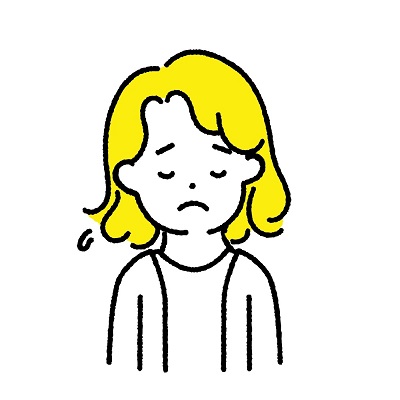
4 目の前の人と心が通じない孤独
人と話していても、心と心の間に壁があるようです。なぜか気持ちが通じません。大勢で会う場面では、みんなが楽しんでいるテンションについていけず、自分だけ仲間外れにされたように感じます。
そのために、「自分の苦しみは、誰も理解してくれない」と無力さを感じます。他人と関わることがよけいに億劫になり、何をしても孤独から逃れられないと感じてしまいます。
5 世の中から必要とされていない孤独
うつ病になると、それまでできていたことができなくなります。何かをすることで自分の価値を見出してきた人にとっては、自分の価値や役割がなくなったと感じます。
例えば、仕事が自分の誇りであった人は、会社に行けない自分には意味を見出せません。料理作りが得意だった主婦は、料理を作れない自分が情けなくなります。その上、1日ゴロゴロして、建設的なことは何もできずに終わってしまったら、「自分は消費だけしている必要のない人間」と自己嫌悪に陥ります。社会から必要とされていない感覚は、つよい孤独として感じられるのです。
6 独りで悩み続ける孤独
うつ病になると、「どうして生まれてきたのか」、「人生の目的は何か」と、哲学的なことを考えがちです。答えのないことに答えを出そうとして、いつも頭の中はネガティブな考えに支配されています。まるで、出口のないトンネルを一人で歩き続けているような感覚です。

うつ病の孤独地獄から抜け出すためには、根っ子にあるうつ気分をしっかり治すことが大切です。気分が楽になることから、世の中との接点も少しずつできるので、孤独の悪循環から抜け出すことができます。
うつ病の人が社会と接点をもてるような施設は、公でも民間でも次々とつくられています。病気の状態によって利用できる施設も異なるので、詳しいことは主治医・ケースワーカー・役所の窓口などに相談してみましょう。
うつ病になった自分を、「カッコ悪い」、「負け組」と考えて、治療に消極的だったり、施設を利用できないでいる人もいます。うつ病になったことはカッコ悪いことではありません。うつ病は誰でもなる病気で、自分を越えて頑張り過ぎた証拠です。スポーツ選手が試合でケガをして休養するのと、本質は変わりありません。
いまは休むべき時であるにも関わらず、うまく行っている人と比べて焦ったり、一人で問題を抱えて人を頼らないことが一番良くありません。病気になったことを素直に受け入れて、「生きてさえいれば何とかなる」と、気楽に考えるようにしましょう。
愛情を感じられない4つの原因
ちょっとしたことでも愛情や喜びを感じられる人は幸せです。どんな状況にも感謝できるので、適応力があります。つらいことを乗り越えられる底力がある人です。反対に、愛情を受けても、否定したり、ひねくれて捉える人は、不平不満も多く、幸せを感じにくいかも知れません。
はたから見たら色々恵まれているのに、本人は「自分は不幸だ」と言っていたら、不思議に思われます。その上、周りの人が色々やってあげても、喜んでもらえなければ、「こんなにやってあげているのに」と嫌われてしまいます。このような人は、なぜ愛情を素直に受け入れることができないのでしょうか?
愛情を感じられないことにはいくつかの理由があります。単に性格の問題で片づけられるものではありません。今回は、愛情を感じられない原因を4つ紹介しましょう。愛情の感じ方で困っている人がいるならば、解決のヒントになることを願っています。

1 愛情を理解できない
心に湧いてくる感情を、言葉で理解できないことを失感情症・アレキシサイミアと呼びます。感情がないわけではありません。自分が体験して心で感じたことを分析することができないのです。例えば、修学旅行の感想文を書けと言われても、出来事を羅列するだけで、感じたことを書けません。職場でハラスメントを受けても、文句を言わずに働き続けます。心の中で起きていることを理解できないことから、気持ちを伝えられなかったり、相手の気持ちも理解できません。愛情を受けても実感を持てないのが失感情症です。
失感情症は病気ではなく、未成年では30~40%、成人したら10~20%に見られる症状で、特別なことではありません。年齢を重ねて減っていくことから、言葉やコミュニケーション能力の未熟さが大きな原因です。また、虐待やいじめなどを受け、つよく感情を抑え込むような状況からも起こります。極端な例をあげると、強制収容所で働かされる人たちです。絶望から感情を押し殺すようになると、ただ黙々と働くだけの人になってしまいます。収容所とまでは言えなくても、一般社会でルールに縛られていたり、自分の主張ができないような生活をしている人にも見られます。
失感情症は、自分の気持ちを表現する経験を積み重ねることを通して、少しずつ改善されます。自分で感じたこと、思ったことを日記に書くことも効果があります。カウンセリングを受けるのもよい手段です。
ただし、対人関係をほとんどつくれなかったり、こだわりがつよい場合は、アスペルガー症候群などの発達障害の可能性があるでしょう。
2 愛情を受けても心に残らない
心の底から人を信じられず、「この人は、いまは優しくしてくれているけれど、将来きっと私を裏切るに違いない」という思いがある人は、愛されている実感を持てません。これを「見捨てられ不安」と呼びます。子供の頃に親子の信頼関係を築けていないことが原因と考えられ、大人になっても残り続けることがあります。
人から愛情を注がれても、「人は裏切るものだ」という信念は変わらず、愛情を素直に受け入れられません。底の割れたコップは、いくら水を入れてもいっぱいにならないように、いくら愛情を注がれてもどこかに流れ出てしまうのです。
見捨てられ不安は治らないものでなく、良い人との出会いやカウンセリングを通して、少しずつ改善されることがあります。ただし、情緒が不安定であったり、衝動性がある場合は、境界型パーソナリティ症という精神疾患の可能性もあるでしょう。

3 愛情を拒否する
人を信用できないため、人との深い交流を避ける人も、愛されている実感を持てません。子供の頃に、親から虐待やネグレクトを受けたり、いじめを受けたことから、人とつながることが怖くなっているのが原因です。深い関係になりそうになると、自然に自分から遠ざかります。孤独が好きなわけではありません。孤独でつらい思いをするよりも、人と深く交わることで傷つくことの方が怖いのです。
見捨てられ不安がある人を割れたコップで例えましたが、愛情を拒否する人は、蓋をしたコップに例えられるでしょう。水を注いでも中に入って行かないように、愛情を受けても心の中に入って行きません。
愛情を拒否する状態も治らないわけではありません。やはり良い出会いやカウンセリングを通して、少しずつ改善されていきます。
4 愛情を誤解する
相手の気持ちを誤解しやすく、好意を悪意としてとらえてしまう人も、愛情が通じません。例えば、親切にしてもらっても、「どうせ下心があるに違いない」と考えます。心の底に「自分は人に好かれない」と思っている人が多いようです。これは、人から大切にされた経験がないことが原因です。愛情を受けても、誤解して跳ねのけてしまうのです。
誤解の仕方がつよい場合は被害妄想と呼びます。うつ病や統合失調症の症状として現れることもあるでしょう。
愛情を感じられないことには必ず理由があります。人から大切にされた経験が少なかったり、子供の頃からのつらい体験が原因となって、愛情を信じられなくなっているのです。もしかすると、何らかの心の病気があるのかも知れません。
もしあなたが、「何で人の気持ちが分からないの?」と言われ、嫌な思いをしているならば、今紹介した4つの理由のどれかが当てはまるかもしれません。カウンセリングなど、誰かに相談する機会を持ってみましょう。
また、あなたの近くに愛情に頑な人がいたら、嫌な人と決めつけがちですが、そうなる理由があるはずなので、誤解しないで接してあげることも大切です。
子どもの頃のストレス 5つの後遺症
虐待、ネグレクト、いじめなど、子どもの頃にたくさんのストレスを受ける人がいます。つらい思いをした人ほど幸せをつかんでもらいたいのですが、子どもの頃にストレスを受けると、大人になっても心と体に後遺症が残ることもあります。
特に思春期までの期間は、心と体がつくられるとても大切な時期です。この時期に虐待、ネグレクト、いじめなどを受けると、それを跳ね返すことはできず、トラウマになって残ったり、神経系やホルモン系に異常を残してしまいます。
今回は、子どもの頃のストレスで大人になっても残ってしまう5つの後遺症を紹介しましょう。

1 自己肯定感が低く、良好な対人関係をつくれない
子どもの時に十分な愛情を受けられず、ネガティブな感情をぶつけられてばかりいると、自己肯定感が育ちません。「自分は必要な人間だ」、「生きていていいんだ」という感情がないままに大人になってしまいます。
自己肯定感が低いので、良好な人間関係もつくれません。他人と仲良くなることが怖かったり、親しくなると依存的になったりと、適当な距離感を保つことができないのです。
また、大人になっても感情を表に出せなかったり、コントロールを出来なかったりするので、発達障害と診断される人もいますが、実は子どもの頃のストレスが原因であるケースも大変多いことです。
2 ストレスに敏感な体質
子どもの頃にストレスを受けすぎると、大人になってからストレスに敏感な体質になります。問題に直面すると冷静に対処できず、うつや不安を感じやすかったり、疲れやすい体質になるのです。
ストレスに敏感になるのは、ストレスホルモン分泌のコントロールがうまくできないことが原因です。ストレスホルモンとは、ストレスを受けた時に副腎から分泌されるコルチゾールと呼ばれるホルモンで、ストレスに対応できるように、全身の細胞を活発にさせる効果があります。非常事態に疲れていても頑張れるように、体に無理をさせるホルモンと言えるでしょう。
研究によると、子どもの頃にストレスを受けすぎると、ストレスホルモンが高い状態が慢性的に続くようになります。このような状態は、脳に悪い影響を与え、特にセロトニンの分泌が減ることから、ストレスに敏感になるのです。
3 うつ病になりやすい
脳のセロトニン分泌は、うつ病やパニック症などの精神疾患と深い関係にあります。子どもの頃にストレスを受けると、ストレスホルモンの影響でセロトニン分泌が減りやすくなり、うつ病やパニック症になりやすくなります。研究では、うつ病になる割合が健康な人よりも2~3倍も高いと言われています。

4 アレルギー体質になりやすい
ストレスホルモンは免疫系の働きを抑えるため、高い値(あたい)が続くことで、アレルギーの症状が現れることがあります。例えば、アトピー性皮膚炎、気管支ぜんそくなどの病気になりやすいことも報告されています。
5 生活習慣病になりやすい
高い値のストレスホルモンが続くと、食行動や睡眠にも影響が出ます。具体的には、ストレス食いなどの過食の傾向が出たり、不眠症になります。こうしたことから、糖尿病、高脂血症、高血圧などの生活習慣病になりやすいことが知られています。
子どもの頃のストレスの後遺症により、心では自己肯定感の低下、体ではストレスホルモンが高い値になることを説明しました。マイナスのことばかりを話しましたが、心にも体にも自然治癒の力があるので、子どもの頃のストレスの影響は少しずつ改善させることができます。今回のサインに当てはまる人は、自然治癒を後押しできるような生活が大切です。
まず、毎日心が安らぐ時間をもちましょう。楽しみを増やすこと、趣味をすること、人と話すことなど、「生きていて良かったな」と感じられる時間をできるだけ多くすることです。当たり前のようですが、毎日の生活に安心や癒しを意識することで、自己肯定感も上がり、ストレスホルモンの分泌も減るようになります。
ストレスホルモンを減らすためには、睡眠、食事、運動の生活習慣を見直しましょう。最低でも1日7~8時間の睡眠が必要ですので、睡眠時間が不規則になりがちな残業の多い仕事、夜勤の仕事、シフトのある仕事は避けた方が良いかも知れません。「みんな寝不足でも頑張っているのに、寝てばかり」と自分を責めないで、ストレスに敏感な人はともかく睡眠を大切にするべきです。
毎日の軽い運動は、ストレスホルモン分泌の切り替えに効果があります。ストレッチでも散歩でも良いので毎日体を動かす習慣をもちましょう。また、これを食べたらストレスホルモンが減るという食べ物はありませんが、栄養バランスを良くすることが大切です。