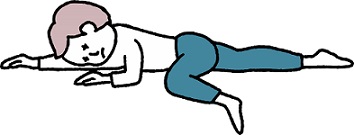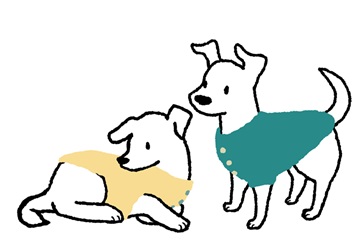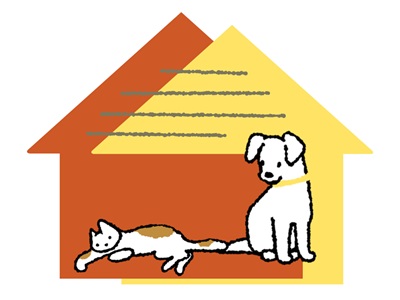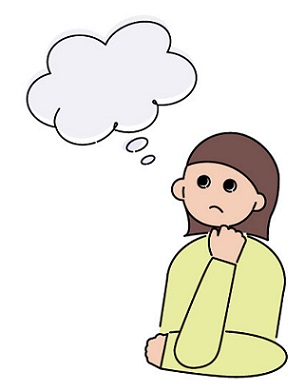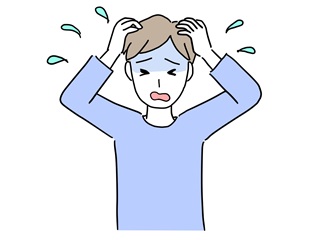うつ病の先延ばし 6つの特徴
やらなくてはならない大事な仕事や勉強を始めようとすると、なぜか気持ちにブレーキがかかってしまい、取り掛かれないでいることを「先延ばし」と呼びます。例えば、「夏休みの宿題を学校が始まる前日までやらない」、「大事な報告書を書かなくてはいけないのに、始めるきっかけをつかめない」、といったように、誰でも経験したことがあるものです。
ところが、これが癖になって、実際に仕事に支障が出ることを「先延ばし症候群」と呼ぶことがあります。「大事なお客さんのところへいつまでも顔を出さない」、「大事な書類を提出しない」となると職場も困ってしまいます。症候群と言っても、ほとんどは病気ではありませんが、中には精神疾患が隠れていることもあります。
先延ばしの原因は一つではありません。「仕事量が多過ぎる」「仕事のレベルが高過ぎる」といった仕事自体の問題もあれば、「疲れがたまっている」など、自分自身の体調の問題もあります。中には、面倒くさがりという性格の問題もあるかも知れません。
ただし、「好きなことから初めて優先順位をつけられない」「スケジュール管理ができないために大事な要件を忘れてしまう」といった場合は、「天然」「おっちょこちょい」と性格の問題に考えがちですが、深刻なミスが続くようならばADHDという発達障害の可能性もあります。
うつ病の症状としても、先延ばし症候群はたいへん多く見られます。うつ病は物事への興味や関心がなくなり、何かに取り組む意欲も低下する病気だからです。「それまできちんとできていたのに、最近先延ばしが増えて仕事に支障が出てきた」という場合は、うつ病の疑いもあります。それでは、実際にどのような状況になってしまうのか、今回は、うつ病の先延ばしの特徴を6つ紹介しましょう。

1 不安で先延ばししてしまう
やることが明確でなかったり、重要なことであると、「できなかったらどうしよう」、「間に合わなかったらどうしよう」という不安を感じます。また、一度経験していることでも、大変だった記憶だけが蘇り、できた自信よりも、不安の方が大きくなります。不安が妨げとなり、仕事に取り掛かろうとする意欲を妨害します。「何とかなる」と、開き直れません。やってしまえば何でもないことでも、不安によって取り掛かるまでのハードルが高くなるのです。
2 ちょっとした出来事が妨げになる
小さな一つのつまずきが、先延ばしのきっかけになります。例えば、「皿洗いを始めようとしても、洗剤の容器が空になっていたからやめてしまう」、「隣の人の話し声がきっかけで、仕事に取り掛かるタイミングをもてない」といったように、ちょっとした出来事が心の中で大きなハードルとなり、前へ進めなくなるのです。
3 すべてができなくなる
一つのことにつまずくと、すべてのことに対して意欲を失い、逃げ出したくなります。例えば、一つの業務に困難を感じると、他の業務すべてのやる気を失い、会社そのものが嫌になってしまうのです。会社から逃げ出したくなり、いまの人生から逃げ出したくなることもあるかも知れません。
4 何かに逃避する
仕事や勉強を先延ばしして、何をするかと言うと、ゲームをしたり、動画を見たり、コーヒーやたばこで気分を変えようとします。昼からお酒を飲んでしまう人もいますが、これはアルコール依存症のきっかけになる大変危険な行為です。それでもやる気がでないので、ふて寝をすることもあります。
5 自分はダメな人間だと責める
大事なことから逃げ出したくなるので、これを責任感の問題ととらえて、自分はダメな人間だと思い込みがちです。自信を失い、自分に価値を感じなくなります。できれば消えてなくなりたいこともあります。これは、うつ病で起こる無価値感というものです。
6 物忘れ
うつ病では物忘れも起こりますので、スケジュール管理に失敗する場合もあります。メモやカレンダーに書いてあっても見落としてしまいます。大切な用事をすっぽかし、先延ばしになることもあるでしょう。
先延ばし症候群は、心のSOSのサインです。それまで問題なくやれていた仕事に手がつかなくなり、先延ばしをするようならば、うつ病の可能性もあります。うつ病により、意欲や作業能力が落ちていることが原因です。病気に気づかず、性格や責任感の問題ととらえて、自分を責めてしまうのもうつ病の特徴です。いつもよりも先延ばしが増えているならば、心の状態がよくないことを自覚しましょう。
気分の落ち込みや睡眠障害など、他にも症状が出るようならば、精神科を受診するべきです。そこまでではないとしても、心の状態が良くないことを理解し、できるだけ仕事を減らし、休みをとるようにしましょう。もしかすると、心配事を抱えている、我慢や無理のし過ぎなどが原因かも知れません。普段から、「できないことは断る」、「頼めることは人を頼る」、というように、自分だけが負担を抱えないようにすることも大切です。
自殺の直前に見せる8つのサイン
何事もなかったのに、ある日突然自殺をするということはありえません。必ず、自殺に至るまでの長いプロセスがあります。お金や仕事の心配、人間関係の悩みなど、辛いことがあると心はどんどんと弱ってきます。これが、限界に達してしまうと、何かのきっかけで衝動的に自殺を試みます。引き金になるのは、いじめや争いごとで、心が傷つく言葉を浴びせられることが最も多いようです。
ある調査では、自殺者の70%には遺書がなく、自殺のほとんどが衝動的な行為と言われています。自殺を試みるときは、「死んだらどうなるのだろう?」「みんなを悲しませるかな?」「死ぬ時って痛いのかな?」と、普通ならば思いつくことを考えるスキもありません。正常な精神状態ではないのです。
自殺をする人は甘えと言われることがありますが、助けをもらえなかった人が自殺をしてしまいます。大切な人が自殺をしてしまうことは、大きな心の傷になります。「もしかしたら助けられたかも知れない」と、後悔をしないように、今回は「自殺の直前に見せる8つのサイン」をご紹介いたします。

1 生気がない
いつもと違って明らかに元気がないような場合は要注意です。好きなことをしなくなったり、「何をしても楽しくない」という言葉を発します。休日は寝たきりになり、自分から外に出て行動をすることがなくなります。
2週間程度で元に戻る場合は問題ないですが、それ以上続くようであれば、うつ病の可能性があります。自殺の原因のほとんどに精神疾患が背景にあると言われています。
2 いつもと言動が違う
自殺の直前に、人はいつもと違う言動をとります。例えば、「このままではいけない」と言って突然仕事を辞めたり、精神科に通院している場合は、「薬に頼っている場合でない」と言って薬を飲むのをやめたり、普段と違う行動をするのです。
「死にたい」と漏らしていた人が、急に言動が変わった時は要注意のサインです。特にうつ病で治療中の人が急に薬をやめてしまうことは大変危険なことです。
3 自殺の仕方をサイトで調べる
「自殺の仕方」や「楽に死ねる方法」などをサイトで調べる行為は、とても危険なサインです。本人のスマホを調べることはなかなか難しいので、会話の中で「自殺」などの言葉が出てきたら注意が必要です。
「死にたい」という言葉は簡単に出てくる言葉ではありません。きっとその人はあなたなら相談に乗ってくれると思って打ち明けたのだと思います。「死にたい」と言うと、相手の気を引くために言っているのではないかと疑う人もいますが、本当に自殺してしまうケースも多のです。聞く側が真面目に受け止めてあげなくてはいけません。また、「死んでほしくない」と相手にきちんと伝えることも大切です。
4 自傷行為
リストカットなどの自傷行為を行うことが、すぐに死につながる訳ではありませんが、自傷行為が繰り返されて、自殺に至る可能性もあります。自傷行為は本人が何らかのSOSを出しているサインでもあり、本人の辛い気持ちに目を向ける必要があります。もし自傷行為を発見したら、無理やりやめさせようと説教するのではなく、何が辛いかについて優しく聞いてあげましょう。

5 薬を沢山飲む
命の危険をかえりみずに、快楽目的で大量の薬を飲むことを、「オーバードーズ」、略してODと言い、最近では「トーヨコキッズ」と呼ばれる子供たちの間で行われていたことがニュースになっていました。自傷行為の1つであり、「自己破壊的行動」とも呼ばれています。
薬は多く飲まれないように医師が調整していますが、いくつかの病院をはしごして、たくさんの薬を蓄えている人もいます。死につながる危険な行動のため、注意が必要です。
6 感情の起伏が激しい
突然怒ったり、泣いたり、感情の起伏が激しい状態は、自殺の危険なサインです。気持ちが落ち込んでいるときは、自殺をするエネルギーはありませんが、むしろ、感情の起伏が激しいときに、衝動的に自殺が起こりやすいと言われています。
例えば、口喧嘩をしてしまい、そのまま窓から飛び降りてしまう、などもあるので気をつけましょう。相手が感情的になっているときこそ、冷静に対応することが求められます。
7 お酒を飲み過ぎている
お酒を飲んでいて、理性が働かない状態は、自殺の危険なサインです。特に、楽しくお酒を飲んでいるのは良いのですが、やけ酒のような場合は非常に危険です。普段から死にたいという気持ちを強くもっている場合、お酒を飲むことで衝動的になり、自殺を実行に移してしまうことがあります。
8 大切な人がいなくなる
家族との死別、失恋など、大切な人がいなくなった時、人は大きな悲しみを感じ、これを喪失体験と言います。喪失体験はうつ状態と似ていますが、薬が効きにくいことが多く、時間が解決してくれるのを待つしかありません。絶望に陥ってしまい、生きる希望がなくなり、後を追いたい気持ちが出て来ることもあります。これは危険なサインです。

今回は、自殺の直前の8つのサインをご紹介しました。
統計データによると、どの国でも自殺者は圧倒的に女性よりも男性が多くいます。困ったとき、女性の方が、周囲に助けを求めることができるからです。別の調査では、男性の方が、相談相手のいないケースが多く、辛い時にがまんして、弱音を吐くことを嫌う傾向がありました。孤独で相談相手がいないことや、「弱音を吐いてはいけない」という考えを持っていることが、自殺につながる大きなリスクであることが理解できるでしょう。
自殺を防ぐためには、周りの身近な人の対応が重要です。もし、「死にたい」と相談されたら、「何で死にたいの?」「何が辛いの?」と聞いてあげるようにしましょう。
逆に、「その考えは間違っている」、「私も苦労を乗り越えてきたんだ」と説教や自分語りをしても意味がありません。話を遮らずに聞いてあげて、気持ちを理解してあげることが大切です。自殺を食い止めようと努力するよりも、気持ちを理解してあげようと努力するべきなのです。
大人の愛着障害 3種類の人間関係
人間関係の悩みがない人は、世の中にいません。相手の好き嫌いもありますが、親密が好きな人、距離を置くのが好きな人と、人によって居心地のよい距離感が違うことも理由です。中には、「いつも人に依存している」、「人と決して交わろうとしない」という、極端な人間関係の人もいます。これでは、生きづらさを感じ、付き合う人もつらい思いをします。こうした極端な人間関係をとるのはなぜでしょうか?心理学では、子供の頃の親子関係が大きく影響していると説明しています。
親子の情的な絆を愛着と呼びます。愛着は大人になってからの心の土台になるもので、人間関係のとり方も愛着の影響を受けています。子供の頃に親から愛情を注がれていないと、愛着が育ちません。愛着の障害を引きずると、人間関係が不安定になります。これを大人の愛着障害と呼んでいます。
本来の人間関係は、相手を信頼・尊重し、必要に応じて助け助けられる関係です。親から愛され、良好な親子関係で育てば、このような人間関係をつくることができ、これを「安定型」の人間関係と呼びます。ところが、大人の愛着障害では、「いつも人に依存する」という近すぎる距離感や、それとは逆に、「人と決して交わらない」という遠すぎる距離感をとる傾向が出てきます。さらに、この両極端の距離感が、一人の相手に揺れ動くという人もいます。
今回は、大人の愛着障害の3種類の人間関係のとり方について説明しましょう。

1 人に依存する
親の情緒が不安定であると、子供を可愛がる時もあれば、大きな理由もなく突っぱねたりと、子供の扱いに情的な一貫性がありません。子供は、親から安心感を得られないために、人を心から信頼することを学べません。自分が愛される価値があるかどうかに不安を抱き、相手からの愛情や安心感をつよく求めるようになります。このような不安を「見捨てられ不安」と呼びます。
大人になってからも、パートナーや友人に見捨てられることを恐れ、常に束縛しようとします。姿が見えないと、仕事中にも電話をしたり、常につながりがあることを確認したがります。相手の愛情に確信をもてないので、わざと相手を困らせたり、愛情を試すような行動をすることもあるでしょう。これでは、付き合う人は疲れ果ててしまいます。
このような人間関係のとり方を「不安型」と呼びます。自分の寂しさを満たすことが、人間関係の目的となるために、相手に依存してしまうのです。
2 人と交わらない
親が子供を放任したり、常に冷たく接していると、子供は、「自分の願いは他人を通して叶えられない」と学ぶようになります。人に何かを求めても失望が待っているので、親しくすることが怖くなるのです。すると、常に感情を抑え込み、自己完結的な行動を取るようになるでしょう。
大人になっても、感情的に深い人間関係を築くことを避けます。人に頼ることが苦手で、全て自分で背負い込み、孤立します。しかし、本音は誰かと親しくしたいという矛盾した状態にいるのです。
パートナーから束縛されることを嫌い、常に一人で過ごそうとします。これは、親密なことが不快であり、自分のプライバシー空間に誰かが踏み込んでくることに不安を感じているためです。
また、心の内を明かさず、共感することが苦手なために、周りからはクールな人に見られます。恋愛関係や友達関係でも、表面的となり、情的に深く関わることができません。このような人間関係のとり方を「回避型」と呼びます。

3 依存と回避が共存する
子供の頃に親が突然いなくなったり、虐待やネグレクトなどの酷い仕打ちを受けた場合は、「不安型」と「回避型」の両方の傾向をもつことがあります。相手に対して、安心感を求めて親しくなろうとする気持ちと、近づきすぎて傷つけられるのを恐れるという矛盾した気持ちの間で苦しむようになるのです。
仲良くしていたのに、ちょっとした相手の言葉や態度で感情が爆発し、関係を壊してしまうといった激しい変動がみられます。パートナーになると、情緒の不安定さから相手を振り回してしまうこともあるでしょう。このような人間関係のとり方を、「恐れ・回避型」と呼びます。
見捨てられ不安から、自殺未遂や暴力事件を起こす場合は、「境界型パーソナリティ症」という病気の可能性もあります。

愛着の問題から、人間関係で悩んでいる人は沢山います。その根底には、自己肯定感が低く、自分に自信を持てないために、人が自分をどのように見ているかを過度に気にすることがあるのです。同時に、自分は愛される価値がないと感じてしまい、これが人との親密な関係を築くことへの恐怖につながります。この根本の問題を解決しない限りは、人間関係も改善されません。
では、愛着の問題はどのように克服すれば良いでしょうか?一番良い方法は、思いやりのある「安定型」の人と交流することで、愛着を学び直すことです。「不安型」の人に対して、感情が安定している「安定型」の人ならば、優しく要求を満たしてあげる関係を持つことができ、「人から裏切られる不安」が解消されていきます。また、「回避型」の人に対しては、適度な距離をとった関係を持つことができ、この関係が長く続けば、人と親密になることへの不安が解消されていくでしょう。
ところが、実際には、自分に似ている人からパートナーや友人を選ぶ傾向があります。人間関係のパターンも、似たもの同士がつきあう確率が高いのです。例えば、「不安型」同士で付き合ってしまうと、お互いが依存的になり、愛を確かめる行動をとってしまうため、不安傾向がよけい強くなる結果となります。「回避型」同士であると、なかなか互いを信頼することができず、疎遠になってしまいます。互いに心の傷を深める結果となり、さらに回避傾向がつよくなります。愛着の問題を抱えている人にとっては、友人やパートナー選びはとても大切なことです。
良い出会いがないからといっても、落胆することはありません。愛着の問題を、自分自身でケアをする方法もあります。例えば、カウンセリングに通って自己理解を深める、仕事や得意な分野で努力して成功体験をする、ペットや植物を愛してみる、といった方法もあります。映画やドラマを通して疑似的に学ぶこともできます。
兄弟が仲良くなれない5つの理由
昔から、「兄弟は他人の始まり」と言います。子供の頃はあんなに仲が良かったのに、大人になったら全く縁をもたない兄弟も大変多いのです。
仲の良くない兄弟と言えば、聖書には、カインとアベルという有名な話があります。アダムとエバの長男がカイン、次男がアベルです。カインとアベルは神に供え物をしましたが、神はなぜか弟のアベルの供え物だけを受け取り、兄のカインのことは気にかけませんでした。このことをアベルは自慢したため、カインは嫉妬してアベルを殺してしまいました。聖書によれば、人類最初の殺人事件は、嫉妬が原因で兄弟の間で起きたのです。
カインとアベルのように、兄弟の間には複雑な心理が働きます、そのために仲良くなれない兄弟もいるのです。今回は、兄弟が仲良くなれない理由を5つ紹介しましょう。
1 親の愛情を奪い合う関係
弟や妹が生まれると、親はそちらの世話に追われます。それまで、親の愛情を独り占めにしていたのに、弟や妹に奪われてしまうのです。子供にとって親の愛情ほど大切なものはありませんから、その奪い合いが兄弟関係を悪くさせます。
これとは逆に、親が上の子の世話に追われて、下の子の世話が十分にできないこともあります。「何事も上の子が優先、下の子の服や持ち物はすべてお下がり」、という状況が続くと、やはり兄弟関係が悪くなるでしょう。
こうした時に親がうまく立ち回れば良いのですが、余裕がないことが多く、さみしがっている子供を叱ったり、無視することもあります。兄弟間の憎しみはさらにつよくなり、兄弟の溝が埋まらないまま、大人になることもあるでしょう。
2 ライバル関係の兄弟
勉強でもスポーツでも、成長するに従い、周りからの評価が伴うようになります。良い評価をとろうとするのが当たり前ですから、年の差が近い兄弟ほど競争になってしまいます。競争ですから、仲良くしていては、よい結果を出せません。いつのまにか兄弟がライバル同士になってしまい、互いを遠ざけるようになってしまいます。
3 兄弟格差がある
同じ親から生まれた兄弟でも、能力の差があるのが普通です。片方は勉強ができて、片方は成績が悪いと、助け合おうというよりも、見下したり、気まずかったりでお互いの距離が離れがちになります。姉妹だったら、片方が美人で周りからチヤホヤされると、やはり見下したり、気まずかったりで、姉妹の距離は離れてしまうでしょう。
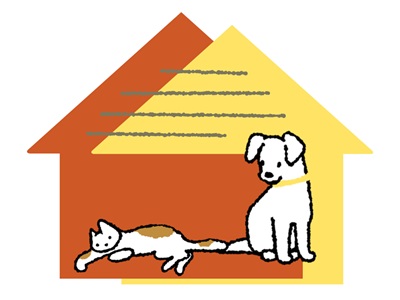
4 傲慢さ
子供は周りからチヤホヤされると、自分が何でも1番であると考えます。兄弟で優劣の差がある場合、優秀な子はそうでない兄弟を見下すようになるでしょう。自分は兄弟の中で一番なのだと驕り高ぶってしまうのです。
特に問題になるのは、下の子の方が優秀な場合です。その子は上の兄弟を馬鹿にしてしまうので、兄弟げんかが絶えなくなります。まさに、カインとアベルの時と同じように、兄弟の優劣が逆転すると激しい嫉妬が生まれてしまうのです。
5 親の愛情に偏りがある
兄弟関係を調整できるのは、唯一親だけです。兄弟仲が悪いのは、親にも原因があります。親はつい優秀な子や可愛い子に対して、より多くの愛情を注ぎがちですが、これが兄弟間のバトルを炎上させます。親が優位な子の立場だけを認めていたら、劣る子の立場は完全になくなってしまうからです。
親の対応によっては、兄弟関係は完全に分裂してしまいます。それだけでなく、親にも兄弟にも認められない子供は、心の病気になったり、家庭の外に癒しを求めて非行に走ることもあるでしょう。
兄弟関係を良く観察しながら、注ぐ愛情のバランスを調整するのが親のあるべき姿です。できる子だけを褒めるのでなく、できない子にも愛情を注いで慰めてあげる努力をしなくてはいけません。
兄弟が仲良くなれないのは、兄弟に格差があることと、親が間をとってあげられなかったことが原因です。年をとると親も入る余地はなくなりますから、兄弟同士で歩み寄らなければ、距離はどんどん遠ざかってしまいます。それでも生きていく上では問題はないのかも知れませんが、仲の良かった兄弟が大人になって絶縁してしまうのはさみしい気もします。
一度壊れた関係を修復することは大変難しいことです。兄弟が関係を修復し、昔のように仲良くなるためには、優位な立場にいる兄弟から優しく訪ねてあげることが必要でしょう。もし、兄弟を見下したことで関係が壊れてしまったのならば、見下したことを謝罪して仲直りする必要があります。いつまでも「俺が上だ」と言っている限り縁は戻りません。兄弟であっても、仲良くするためには、互いに謙虚な気持ちが大切なのです。
もし弟のアベルが、「たまたま俺の供え物が受け取ってもらえただけだよ」と、カイン兄さんに謙虚に歩み寄っていれば、人類初の悲劇は起きなかったかも知れません。
うつ病の人に贈る 7つの言葉
うつ病ほど誤解を受けやすい病気はありません。見た目は変わらないのに、仕事や家事をしなくなるので、「怠け」と勘違いされます。病気になったら心配されるのが普通なのに、うつ病では、「元気出しなよ」、「気のもちようだよ」と、むしろ追い立てられることもあります。病気の苦しみを理解されないことほど辛いことはありません。うつ病はとても理不尽な病気です。
今回は、うつ病を抱えて苦しんでいる人のために、7つの言葉を準備しました。長い闘病生活を少しでも楽に過ごせるように、力になると幸いです。
1 心が弱いからうつ病になるのではありません
うつ病は、心の弱い人がなる病気ではありません。以前は、うつ病になりやすい性格が論じられていましたが、結論は出ませんでした。今では、つよいストレスを抱えたり、休みなく無理をしていたら、誰でもなる病気と考えられています。むしろ、頑張り過ぎた証拠とも言えるでしょう。
2 病気だから、できないのが当たり前です
うつ病は、仕事だけでなく、家事や身の回りのこともできなくなる病気です。部屋は汚れ、風呂も入らない、というだらしない生活になります。これは症状によるものですから仕方がありません。むしろ、部屋がきれいで、身だしなみもきちんとしているならば、うつ病は治っています。できない自分を「情けない」と責めるのでなく、「病気だからできなくて当たり前」と開き直りましょう。
3 人より多くの荷物を背負っています
病気を抱えて生きて行くことは、人よりも見えない荷物をたくさん背負っていることです。
同じことをするのに、健康な人よりも何倍もエネルギーが必要になります。ですから、人とペースが同じでなくても良いのです。人と比べないようにしましょう。「今日1日、洗濯しかできなかった」でなく、「今日は洗濯を頑張れた」と、胸を張るべきです。
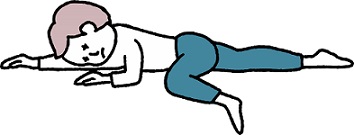
4 休むことは自分を大切にすることです
健康状態に応じて休むことは、サボることではありません。自分を守るために大切なことです。むしろ、自分を大切にしてこなかったから、うつ病になったのかも知れません。
「みんなが働いているのに、休むのは罪深い」、「働いていないと気が済まない」という人も多いのですが、自分の健康は自分でしか守れません。周りに合わせるだけでなく、「できないことはできない」、「やれないことはやれない」とブレーキをかけないと、自分が壊れてしまいます。休むことは、自分を大切にすることです。
5 克服しなくてもいいのです
「病気を克服する」という言葉がありますが、うつ病は努力して良くなる病気ではありません。むしろ、力を抜くことで回復して行きます。朝の散歩や運動は、確かに効果がありますが、無理してやればよけい悪くなるでしょう。「今日も何もできなかったな」という日を重ねているうちに、自然に回復して行くものです。
また、薬を飲んで生活ができているのならば、治ったと考えましょう。予防のために薬を続けながら、少しずつ減らしていけば良いだけです。
6 薬は長く飲んでも問題ありません
たくさんの人が一番気になることは、10年20年と、こんなに長く薬を飲んでも大丈夫かということです。うつ病に使う薬が世に出て60年以上たちますが、大きな問題はありません。
欧米の情報をもとに、安定剤や睡眠薬で依存症や認知症になると言う医師やメディアがいます。実際には、日本と欧米では、体質、医療制度、法律、歴史と、事情が大変異なります。適切に使用する限り、依存症に関しては、日本で大きな問題は起きていません。また、安定剤や睡眠薬で認知症になることは否定されています。医師が健康保険で処方している薬は、心配なく飲むことができます。
ただし、うつ病の薬の中には、食欲が出たり、便秘をするものもあるので、体重増加による生活習慣病には注意しましょう。
7 生きる意味を知っているのは神様だけです
うつ病には無価値感という症状があり、「自分は価値のない人間である」と悩むようになります。うつ病の時に生きる意味を考えるのは症状の一つなのです。生きる意味や目的は人それぞれ。それを知っているのは、神様だけです。
答えの出ないことが頭の中をグルグル回り始めたら、意識を他に向けて無視するのが良いでしょう。体を動かす、飲食をする、人と話す、など、体や外の世界へ意識を向けるのです。ただし、お酒で紛らわすのは良くありません。物事の考え過ぎが余計具合を悪くさせます。

世の中には、うつ病で働けないことをバッシングする心無い人がいます。「働かなくてズルい」と言うのです。こうした人たちは、病気で働けないことが、どれだけ辛いことかが理解できていません。
アメリカのポジティブ心理学の第一人者であるマーティン・セリグマンによると、働くとは、それ自体が生きがいとなり幸福感につながります。誰でも、忙しくて一時的に「働きたくない」と考えることはありますが、健康に働けて、世の中の役に立っていることほど幸せなことはありません。お金の問題以上に、働けていること自体が幸せなのです。ですから、病気で働けないこと、失業などで働いていないことほど苦しいことはないのです。
うつ病を理解できない人の声は無視して、無理をせず、医療だけでなく積極的に福祉も利用しましょう。実際に、障害年金や生活保護などをステップにして、元気を取り戻している人がたくさんいます。自分を責めて、自分が嫌いになって、どんどん深みにハマるのが一番良くありません。いろいろな人の助けを受けながら、少しずつ本来の自分を取り戻しましょう。
苦労し過ぎて無力感を感じている人 6つの特徴
人生、どんなに頑張っても失敗ばかりです。受験、就職では良い思いをしたことがないし、どこへ行っても認められた記憶もありません。産まれてから一度もうまく行ったことがない気もします。働けてはいますが、何か新しいことをしようとしても、「またどうせダメだろうな」と、諦めが先立ちます。夢や希望はありません。
思い切って精神科に行ってみましたが、「働けているから大丈夫だよ」と、医師に軽くあしらわれてしまいました。こんな生きづらさを感じている人はいないでしょうか?
これは、いくら努力をしても実らないので、生きることすべてに自信を失った状態です。うつ病とまでは言えませんが、「うつ病グレーゾーン」とか、「うつ病予備軍」と言ったらよいかも知れません。心理学的には、「学習性無力感」と呼び、どうにもできない問題を長く抱えこんでいると、どんどんネガティブになり、ついには何とかしようとする意欲すらなくなります。
終身刑で牢獄にいる人、強制労働所に入れられている人などが代表的な例です。実際には、ふつうに社会で生きている人にも見られる現象なのです。
今回は、苦労し過ぎて無力感を感じている人の特徴を6つ紹介しましょう。

1 微笑みうつ病
アメリカの心理学者・ハイジ・マッケンジーは、表面的には笑顔で仕事をこなしていても、日常のほとんどは気分が落ち込んでおり、プライベートは無気力に生活している人を「微笑みうつ病」と呼びました。正式な病気ではありませんが、このような状態の人が世界的に大変多くいます。微笑みうつ病は、苦労し過ぎて無力感を感じている人にピッタリ当てはまる呼び方です。
ただし、いまは病気ではなくても、生活に支障が出るようになったら、うつ病と診断されるでしょう。何かのきっかけでうつ病になるリスクがある状態です。
2 心にポッカリ穴があいている
いくら努力しても結果が出ないと、だんだん自分自身が嫌になって行きます。自分は価値のない存在と感じるようになり、自己肯定感が下がって行くのです。自己肯定感は、心の中心にあるものですから、心の真ん中にポッカリ穴があいているようで、いつも虚しさを感じています。仕事でも趣味でも、「こんなことをしていて良いのだろうか?」と心から楽しめません。
虚しさは、自分のことを嫌いになってしまったサインです。自分を好きになれないことが、無力感の本質とも言えるでしょう。
3 ネガティブ
基本的に気分は落ち込んでいて、考え方もネガティブです。将来に対しても希望を持てません。不安が多く、心配ばかりしています。過去の失敗を思い出して、今更どうにもできないのに、「ああしていれば良かった」と後悔ばかりです。
4 自分の気持ちを外にださない
主張することで嫌な思いをしてきたので、自分の意見を言わない習慣がついています。いつも自分の気持ちに蓋をしているのです。気持ちを溜め込んでしまい、それがさらにストレスになり、よけいに心を病んでしまいます。
5 常に最悪のことを考える
挫折をたくさん経験してきたので、新しいことに用心深くなっています。何かにチャレンジしようとしても、「また失敗するかも?」とブレーキがかかるのです。
ただし、これにはメリットもあります。安全な選択をするので、大成功はないかも知れませんが、大失敗はしないで済むでしょう。
6 人に優しい
挫折した人の気持ちを理解できるので、弱い人の味方です。基本的に優しい人ですが、要領よく成功している人や、親に対しては、辛辣な場合もあります。中には、「うまく行かないのは、親のせい」という考えから抜け出せない人もいます。
突然ですが、海や川で溺れそうになった時、どうしたら良いかご存じですか?慌てて、陸に向かって力の限り泳ぐのが一番良くありません。流れに逆らえず、力尽きて溺れてしまうからです。むしろ、力を抜いてプカプカ浮いて、助けを待つのが一番良いと言われています。人生もこれに似ています。
うまく行かないことがある時、焦って無理をしていると、力尽きて、生きるエネルギーを使い果たしてしまいます。無力感から抜け出せなくなり、ついにはうつ病になることもあります。一番良くないのは、うまく行っている人と比べてしまい、焦ったり、できない自分を責めてしまうことです。自分が嫌いになってしまったら、生きる意味すら感じなくなります。
うまく行かない時は、比べず、焦らず、無理をせず、そのうち運が回ってくるのを待つのが良いのです。克服しようとするのでなく、力を抜きましょう。できない自分を責めてはいけません。むしろ、休みをとったり、楽しみを増やしたりして、自分を大切にするようにします。また、話を聞いてくれる人、助けてくれる人との出会いを大切にしましょう。そのうち運が回ってくる時が必ず来るはずです。これが、苦労をしても、生きづらさを感じないコツです。
心がつらい時に陥りやすい考え方 6つの特徴
いつまでも解決できない問題を抱えたり、つらいことが重なると、元気でいられる人はいません。いつも気分は落ち込み、何かをしようとする気力もなくなってしまいます。こんな時は、物事の考え方もネガティブになります。いつも悪いことばかりを考え、考えれば考えるほど、おかしな方向に結論を出してしまうのです。
気分が落ち込んだ時の考え方は、人によって違うのでなく、いくつかの共通の特徴があります。これが、よけいに問題をこじらせてしまう原因です。あらかじめこの考え方の特徴を知っていれば、誤った判断をしないための予防になるかも知れません。
今回は、心がつらい時に陥りやすい考え方の特徴を6つ紹介しましょう。

1 思い込み
心がつらいと、情緒が不安定になり、思い込みで判断しやすくなります。また、暗示にかかりやすい状態です。
「地面師たち」というドラマをご存知ですか?実話をもとにした、土地がらみの詐欺の話です。詐欺師に騙される人は、仕事に失敗して精神的に追い詰められた立場でした。思い込みがつよい状態であったため、冷静に考えれば、詐欺師の嘘を見抜けたはずなのに、まんまと罠にハマってしまったのです。
また、世の中には、2度も3度も続けて詐欺にあってしまう人がいます。「何でそんなに騙されてしまうのだろう?」と不思議に思うかも知れませんが、1度目の詐欺の被害で気持ちが不安定になり、思い込みがつよくなっているタイミングで、次の詐欺にあってしまうのです。
2 全体の意味を読み取れない
視野が狭くなり、全体を見ることができません。例えば、つらいのでお酒を飲んでいると、「飲み過ぎは体によくないよ」と、家族から言われたとします。家族は、心配の気持ちで言ったのですが、「こんなにつらいのに酒をやめさせるのか!」と怒ってしまいました。心配の気持ちは理解できず、「酒をやめた方がいい」という言葉しか頭に入らなかったのです。
このように、会話の内容も一部分しか頭に入らないので、相手の気持ちを誤解することが起きます。
3 全か無か思考
物事を、「あるか」、「ないか」で判断し、中間がなくなります。これを「全か無か思考」と呼びます。
例えば、これまで生きてきて、良かったことも、悪かったことも両方あったはずですが、つらい気分の時は、「良かったことは一つもなくて、すべてが悪いことだけだった」という極端な考え方になります。まるで記憶が書き換えられたような状態です。よけいに悲観的になって、自己肯定感を失います。

4 自分と関連付ける
特に因果関係がなくても、悪いことは自分のせいであると考えます。自己肯定感が下がるために、周りで起きる出来事を、「自分はダメな人間だ」という考えに結び付けてしまうのです。
例えば、「家族が病気になったのは自分のせいだ」、「会社のプロジェクトが失敗したのは自分のせいだ」と、自分を責めるようになります。
5 グルグル思考
過去の失敗が浮かんできて、頭の中をグルグルと回っています。心理学では、「反芻(はんすう)思考」と呼びます。「反芻」とは、牛などの草食動物が、胃で消化した草を再び口に戻して咀嚼し、これを何度も繰り返すことです。食べ物が、口と胃を行ったり来たりするように、ひとつの考えがいつまでも頭の中を行ったり来たりして、結論が出ません。
反芻する内容の代表は、後悔です。「こうしておけば良かった」、「なんでああしなかったのだろう」と、後悔が止まりません。特に、風呂に入っている時、眠る前など、周りが静かでゆっくりしている時に限って浮かんできます。
「将来うまく行かない」という考えも反芻されます。新しい出来事は、過去の失敗と重なり、失敗の可能性ばかりを考えてしまうのです。
6 生きる意味を考える
生きる意味や目的を考え始めるのも、反芻思考の一つです。いくら考えても答えは出ません。そこで修行をしたり、深い思考にふけり、新たな生き方を見出せるのは、歴史に名を残すような宗教家や哲学者だけです。ふつうの人には答えは出ません。それどころか、「自分には生きる価値がない」という悪い結論を出してしまいます。

今回紹介したように、心がつらい時は、ネガティブな考え方になります。誤った判断につながり、自分を窮地に追い詰めてしまいます。思い込みで人を誤解するだけでなく、暗示や誘惑に引きずられるため、良くない人と交流をもったり、大きな買い物で失敗したり、仕事で間違った判断をすることがあるのです。先ほども紹介しましたが、詐欺師に騙されることもあるでしょう。
心がつらい時は、大きな決断をしてはいけません。生きる意味や目的も、考えない方が良いのです。何よりも、心と体を休めることを優先しましょう。脳を休めることで、ネガティブな考え方を止めることができます。特に睡眠と食事をきちんと確保することに意識を向けましょう。
今回紹介した考え方の特徴は、うつ病の人にも大変多く見られるものです。このような考え方に陥っているだけでなく、眠れない、食べられないが続いて、脳を休めることができないならば、自分の力で悪いループから抜け出せません。これは、うつ病の可能性もあります。放置しないで、精神科を受診するのが良いでしょう。
治療が必要な大人のADHD 4つのサイン
メディアなどを通して、大人の発達障害の知識が広がり、特に注意欠如多動症・ADHDのことは、よく知られるようになりました。メディアに登場する実業家や芸能人にも症状が見られるため、「あの人はADHDだ」と、素人判断する声をよく耳にします。最近では、毒舌ツイートで非難を浴びた女性タレントがそうでした。
「遅刻や物忘れの常習犯」、「思ったことはすぐに口に出し、先輩にもタメ口」、「本番中も落ち着きなくスマホをいじっている」、といったところで判断されたのでしょう。
ADHDとは、不注意、多動、衝動といった、生まれつきの性格や行動の偏りです。成長に伴い、多動と衝動はほぼ改善されるため、大人の場合は、遅刻や忘れ物などの不注意の症状が特徴になります。仕事や日常生活に大きな支障がない場合は、個性として考え、特に治療は必要ありません。むしろ、人付き合いの良さからうまく世渡りできている人もたくさんいます。
最近、「ADHDかも知れない」ということで、パートナーや職場の上司に連れられて、精神科を受診する人も増えています。「人の話を聞いていない」、「遅刻や物忘れが多く、仕事のミスが多い」、「不注意で車の事故が多い」など、不注意によるトラブルが多いようです。それだけでなく、躁状態、うつ状態、依存症などによる深刻な問題で受診するケースもあります。
ADHDには治療薬があり、注意を維持する時間を延ばしたり、衝動を減らしたり、気分を改善させる力があります。生活に支障が出る場合は、薬の治療を受けた方が良いでしょう。それでは、どのような症状があると治療を受けた方が良いのでしょうか?今回は、治療が必要な大人のADHDのサインを4つ紹介しましょう。

1 躁状態
「一人でしゃべり続けて、会議の進行を止めてしまった」、「自分の正当性を訴えて怒り、周りに食ってかかる」、といったトラブルで受診する人もいますが、これはADHDというよりも、躁状態の可能性があります。
躁状態とは双極症で見られるもので、気分が高揚して自尊心が高くなり、頭もフル回転して、話題が次から次へと変わります。「自分は何でもできるすごい人間だ」という誇大妄想もあるのが特徴です。同時に、不注意、落ち着きのなさ、衝動性があるので、専門家でもADHDとの区別は難しくなります。そもそも、ADHDと双極症が合併するケースは多く、遺伝的な共通点も見つかっています
躁状態がずっと続くということはありませんが、周りとのトラブルが増えるので、早めに薬の治療を受ける必要があります。
2 うつ病や不安症
職場でのADHDの人は、「作業やスケジュールの整理ができない」、「作業に集中できない」、「結果を考えず、その場の気分で大事な決断をする」、といったことが起こります。それで仕事の失敗が続き、一つの職場に長居できません。これが重なると自尊心を失い、ついにはうつ病や不安症になる人もいます。大人のADHDの人は、健常な人の2~3倍もうつ病や不安症になりやすいのです。
こうなると、仕事や日常生活ができなくなるため、精神科の受診が必要です。うつ病や不安症で受診して、それがきっかけでADHDが見つかる人もたくさんいます。
一番心配なのは、自殺に至る人が多いことです。「気分が沈む」、「不安がつよい」という場合は、早めに精神科を受診しましょう。

3 事故や事件が多い
ADHDの人は、よく交通事故に巻き込まれます。車をこすったり、前の車にぶつけたりと、不注意で周りをよく見ていなかったことが原因です。慌てたことで操作を間違えることもあります。大事故につながらないように、車や自転車の事故が続くような場合は、精神科を受診するべきでしょう。
また、衝動のつよさが残る人は、暴力などの事件を起こすリスクがあります。「職場や家庭で認めてもらえない」、「うまく行かないことがある」、といったストレスの積み重ねが引き金になって、暴力や物を壊すなどの行動につながってしまうのです。
4 アルコール依存、薬物依存、ギャンブル依存
アルコールなどの精神を刺激する物質が、脳のドーパミンという物質を増やすことにより、ADHDの症状を抑えてくれることがあります。そのために、アルコールなどを手放せなくなる人もいます。
また、ADHDは脳の報酬系という部分に問題があると考えられており、報酬系は依存症とも関係の深い部分です。「それをやると人生が終わってしまう」という結果を考えられず、よりつよい刺激を求めて、依存の沼にハマりやすい傾向があります。
依存症になる人は、ADHDをもっていることが大変多いのです。
30年くらい前までは、ADHDは子供の病気で、成長とともに自然に治ると考えられていました。1990年代後半に、サリ・ソルデンの「片付けられない女たち」という本の出版がきっかけとなり、大人になってもADHDの症状が残ることが、広く世の中に知られるようになりました。
ところが、学校でも職場でも、遅刻や物忘れ、片付けができないというのは、「だらしない人」、「ダメな人」というレッテルを貼られます。ADHDが原因であるのに、人格の問題として扱われてしまうのです。そのために、安定した仕事に就けないことも起きるでしょう。
現在では、いくつかの治療薬も開発されていますので、ADHDの症状を軽くさせることができます。ずっと飲み続ける必要がありますが、生活は改善されます。今回紹介したような症状に気づいた場合は、精神科に相談してみましょう。ただし、一部のADHDの薬の処方には資格制度があるので、処方できる精神科かどうかを確認してください。
うつが長引くのはなぜ?
病気には、大きく分けて「急性疾患」と「慢性疾患」の2つの種類があります。急性疾患とは、風邪などのように比較的短期間で治るもので、慢性疾患とは、糖尿病や高血圧のように徐々に発症し、経過が長期に及ぶものです。それではうつ病はどちらに分類されるでしょうか?
うつ病は、基本的に慢性疾患に分類されます。薬を飲めば、1カ月くらいで症状は落ち着きますが、多くの人は再発を繰り返すために、数年から数十年と治療や予防を続けることが必要です。糖尿病や高血圧になった人が、生涯にわたって治療や予防するのと似ています。
薬品メーカーのキャンペーンで、「うつ病は心の風邪」と言われていたことが、30年ほど前にありました。ところが、うつ病が良くなった患者さんのその後の経過を調査したところ、4人に1人は半年以内に再発し、2人に1人は1年以内に再発しています。5年間を見てみると、なんと3人に2人が再発していました。また、再発を繰り返すほど、症状は重くなり、さらに再発する頻度も上がるという悪い循環に入ります。うつ病は心の風邪どころか、深刻な慢性疾患です。
調査によると、うつ病が慢性化する人にはいくつかの特徴があることが分かっています。今回は、うつ病が長引く人の7つの特徴を紹介しましょう。当てはまる人は、数年から数十年と長く薬を飲んで再発を予防する必要があります。

1 症状が重かった人・再発が多い人
当然かも知れませんが、症状が重かった人は、薬を長く飲む必要があります。例えば、長い期間入院した人、被害妄想などの精神病的な症状があった人、寝込んでしまって日常生活が何もできなくなった人などです。
再発を繰り返す人も同じで、長い治療が必要になります。仕事柄、休むことができないなど、ストレスを避けられない人が当てはまるかも知れません。再発を繰り返すたびに症状は重くなるので、薬を続けて予防に心がけましょう。
2 不安症状・パニック発作がある人
不安の症状がつよい人は、うつ病が慢性化する傾向があります。これは不安症も合併しているからです。ただし、うつ病も不安症も治療の薬は同じですので、飲む薬は変わりません。
特に多いのが、パニック発作という発作性の不安がある場合です。これは不安症の中でもパニック症と呼ばれるものです。逆にパニック症からうつ病になる人もいて、ともに長い治療が必要になります。
3 10代から20代前半に発病した人
若い頃に発病した人は、うつ病が長引くことが知られています。10代から20代前半の時期は、世の中の色々なことを学ぶ大切な時期です。若い頃のうつ病のために、世の中との接点がなくなり、社会に出ることの妨げになる場合もあります。こうならないように、薬で再発を抑えることが大切です。
子供が発病した場合、親としては、薬を長く飲ませることが心配です。大きな副作用はないので、親の判断ですぐに薬を止めないようにしましょう。
4 孤立している人
病気を抱えているだけで大変なのに、周りの人が理解してくれないことほど、辛いことはありません。特に、家族が病気に理解がなく、「うつ病は気の持ちようだ」、「いつまで薬を飲むの?」と追い詰めるようでは、良くなるものも良くなりません。このように、支えてくれる人がいない場合は、うつ病は長引きます。

5 発達障害やパーソナリティ症がある人
発達障害やパーソナリティ症のある人は、そうでない人よりも3~4倍の確率でうつ病になりやすく、さらに長引きやすいことが知られています。脳の感情をコントロールする部分に生まれつきの障害があることが、うつ病や双極症になりやすいと考えられています。また、対人関係の問題から、職場や学校でストレスを感じやすいことも大きな原因の一つです。
6 産後のうつ病
女性にとって、赤ちゃんを産むことは嬉しいはずなのに、出産後になぜか悲しく、涙が出ることがあります。これはマタニティーブルーと呼ばれ、ふつう3日くらいで改善しますが、出産後2週間を過ぎても気分の落ち込みやイライラがとれない場合は、産後うつ病です。
妊娠する前にうつ病を経験していた人の場合は再発と考えられます。また、子育てに自信がなかったり、妊娠中に夫の浮気が見つかったりと、夫婦間の心理的な問題も絡んでいることもあり、原因は複雑です。子育てが負担になるために、産後うつ病は慢性化することがあります。
7 飲酒の習慣がある人
アルコールは、一時的にうつ気分を良くするので、飲酒の習慣があるうつ病の人は多くいます。ところが、長い目で見ると、アルコールは脳の神経細胞に悪い影響を与えますので、うつ病を悪くさせたり、長引かせることになります。酷い例えですが、うつ病の治療を受けながら、飲酒を続けることは、毒を飲んでいることと同じかも知れません。
うつ病の再発を下げるために最も大切なことは、規則正しい生活を心がけ、ストレスを少なくすることです。ところが、生きて行くためには、無理をすることは避けられません。突然のトラブルに巻き込まれることもあります。計画通りに行かないのが人生です。そうなると、確実に再発を予防するためには、医師の指導のもとで薬の治療を続けることです。
「薬を飲むのは弱い人間だ」と考えて、引け目を感じながら薬を飲んでいる人もいますが、大きな誤解です。考え方を変えて、「薬を何粒か飲むだけで、予防ができるならば得なことだ」と考えるべきでしょう。
今回紹介した内容に当てはまる人は、10年20年と薬を飲む可能性があるかも知れません。薬は長く飲んでも大きな問題はありません。薬の力でそれなりに毎日を生活できているならば、うつ病を克服している証拠です。
こころが疲れているときに現れる10個のサイン
心配事が絶えず、やらなくてはならない事が多いと、休んでいるつもりなのに、頭の中を色々な思いがグルグル回っています。眠ろうとしても、なかなか寝つけません。朝早くから目が覚めてしまうこともあります。これは、「心の疲れ」とか、「精神疲労」と呼ばれるものです。
脳の使い過ぎにより、脳が常に目覚めた状態になっているのが原因です。脳は本来、活動と休息を切り替えることが大切なのですが、頭を使うことが多すぎると、常に活動している状態になってしまいます。これを「覚醒状態」と呼びます。
覚醒と言っても、集中力が上がって効率よくできる状態ではなく、目覚めているのに疲れているというアンバランスな状態です。例えれば、充電が切れかけたスマホを、無理やり使っているような感じです。
心の疲れは少しずつ蓄積していきます。やらなくてはならないことがあり、まだまだ頑張れると思っていても、すでに限界になっていることもあります。そんな時、心はいろいろな形でSOSのサインを出しています。仕事への義務感から心の悲鳴を聞き逃すことがないようにしましょう。放っておくと、うつ病などの病気になる危険性があります。
今回は、心のSOSのサインを見逃さないように、あなたの心が疲れている10個のサインをご紹介します。

1 悪夢
心の疲れをとるためには、何よりも十分な睡眠が必要です。ところが、脳が覚醒状態のために睡眠の質が悪くなります。眠っていても、夢ばかりで疲れがとれません。特に悪夢が多くなります。夢の内容は、現実の嫌な場面がそのまま出てきたり、過去の辛かった思い出です。疲れが、象徴的な内容で現れることもあります。例えば、「戦争や犯罪者に追われる」、「家や車が壊れる」、「高いところから落ちる」、「洪水にのまれる」、「たくさんの虫に襲われる」、などの夢は、心が不安定である証拠です。変わったところでは、「歯が抜ける」という夢も、国や人種に関係なく、心が疲れた時に見る夢です。
2 ネガティブ
覚醒状態とは、脳が常に危険に注意を払っている状態です。いつ獣(けだもの)に襲われるかドキドキしながら、1日中ジャングルの中をさまよっているようなものです。ちょっとしたことでも心配になり、不安感に襲われます。良いことがあっても、「どうせダメになるに違いない」と、悪い側面しか目に入りません。
3 イライラ・怒りっぽい
情緒が不安定になるため、些細なことでイライラします。すぐに人を叱ったり、怒ってしまい、職場や家庭の雰囲気を悪くしてしまいます。
突然涙がこみあげてくることもあります。ちょっとした言葉がスイッチになり、悲しい感情が襲ってきて、涙が出てくるのです。
4 大事なことを先延ばしにする
脳は覚醒していても、脳の活動自体は弱っているので、気力が出ません。大事な仕事をやらなくてはならないのに、気持ちが乗らずに先延ばしにします。「すぐにやって欲しい」と頼まれても、何度もトイレに立ったり、スマホをいじってみたりで、なかなか取り掛かることができません。
家庭でも同じで、部屋の片付けも後回しになります。流しに汚れた皿が山積みになっていたり、脱いだ服がそのままであったり、いつかやろうと思っていても、気がつくと部屋に足の踏み場がなくなっています。
5 集中できない・うっかりミス
集中力が落ちるため、入力の間違い、誤字や脱字、計算の間違い、など、ちょっとしたミスが増えます。
書類や本などの文字に集中しようとしても、頭に入ってきません。周りの音に敏感になり、ドアの開け閉めの音、人の足音、子供の声など、それまで気にしなかった音でも不快に感じ、集中が妨げられるようになります。
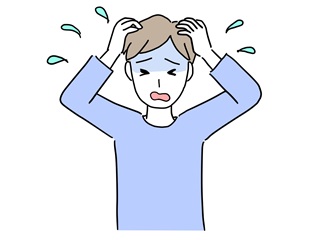
6 物忘れ
脳の働きが弱るため、物忘れが増えます。歯医者や美容院の予約を間違えたり、仕事の約束を勘違いして、大失敗してしまうかも知れません。スマホや財布を電車の中に置き忘れたり、人の名前や暗証番号を思い出せなくなることもあります。認知症になったのかと慌てる人も多いのですが、その前に心が疲れていることを疑いましょう。
7 体調不良
心の疲れは体にも現れます。代表的なものが自律神経の失調です。動悸や息苦しさを感じるようになり、心臓の病気かと不安になる人もいるでしょう。
免疫力も落ちるので、風邪をひきやすかったり、長引いたりもします。また、アレルギーによる喘息や皮膚のトラブルも増えるでしょう。
8 コリや痛み
心の疲れから、肩こり・腰痛・頭痛などの痛みが出ることがあります。神経の緊張から血の巡りが悪くなり、それがコリや痛みになるのです。検査をしても異常がないため、痛み止めで我慢するしかありません。マッサージを受けて良くなっても、一晩寝ると痛みが戻ってきます。
9 食べられない・食べ過ぎる
自律神経の失調から、食欲がなくなり、人によっては吐き気を感じます。病院で検査をしても大きな異常がない場合は、心の疲れが原因かも知れません。
これとは逆に、過食になることもあります。特に、味の濃いスナックやスイーツをたくさん食べたくなるのは、アルコールやタバコと同じような効果があるためです。
10 嗜好品が増える
アルコールやタバコには、心の疲れを一時的におさめてくれる効果があります。しかし、切れてくると、よけいに疲れを感じるので、量がどんどん増えて行くでしょう。これは、無意識のうちに、心の疲れを嗜好品で誤魔化しているサインです。

心が疲れている10のサインを紹介しました。これらは、あなたの脳が覚醒状態である証拠です。こうした症状は、サプリを飲むとか、2~3日休んだら改善するというものではありません。1つでも思い当たるものがあれば、2週間以上の休みをとった方がよいでしょう。
長い休みがとれない場合は、できるだけ仕事を減らします。通常の6割くらいが目安です。これを「6割主義」と呼びます。
また、睡眠を大切に考え、寝床につく1時間前からは、スマホをいじらず、のんびりと過ごすようにしましょう。暴飲暴食やお酒の飲み過ぎに注意します。このような生活を続けることで、少しずつ脳の覚醒状態が改善されるはずです。
2週間以上も改善されず、仕事や日常生活に支障が出ている場合は、うつ病の可能性がありますので、精神科に相談してみましょう。