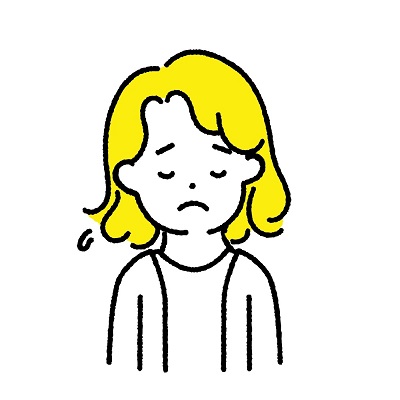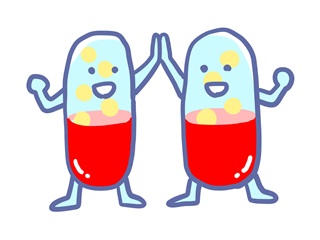愛着障害がある人の6つの特徴
皆さんご存じの人気マンガ「鬼滅の刃」。今から100年前の大正時代を舞台にした剣士たちの物語です。その中に、親が子供を売るというショッキングなシーンが何度か出てきます。「身売り」と呼ばれるこのような行為は、80年前の昭和初期まで続いていました。今では子供の人権が認められていますが、つい最近まで「子供は親の所有物」という考えがあったのです。
遊郭や工場などに売られた子供たちは、雇い主のいいなりに生きるしかありませんでした。自分を主張すればとんでもないことが起きるので、自分を消して、自分がない生き方をしました。大人になっても、言われたことに黙って従う人のままです。身売りは過去の話になりましたが、このような自分を主張しない生き方をしている人は、現在でもたくさんいます。
なぜ、自分を主張しない生き方をするのでしょうか?大きな原因は親子関係にあります。幼い頃、親子の情的な絆がつくれないままでいると、親に守られているという信頼が育ちません。すると、親から見捨てられる不安感がいつまでも抜けなくなります。
自分を主張することは、見捨てられることにつながるので、つよいものに従って生きるしかありません。それで、主張しない生き方をするようになるのです。親子の情的な絆を愛着と言いますが、親子関係が悪かったために起きてしまう、このような性格の偏りを愛着障害と呼びます。
愛着障害は、虐待やネグレクトだけで起きるのではありません。衣食住は満たされても、良好な愛着関係が築けない場合、例えば、母親自身に愛着の問題があったり、何らかの精神疾患がある場合などでも起きます。
それでは、親子関係を築けず、愛着の問題がある人は、大人になってから具体的にどのようになるのでしょうか?今回は、愛着障害がある人の6つの特徴を紹介しましょう。

1 見捨てられ不安
赤ちゃんは、親に守られて生活をする中で安心感をおぼえます。「親は裏切らない、必ず守ってくれる」という安心感は、生涯にわたって心の中心になる大切なものです。ところが、親子の情的な絆がつくれないと、安心感が身につきません。そうなると、何をしていても見捨てられるような不安につきまとわれるようになります。これを「見捨てられ不安」と呼びます。人によって漠然とした不安として感じていたり、孤独やさびしさ、人に嫌われているという被害妄想として感じることもあるでしょう。
中には、不安を解消するために、常に人から好かれるように頑張ってしまう人もいます。人に喜ばれるように行動しているのですが、実際は相手を思っているというよりも、見捨てられ不安に追い立てられているのです。
2 自分の考えをはっきりと持てない
子供は、親から安心感をもらいますが、それができた土台で親離れが始まります。自分という意識ができてくると、自然に一人で行動するようになります。ところが、安心感がなければ、見捨てられ不安に邪魔をされて、親から離れることはできません。安心して自立ができないのです。いつまでも自分を主張することができず、反抗期もないまま、大人になってしまいます。愛着障害のある人は、自分の考えをはっきりと持てません。
3 他人の目を気にする
「ありのままの自分は認めてもらえない」という思いがあるので、人前では良い人を装っています。ですから、他人からどう見られているかを常に気にしています。SNSでは、自分へのコメントをいつもチェックして、人から何か悪いことを指摘されると、そのことが頭から離れません。何事も「人は人、私は私」と開き直ることができないのです。
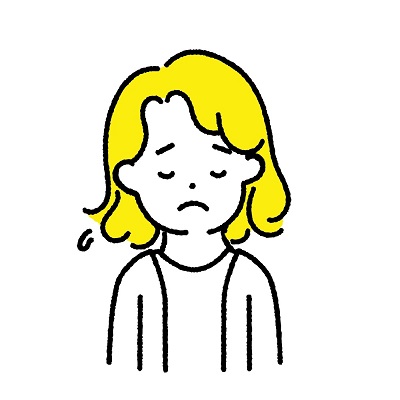
4 嫌と言えない
つよく言われると断れず、渋々受け入れてしまいます。結局損をすることは分かっていても、「NO」と言えません。自分を主張できないのです。
後から悪い結果が出たら、「無理やりやらされた」と、押し付けた人のせいにします。自分がやったことに責任を持とうとしません。
5 自分で決められない
物を買う時、仕事を選ぶ時など、何かを選択する場面では、優柔不断なために自分で決められません。「失敗したらどうしよう」と、選んだことに責任を持ちたくないので、人に決めてもらおうとします。そもそも、自分の好きなことをハッキリ言いません。
6 自分で切り開こうとしない
困った時、自分で自分の道を切り開けません。自分の力で解決しようとせずに、必ず誰かに頼ろうとします。中には、いろいろな人に助けをもらい過ぎて、頭の中がよけい混乱する人もいるでしょう。周りからは、無責任で、辛いことから逃げ回っていると思われます。
愛着障害は、一生背負わなくてはならないのでしょうか?そんなことはありません。原因は、心の中に十分な信頼と安心がないことです。本来ならば、子供の頃に身につくべきものが、まだ身についていません。大人になってからでも、信頼できる人との交流を通して、心の中に信頼と安心を築くことができれば良いのです。もう親は必要ありません。いくつになっても、信頼できる人との交流を積み重ねて行けば、少しずつ愛着障害は改善して行きます。
地位や立場があるから信頼できるのではありません。緊張せずに、心から何でも話せる人が本当に信頼できる人です。人に限らず、犬や猫であっても、あなたのことを大切に思い、肯定してくれる存在であるならば、そこに良い愛着関係をつくることができます。
愛着障害の人は、不安があるために、いつも緊張感を抱えて生活をしています。そのために、体がガチガチで硬く、リラックスができていません。こうした緊張がとれるように時間やお金を使いましょう。心から楽しめる遊びや趣味をもつこと、マッサージやヨガで体の緊張をとることがお薦めです。
音楽や映画など、エンタメを通しての感動体験も大切にしましょう。疑似的な体験であったとしても、愛着を育てる栄養となります。
将来のために貯金をすることも大切かも知れませんが、それ以上に、心の癒しのためにお金を使うことは、何よりも価値のあることです。
劣等感に悩む人の4つの特徴
私たちは、子供の時に成績の順位をつけられ、大人になってからも、学歴、地位名誉、さらには収入、容姿などでも比較されます。人より上なら安心しますが、劣っている場合は、不安や焦りに襲われることもあるでしょう。これを劣等感と呼びます。
職場や学校で周りの人が輝いて見えて、自分が情けなく感じるのは、劣等感が原因です。「みんなができているのに自分だけできない」ということがあれば、こんな苦しいことはありません。
また、SNSで輝いている同世代の人を見て、自信を失うだけでなく、憎たらしくもなります。人を憎んでしまう自分が情けなく感じることもあるでしょう。「できれば、比べられることのない世界に行きたい」と、思うことはないでしょうか?
そこで今回は、劣等感で悩む人の特徴を4つ紹介しながら、その対処法についてご説明します。

1 自分の価値に気づくことができていない
ドイツの精神分析医であるエリクソンによると、劣等感のルーツは小学生の頃にあります。この時期は、集団の中でさまざまな知識を学び、能力を獲得するため、互いに能力の差があることに気づくのです。
次の中学生からは、何のために生きるのか、社会のどのようなことに役立つのか、いわゆるアイデンティティというものを確立するための期間です。自分の価値を模索する時期ですので、人からの評価が非常に気になります。人の評価で自分の価値を決めやすいので、劣等感をつよく感じる時期です。
自分の価値や使命を悟るようになれば、劣等感をそれほど感じなくなります。人の評価が気にならなくなるからです。逆に言えば、自分の価値や使命を発見できていない人は、いつまでも他人の評価が気になってしまいます。
劣等感で苦しむ人は、自分の評判を上げることよりも、自分の生きる目的を探し出すようにしましょう。生きる目的といっても、大げさな内容ではありません。「家族を愛するため」「友人を大切にするため」「仕事で人に喜んでもらうため」など、ふだんから自分が大切にしていることが生きる目的です。自分で納得できる生き方をするようになると、周りからの評価は気にならなくなります。
2 「比べること」と「自分を責めること」がいっしょになっている
人には向上心があるので、劣等感が引き金になって、「負けないぞ!」と努力をします。劣等感とは、人がより快適な生活を手に入れるために必要な感情です。人よりも劣っていると感じるのは、心が健全である証拠なのです。
オーストリアの精神科医アドラーは、「劣等感とは、理想と現実のギャップである」と言いました。そして、「負けないぞ!」となれないのは、このギャップを乗り越えられないことから、自分の無力さを責めたり、うまく行っている人を憎んでしまうからだと説明しました。
アドラーによれば、劣等感は健全な感情であるけれど、それをネタに、自分や人を責めてしまうことが良くないと言うのです。比べることと自分を責めることは別にして考えるべきなのです。
自分よりも優れた人を見たら、「良く頑張っているな」、「才能があるのだな」と客観的に観察するだけにして、「できない自分はダメだ」、「あの人はずるい」につながらないようにしましょう。

3 負けず嫌いな性格
何事でも勝ち負けへのこだわりがつよく、ゲームでも勝つまでやらないと気が済まないような人は、劣等感を敗北感として感じます。いつまでも素直に負けを認められず、悔しさから自分を責めてしまうことがあるのです。
SNSには自慢がたくさん載っています。負けず嫌いの人は、輝いている同年代の人のSNSを見て、悔しい思いをしているかも知れません。「家族の幸せ自慢」「出世や名誉の自慢」「金儲けの自慢」「買い物自慢」「美しさの自慢」など、こんな自慢話で勝負をしても何の価値もありません。
そもそも、内容を盛っている可能性もありますから、その情報を信じる必要もないのです。自慢話のSNSは見ないようにしましょう。
4 職場や友人関係が合っていない
「有名な会社に就職できた」、「難関校に合格した」と、レベルの高いところに就職や入学できて喜んでいる人がいます。入ったのは良いものの、みんな優秀なために、どんなに努力をしても最低の評価しかもらえません。
背伸びをして良い職場や学校に入っても、周りのレベルが高すぎて嫌な思いをすることもあります。毎日を気持ちよく過ごすためには、職場や学校のレベルを下げた方が良いのです。
友達関係も同じです。背伸びをしなくては付き合えないような人間関係は必要ありません。いっしょにいて居心地の良い思いをする人間関係を優先するべきです。
劣等感は、より快適な生活を手に入れるために必要な感情です。ただし、理想に到達できない時に、自分や人を責めてしまうことは良くありません。できない自分を責めるのならば、比べない方が良いのです。「人は人、私は私」と割り切って考えましょう。
みなさんは、イソップ寓話の「ウサギとカメ」をご存じだと思います。ウサギとカメが徒競走をした話です。ウサギは、カメがあまりにも遅いので、手を抜いていいかげんに走りました。カメは、ウサギが何をしようと関係なく、自分のやることだけを考えて真面目に歩きました。最後に勝ったのはカメです。
これは単なる子供のおとぎ話ではありません。人生を象徴する話だからこそ、2500年以上も昔から伝えられて来ました。最後にうまく行くのは、カメのように周りと比べることなく、自分のやるべきことをコツコツやる人なのです。
どうして自分を傷つけるのか―自傷行為―
自分で自分を傷つけることを自傷行為と呼びます。例えば、リストカット、タトゥーやピアスを何度も入れたり、タバコの火を自分に当てる根性焼き、などが代表的なものです。リストカットにいたっては、女子中高生の10%に経験があるというデータもあり、決して珍しいことではありません。
最近、新宿歌舞伎町に集まる「トー横キッズ」と呼ばれる子供たちが、気分を高揚させるために、市販薬を過量摂取していたことが話題になりました。直接体を傷つけているわけではありませんが、命の危険をかえりみずに大量の薬を飲むことは、「自己破壊的行動」と呼ばれています。
自傷行為も自己破壊的行動も、実際に死にたいわけではありません。自殺の試みとは異なるものです。第三者には、わがままな人が、周りの関心を引くためにやっているとしか見えません。
死にたいわけでないのに、どうして自分を傷つけるのでしょうか?今回は、その理由について説明しましょう。

1 我慢の限界で起きること
人は、辛いことを我慢し続けると、ネガティブな感情が心の中に溜まってきます。ため込める容量があるので、我慢は無限にできません。溜まり過ぎたネガティブな感情は、ついに火山の噴火のように爆発します。
突然、逆らえないような強烈な思いが襲ってきて、何か行動に移さないと気が済まなくなるのです。これを「衝動」と言います。例えば、怒りの爆発、衝動買い、やけ食い、など、誰でも思い当たることがあるかも知れません。
衝動とは、我慢の限界を超えて、心が病気になったり、壊れてしまうのを防ぐために起こります。衝動的な行動の後は、たまっていた緊張がとれ、気持ちは楽になるでしょう。自分が壊れないようにリセットするためには必要なことなのです。
ところが、人によっては、衝動から自分を傷つけてしまうこともあります。たまった怒りの対象が、漠然としたものであったり、親や学校などの逆らえない存在であると、自分を攻撃するしかありません。これが自分を傷つける行為の正体です。
自分を傷つける人は、死にたいわけではありません。耐えきれないくらいの苦しい立場から逃れ、心の平安を取り戻したいだけなのです。
2 自分を傷つける人の特徴
自分を傷つける人にはいくつかの特徴があります。自尊心が低く、自分を大切にできません。感情表現が苦手なため、つらい気持ちを相手に伝えたり、助けを求めることも苦手です。
こうなってしまう原因には、親子関係や学校でのいじめられた体験などが関係しています。虐待や放任、それとは逆に厳格過ぎる家庭で育ち、親から十分な愛情を注いでもらえませんでした。産まれて来てから、人生で肯定された経験がないのです。
また、発達障害を持っている人は、ストレスの処理が苦手なため、自分を責めやすい傾向があります。自閉スペクトラム症では、自分の気持ちを表現するのが苦手であり、注意欠如多動症・ADHDでは、衝動のコントロールが苦手です。ストレスが溜まると、自傷行為や自己破壊的行動に結びつきやすいと考えられます。
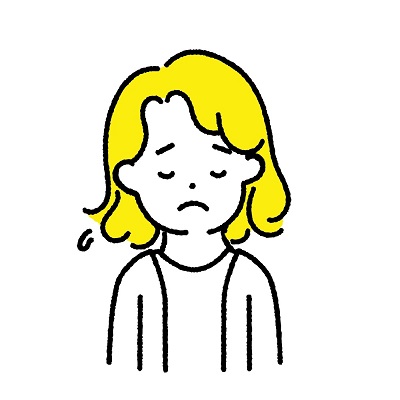
3 自分を傷つけることで気分が改善される
皮膚を切ったり、体に苦痛を与えると、脳の中ではエンドルフィンという物質が放出されたり、ドパミンという物質の濃度も増えます。エンドルフィンやドパミンは脳内の快楽物質とも呼ばれ、一時的に落ち込んだ気分を吹き飛ばしてくれます。不思議なことですが、痛みによる刺激が、麻薬のような効果で苦しさをとってくれるのです。
麻薬と似た効果ですから、習慣になりやすいという落とし穴があります。自傷行為で辛い気持が和らぐ経験をすると、依存的に繰り返すことがあります。
4 生きるために自分を傷つける
リストカットなどの自傷行為は、知られないように隠れて行うのがほとんどです。決して人の関心を引こうとしているのではありません。自分を傷つける行為は、自分の心を守るために起きている現象です。死にたいどころか、むしろ生きるために必死に悶えている姿なのです。
5 あなたが自分を傷つけたいと思った時に
自分を傷つけたいと感じることは、いまあなたが辛い状況にいて、それを乗り越える手段が見つからないということです。誰かにいまの苦しい気持ちを理解してもらえるだけでもスッキリすることもあります。
話すことはとても大切なことです。身近な人に相談しても、「甘えていると説教されるだけ」、「相手にされず、否定されるだけ」と感じている人、また、話すことが苦手な人もいますので、その場合は、国や都道府県の公的な相談窓口、カウンセラーや精神科などの専門家に相談するのが良いでしょう。これらの連絡先は、ネットで検索することができます。最近ではラインでの相談を行っている施設もあります。
人の心に一番大切なのは安らぎです。安らぎがない生活が続いていると心が壊れてしまいます。自分を傷つけてしまうのは、生活に安らぎがなくなっている心の叫びなのです。
人から言われた嫌な言葉が頭から離れない
人から言われた嫌な一言が、頭の中をグルグル回り、辛い思いをしたことはありませんか?こちらに非があるとは思えないので、素直に受け止めきれません。その言葉が浮かんで来て、日中はイライラするし、寝ようとしても頭が冴えてしまいます。「何であんなに酷いことを言われたのだろう?」と考えてしまい、自分を責めたり、相手を責めたりの繰り返しです。
このように、嫌な言葉が頭から離れないで苦しい時、どのように対処したら良いのでしょうか?SNSで調べてみると、体を動かしたり、美味しいものを食べたり、と、意識を他に向けると良いと書いてあります。また、友人や家族に話して、話題を共有することも勧められています。
意外に思われるかも知れませんが、心の専門家のカウンセラーや精神科医であっても、クライアントの一言に傷ついてしまうことがあります。クライアントが感情的になって、聞き手を言葉で攻撃することもあるからです。もちろん、それでけんかをしては良くないので、その場をうまく収めますが、当然、心にはダメージが残ります。心の専門家は、自分で自分の心を癒さなくてはいけません。そこで使われるのが、「メンタライゼーション」というテクニックです。
メンタライゼーションとは、精神分析の言葉で、心の動きを推測することです。相手がなぜそのような言葉を発したのか、その理由や気持ちが理解できると、心のモヤモヤがとれて、スッキリしてきます。モヤモヤの正体が明らかになるからです。メンタライゼーションは、誰でも日常に利用することができ、辛い気持ちから解放されるテクニックの一つです。
大きな理由もなく、相手が嫌な言葉を発する原因は、ほとんどの場合、自分でなく、相手にあります。そして、次の5つのパターンに分けられるでしょう。今回は、その5つのパターンを紹介します。人から言われた嫌な言葉が、頭から離れないで辛い時は、必ずどれかのパターンに当てはまっているはずですので、どれに当てはまるかを分析してみてください。

1 相手が別のことでイライラしている
腰痛で整形外科クリニックに通院中のAさん。ある日の診察の時に、体調が悪いことを相談したところ、「それは内科で相談してください!」とつよい口調で怒鳴られました。びっくりしたAさんは、その場は謝罪しましたが、特に変なことを言ったつもりはないので、怒られたことに納得がいきません。医師の言葉が頭から離れず、何日たっても、「言い方がまずかったのだろうか?」「私は嫌われているのだろうか?」と悩みました。
気になったので、手元のスマホを使って、このクリニックの評判を調べてみました。なんと、自分と同じように、この医師に突然怒鳴られたという体験を書いている人がいたのです。中には、経営が大変だから、医師がいつもイライラしているのではないか?というコメントまでありました。これを読んだAさんは、心のモヤモヤが消えて、スッキリしました。医師が怒鳴ったのは、自分に問題があったのでなく、医師のプライベートに問題があると分かったからです。そして、別のクリニックに通院することにしました。
イライラで情緒が不安定になっている人は、冷静を装っていても、何かのきっかけで棘のある言葉を吐く場合があります。こうした人と接していると、傷つけられることがあるでしょう。無理して付き合わず、距離を置くことが賢い選択です。
2 相手が不安になっている
うつ病で療養中のBさん。復職のことで悩んでいます。そんな時に、父親から「いつから働くんだ?」と言われました。一番悩んでいるのは、Bさん自身ですから、まるで「早く働け!」と怒られたようで、その言葉に大変傷つけられました。
いつまでも父親の言葉が頭から離れないので、母親を通して、傷ついた気持ちを父親に伝えてもらいました。後日、父親から謝罪の言葉を受けましたが、Bさんが働かないことを怒ったのでなく、病気がいつまでも治らないことが不安だったのだと説明してくれました。それを聞いて、Bさんの怒りもおさまりました。
Aさんのところでも紹介しましたが、相手が不安になって、逆に傷つけるような言葉を発してしまうこともあるのです。
3 相手が、別の誰かと重ねて見ている
母親から、きつい言葉ばかりかけられていたCさん。大人になっても、その言葉の一つ一つが心の中に残っています。年をとってから、母親の言葉に傷ついてきたことを思い切って伝えました。
母親からは、Cさんのことは愛していたつもりだけれど、Cさんの顔や言動が父親に似ていたから、父親を思い出して怒っていた、という理由を聞かされました。実は、Cさんの父親は、アルコール依存があり、いつも夫婦喧嘩が絶えない家庭だったのです。母親のきつい言葉は、嫌な夫の姿を娘に重ねてしまったのが原因だったというのです。これを聞いたCさんは、母親の苦労を知っていたので、少し許す気持ちが出て来ました。
心の中の嫌な気持ちを、他の人に押し付けてしまうことを投影と呼びます。Cさんには問題がなかったのに、両親の仲が悪かったことの犠牲になっていたのです。

4 相手がマウントをとろうとしている
生徒思いで、教育に熱心な先生であるDさん。生徒や父兄からの評判もとても良く、人気者です。ところが、校長から「余計なことをするな!」と怒鳴られました。校長の目からは、職員の秩序を乱す人として映っていたようなのです。
Dさんは、ショックを受けましたが、後日、理事長が来た時に、ペコペコする校長の姿を見て、校長が怒鳴った理由を納得しました。校長は、目上の人には媚びへつらい、目下の人には権威を振るうという、典型的な権威主義の人なのです。自分を怒鳴りつけた校長が、器の小さい人物であることが分かったので、Dさんはスッキリしました。そして、この学校はやめることに決めました。
5 相手に発達障害やパーソナリティの問題がある
会社員のEさん。後輩のデリカシーのない言葉に悩んでいます。今回は、「今日はメイクが濃いですね」と言われて腹が立ちました。いつもは受け流していたのですが、「そういう言葉は失礼だよ!」と、我慢できずに叱りつけました。ところが驚いたことに、後輩はキョトンとしています。自分の言葉がEさんを傷つけていると感じていなかったようなのです。
相手が発達障害やパーソナリティの問題をもっている場合、思っていることがそのまま口に出たり、場の雰囲気を考えずに発言することがあります。本人は、自分が人を傷つけていることには気づきません。このような場合は、我慢していないで、こちらから説明してあげることも必要かも知れません。
言われた言葉に傷つき、それが頭から離れないような場合は、今回紹介したパターンのどれかが当てはまると思います。どれをとっても、あなたに問題があるのではなく、相手に問題があることの方が多いのです。自分を責める必要はありません。
また、相手のちょっとした言葉でも悪くとらえてしまい、それが頭の中をグルグル回って、生活に支障が出るような場合は、心の抵抗力が弱っているサインです。うつ病などの精神疾患の可能性もあるので、注意が必要です。
孤独の危険なサイン
新型コロナウイルスのパンデミックでは、人と人とのつながりが切れ、感染の問題以上に、孤独の問題が深刻になりました。それが原因で、うつ病などの精神疾患が増え、自殺者も増えるということが世界的に起きています。コロナ禍を越えて、ようやく社会もつながりを取り戻しつつありますが、みなさんは孤独から解放されたでしょうか?
不思議なことに、一人でいても孤独を感じない人もいれば、たくさんの人に囲まれているのに感じる人がいます。人によって感じ方が異なるのです。また、アルコールやタバコなどの嗜好品には、一時的に孤独感を解消する作用があるので、これらで孤独感を麻痺させている人もいます。過食や浪費、自分を傷つけるような行為で解消している場合もあるでしょう。ホストクラブで散財した人もいるかも知れません。
孤独は、うつ病などの精神疾患を発症する引き金にもなります。特に、うつ病の大きな原因であり、同時にうつ病の症状でも孤独を感じるので、孤独の深みにはまり、死を選択しようとする場合があるので、注意が必要です。
このように、長い期間、先の見えない孤独を感じ続けることは、メンタルヘルスに良くありません。今回は、孤独の危険なサインを5つ紹介しましょう。

1 話し相手がいない
コロナ禍では、家にこもることを強いられ、丸一日誰とも話さないという人もたくさんいました。このために、うつ病になる人の数が2倍になったという報告もあります。会話を通して人とつながることは、とても大切なことです。話し相手が一人でもいることは、孤独の解消に大きな力となります。
世の中には、孤独な人の力になりたいと感じている誠実な人もたくさんいます。もし話し相手がいないと感じているならば、こうした人との出会いがあるように、趣味のサークルに所属してみたり、カウンセリングや相談窓口を利用してみましょう。
2 自分を理解してくれる人がいない
例え話し相手がいても、自分のことを理解してもらえない場合は、つよい孤独を感じます。いっしょに住んでいる家族がいて、いっしょに働く仲間がいても、本当の気持ちを分かってもらえない生活は、心が満たされません。しかし、苦しんでいることの一部分でも理解してくれる人がいれば、孤独感は解消されます。残念ながら、そのような人とは、なかなか出会えないのが現実です。
むしろ、どんな時もなついてくれる犬や猫などのペットの方が、自分の本音を分かってくれていると感じることがあります。
また、自分と似たような人の話を、映像や本を通して見たり聞いたりすると、孤独が解消されます。エンタメにも孤独を癒してくれる力があるのです。信仰を通して、神や先祖に自分を分かってもらえていると感じ、孤独を乗り越えている人もいます。宗教で孤独が解消される人もいるのです。

3 仲間外れにされている
いじめやハラスメント、転校や転職して仲間に入れない、こうしたことも孤独の大きな原因になります。
いじめやハラスメントがあっても、「仕事の収入がなくなるから我慢する」、「よけいに孤独になるから我慢する」という人もいますが、嫌な思いをしながらその場にいる必要はありません。新しい出会いが必ずあるので、居心地の悪い場所には長居しないようにしましょう。
4 社会から孤立している
年をとること、家族の死、病気、貧困、災害など、さまざまな理由から、人は孤立してしまいます。また、発達障害でコミュニケーションの能力に問題があることから、周りから孤立する場合もあります。
何とか辛い状況から抜け出そうとしても、頼れる人がいない場合が多く、そもそも、どこの誰に助けを求めたら良いのかも分かりません。2023年には、孤独・孤立対策推進法が成立しました。現在は、国をあげて、孤独や孤立への対策が進められています。最寄りの役所だけでなく、電話やネットにも公的な窓口があります。気軽に相談してみるも良いと思います。
5 孤独で死にたい
常につよい孤独を感じる場合は、すでにうつ病になっている可能性があります。うつ病は気分の落ち込みの病気ですが、症状で孤独を感じる場合もあります。それだけでなく、「不安感」、「人と会いたくない」、「何もしたくない」、「昼夜逆転」、「食欲の低下」、「体調不良」などの症状がある場合は、うつ病の可能性があります。特に、自分に生きる価値がないと感じて死にたいと思うことは、大変危険なサインですので、早めに精神科を受診しましょう。
また、孤独感から妄想を抱えてしまうことがあります。「誰かに見られている」、「誰かに嫌がらせをされている」と感じて、カーテンを閉め切った生活をするのは、精神疾患の症状です。
調査によれば、日本人の14人に1人は、深刻な孤独を抱えています。人生ではたくさんの人と出会いますが、自分のことを理解してくれる人はほんの僅かです。100%分かってくれる人となると、一生出会えないかも知れません。ですから、少しでも気持ちを分かってくれる人が、世の中に一人でもいるならば、それは宝のような存在です。
カウンセリングや精神科で、心の専門家に相談しても、話のピントが合わず、理解されている感じを持てないこともあります。人には相性の良し悪しがあるからです。しかし、趣味で出会った人に何気なく話したことを通して、自分の一部分でも分かってもらえると、孤独感がスーと消えることがあります。良い出会いがあるように、諦めずに行動してみることが大切なのかも知れません。
苦労が心の豊かさとして実るために必要なこと
世の中には、何をやってもうまく行く人と、それとは逆に、何をやってもうまく行かない人がいます。誰だって、何でもうまく行くようになりたいですが、残念ながら、人は生まれた時から平等ではありません。
才能を持って生まれる人、美人に生まれる人、お金持ちの家に生まれる人など、生まれた時から出発するところが違います。徒競走で例えると、ゴールの近くからスタートできる人から、遠いところからスタートしなくてはならない人がいるようなものです。スタート時点が違うので、同じ幸せを手に入れるためにも、楽できる人もいれば、苦労する人もでてくるでしょう。
苦労が多すぎれば、「なんでこんな酷い目に会うのだろう」、「こんな人生に価値はない」と、恨みになることもあります。しかし、人より苦労することは決してマイナスではありません。苦労は心の豊かさにつながります。苦労が、心の成長を促(うなが)して、その人の魅力として実ることがあるのです。
今回は、オーストリアの精神科医・フランクルの言葉を通して、苦労が心の豊かさとして実るために必要なことを紹介しましょう。
フランクルは、アウシュビッツ強制収容所に収監されながらも生還した人です。ガス室で処刑される不安、過酷な労働、兵士からの暴力、栄養失調、チフスの流行、寒さという、あらゆる地獄を経験しました。そうした極限の状況で、自分や収容所の人の心の動きを客観的に観察し、1946年に、「夜と霧」という本を発表しました。
そこには、絶望が人を滅ぼすこと、生きる目的をもつ人は、過酷な環境でも耐えられることが描かれています。現在、生きる意味に注目するフランクルの心理療法は、ロゴセラピーと呼ばれています。

1 希望がない苦労は、心に悪い影響がある
すべてを失い、抵抗もできない強制収容所の人の多くは、感情を失い、無反応、無気力になりました。辛いことでも、いつまでに終わると分かっていれば、我慢することができます。
収容所の人たちは、「クリスマスには解放されるだろう」と楽観的な希望を持ち、耐えていました。しかし、苦労がいつまで続くか分からなくなった時に、すべての希望を失います。実際には、クリスマスを過ぎても収容所の様子は変わりませんでした。
すると、それから数日の間に、処刑されたわけでもないのに大量の死者が出ました。直接の原因は、チフスであったり、栄養失調であったかも知れませんが、絶望によってたくさんの命が尽きてしまったのです。
人は、絶望によって滅びてしまいます。心が動かなくなるだけでなく、内臓の動きや免疫力も低下することによって、生命を維持することもできなくなります。希望がない苦労は、心に悪い影響しかありません。
2 苦労の意味を見つける
フランクルは、生き残って、収容所の体験を発表することを夢にもちました。極限の状況の人々の心理を研究し、それを将来に残すことを使命に感じたのです。このことを希望として、過酷な生活を耐え抜きました。
収容所の中には、自分のことよりも、他人を優先する人もたくさんいました。極限の状況でも、弱っている人を励ましたり、食べ物を分けて与える人もいて、フランクルも生きる力をもらったそうです。こうした人たちは、収容所生活に何か自分なりの意味を見出していたと言います。
苦労の中でも、何か自分なりの意味を見つけようとする人は、苦労が無駄になりません。苦労の意味は、その時は分からなくても、後から理解できることもあります。また、自分のためにというより、身近な人や世の中に役に立つことを使命として考える人は、苦労が心の成長につながると言うのが、フランクルの考えです。

3 名もなき人の生き方が偉大
ここで、うつ病で長年闘病中のAさんの話を紹介しましょう。
Aさんのお父さんは早くに亡くなり、年老いたお母さんと2人で生活しています。兄弟たちはそれぞれに家庭を持ち、今は遠いところに住んでいて、ほとんど会う機会もありません。Aさんは、何で自分だけ貧乏くじを引いてしまい、こんな苦労をしなくてはならないのか不満です。「若い頃から病気で何もできず、いまでも家族に迷惑ばかりかけている。そんな人生に意味などない。」と、いつも考えています。
先日、お母さんがケガで入院することになりました。Aさんの体調も良くなかったのですが、遠方の兄弟を頼ることもできず、入院の付き添いをしました。その時、お母さんの口から、「いつも近くにいてくれて、1番親孝行な子供だと思う。」と、感謝の言葉をもらいました。早くに夫をなくして、心細かったお母さんにとって、Aさんはいつも大きな存在だったと言うのです。
1番お母さんの役に立っていたのは、成功して立派に働いている兄弟たちでなく、病気で何もできない自分だったことを知って、Aさんは嬉しく思いました。自分の人生にも意味があったのだと感じ、気持ちが楽になったそうです。
良心的に生きている人は、気付かないうちに、必ず誰かの役に立っています。フランクルは、「名もなき人の生き方が偉大」と呼びました。何か大きなことを成功させて世の中に貢献する人たちは立派ですが、ささやかに暮らしている名もなき人たちの生き方にも、必ず意味があると言うのです。むしろ、良心を持っているひとりひとりが、世の中を良い方向に進ませているのであり、大きなことを成し遂げる人は、それを代表しているだけのことであるというのが、フランクルの考えです。
最後に、フランクルが残した名言を紹介しましょう。
どんな時も、人生には意味がある。
あなたを待っている「誰か」がいて、あなたを待っている「何か」がある。
そして、その「何か」や「誰か」のために、あなたにもできることがある。
辛い別れを経験したときに知っておきたい事
大切な人が亡くなった時は、さみしさや悲しみに襲われ、大変辛いものです。また、人だけでなく、犬や猫などの大切なペットとの別れも、同じくらいに辛いことです。最近では、災害や事故で、予期しない突然の別れを経験する人もいます。
しかし、亡くなった人やペットは戻ってきてくれません。長い間、気持ちのやり場もなく、さみしさや苦しみが続くことがあります。残された人は、辛い思いをどのように乗り越えたら良いのでしょうか?
今回は、辛い別れを経験した時に知っておきたいことを、5つにまとめてみました。

1 通常は2カ月くらいで自然に乗り越えられる
仲が良ければ良かっただけ、別れは辛くなります。辛いのは、お互いが深く結ばれていた証拠です。これは人としての自然な心の反応で、「死別反応」とか、「悲嘆反応」と呼ばれています。苦しい感情は、孤独感と喪失感が中心で、波がありますが、日を追うごとに徐々に弱くなって行きます。だいたい2カ月くらいで落ち着いてくるのが普通です。
大切な人が亡くなった直後は、理性で分かろうとしても、気持ちでは受け止められません。葬儀などを通して、少しずつ亡くなった現実を受け止めるようになります。最初は絶望から始まりますが、良い思い出をくれたことなど、肯定的な思いも入り混じるようになり、少しずつ心が整理されて行きます。
最終的に、亡くなった人を思い出す時には、さみしさよりも、懐かしさや感謝を感じるようになります。これは、亡くなった人との間に新しい関係が築き上げられたことであり、思い出の中で永遠の絆ができたのです。このような一連の気持ちの流れを、「喪の作業」と呼びます。
2 悲しみを1人で抱え込まない
葬儀などの儀式の場があると、親交のあった人たちが集まります。そこでは、亡くなった人を悼み、みんなで悲しみを共有します。このような習慣は、どこの民族にも宗教にも、古くからあります。単なる儀式として考えている人が多いのですが、悲しみをみんなで共有することは、実は、喪の作業のためにとても大切なことなのです。
悲しみを1人でため込むと、喪の作業が進まず、逃げ場を失った負の感情は、怒りや罪悪感となって、心や体を蝕むことがあります。これを「遅延性悲嘆」と呼んでいます。症状によっては、専門家による治療が必要になる場合もありますので、後で詳しく説明しましょう。
別れの悲しみは、1人でため込んではいけません。周りの人と死別の苦痛を共有することを通して、苦痛は軽くなっていきます。ですから、葬儀や法要は、単なる儀式ではなく、私たちの心のために、とても大切なイベントでもあるのです。
3 自分を責めるのは良くない
「酷いことを言ってしまった」、「もっと大切にしてあげていたら」など、後悔の気持ちが出てくるのも、自然な死別反応の一つです。ただし、遅延性悲嘆で説明したように、悲しみをため込み過ぎることで、自分を責める気持ちがつよくなることがあります。これは、喪の作業が進んでいないのかも知れません。
自分を責める気持ちには、自分でブレーキをかけた方が良いのです。悲しむことは大切ですが、自分を責めることは、亡くなった人も喜ばないでしょう。

4 死別反応とうつ病は違うもの
死別で悲しみがつよい場合、うつ病になったのかと感じる場合があります。死別は、うつ病と大変似ている状態ですが、あくまでも正常な心の反応であり、症状は波のように上がり下がりしながら、最終的に2カ月くらいで自然におさまります。また、仕事が手につかなくなるなど、日常生活に大きな支障を起こすことはありません。
ただし、人によっては、悲しみが大きく長く続いてしまい、仕事ができなくなったり、ひきこもりになったりと、生活に支障が出るような場合があります。これを「複雑死別」と呼びます。症状だけを見る限り、うつ病と区別がつきません。自然に良くならずに、カウンセリングや精神科での治療が必要になるケースもあるので、注意が必要です。
5 治療が必要な複雑死別
複雑死別には次の4つのタイプがあります。
1つめは、「慢性悲嘆(まんせいひたん)」と呼ばれるもので、悲しみがいつまでも続いてしまうことです。生きていた時よりも慕う気持ちがつよくなったり、「何で先に死んでしまったんだ」という怒りの思いが湧いてくることもあります。
亡くなった人と親密であったり、依存的な関係であった場合に起こりやすく、孤独なために、喪の作業が進まないことも原因になります。特に1年以上続く場合は、専門家のもとで治療する必要があるでしょう。
2つめは、「肥大化悲嘆(ひだいかひたん)」と呼ばれるもので、激しい悲しみ・不安・孤独感などに襲われることです。この場合は、日常生活に大きな支障が出るので、専門家の治療が必要でしょう。突然の予期しない別れによって起きることが多く、ひきこもりになることがあります。
3つめは、最初に紹介しましたが、「遅延性悲嘆(ちえんせいひたん)」と呼ばれるもので、悲しみを心の底に押し込めることで、喪の作業が進んでいない状態です。「辛いはずなのに、悲しみが湧いて来ない」と感じ、心の中で怒りや罪悪感が渦巻いてイライラしたり、倦怠感、頭痛、胃痛、下痢、腰痛などの体の症状が現れることもあります。
4つめは、「外傷性死別(がいしょうせいしべつ)」と呼ばれるもので、災害・事故・犯罪により、突然の別れを経験することです。激しい悲しみや不安が長く続き、慢性悲嘆と肥大化悲嘆が合わさった症状を持ちます。
さらに、亡くなった状況がトラウマとなるため、不安と恐怖に繰り返し襲われ、亡くなった人との良い思い出は遮断されてしまいます。喪の作業が進まないため、自然に良くなっていく道が開きません。これも、専門家による治療が必要な状態です。
大切な人やペットとの別れがあった時は、人それぞれの感じ方、乗り越え方があり、死別反応という一言では片づけられない世界があります。ただし、悲しむことは悪いことではないこと、むしろ、一人で抱え込まずに、辛い気持ちはできるだけ表に出して、それを人と共有することが大切であることを知っていただきたいと思います。
もし、永遠の魂があるのでしたら、亡くなった人に感謝の思いを送ってあげることが、最も良い供養です。別れの気持ちが整理できたら、祈りを通して、感謝の気持ちを送るようにしたら良いと思います。亡くなった人は、心の中で永遠に生き続けることができるでしょう。もしかすると、あなたが亡くなった時、大切な人やペットと、天国で再会できるかも知れません。
いつも両親が喧嘩をする環境に育った人に現れる影響
人気韓流ドラマの「夫婦の世界」は、夫婦間の激しいバトルが描かれた作品でした。争ってばかりいる夫婦の間に挟まれた子供が、徐々に心を病んでいく姿も描かれています。
親のけんかばかりを見て育てば、子供の心が病むのは当然です。成績は下がり、情緒も不安定になり、不登校や非行などの問題が起こりやすくなるでしょう。大人になっても尾を引いてしまい、社会に出てから生きづらさを感じている人もいます。
しかし、世の中にけんかをしたことのない夫婦はいません。どんなに仲の良い夫婦であっても、意見の違いが出るのは当然です。ですから、すべての夫婦げんかが、子供の心に悪い影響を与えるわけではありません。アンケート調査によると、頻繁に夫婦げんかを目撃した子供の80%は、自分が大人になったら子供の前では夫婦げんかはしないと言っています。親が反面教師になってくれるのです。
それでは、子供の心に悪い影響を与える夫婦げんかとは、どのようなものでしょうか?それは、殴るけるの暴力、大声で相手を罵倒する、無視する、家出をする、奴隷のように服従させる、といった内容が含まれるものです。親の暴力や罵声が、自分に向けられたように感じてしまうことが原因です。また、けんかをしていた期間や、けんかの後に子供の心をフォローできたかどうかも影響があります。
親のけんかを目撃してきたことが、心のトラウマとなり、大人になっても残るケースもあります。これを複雑性PTSDと呼んでいます。子供の頃の辛かった経験が、大人になってからの自分の評価や人間関係に悪い影響を与えてしまうのです。今回は、親のけんかがトラウマとなっている人が、大人になってからどのような生きづらさを経験するのかを5つ紹介しましょう。

1 人生に悲観的
家庭の一番大切な役割は団らんです。ところが、夫婦がいつも怒鳴りあっている、無視しあっている家庭には、安らぎはありません。いつも緊張感があり、居心地の悪い家庭です。そこでは、良い親子関係も築けませんから、子供の心も育まれません。
また、子供には、親がなぜけんかをするかが理解できないので、原因が自分にあると感じる場合があります。自分がいるから争いごとが絶えないと勘違いして、自分を責めてしまうのです。
このような家庭状況で育つと、子供の心の中に、「自分は生きる価値がある」、「生きていて良い存在である」という自己肯定感が育ちません。大人になっても、「生きている意味が分からない」、「自分は必要のない人間である」といった思いに苦しむようになります。自分の人生に希望を見出すことができないのです。
2 感情のコントロールが苦手
長い期間にわたり、親の暴力や罵声を目撃した子供は、実際に虐待を受けた子供と同じようなダメージがあると言われています。調査によると、脳の発達にも影響を与え、認知機能全般が低下することが分かってきました。大人になってからの社会生活で特に問題となることは、感情のコントロールがうまくできなくなるケースです。親と同じように、自分の思い通りにならない状況で、感情を爆発させてしまうことがあります。

3 人と信頼関係を築けない
親子関係は、大人になってからの対人関係の取り方に大きな影響を与えます。親がけんかばかりしていると、親子の情的なつながりが築けません。そのために、大人になっても対人関係の距離感が分からなく、人とうまく話せなかったり、人と衝突することが多くなります。
また、子供は親の対人関係のパターンを見て学びます。親が、自分の意見が通らないと怒る、無視する、という対人関係のパターンをとっていると、それを無意識のうちに学んでいる子供もいます。気に入らなければ、相手を攻撃する、無視するという手段を使うようになるのです。コミュニケーションは、感情を抑えながら、言葉を介してやりとりするのが基本です。それができないために、人との信頼関係を築きにくくなります。
4 結婚生活に不安
先ほども言いましたが、ほとんどの子供は、けんかばかりする親の姿を反面教師として学びます。育った家庭に安らぎがなかったので、自分は平和な家庭を作ろうと必死に努力するようになるのです。
中には、いつまでも結婚というものに希望を持てない人もいます。自分が結婚しても、親と同じことになるのではないかと、家庭を持つことが不安になります。結婚することで幸せになるというイメージが湧きません。
5 心の病気になりやすい
親のけんかばかりを見ていると、子供の情緒は不安定になり、医師に診察してもらったところ、注意欠如多動症と診断されることもあります。思春期になると、さみしさを埋めるために、過食嘔吐などの摂食障害、自傷行為、さまざまな依存症が起こりやすくなるでしょう。こうした思春期に発病した精神疾患は、大人になっても尾を引きます。
また、社会に出てから、人間関係を中心に生きづらさを感じることから、うつ病を発症する人もいます。
人にはそれぞれの個性がありますから、考え方もそれぞれに異なります。どんなに仲が良い関係でも、意見が異なることが起きるのは当然です。そんな時、理性を働かせて一生懸命に話し合い、お互いに納得して一致するところに発展があります。全く反対のように聞こえる他人の意見でも、よく話し合って行くと、自分の考えをレベルアップさせてくれる内容であったりします。ですから、意見の違いでもめることは悪いことではありません。
これに反して、子供の心に悪い影響を与える夫婦げんかとは、相手の意見に一切耳を傾けず、腕力や言葉の暴力を使って、強制的に意見を受け入れさせようとする行為です。感情を爆発させ、腕力や暴言を武器に相手を傷つける戦争のようなものです。そうではなく、相手を理解しながら、同時に言葉やスキンシップで自分の気持ちを伝えることが、本来の対人関係のあるべき姿でしょう。
親のけんかで心を傷ついた人は、親の乱暴な対人関係の取り方を目撃して傷ついてきました。ですから、相手を思いやり、言葉を使ったコミュニケーションができる人との付き合いを通して癒されていきます。言葉や腕力を武器にするのでなく、言葉をつかって人を理解し、優しさを伝えられる人との交流が大切なのです。世の中には、このような対人関係をとることのできる人もたくさんいます。こうした人との出会いを大切にして、長く交流することに意識を向けてみましょう。
しかし、出会いは運ですから、なかなか良い出会いに巡り合えないこともあるでしょう。このような場合は、心理カウンセラーのもとを訪ねてみるのも良いかも知れません。
トラウマは、自分の努力でどうにかなるものではありません。親子関係で傷ついてきた心は、良い人間関係を通して癒されることが必要なのです。
気分変調症ってどんな病気?
うつ病は、元気に生活していた人が、気分が落ち込むようになり、生活に支障が出てしまう病気です。ところが、いつ発病したか記憶になく、物心ついた頃からずっと気分が落ち込み、自分は必要のない人間であると思い続ける病気があります。
これはうつ病とは違い、「気分変調症」・「持続性抑うつ症」という病気です。子供や学生の頃に発病することから、「子供の頃からずっと死にたかった」と訴える人もいます。
軽いうつ病と同じような症状ですが、学校や職場には行けるので、病気というよりも性格と考えている人もいます。昔は、「抑うつ性人格」と呼ばれていた時代もありました。
軽いうつ病の症状が、2年以上続いている場合に診断がつけられます。実際に病名をつけられる場合は、気分変調症と言う言葉よりも、分かりやすいので、うつ病と言われることが多いかも知れません。しかし、正確には、うつ病とは近いものでも、違う病気として分類されています。
実は、とても多い病気で、人口の5%に見られるという調査結果もあります。ところが、性格の問題と考えてしまい、辛くても治療をしない人がたくさんいます。
今回は、気分変調症とはどのような病気か説明しましょう。

1 子供の頃から死にたかった
「気分変調」という言葉は、そもそも不機嫌という意味から来ています。周りの人からは、病気というよりも、いつも機嫌が悪い人とか、無気力な人に見られます。いっしょに生活している家族から、「暗い」、「不愛想だ」、「元気を出しなさい」と叱られることもあるでしょう。
学校や職場には行けますが、「気づいた時からずっと落ち込んでいる」と訴え、自分には生きる価値がないと考えています。いつも元気がなく、何かに熱中することもありません。
繊細で、周りの人の言動に敏感に反応することもあり、感情的になります。そのために、学校や職場でトラブルを起こしたり、ひきこもりになることもあります。
「子供の頃から死にたかった」というように、子供や学生の頃に発症し、大人になっても同じ状態がずっと続きます。自然に良くなることもありますが、治療をしないで、一生涯そのままの人もいるでしょう。
2 病気と気づくまでに10年くらいかかる
若い頃から病気の中にいるために、元気がないのが病気であるとは、自分も周りも気づきません。病気と気づいて受診するまでに、10年くらいかかる人が多いと言われています。原因が分からずにひきこもりになっている人の中には、気分変調症の人がたくさん含まれているとも考えられています。
3 子供の頃に失望体験がある
気分変調症の原因はまだ十分に分かっていませんが、子供の頃に失望した体験が原因であるという説があります。人間関係で傷ついたことが、その後の性格形成に何らかの影響を与えたのではないかというのです。子供の頃の辛かった体験を通して、「自分は必要のない人間である」、「誰も助けてくれない」、「一生幸せになれない」といった、ネガティブな考え方が、心に染みついてしまったのかも知れません。
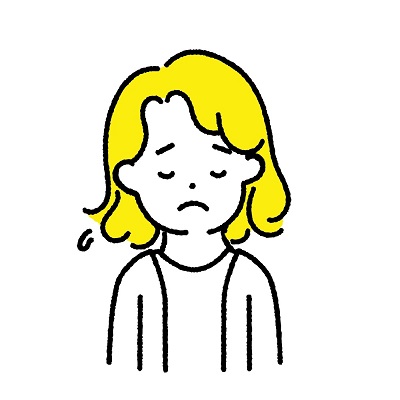
4 治療は長くかかる
子供の頃の心理の問題が影響していることから、治療は、カウンセリングが中心になりやすい傾向にあります。しかし、抗うつ薬の治療に大きな効果があるので、医師から薬を勧められたら積極的に飲むようにしましょう。
抗うつ薬の力で気持ちが楽になると、社会との接点も増えてきます。それを通して、楽しみが増え、生活が良い方向に向いてくると、自己肯定感も改善されます。このように、薬を飲むことをきっかけに、生活の良いループに入ることが、最も回復につながります。
ただし、1年間の治療で良くなるのは、10%くらいと言われており、治療には何年間もかかります。「どうせ長くかかるなら、治療を受けなくても良い」と考える人もいますが、時間はかかっても、治療を受ければ回復しますので、放置するのは良くありません。
5 うつ病や双極症になることがある
気分変調症の人の経過をたどってみると、20%の人がうつ病になり、15%が双極Ⅱ型障害になるという調査結果があります。気分変調症に、うつ病や双極Ⅱ型障害が重なるケースはとても多いのです。むしろ、気分変調症だけでは、病気と気づかなかったのに、うつ病や双極Ⅱ型障害になったことがきっかけで、精神科に通うようになったという人もいます。
また、うつ病の診断で、2年以上精神科に通院している人がいますが、その半分近い人に気分変調症があるという調査結果もあります。
大きな原因もなく、若い頃から生きる価値を感じられていない人は、気分変調症の可能性があります。うつ病のようですが、うつ的な暗い性格と間違ってしまう病気です。
ずっと性格の問題かと思っていて、30才、40才になってから病院へ行って、抗うつ薬を飲んだところ、生活がとても楽になったという人もたくさんいます。長い間、「性格の問題では?」、「親子関係の問題では?」など、苦しんでいた気持ちが、薬1粒で良くなるというケースもあるのです。
ただし、薬は長く飲む必要があります。特に大きな副作用はありません。精神科の薬に抵抗がある人も多いのですが、治療が面倒な手術やリハビリでなく、「毎日1粒の薬を飲むだけで人生が楽になるならラッキー」と、考えてはどうでしょうか?
苦労が心の豊かさとして実るために
世の中には、何をやってもうまく行く人と、何をやってもうまく行かない人がいます。誰だって、何でもうまく行くようになりたいと思います。しかし、残念ながら人は生まれた時から平等ではありません。才能を持って生まれる人、お金持ちの家に生まれる人など、生まれた時から出発するところが違います。
徒競走で例えると、ゴールの近くからスタートできる人から、遠いところからスタートしなくてはならない人がいるようなものです。スタート時点が違うので、同じ幸せを手に入れるためにも、楽できる人もいれば、苦労する人もでてくるでしょう。
苦労が多すぎれば、「なんでこんな酷い目に会うのだろう」、「こんな人生に価値はない」と、恨みになることもあります。しかし、人より苦労することは決してマイナスではありません。苦労は心の豊かさにつながります。苦労が心の成長を促し、その人の魅力として実ることがあるのです。
今回は、オーストリアの精神科医・フランクルの言葉を通して、苦労が心の豊かさとして実るために必要なことを紹介しましょう。
フランクルは、アウシュビッツ強制収容所に収監されながらも生還した人です。ガス室で処刑される不安、過酷な労働、兵士からの暴力、栄養失調、チフスの流行、寒さという、あらゆる地獄を経験しました。そうした極限の状況で、自分や収容所の人の心の動きを客観的に観察し、1946年に「夜と霧」という本を発表しました。そこには、絶望が人を滅ぼすこと、生きる目的をもつ人は、過酷な環境でも耐えられることが描かれています。現在、生きる意味に注目するフランクルの心理療法は、ロゴセラピーと呼ばれています。

1 希望がない苦労は、心に悪い影響がある
すべてを失い、抵抗もできない強制収容所の人の多くは、感情を失い、無反応、無気力になりました。辛いことでも、いつまでに終わると分かっていれば、我慢することができます。収容所の人たちは、「クリスマスには解放されるだろう」と楽観的な希望を持ち、耐えていました。しかし、苦労がいつまで続くか分からなくなった時に、すべての希望を失います。実際には、クリスマスを過ぎても収容所の様子は変わりませんでした。
すると、それから数日の間に、処刑されたわけでもないのに大量の死者が出ました。直接の原因は、チフスであったり、栄養失調であったかも知れませんが、絶望によってたくさんの命が尽きてしまったのです。
人は、絶望によって滅びてしまいます。心が動かなくなるだけでなく、内臓の動きや免疫力も低下することによって、生命を維持することもできなくなります。希望がない苦労は、心に悪い影響しかありません。
2 苦労の意味を見つける
フランクルは、生き残って、収容所の体験を発表することを夢にもちました。極限の状況の人々の心理を研究し、それを将来に残すことを使命に感じたのです。このことを希望として、過酷な生活を耐え抜きました。
収容所の中には、自分のことよりも、他人を優先する人もたくさんいました。極限の状況でも、弱っている人を励(はげ)ましたり、食べ物を分けて与える人もいて、フランクルも生きる力をもらったそうです。こうした人たちは、収容所生活に何か自分なりの意味を見出していたと言います。
苦労の中でも、何か自分なりの意味を見つけようとする人は、苦労が無駄になりません。苦労の意味は、その時は分からなくても、後から理解できることもあります。また、自分のためにというより、身近な人や世の中に役に立つことを使命として考える人は、苦労が心の成長につながると言うのが、フランクルの考えです。

3 名もなき人の生き方が偉大
ここで、うつ病で長年闘病中のAさんの話を紹介しましょう。
Aさんのお父さんは早くに亡くなり、年老いたお母さんと2人で生活しています。兄弟たちはそれぞれに家庭を持ち、今は遠いところに住んでいて、ほとんど会う機会もありません。Aさんは、何で自分だけ貧乏くじを引いてしまい、こんな苦労をしなくてはならないのか不満です。「若い頃から病気で何もできず、いまでも家族に迷惑ばかりかけている。そんな人生に意味などない。」と、いつも考えています。
先日、お母さんがケガで入院することになりました。Aさんの体調も良くなかったのですが、遠方の兄弟を頼ることもできず、入院の付き添いをしました。その時、お母さんの口から、「いつも近くにいてくれて、1番親孝行な子供だと思う。」と、感謝の言葉をもらいました。早くに夫をなくして、心細かったお母さんにとって、Aさんはいつも大きな存在だったと言うのです。
1番お母さんの役に立っていたのは、成功して立派に働いている兄弟たちでなく、病気で何もできない自分だったことを知って、Aさんは嬉しく思いました。自分の人生にも意味があったのだと感じ、気持ちが楽になったそうです。
良心的に生きている人は、気付かないうちに、必ず誰かの役に立っています。フランクルは、「名もなき人の生き方が偉大」と呼びました。何か大きなことを成功させて世の中に貢献する人たちは立派ですが、ささやかに暮らしている名もなき人たちの生き方にも、必ず意味があると言うのです。むしろ、良心を持っているひとりひとりが、世の中を良い方向に進ませているのであり、大きなことを成し遂げる人は、それを代表しているだけのことであるというのが、フランクルの考えです。
どんな時も、人生には意味がある。
あなたを待っている「誰か」がいて、あなたを待っている「何か」がある。
そして、その「何か」や「誰か」のために、あなたにもできることがある。
これは、フランクルが残した多くの言葉の中のひとつです。ここには、フランクルの思いが詰まっています。もしかすると、何かきっかけがあったときに、ふと思い出すことがあるかもしれませんね。