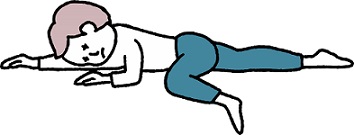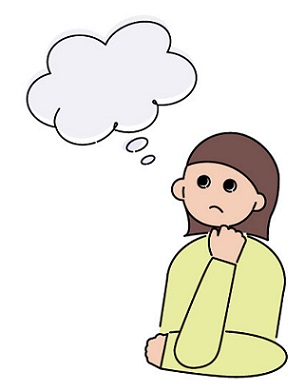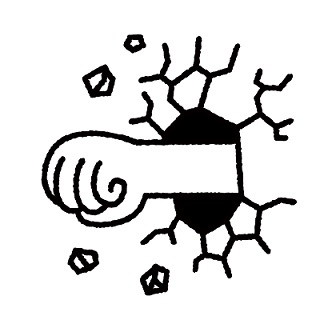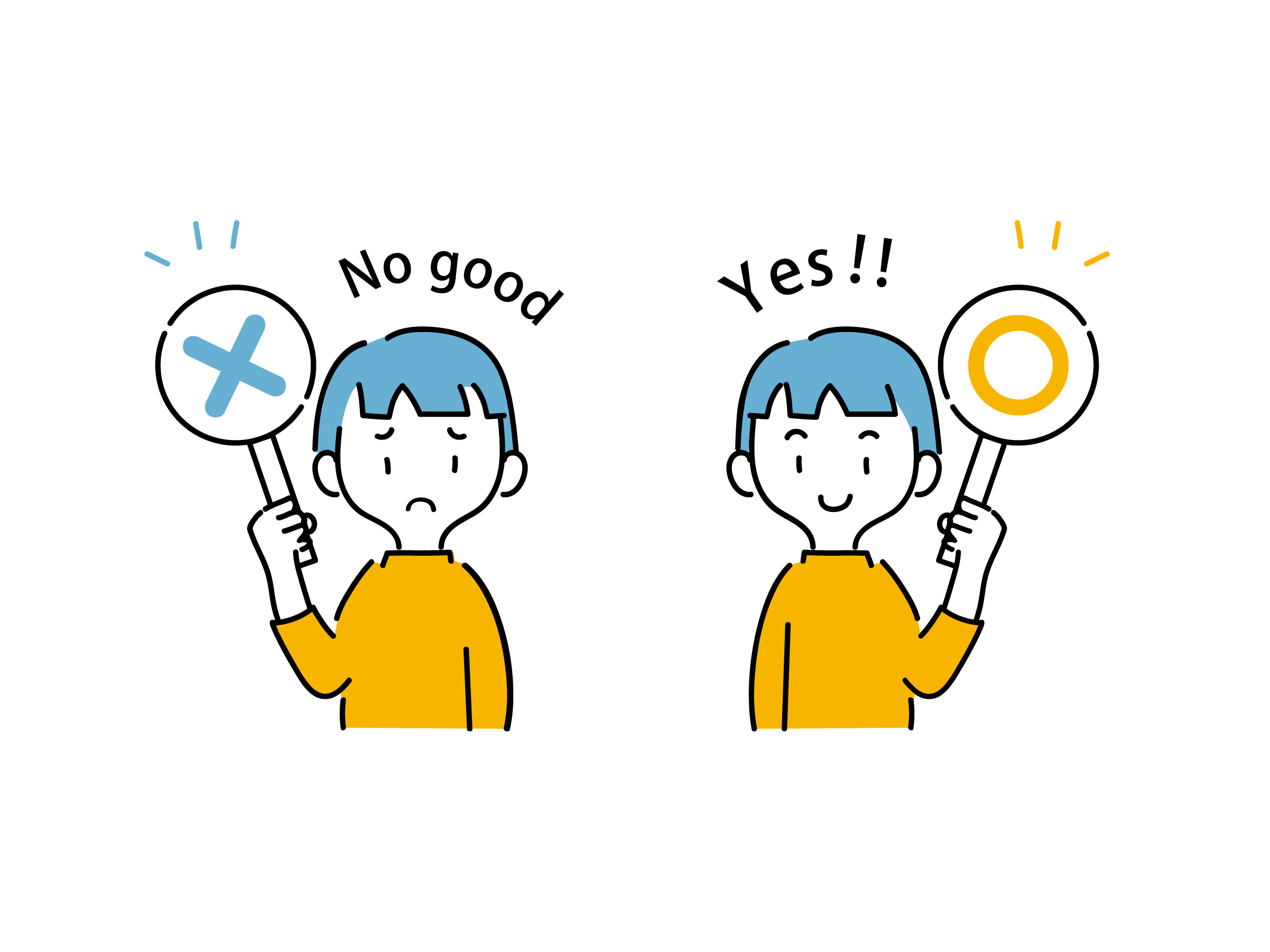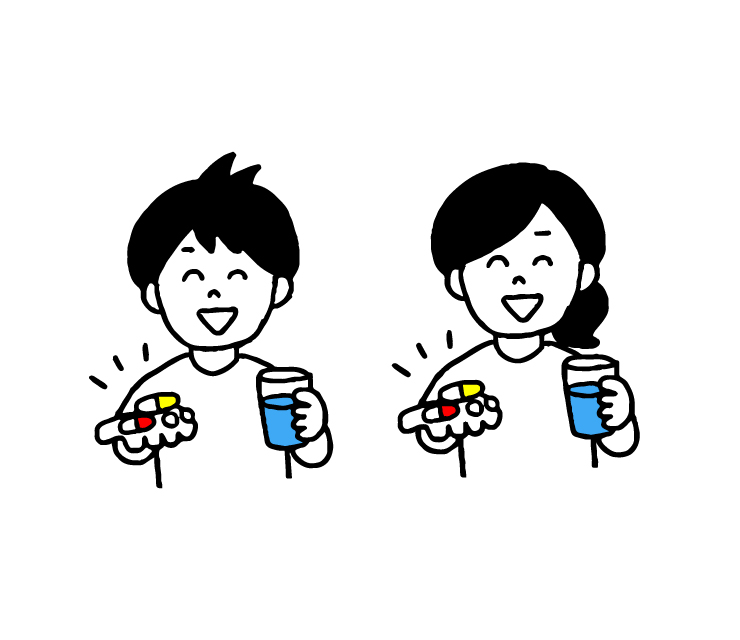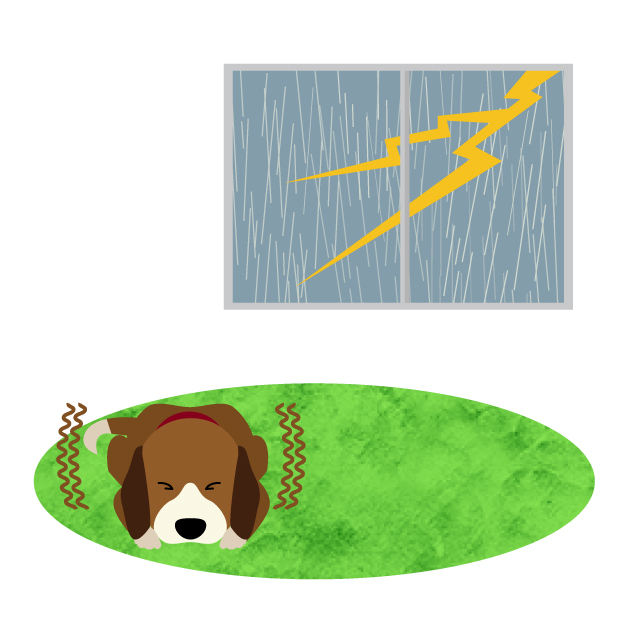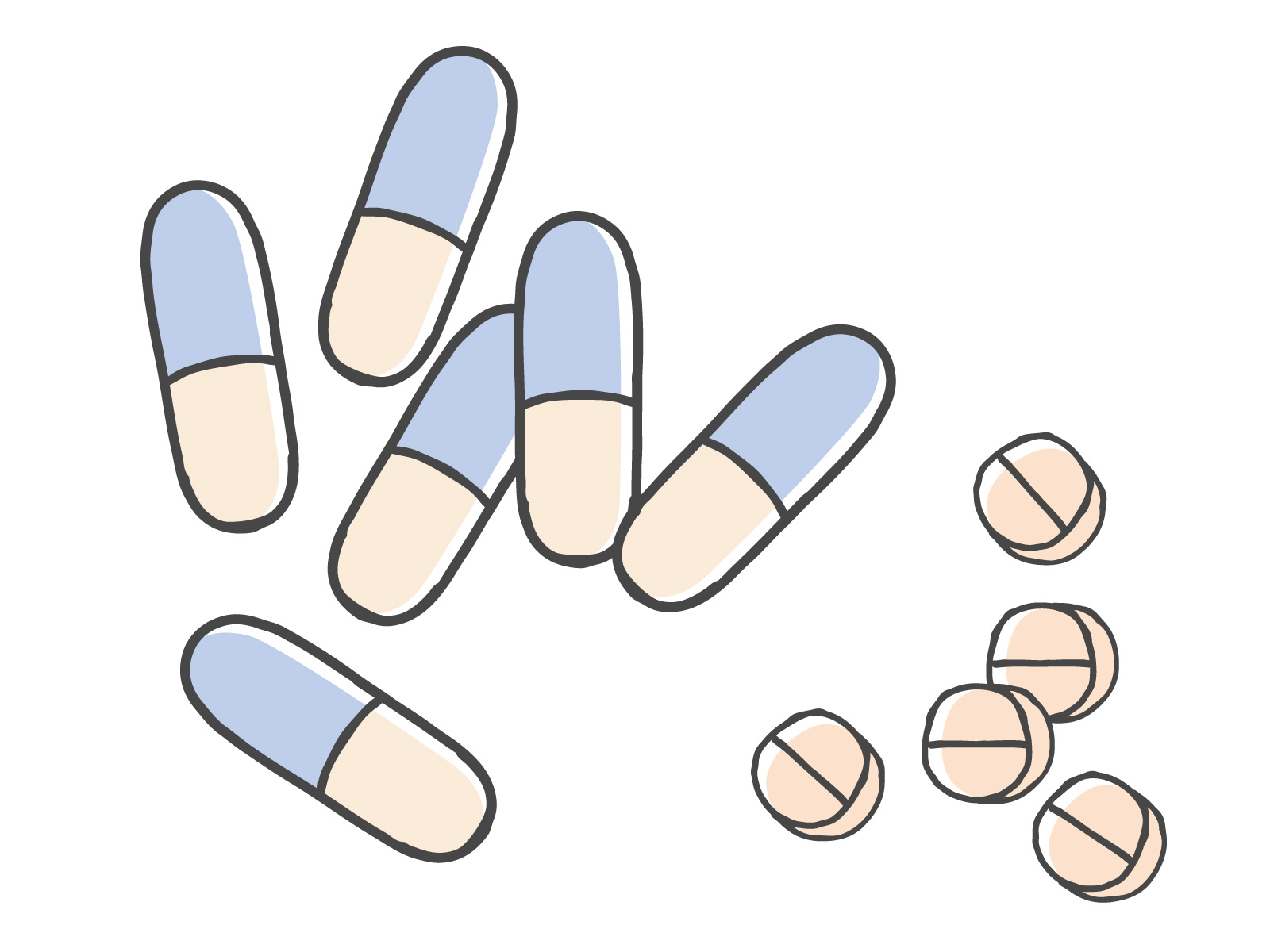うつ病で療養中の人に言ってはいけないこと
心の病気を治すために必要なものは何でしょうか?病院、薬、支えてくれる人など、いろいろなことが思いつきますが、実は最も大切なものは安心感です。
仕事の心配、お金の心配、将来の心配のために、生活に安心感がなければ治るものも治りません。名医とは、何よりも安心感を与えてくれる人とも言えるでしょう。体を維持するためには空気を吸わなくてはならないように、心にとっての空気が安心感です。これがなければ心の自然治癒の力も働きません。
ですから、療養中の人に接する場合、家族、職場の人たちは、何よりも安心感を与えてあげるべきです。ところが、昔から心の病気は、「怠け」と見られてしまう傾向があります。病気で何もできずに苦しんでいるのに、家族や職場の人から、「頑張れ」、「努力しろ」と言われてしまうと、針のむしろの状態になってしまいます。
風邪で熱が出て苦しんでいるのに、「運動したら治るよ」なんて言う人はいません。しかし、心の病気に関しては、言ってはいけないこと、やってはいけないことが普通に行われてしまうのが現実です。良かれと思って、病気の人を苦しめていることが多いのです。
それでは、家族や職場の人はどんなことを言ったり、やったりしてはいけないのでしょうか?今回は、特にうつ病で療養中の人に言ってはいけないこと、やってはいけないことを6つ紹介しましょう。
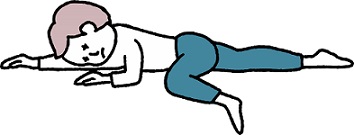
1 説教する
うつ病ほど誤解されやすい病気はありません。元気がないのは、「気の持ちようだ」と思っている人もたくさんいます。確かに、認知療法という、うつ病の人の考え方に働きかける治療があります。
勘違いする人もいますが、認知療法はプラス思考にさせる治療法ではありません。ものの捉え方を心理学では認知と呼び、一部のうつ病の患者さんに、ネガティブな情報ばかりを集めやすい認知の偏りがあることが知られています。これを、客観的な認知を学ぶことで改善させていくものが認知療法です。強制的に考え方を変えるような治療ではありません。
そもそも、うつ病とは、生きるエネルギーが枯れ果ててしまい、プラス思考になれない病気です。「気の持ち方を変えなさい」と説教されてもできる訳がありません。足の骨が折れているのに、「歩きなさい」と言っているようなものです。
2 強要する
うつ病は、現代病の代表になったので、その情報がネットにたくさん溢れています。しかし、根拠のない情報もたくさんあります。病院では、調査で証明されている確実な治療だけを提供しています。
健康保険が使えないものは、一部に効く人がいても、確実性がありません。安易にサプリメントを紹介するなど、「これで治るらしいよ」と不確かなことを強要するのは避けましょう。
3 追い詰める
うつ病は、病気でなく「甘え」だと思っている人がいます。人は追い詰められたら、本気を出すとばかりに、追い詰められたら病気も良くなると勘違いしている人が多いのです。うつ病は生きるエネルギーがなくなっている状態なので、追い詰められても、そのまま何もできないか、逃げ出すことしかできません。
実際によくある話ですが、死にたいと訴える人に向かって、「死ねるものなら死んでみろ」「死ねる勇気があるなら頑張ってみろ」と言う人もいます。それで本当に自殺してしまう人もいます。うつ病は「甘え」でなく、病気です。うつ病の人を追い詰めることは、決してしてはいけません。

4 焦らせる
何カ月も療養していると、家族からこんな言葉が出ることがあります。「いつ治るの?」「学校どうするの?」「そろそろ仕事をしたら」。家族も心配しての言葉ですが、一番焦っているのは病気をしている本人です。
うつ病からの回復には数カ月、人によっては年単位に必要な人もいます。十分に回復しない状態で、焦って仕事や学校に戻れば、すぐに悪くなってしまいます。むしろ、「焦らなくてもいいよ」とブレーキをかけてあげることが大切です。
5 無関心
療養中は、自宅でゆっくりしているのが一番良いのですが、孤独はよくありません。みんなから忘れられてしまうのも辛いことです。
特に、「医者が何とかしてくれるだろう」と、家族が無関心でいるのはよくありません。少しでも言葉をかけてあげたり、短い時間でも話を聞いてあげることが回復への力になります。
6 薬をやめさせる
うつ病は、脳の神経伝達物質であるセロトニンの分泌が少なくなる病気です。抗うつ薬で調整することで回復に向かいます。また、十分な睡眠が必要なため、睡眠薬を使うこともあります。
これらの薬は大きな副作用はなく、もちろん麻薬ではないので、依存症になることもありません。こうした薬は世に出て60年以上が経ちますが、大きな問題なく今に至っています。
ところが、「いつまでも薬に頼っていてはダメになる」、「薬は体に悪い」とそれをやめさせようとする人もいます。薬の処方は、専門家の主治医に任せましょう。
うつ病は気持ちの問題ではありません。生きるエネルギーがなくなり、脳の活動も弱っている状態です。薬で脳の神経伝達物質を調整し、ゆっくり休むことで少しずつ回復していきます。「ダラダラしているから治らない」「好きなことばかりしているから治らない」ということはありません。家族や職場の人は、暖かく見守りながら、自然な回復を待ってあげましょう。そして、安心できるような言葉をかけてあげましょう。
抑圧家庭に育った人の5つの特徴
家庭の中で、子供の成長に悪い影響を与えることと言えば、虐待やネグレクトがよく知られています。しかし、社会的にきちんとした両親がそろっている家庭でも、子供の成長に大きな問題が起きる場合もあります。特に問題となるのは、「~でなくてはならない」という厳しいルールがある家庭です。
例えば、「親が高学歴なので、子供たちも一流大学に入らなくてはならない」といったように、家庭の中に見えない圧力がある場合です。高い理想や目標があり、そのために手を抜くことなく努力し、自分に厳しく、何よりも他人からの評価を気にすることを完全主義と呼びます。「~でなくてはならない」という見えないルールに縛られている家庭は、完全主義の家庭であり、心理学では抑圧家族と呼んでいます。
厳しい抑圧家族に育った人は、親子の情的なつながりが乏しいため、大人になっても心の問題を引きずることがあります。儒教文化の影響のつよい日本は、外国に比べて抑圧家族が多いと言われています。特に高度成長期には、「感情を表に出さず、真面目で勉強ができて一流大学に入る」という良い子のイメージがすべての子供に押し付けられていました。
日本の学歴社会はすでに壊れたとも言われていますが、このような抑圧家族は現在もたくさん残っています。また、親の職業を継がなくてはならない家族、家柄を重視する名家、信仰に熱心な家族、しつけの厳しい家族なども抑圧家族に陥りやすいと言われています。
抑圧家族に育った人は、大人になっても生きづらさを抱えることがあります。今回は、抑圧家庭に育った人の特徴を紹介しましょう。
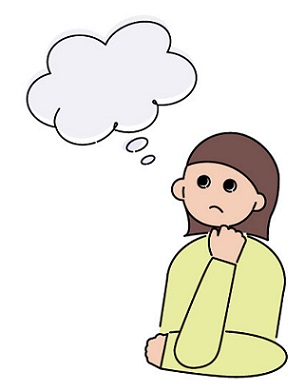
1 いつも虚しい
抑圧家族の中で、最も優先されることは、親の決めたルールを守ることです。ルールを守り、何らかの成果を出さない限りは親に認められません。本来、親からの愛情は、子供に無条件に注がれるものですが、抑圧家族の愛情は条件付きです。
親に甘えることができないまま、感情を抑えて子供時代を過ごします。情的に満たされることなく成長すれば、大人になっても虚しさや孤独感がついて回ることになります。
2 自分に完全さを求める
抑圧家族で育った人は、何をしても、「本当にそれでいいのか?」という内なる声が聞こえるといいます。「もっと良い方法はないのか?」、「もっと別の方法はないのか?」と自問自答して、手を抜くことができません。自分に寛容さがなく、失敗すると自分を責める傾向があります。
また、人にも完全さを求めるために批判的です。人を褒めることが苦手で、失敗を許しません。
3 他人の評価を求める
何か実績を上げない限りは、生きている価値がないと考えます。「生きているだけでもよい」という価値観を持てません。
人からの評価が自分の価値を決めてしまうのです。人から良い評価をもらっている時は順調ですが、少しでも悪い評価をもらうと大きく傷ついて挫折します。
4 人と親密な関係をつくれない
感情を抑えて生きて来たため、人に心を開くことが苦手です。自分の良いところを見せるのは好きですが、弱みは絶対に見せたくありません。人に甘えることも下手です。それなりに友達はいますが、親友と呼べる人はいません。
5 心の病気になりやすい
抑圧家族で育った人は、親譲りの完全主義を引き継ぐことがあります。完全にできないで人から認められないならば、「やらないほうがまし」と課題を先延ばしにして、不登校やひきこもりになるケースがあります。
また、仕事で手を抜くことができずに無理をして、うつ病になることもあるでしょう。
抑圧家族に育った人の生きづらさは、親からの条件的な愛情で育ってきたことが大きな原因です。ただし、この生きづらさは一生続くものではありません。大人になっても、心の温かい友人やパートナーに恵まれると愛情の学び直しはできます。心はいくつになっても成長することができるのです。
そうは言っても、良い出会いに恵まれるのは運でもあり、なかなか難しいことです。ですから、生きづらさを感じているならば、積極的に癒しを求めてみましょう。癒しを感じるものは人それぞれに違うものですが、愛情に触れるので癒しを感じるのです。
特に、自然や動植物は私たちの気持ちを裏切りません。旅行やキャンプで自然に触れたり、動植物を育ててみることはお勧めです。また、マッサージやカウンセリングを受けて見るのも良いでしょう。「こんなことをしてもお金や時間の無駄かな」と思えても、それで気持ちがスッキリしたり、安心を感じるならば、心が癒されている証拠です。無駄の中にも喜びを見つけられるようになったならば、抑圧家族から解放されてきたサインです。
自分から幸せを壊してしまう人
誰でも幸せになりたいと思うのは当たり前のことです。ですから、今回のテーマの「自分から幸せを壊してしまう」というと不思議に感じるかも知れません。
しかし、世の中には、大好きなパートナーや家族、友人を傷つけてしまい、大切な人間関係を自分から壊してしまうという人がいます。自分には幸せになる資格がないという思いが心の底にあり、幸せになることに不安を感じて、その前に自分から壊してしまったり、逃げてしまうのです。
一見矛盾したように見える心の動きですが、子供の頃に親から十分な愛情をもらえず、辛い経験してきたことが影響しています。このような人たちは永遠に幸せになることができないのでしょうか?
今回は、自分から幸せを壊してしまう人の特徴を紹介しましょう。
1 「どうせ私は幸せになれない」という思いが染みついている
子供の頃に親から愛情をもらえなかった人、家庭に居場所がなかった人、孤独や辛い思いをしてきた人、こうした人たちは、「生きていていいんだ」という自己肯定感が育たちません。
「どうせ私は幸せになれない」、「どうせまた辛い目に合う」といった人生への諦めの思いが心に染みついています。安心感がなく育ったため、いつも最悪のことが起きることを想定して生きています。人を心から信用できず、心配症です。
こういった人が幸せを感じるような状況になると、嬉しく思う以上に、「いつ壊れるのだろう?」という不安に襲われます。最悪のことを想定する癖が働いてしまうのです。そして、「この幸せは長続きしない」と思うと、むしろ居心地が悪くなります。
まるで、いつ爆発するか分からない時限爆弾の上に座っているような感じです。楽になるためには、先に進むのをやめるか、逃げるしかありません。
2 我慢のし過ぎで爆発する
親に甘えられず、いつも親の目を気にして生きてきた人は、周りに気を配る癖がついています。相手から嫌われないように、自分の感情を抑え込み、相手に合わせる生活をしてしまうのです。
しかし、我慢は無限にできません。溜まった不満は、怒りとなって爆発します。自暴自棄になって大切な関係を壊してしまう結果になります。

3 見捨てられ不安
普通は、人と仲良くなり、親しくなればなるほど、その関係に安心を感じるものです。ところが、子供の頃に、親や大切な人が突然いなくなる、もしくは裏切られる、といった経験をしている人は違います。
人と親しくなればなるほどに、「この人はいなくなってしまうのではないか?」「裏切られてしまうのではないか?」という不安感に襲われるようになります。これを「見捨てられ不安」と呼びます。
見捨てられ不安がある人は、できるだけ相手と同じ空間にいることを望み、近くにいない場合は、電話やラインで行動をつねに把握しようとします。また、傷つくことをわざと言ってみたり、振り回してみたり、相手の愛情が本物であるか試します。
相手としては、裏切ったわけでもないのに、束縛や意地悪をされているように感じて不愉快になります。不安を解消するための確認行為で、むしろ相手に苦痛を与え、ついには関係が壊れてしまうきっかけになります。
4 不安が高じて自暴自棄になる
見捨てられ不安のある人は、相手のちょっとした言動に、「自分は嫌われている」「迷惑に思われている」と被害妄想のように感じます。
不安のつよい人は、相手の冗談やつよい口調でさえも、拒絶されたと感じます。裏切られることには敏感に反応するため、どんな些細なことでも大切な関係が壊れてしまうサインと捉えてしまうのです。
不安が高じると、自暴自棄になり、お酒を大量に飲んだり、過食をする人もいます。怒りが相手に向けられると、まるで悪魔に取り憑かれたようになり、激怒したり、暴言や吐いたり、物を壊したり、よけい相手に不快な思いをさせる結果になります。
普段大人しい人がヤクザのように変身することもあり、変身していた時に言ったこと、やったことはあまり記憶にありません。これを解離症状と呼びます。見捨てられ不安に耐え切れず、まるで、自分がどこかへ飛んで行ってしまい、代わりに悪魔が体に入り込んで、幸せを壊してしまうのです。
いつも虚しさを抱えて、見捨てられ不安がつよく、解離症状で激しく相手や自分を傷つけてしまう場合は、境界型パーソナリティ症という病気と考えた方が良いでしょう。境界型パーソナリティ症の人は、脳の発達の偏りがあることが多く、生まれつき相手の気持ちを読み取る能力に問題があり、相手の言動に過敏です。
自分から幸せを壊してしまう人は、「誰も私のことを分かってくれない」が口癖です。周りとうまくやろうと一生懸命なのに、不安から空回りしてしまうのです。その上、複雑な心の中を言葉で伝えることも苦手です。
結局、周りを振り回してしまうのですが、「私の大事な人だからこそ、私のことを分かってもらいたい」というのが一番の本音なのです。
それでは、自分から幸せを壊してしまう人が、幸せになるためには、どうしたら良いのでしょうか?一番大切なことは、身近な人が、不幸な生い立ちからくる複雑な心の中を理解してあげることです。
また、自分からも、不安な気持ちを冷静に言葉で伝えるよう努力することも必要でしょう。そのためには、心理カウンセラーなどの専門職の人に手伝ってもらうのも手かも知れません。
複雑な心の状態を理解してもらうことで、生活に安心感を得られるようになれば、自分から幸せを壊すような言動は少しずつ減っていきます。
深刻なうつ病で起こる7つのサイン
うつ病は、少しずつ症状が現れ、本格的な発病に至ります。「怪しいな」と思った時点で早めに病院に行くべきですが、辛いながらもこれまでの通りの生活ができてしまうこともあるので、受診するタイミングが難しいかも知れません。
病院に行くか行かないかを悩んでいるうちに、家族や職場の人に促されてようやく受診するケースも多いのです。うつ病の診断で医療機関にかかっている人は、日本に100万人います。ところが、うつ病であるにも関わらず専門的な医療機関にかかれていない人が、その倍以上の200万人いるという調査結果があります。いわゆる潜在的なうつ病の人たちです。
心には自然治癒の力があります。うつ病になっても、療養できる環境にあれば、病院に行かなくても良くなるケースもあります。しかし、放置しているとどんどん悪くなるケースは、早めに受診するべきでしょう。また、治療を始めるのが遅ければ、回復にも時間がかかってしまいます。
今回は、早めに病院にかかるべき目安の症状を7つ紹介しましょう。これは、うつ病の深刻なサインとも言えるものです。

1 眠れない
うつ病は、セロトニンなどの脳内物質の分泌が減少している状態です。こうした脳内物質の異常は、十分な睡眠によって自然に回復させることができます。ところが、不眠症をいつまでも放置していると、脳内物質の乱れは改善されず、うつ病はどんどん悪くなってしまいます。
眠れない症状がある場合は、早めに病院を受診しましょう。発病してまもない軽い状態ならば、短期間の睡眠薬の服用だけで改善されることもあります。
2 死にたい気持ち
うつ病で最も恐ろしいことは死にたい気持ちが出てくることです。「自分は役に立たない人間だ」、「生きている価値がない」と感じるようになってしまうのです。
こうなると、何かのきっかけで衝動的に行動に移す危険があります。死にたい気持ちがある場合は、早めに病院を受診しましょう。
3 不安や焦りで落ち着かない
うつ病というと、元気がなく静かにしているイメージかと思いますが、不安や焦りがつよく、ソワソワしてジッとしてられないことがあります。
衝動性も高まるため、予想もつかない行動に移ることがあります。これも危険な状態です。
4 気分の大きな変動
気分が落ち込み、うつ病なのかと思っていたら、突然ハイテンションになり、寝ないで活動するケースがあります。お金をたくさん使うようになり、怒りっぽいために周りの人とのトラブルも増えてしまいます。これは、双極性障害の疑いがあります。
以前は躁うつ病と呼ばれていたもので、うつ病とはっきり区別をつけるために双極性障害という名前になりました。双極とは、うつと躁の気分の両極を行ったり来たりするという意味合いがあります。
双極性障害は自然には治りにくい病気です。薬の治療で良くなるので、早めに病院に相談しましょう。

5 被害妄想
うつ病でも被害妄想が現れることあります。「みんなに迷惑をかけている」「自分は罪深い人間だ」「必要のない人間だ」と激しく思い込み、ついには自分の命を絶とうとすることもあります。
また、妄想の病気である統合失調症がうつ病から始まることもあります。正確に言うと、統合失調症の初期症状としてうつ気分が出ることが多いのです。気分の落ち込みとともに、幻聴や妄想などの症状も現れる場合は、統合失調症の疑いもあります。
双極性障害と同じように、自然には治りにくい病気ですので、早めに受診しましょう。やはり薬の治療で良くなります。
6 お酒がどんどん増える
お酒は、脳内のドーパミンという物質を増やし、一時的にうつ気分を改善させます。うつ病が軽いうちは、飲酒でごまかしながら生活をする人もいます。
しかし、お酒は依存性のつよい物質です。うつ気分を和らげるために飲んでいると、少しずつ量が増えるようになります。1日当たり、男性は500㎖ビール2本まで、女性は1本までがリスクの少ない量ですが、これを越えるような場合は危険なサインです。うつ病だけでなく、アルコール依存症や肝臓病の問題まで抱えるようになります。
7 経済的な援助が必要
症状ではありませんが、経済的な問題はうつ病の回復に大きな影響を与えます。うつ病は、こじらせると働けなくなる病気であるため、生活費などの経済的な問題が起きてしまいます。
お金の問題がストレスになり、それがうつ病を悪くさせるという悪循環にもつながるのです。調査によれば、自分から死を選んでしまう一番の原因はお金の問題と言われています。
医療機関を通して、傷病手当、自立支援医療、障害年金などの経済的な補償を受けたり、障害手帳で福祉を利用することもできます。お金の問題が重くのしかかる前に病院に相談しましょう。
一言でうつ病と言っても、その人の性格も影響するため、現れる症状は人によって様々です。ここに紹介した症状は、早めに助けを求めなくてはいけない危険なサインです。「怪しいな」と思ったら、すぐに病院に相談しましょう。うつ病は、早くに治療すれば、それだけ早く治ります。
つらい時にやってはいけない6つの習慣
「思ったことがうまく行かない」、「心配事が解決しない」、「挫折して心が折れている」、このように心がつらい時、あなたはどのように過ごしますか?本音ではゆっくり休みたいのですが、「怠けているのが原因だ」と、よけいに自分を追い詰めてしまうことはないでしょうか?また、「ダメな人間だ」と落ち込んで、自分を責めていないでしょうか?
医学的・心理学的には、心がつらく弱っている時に、無理やり自分を奮い立たせるようなことはやるべきではありません。また、その逆に自分を責めてしまうことも良くありません。
むしろ、最も必要なことは、体と心を休め、誰かに助けを求めることです。自分はつよい人間だと過信して、元気な時にやっていた習慣をつらい時にやってしまうと、よけいに自分を苦しめ、害になってしまうことがあるのです。
今回は、つらい時についやりがちだけれども、本当はやってはいけない6つの習慣を紹介しましょう。
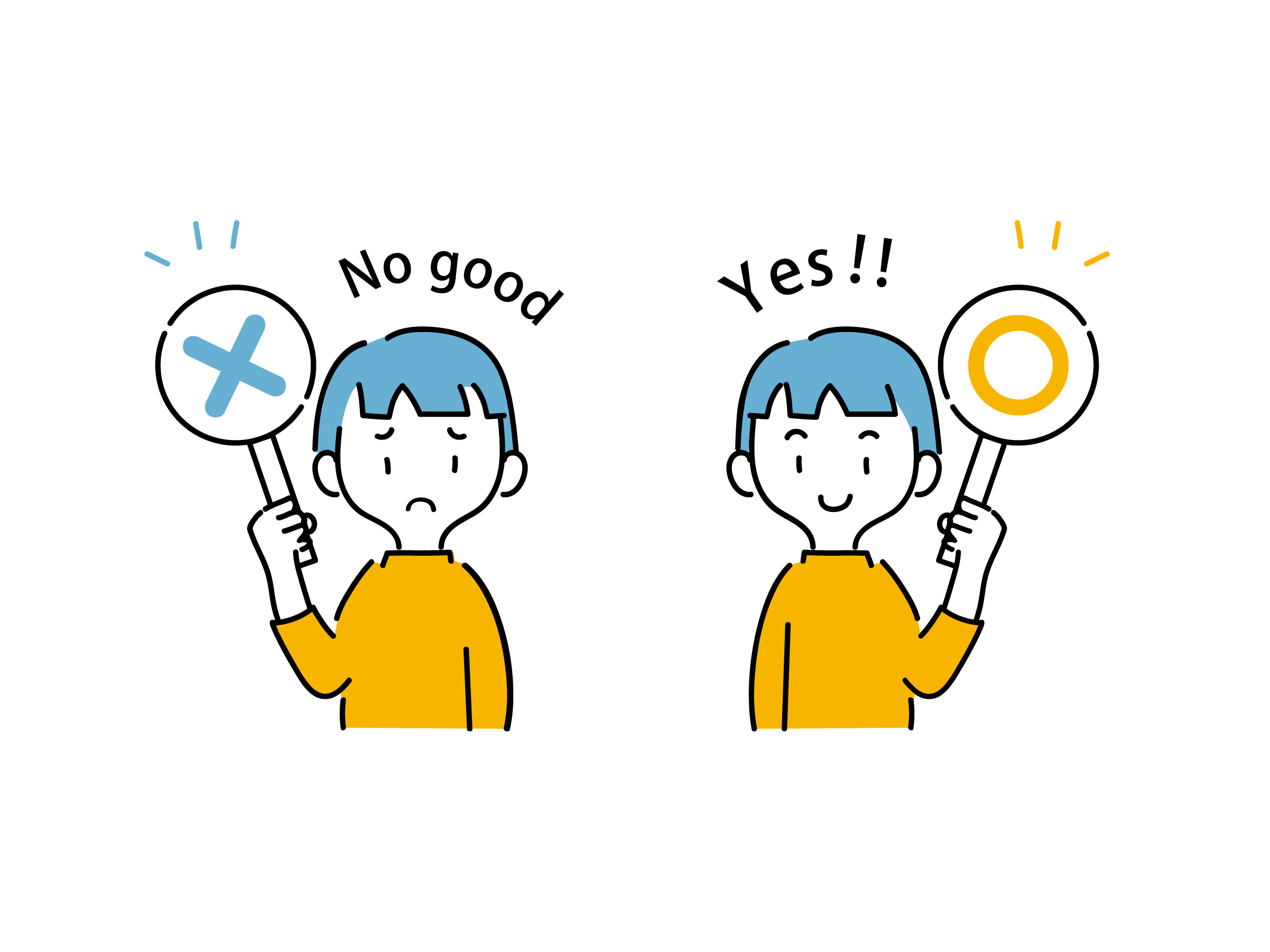
1 うまくいっている人と比べる
心がつらい時に、癒しを求めて手軽に見るのがSNSです。しかし、目につくのは、同年代でも輝いている人、活躍している人、成功している人の姿です。見れば見るほどに、いまの自分が情けなく感じてしまい、つらい気持ちがさらに悪化するでしょう。
しかし、あなたが画面で見ている成功者は、世の中の0.1%にも満たない極少数の人達なのです。自己顕示欲のために、広い交友関係や稼いだお金を自慢する人もたくさんいます。このような人たちと今の自分と比べても何の得もありません。また、この人たち中でどれだけが、数年後も同じように輝き続けていられるでしょうか?
つらい時は、うまく行っている人と比べるべきではありません。SNS断ちとまでは言いませんが、少なくとも自分の成功を自慢する人のサイトには近寄らないようにしましょう。
2 過去を振り返る
比べる対象は、過去の自分の場合もあります。「あの頃は楽しかった」、「あの頃に戻りたい」と、過去の自分の方が良かったと感じやすくなります。
つらい時は、過去の思い出が実際よりも良く見えてしまうものです。どんなに努力しても時間を戻すことはできません。過去の自分と今の自分を比べるのはやめましょう。
3 できないことに執着する
「年収を倍にする」「資格をとる」など、常に何かの目標を持って生活している人も多いことでしょう。しかし、目標を達成できずにつらい時は、目標を修正したり、諦めることも大切です。人生の最終的なゴールは幸せになることです。
目標とは、幸せになるためにその時々で一時的に設定していくものなのです。もし、実現させようとすることが苦痛になり、幸せにつながらないと分かったならば、すぐに修正するのが賢い生き方でしょう。いつまでも執着して、むしろ不幸になってしまうならば、それは本来の目標のもつ価値を失っています。
「諦めは心の養生(ようじょう)」ということわざをご存知でしょうか。失敗や運の悪さをいつまでも悔やまないで、諦めることで精神状態は自然に回復するという意味です。つらい時は、目標から一旦離れてみることが大切なのです。

4 わざと忙しくする
つらい時、そのことを考えないように、無理やり予定を入れて忙しくすることがあります。しかし、一息ついた時に思い出してしまい、疲れと重なると、余計に苦しくなってしまうことの方が多いでしょう。
つらい時は無理に忙しくせずに、ゆっくり休むか、好きなことをした方が良いのです。心には自然に治癒していく力が備わっています。体をいたわり、休ませてあげることで、心のつらさも自然と和らぐようになります。
5 思い切ったことをする
破産に追い込まれる人の中には、最終的に詐欺にあって全財産を失っている人が多いという調査結果があります。大きな損失をすると、あわてて埋め合わせしようとして、詐欺に引っかかってしまうのです。つらい時は、正常な思考が働きません。普段ならば騙されていると気づくような誘いも、理性が働かずにパっと飛びついてしまうことがあるのです。
つらい時には、そこから逃れるために思い切った行動をとりがちです。一発逆転を狙った大きな決断には慎重になりましょう。経験のないような新しい仕事や事業などにチャレンジすることも避けた方が良いかも知れません。特に大きなお金を動かすような決断は禁物です。
6 お酒を飲んでごまかす
お酒には、脳のドーパミン分泌を増やす力があり、不安がとれて気分が大きくなります。一時的ですが、お酒はつらいことから解放してくれるのです。
毎日の量をきちんと自分で管理できていれば良いのですが、それにばかりに頼っていると、量がどんどん増えて行くことがあります。気が付いたらアルコール依存症になっていた、ということがないように、お酒だけで気分をごまかすことは避けましょう。
心がつらい時こそ、自分を大切にしましょう。これ以上無理をしないで、心と体を休めることがお薦めです。信頼できる人がいるならば、助けを求めてみるのも手でしょう。
水に溺れた時は、あわててもがくよりも、むしろ体の力を抜くとスーッと自然に浮いてくるものです。つらい気持ちも同じです。何とかしようと無理をするよりも、時間が解決してくれてことがあるかも知れません。
うつ病の時の気持ち
どんな病気でも、経験していない人には100%理解することはできません。うつ病も、なった人にしか分からない心の世界があります。うつ病の人に向かって、元気がないようなので、「気の持ち方次第だよ」「元気を出しなよ」と励ましてあげて、逆に傷つけてしまうこともあります。
元気づけられて傷つくというのも不思議に思えますが、うつ病は怠けでも単なる疲れでもありません。病気のために考え方を変えたり、元気を出すことができない状態です。
このような人に「元気を出しなよ」と言っても、「できないことをやれ」と言われていようで、受け止め切れません。例えば、足の骨が折れて困っている人に、「がんばって走ってごらんよ」と言っているようなものです。
うつ病は、生きるエネルギーが枯れ果てた状態です。生きるエネルギーとは、愛情、楽しみ、喜びなどの情緒的なエネルギーのことです。
頑張ること、楽しむこと、休むこと、こうしたリズムを繰り返すことで、保つことができます。ところが、休むことなく無理を続けたり、心配が絶えない状況が長く続くと、エネルギーは消耗するだけです。
ついに枯れ果てた状態になると、健康の人からは想像できないようなネガティブな心理状態になってしまうのです。
うつ病の時の心の状態は複雑です。今回は、うつ病がどのようなものかを少しでも理解できるように、その心の状態を具体的に紹介しましょう。

1 朝から疲れている
朝から疲れを感じるのがうつ病です。目覚めた時から、会社から帰って疲れ果てているような状態が始まるのです。
そもそも眠りも浅く、悪い夢ばかりを見ます。朝も早くから目覚め、やらなくてはいけないことが頭の中でグルグル回っています。起きなくてはならない時間になっても、気持ちも体も重く、ふとんから出られません。1日中ずっとふとんの中で過ごしたい気分です。
2 何も楽しめない
これまで楽しめていたことに、全く面白みがなくなります。好きだった音楽や動画に感動しなくなり、趣味をするのも面倒なだけです。電話にも、部屋のインターフォンにも出たくありません。人と関わるのが煩わしくなり、誰からも干渉されずに一人で過ごしたいと思うようになります。
食事もおいしくなく、何を食べても同じ味です。おしゃれにも関心がいきません。いつも同じ服でも気にならないのです。風呂に入るとサッパリするので大好きだったのに、1週間でも平気でシャワーも浴びずに過ごせるようになります。
3 自己肯定感がなくなる
それまでがんばってきたのに、過去の実績はすべて価値を失ってしまい、何もできないダメな人間だと感じるのがうつ病です。
友人、職場の人、SNSやテレビの人など、目に入る人は誰でも自分よりも輝いて見えてしまい、自分が劣っているように見えるのです。自分は、価値のない人間であり、生きていてもみんなの邪魔になるだけだと感じることもあります。
4 希望をもてない
どうやっても今の状況は良くならないと感じます。一つ問題があるだけで、すべてがダメだと思います。何かの心配事がいつも頭の中をグルグル回っています。
何をしてもどうせ失敗すると感じるので、何にも希望が持てません。そもそも何のために生きるのか、生きる目的が分からなくなります。

5 後悔してばかり
失敗したことが頭から離れません。「あんなことを言わなければ良かった」、「どうしてあんなことをしてしまったのだろう」と自分を責めてばかりいます。
今ではどうにもならないような、ずいぶん前の失敗までも頭に浮かんできます。考えても仕方がないのは分かっていても、後悔の思いから抜けられず、自分を責め続けるのがうつ病です。
6 ゲームやネットがやめられない
時間はどんどん過ぎていくのに、一度始めたゲームやネットがやめられません。「やめなくては」と思っていても、単調な繰り返し動作の中に安心感を感じます。楽しんでやっているというよりも、気持ちの逃げ場になっているのです。
ようやく抜け出せても、今度はやり過ぎて無駄な時間を過ごしてしまったことに後悔し、自分を責めてしまいます。これの繰り返しです。
ネット通販にハマる人もいます。同じようなものを何個も買ったり、せっかく買ったのに届いた箱を開けないでそのままの場合もあります。欲しい物があるというよりも、買う行為が止まらないのです。
7 いなくなりたい
仕事でも、家庭でも、何かに責任を持つことができなくなります。無理をしてやろうとするとイライラして、怒りが湧いてきたり、自分が壊れそうになります。自然に涙が出ることもあります。できれば、すべての責任を放り投げて、どこかに逃げてしまいたいです。
さらに辛くなると、過去に戻って人生をやり直したいと思います。それができないのなら、癌や交通事故で死にたいと思います。人生をリセットしたいと思うのです。せめて知っている人のいない世界に行きたいと感じます。
うつ病の心の状態を紹介しました。人は、生きるエネルギーが枯れ果てるとこのようなネガティブな心の状態になります。こうした時は、エネルギーの充電が必要です。
具体的には、社会的な責任を免除してもらい、ゆっくり休むことです。充電のポイントは十分な睡眠と食事をとることです。ところが、度を越えて消耗していると、不眠症と食欲不振が症状として現れます。こうなると薬の治療が必要です。早めに精神科で相談してみましょう。
失恋うつ病って?
失恋をしたり、パートナーに浮気をされたら、誰でも元気がなくなります。しかし、何カ月間も気持ちが沈んだままで、仕事などの日常生活に支障が出る場合、これはうつ病かも知れません。
「たかが失恋でうつ病になるなんて」と驚かれる人もいるかと思いますが、失恋や浮気をされた後の不調で精神科クリニックを受診する人はたくさんいます。特に女性に多く、思春期からあらゆる年代の人に見られます。
また、クリニックを受診しても、原因が失恋とは言い出しにくいので、担当医には仕事が忙しいとだけ訴える人がいます。そのために過労よるうつ病と診断されてしまうのですが、後から良く聞いてみると、うつ病の本当のきっかけは失恋だったというのです。
うつ病は、気分の落ち込み、気力の低下などの症状が2週間以上続くのが特徴です。失恋や浮気をされたことが引き金のうつ病の場合、いくつか特徴的な症状もあります。正式な病名ではありませんが、これをまとめて「失恋うつ病」と呼ぶことがあります。今回は、失恋うつ病のサインを紹介しましょう。

1 自分を責めてしまう
心から愛し、信じていた人から裏切られることは、喪失体験でもあり、トラウマにもなります。受け止め切れない思いは、怒りとなり心の中で渦を巻きます。怒りで相手を責められたら少しは楽なのですが、往々にして怒りの矛先は自分に向かいます。
「自分はダメな人間だ」と、心の中で自分を傷つけてしまうのです。自信を失い、人として価値がないとも感じてしまいます。
浮気をされた妻の場合、「浮気を許すのが良い妻である」という考えから、怒りを心の中に抑え込んでしまうことがあります。マイナスの感情が外へ出て行かずに、心の中でくすぶってしまい、これがうつ病の原因になります。
うつ病を治すためには、夫婦で話し合いの場を設けて、傷ついた心を夫に理解してもらい、心からの謝罪をしてもらう必要があります。
2 過去にとらわれる
「何でこうなったのだろう。」「あの時こうしておけばよかった。」と、頭の中はいつも後悔することを考えています。別れた相手と行った場所、見た映画、食事をした店など、いっしょに過ごした出来事を思い出して苦しくなります。
思い切って、相手に関するものをすべて処分したとしても、何かの機会に思い出して、不快な気持ちになります。別れた時の場面が何度もフラッシュバックすることもあります。
仕事を増やしたり、体を動かすなど、生活を忙しくして思い出さないように努力する人もいますが、それでも、仕事終わり、入浴中、眠る前など、フッと力を抜いた時には相手のことが浮かんできます。
3 人生にネガティブになる
今までの人生、そして未来までも、人生すべてに価値を失います。何のために生きて来たのか、何のために生きているのかが分からなくなるのです。心の視野が狭くなり、他の生き方を考えることができなくなります。
友人から、「新しい出会いがあるよ」と慰められても心に響きません。最悪の場合、将来に一切の希望が見つけられず、自分で命を絶つ人もいます。実は、20代女性の自殺の原因の1位は失恋うつ病なのです。

4 息苦しい、胸が痛い、涙がでる
胸が重く、息をしづらい感じがします。心臓が悪いのかと思い、内科で診てもらっても異常はないと言われます。何かのきっかけで過去を思い出して過呼吸発作を起こす人もいます。仕事中などに、突然涙が出る人もいます。
5 眠れない
寝ようとすると、別れた相手のことを考えてしまい、なかなか寝付けません。夢の中にも相手が出てくることがあります。特に、別れたはずの相手と仲良くしている夢を見ることが多くあります。慌てて目を覚まして、現実を悟ると苦しみがさらに増します。不眠症は、うつ病からの回復を遅らせます。2週間以上も十分に眠れない状況が続く場合は、病院を受診しましょう。
ただし、同じように別れた人が夢に出ても、相手が別の人とつきあっているようでしたら、むしろ、自分の気持ちに踏ん切り(ふんぎり)がついている証拠です。
6 食欲の問題
食欲が落ちて、食事の量が減ります。体重が減る人もいます。体力を失うことは、うつ病からの回復を遅らせてしまいます。不眠症と同様に、体重が何キロも減ってしまう場合は病院を受診しましょう。
逆に食べることで気持ちを発散して過食になる人もいます。過食が一時的なら良いのですが、体重が増えることを恐れて食べたものを吐くようになり、過食嘔吐が習慣になるケースもあります。これを摂食障害と呼びます。失恋をきっかけに摂食障害になってしまう人もいるのです。
失恋うつ病は、睡眠と食事がきちんととれていれば、少しずつ自然に改善し、半年以内に本来の自分を取り戻せます。しかし、つよいトラウマとなって、その後の人生に悪い影響を与えてしまうこともあります。
特に、一途に人に尽くす人、何よりも恋愛を優先する人、潔癖で完全主義の傾向がある人、などは失恋で大きなダメージを受けると言われています。
心には自然に回復する力があります。体のケガが、無理をしなければ自然に治るのと同じように、心にも自然治癒の力が働きます。そのためには安心感のある生活が必要です。
家族や友人の支えの中で無理をしないことが大切です。相手を忘れるために生活を忙しくするよりは、ゆっくり休養をとったり、マッサージを受けるなど、体を大切にするようにしましょう。焦ってすぐに次の恋愛に進むのも良くありません。十分に回復しないままに同じことを繰り返して、よけいに状態が悪くなるケースもあります。
2週間以上も不眠症や食欲不振が続く場合や、何か月たっても良くなる実感がない場合は、精神科を受診してみましょう。体の症状がない場合は、心理カウンセリングも効果があります。
愛着障害を乗り越えているサイン
心理学では親子の情的な絆を愛着と呼びます。ところが、子供の頃に、親との突然の別れがあったり、親から冷たい仕打ちを受け続けると、愛着が育たちません。
これは、心の成長にも影響を与えます。そのまま、誰からも助けがないままに大人になると、心はいつまでも傷つきやすく、自信を持てないままになります。これを大人の愛着障害と呼びます。
愛着障害の人は、低い自己肯定感、劣等感があり、人間関係の距離感が分からないことで辛い思いをします。特に、人間関係の作り方や保ち方が分からないために、社会に出てから様々なトラブルが起きてしまいます。
愛着障害を持つ人は、過去の出来事に振り回されているので、何か希望に向かっていく人生というより、過去の問題を乗り越えて行く人生です。良いパートナーに出会えてもけんかばかりしてしまう、人間関係で失敗して仕事のチャンスを逃してしまう、何をやっても自信が持てない、など、当たり前の幸せがつかめません。
友人や同僚とは、出発点が違うため、周りはどんどん先へ行ってしまうように感じます。また、「普通の人ができることができない」、「できないことを分かってもらえない」という悩みがいつもついて回ります。
しかし、いつまでもこのままではありません。ほとんどの人は、時間をかけながら少しずつ愛着の問題を乗り越えることができています。安心できる場所、親切な人との出会い、仕事で評価される喜び、子育て、ペットや植物を育てること、没頭できる趣味など、プラスになる出会いを通して、過去の問題は少しずつ癒されて行きます。
大人の愛着障害のゴールはどこにあるのでしょうか。今回は、愛着障害が改善されて、親に愛されてこなかったことを乗り越えられたサインを紹介しましょう。

1 過去を思い出しても動揺しない
過去の親子関係が清算されていないと、親のことを思い出すたびに、憎しみや悲しみが湧いてきて、語り出すと感情的になります。しかし、心には、心の傷を修復する力、悪い思い出を解毒する力が自然に備わっています。
安心、楽しみ、喜びがあると、毒のような過去の思い出は解毒されて、苦しみの伴わない思い出になります。そうなると、親のことを思い出しても動揺しなくなり、浮かんでも来なくなります。
2 過去の辛かったことを冷静に語れる
辛い過去の出来事は、人に知られたくありません。生い立ちを聞かれても、本当のことは言えずに隠してしまいます。
「どうせ分かってもらえない」「恥ずかしい」、「変に思われるだろう」といった思いが、過去の出来事を言葉にすることを邪魔します。また、理解してくれる人に話し始めても、冷静に話せず感情的になってしまい、まるで親に向かって文句を言っているような口調になってしまいます。
しかし、過去の出来事が心の中で解毒されていると、動揺せずに言葉に出して話せるようになります。例えば、友人やカウンセラーに過去のことを聞かれて、自分の経験を自然に話せていたら、それはすでに親子の関係が清算されているサインです。
3 親を理想化していない
愛着の問題は、親が拒絶的な場合に起こると考えがちですが、過保護や過干渉の場合も起こります。過保護や過干渉とは、親は子供のことが心配だと言いながら、実際は、自分の理想を子供に押し付けているだけの場合が多いのです。
親は、子供が自分の思い通りになる場合だけに愛情を注ぐことをするため、そこには本来の愛着は築かれません。子供は、いくつになっても親と反対の意見を言えず、親子関係は支配的な上下関係になっていることがあります。
ところが、このような状況で育った子供の中には、「自分の親はすばらしい親だ」と親を理想化していることも多いのです。
しかし、人はいつまでも親に守られて生きていけないので、このような親子関係は永遠に続きません。挫折体験や、友人やパートナーからよい影響を受けることを通して、親の間違いに気づく時が必ず来ます。
その後、「親も同じ悩みや弱さをもつ人間だ」と感じられるようになれたら良いでしょう。これも、愛着の問題を乗り越えたサインの1つです。
4 信頼できる人がいる
大人の愛着障害で大きな問題の1つは、人を心から信頼できないことです。親しくしてくれる人がいると、「いつ裏切られるのだろう」と疑いをもって見てしまいます。
親しくなればなるほど、疑いの思いは大きくなるという矛盾の中にいます。本当に信頼してもよいのか、わざと嫌われるようなことをして、相手を試すこともあります。
しかし、例え1人でも信頼できる人ができたならば、または、いっしょにいて安心できるような人ができたならば、愛着の問題を乗り越えて来たということです。
家族でも、友人でも、カウンセラーでも、世の中に1人でも良いので、疑うことなく何でも話せる人がいるならば、辛かった過去を乗り越えたサインなのです。

恨みをなくすための3つの方法
なかなか忘れられない悪い思い出はありませんか?忘れたくても自然と浮かんできて、何をしても気持ちを紛らわすことができない思い出です。
特に、信じていた人や職場に裏切られた思い出は、つよい恨みとなって心に残ります。親や親友などに対して、信じ愛し、期待していたのに、裏切られた時の辛さは心に深く刻まれるのです。この気持ちを解消するにはどうしたら良いのでしょうか?
復讐が唯一の解消法と考える人がいます。辛ければ辛いほどに「思い知らせてやりたい」と感じるのは当然なことです。それだけでなく、復讐すれば他の犠牲者も救うことができるので復讐は正当化されます。
しかし、時間が経つにつれて、復讐するべきでないという心も湧いて来るのが自然です。復讐は本質的な解決方法ではなく、復讐すれば、こちらも憎い相手と同じレベルの低い人間に落ちてしまうことに気づくからです。
それよりも、恨みの感情から解放されて、より良い人生を生きたいと思うようになります。結局、相手を許すようになることが、自分を苦しみから解放する最善の方法であることに気づくようになるのです。
16世紀イギリスの哲学者・フランシス・ベーコンは、「復讐する時、恨みの相手と同じレベルである。しかし、許す時、恨みの相手よりも上にある。」と言いました。しかし、頭では、許すことがより良いことである分かっていても、気持ちは納得しません。
恨みや怒りを無理やり心の底に押し込んでしまうと、心や体がおかしくなることがあります。結局、恨みの気持ちは、心の外に出しても報われないし、中に押し込んでも苦しくなる、とても厄介な存在なのです。
では、このような恨みや怒りを自然に解消するためには、どうしたら良いのでしょうか?今回は、悪い思い出を消して、恨みをなくすための3つの方法を紹介しましょう。

1 人に話す
気持ちを言葉にすることは、心に溜まっている悪い感情を外に出す効果があります。これを心理学では「カタルシス」と呼びます。同じ体験をもつ人と話し合ったり、カウンセラーなどの理解してくれる人に話すことで、悪い思い出や恨みの感情を薄めることができます。
2 今の生活に集中する
人間の脳は、コンピューターのように一字一句正確に記憶しません。感情に左右され、無意識のうちに記憶が書き換えられることがあります。これは脳がコンピューターよりも劣っているという意味ではありません。
脳は自分を守るために、記憶を都合よく書き換える作業ができるのです。心が安定していると、悪い記憶は少しずつ消去されていき、害がなくなります。大きなトラウマを受けても、その後に安心できる生活を送っていれば、トラウマは自然に消えていきます。いまの生活に満足していると、悪い思い出は自然に書き換えられ、恨みも消えていくのです。脳はコンピューターよりもはるかに優秀です。
ところが、心が不安定で過去に執着してばかりいると、悪い記憶は余分なものまで付け足されて、もっと悪い記憶に更新されてしまうことがあります。なかったことがあったことと記憶され、恨みの気持ちが高まってしまうこともあるのです。過去にとらわれてばかりいると、悪い思い出はもっと悪いものになってしまいます。
「幸福に生きることが最高の復讐である。」というスペインのことわざがあります。脳の仕組みから考えると、幸せに向かって今を大切に生きていくことが、悪い思い出を消すための最善の方法なのです。
3 恨みを社会に役立つ方向に向ける
親から虐待された人が、親を恨むのは当然のことです。しかし、自分以外の子供たちには、同じような辛い思いを経験させたくないと感じて、大人になってから子供たちを守るボランティアに参加する人もいます。
親を恨む気持ちを、子供を守るためのエネルギーに変えているのです。大切な家族を交通事故で亡くしても、加害者を恨む気持ちをエネルギーに変えて、交通事故撲滅のための運動をしている人もいます。これらは、恨みや怒りのエネルギーを、社会に役立つ方向に向けて発散させているのです。社会貢献が人から喜ばれると、そこに自分の新しい価値をみつけることができます。また、そこから新しい出会いも生まれるでしょう。生活には充実感が生まれ、心の成長も期待できます。
このように、辛い気持ちを社会に貢献するエネルギーに転換することを、心理学では「昇華」と呼んでいます。長い時間と大変なエネルギーが必要なことですが、辛い気持ちから解放されるための理想的な方法と考えられています。

いまを大切に生きていると、過去の辛い思い出は、自然に毒が薄まり、心の中にあっても受け入れられるレベルになります。人によっては、加害者の立場に共感できるようにもなるでしょう。例えば、親に辛い思いをさせられたのならば、「親自身も子供の頃に酷い目に合っていた」「親は精神的な障害を抱えていた」と、親の仕打ちを自分なりに理解できるようになります。
悪い思い出を受け入れるまでには、大きな愛情やエネルギーが必要なことです。恨みがつよいほどに時間もかかります。しかし、そこに到達できたら、大きな満足や解放感を手に入れることができます。これは人として大きく成長した証拠でもあります。誰からも褒められることはありませんが、人生の大きな試練を乗り越えたと誇ることができるでしょう。
ただし、実際に人を傷つけようとしたり、物を壊したり、恨みの気持ちが自分で制御できないくらいつよい場合は、うつ病、双極性障害、統合失調症などの精神疾患の可能性も考えられます。このような場合は、精神科に相談してみましょう。
子供の頃のトラウマがまだ完全に癒えていない6つのサイン
子供の頃に、親からひどい仕打ちを受けたり、学校でいじめを受けると、心に傷跡が残ります。これをトラウマと呼びます。軽い場合は、時間と共に自然に癒されますが、重症な場合はすぐには消えません。親やクラスメートからの、深刻な暴力、否定、無視が長い期間にわたって続いた場合、大人になってもトラウマが残ることがあります。
子供の頃に大きなケガを負うと、大人になっても何かのきっかけで痛みが走るように、トラウマも生活の様々な場面で生きづらさとして現れることがあります。自分では、もう辛いことはお別れできたと思っていても、トラウマが治りきっていないことがあるのです。
そこで今回は、子供の頃のトラウマがまだ完全に癒えていないサインを6つ紹介します。
1 自己評価が低い
「自分は生まれて来なければ良かった」と感じており、生きていることに罪悪感を持っています。人の好意にも心を開けません。人前で自分を出すことができず、目立つことを避けてしまいます。「どうせダメだから」と新しいことにチャレンジできません。
2 孤独
人への恐怖、不安、怒りが残っており、基本的に人を信頼できません。人と接しているとイライラや怒りを感じることが多く、人づき合いが苦手です。人との関りを避けてしまい、いつも孤独を感じています。
3 現実感がない
現実がぼんやりして、目が覚めていても夢の中にいるようです。自分と現実に壁があると表現する人もいます。また、心と体が離れてしまい、自分を外から見ていることもあります。これを離人感と呼び、時間がすすむのを遅く感じる人もいます。
4 集中できない
親の機嫌を気にして子供時代を過ごしていると、脳が周囲の状況にすぐに反応できるように、常に警戒している覚醒状態となります。すると、眠りは浅くなり、ちょっとした物音で目が覚めてしまいます。日中は頭にモヤがかかったようになり、集中できません。これを脳に霧がかかっているという意味で「ブレイン・フォグ」と呼びます。
5 自己破壊行為
ベトナム戦争を描いたアカデミー賞作品の「ディア・ハンター」では、戦争でトラウマを受け、ロシアンルーレットというデス・ゲームに参加し続ける男性の姿が描かれます。トラウマがあると、アルコールや薬物の乱用、ギャンブル、自傷行為、危険な性関係などの自己破壊的な行為で自分の気持ちを紛らわそうとする場合があります。なぜこのような危険に自分から飛び込むのか、自分でも説明できません。いつのまにか依存的になり、常習となることがあります。
6 うつ病やパニック症になりやすい
学生時代のいじめの被害で、うつ病やパニック症になるリスクが1.5倍に増えるというデータがあります。トラウマが残っていると社会と歯車が合いません。それがストレスとなり精神疾患を発症しやすいのです。精神科に通院するようになり、そこでトラウマがあることを指摘され、初めて自覚できるケースもあります。
トラウマは、安心できる場所で安心できる人に、トラウマを受けた状況を話すことで少しずつ癒されて行きます。相手は治療者に限らず、家族でも良いし、恋人や親しい友人でもかまいません。相手に共感してもらうことで、トラウマは解消されて行きます。ただし、無理は禁物です。安心した状況で再体験できることがポイントです。
また、不安感・不眠がつよい場合、うつ病やパニック症を合併した場合は、精神科で薬の治療を受けましょう。薬の力で体調や気分が良くなることで、トラウマが解消されやすくなります。また、医療機関での安心できる人間関係が、トラウマを解消するために役立ってくれます。